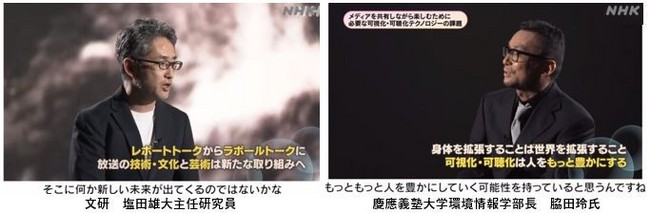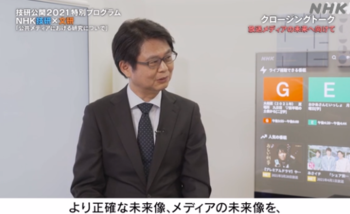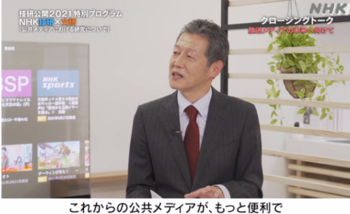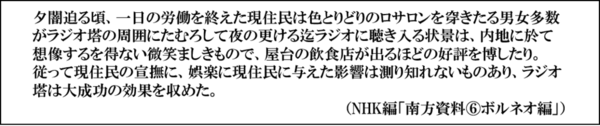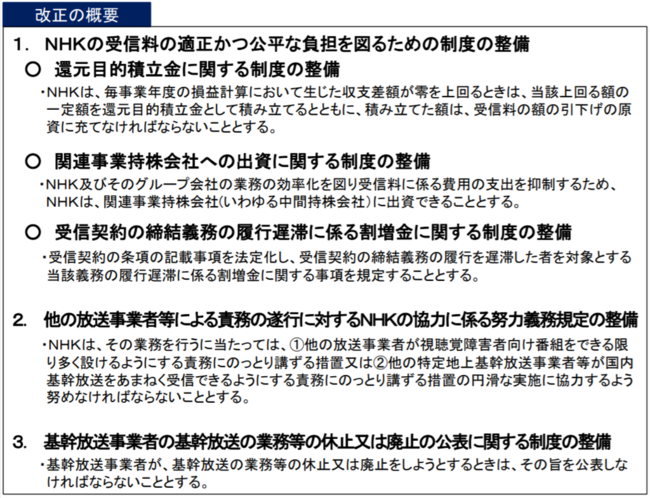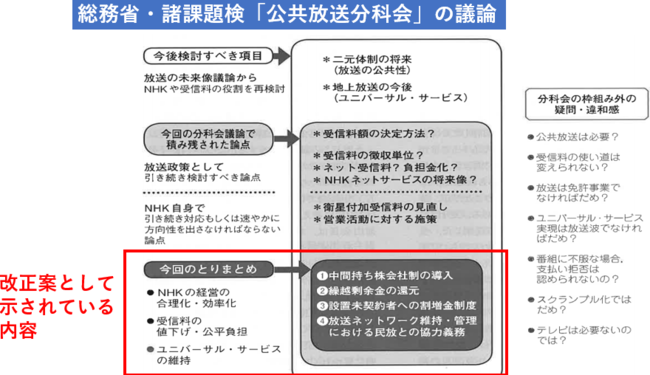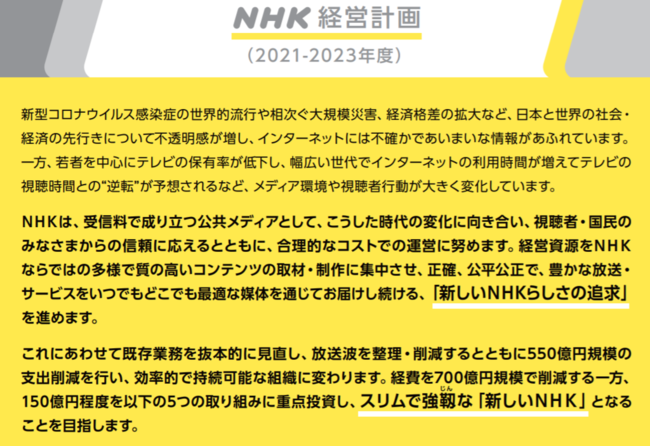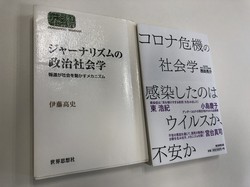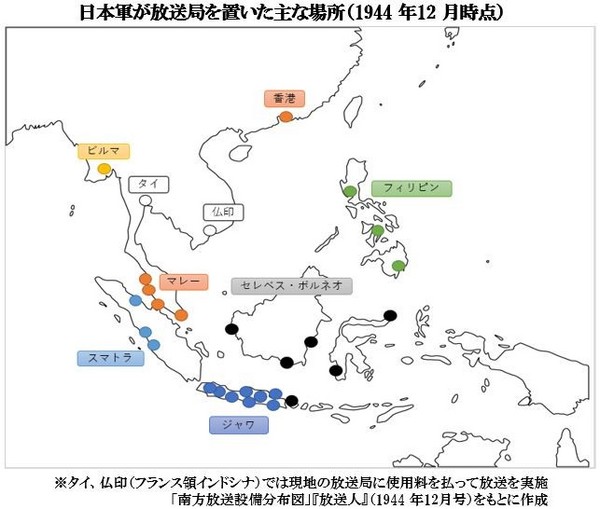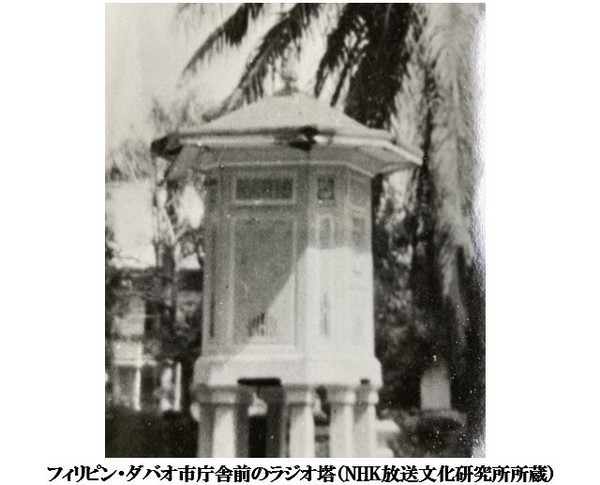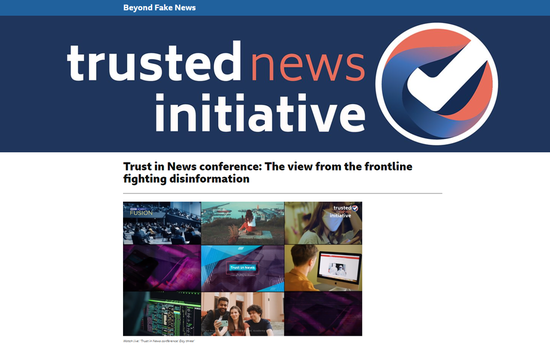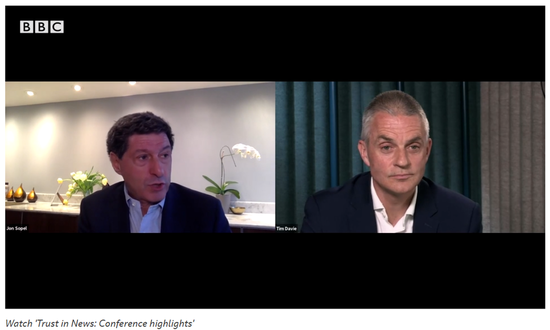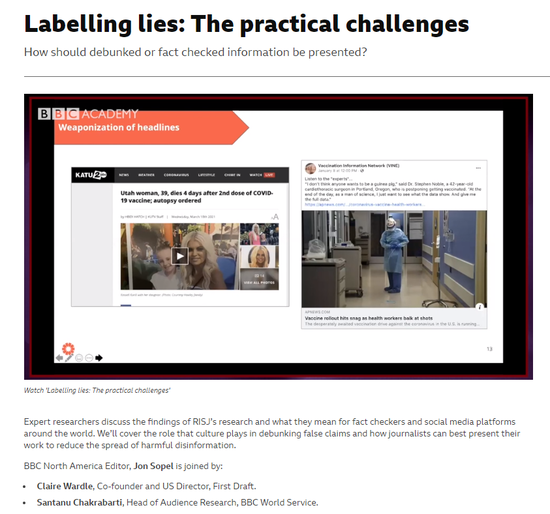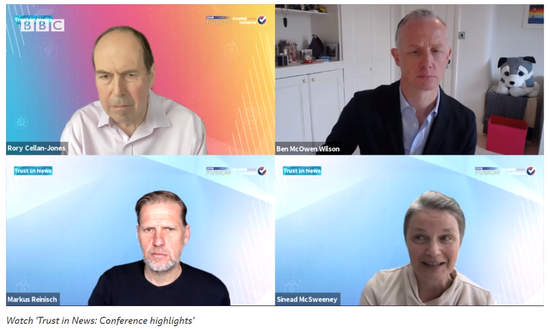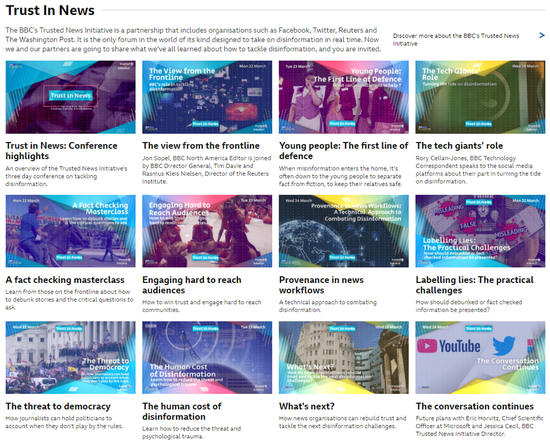放送文化研究所 島田敏男
「大型の長い連休を抜けると、恐ろしく急な下り坂であった」5月のNHK世論調査の結果を見て、菅総理大臣はこんな思いになったのではないでしょうか。
大型連休明けの10日(月)にまとまったNHK月例世論調査で、菅内閣に対する支持・不支持を見ると、「支持する」35%、「支持しない」43%でした。この支持率35%というのは去年9月に菅内閣が発足してから最も低い数字で、コロナとの戦いの途中で退陣した安倍内閣の最後の支持率(34%)と同じレベルです。
4月の調査と比べると「支持する」が一気に9ポイント下がり、逆に「支持しない」は5ポイント上がりました。この内閣支持率の急落は、まさにコロナとの戦いぶりに対する国民の不満の現れに他なりません。
今回の調査は5月7日(金)の夕方から始め、9日(日)までかけて電話で行いました。7日というのは政府の対策本部が東京・大阪・京都・兵庫の4都府県に4月25日から出していた緊急事態宣言を5月31日まで継続することを決め、新たに愛知・福岡も宣言対象地域に追加した、まさにその日です。
 菅首相
菅首相
4月25日からの緊急事態宣言を4都府県に出した際には、菅総理も小池東京都知事も「短期集中」と強調していました。しかし、大型連休中に人の流れをある程度抑えることはできたにしても、コロナウイルスの感染に繋がる人と人との密接な接触を減らすことはできませんでした。
「短期集中で抑え込む」と豪語していたにもかかわらず、結果として事態の解決に繋がらなかった。逆に宣言対象地域を拡大せざるを得なかったことに不満が噴き出すのは当然です。
去年5月の調査から続けて聞いている「あなたは新型コロナウイルスをめぐる政府のこれまでの対応を評価しますか?」という質問に対する今月の結果です。「評価する」33%、「評価しない」63%でダブルスコアに近い開きが出ました。「評価しない」が60%を超えたのは初めてです。
新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が繰り返し指摘しているように、緊急事態宣言によって感染者数の増加が減少に転じても、急ぎ足で元に戻ろうとすれば強烈なリバウンドが発生します。前回の緊急事態宣言を東京などより早めに解除した大阪で、今回深刻な医療崩壊状況に見舞われたことが、それを明瞭に物語っています。

そして事態打開の切り札でありながら、なかなか進まないのがワクチンの接種です。医療従事者は2月17日に、高齢者は4月12日にそれぞれ接種がスタートしましたが、その後の全国での進み具合に加速感はありません。
今回の世論調査で「菅総理は7月末を念頭に高齢者へのワクチン接種を完了できるよう取り組む考えを示しています。あなたは接種の進み具合は順調だと思いますか、遅いと思いますか?」と尋ねました。
結果は「順調だ」9%、「遅い」82%でした。これを年代別で詳しく見ると、50歳代、60歳代で「遅い」がほぼ9割を占めていて、他の年代よりも特に高くなっています。加齢とともに自分の健康維持に関して敏感になっている年代。だけど、より高齢の人たちほど優遇されない年代。この人たちがワクチン接種の遅れに極めて厳しい眼差しを向けているようです。
菅総理は今月7日の4都府県に対する緊急事態宣言継続と2県の追加決定に際して「1日100万回の接種を目指す」と強調しました。そのペースで進めることができれば、3,600万人の高齢者に対する接種の目標完了に漕ぎつけることが可能という説明です。
海外の製薬会社からのワクチンの入手は約束通りに進むのか?各地で接種にあたる医師や看護師など医療従事者の確保は大丈夫なのか?まさにここからが胸突き八丁で、7月末というチェックポイントは、コロナと戦う夏の陣とも言えます。
菅総理にとって、7月23日に開会式を予定しているオリンピック、その後のパラリンピック、さらには自民党総裁選挙、衆議院総選挙という夏以降に控える大きな政治日程の行方。すべてがコロナと戦う夏の陣の展開にかかっています。

立憲民主党の枝野代表は、10日の衆議院予算委員会で質問に立った後、記者団に「菅総理は野党側が内閣不信任決議案を提出すれば、衆議院を解散する可能性があると明言している。しかし、コロナウイルスの感染が拡大している現状は、衆議院を解散できる状態ではない」と述べました。6月16日に会期末を迎える今の通常国会で、衆議院の解散につながる内閣不信任決議案の提出は避けるべきだという考えを示したものです。
これについて、共産党の小池書記局長も「菅政権は100回ぐらい不信任に値すると思うが、今の時点で不信任決議案を出すべきではない。国民の生命、健康を守るという点からも解散・総選挙はありえない」と応じました。
国民の声は「今は解散・総選挙よりも、新型コロナウイルスの感染収束が最優先」ということに尽きます。コロナとの戦い夏の陣は、与党も野党も協力してワクチン接種の加速に力を尽くすことが第一です。
その夏の陣の成果によって感染の新たな波の襲来を押さえ、その上で秋の政治の季節に移っていく。これが国民にとって好ましい展開だと考えます。