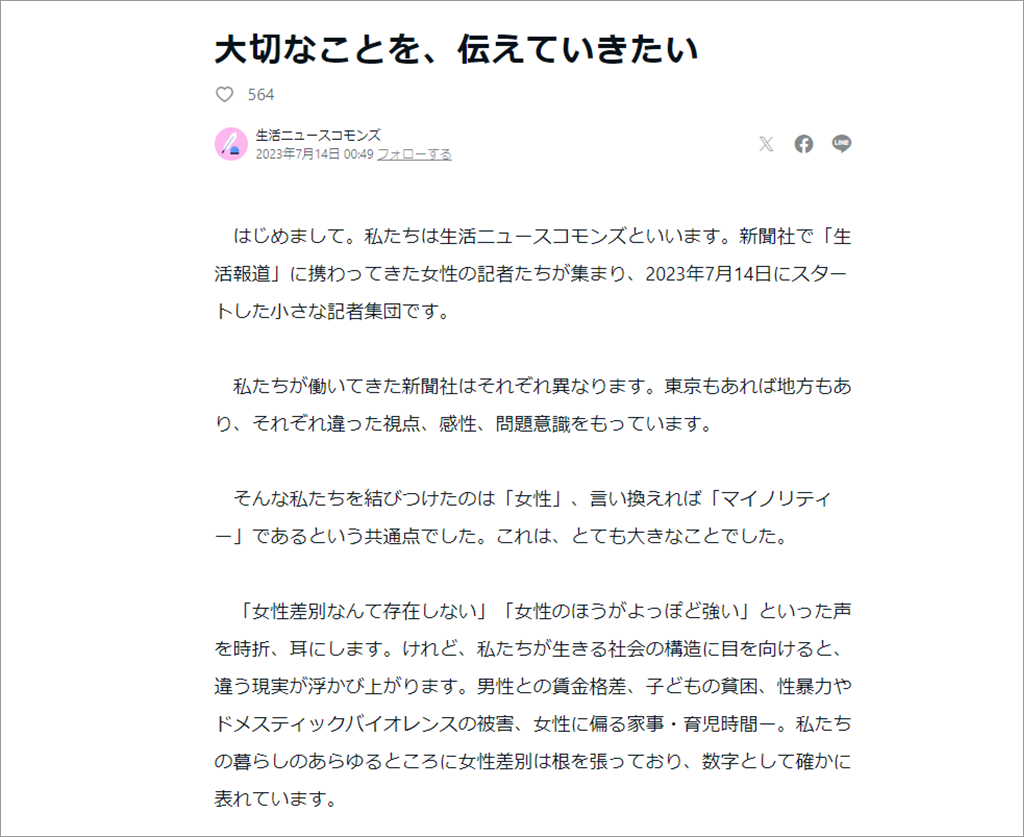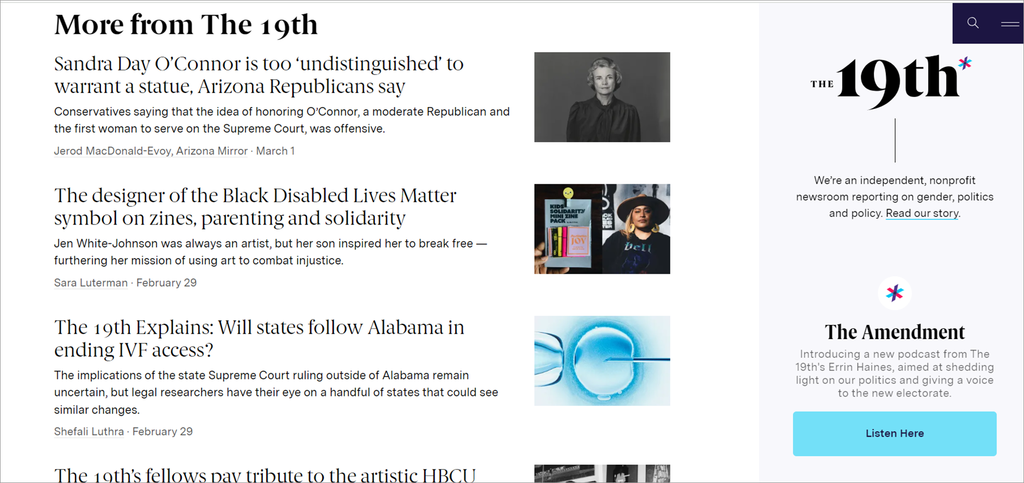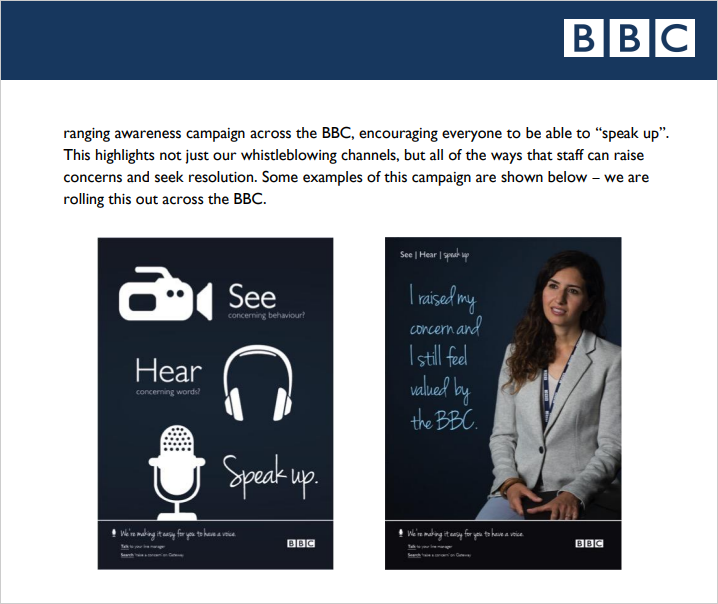メディア研究部(メディア情勢)熊谷百合子
 3月8日は「国際女性デー」。
3月8日は「国際女性デー」。
そのシンボルフラワーの黄色いミモザは、春を告げる花として、西洋では“幸せの花”と親しまれているそうです。この時期、街なかでミモザを見かけることが増えましたが、日本のジェンダーギャップ解消の道のりが険しいことを感じさせるのが、世界経済フォーラムが公表する「ジェンダーギャップ指数」の数字です。
2023年版の最新ランキングで、日本は146か国中125位。前年の116位からさらに後退し、2006年の公表以来、過去最低の評価でした。指標別では「医療」や「教育」は男女平等に近づきつつあるものの 「経済」と「政治」が世界最低レベルの水準です。「政治」では衆議院における国会議員の女性比率は1割にとどまるなどして138位、「経済」では女性管理職比率のほか、同一労働における賃金や推定所得の男女比にも格差があり123位。これが日本のジェンダーギャップの現在地です。
ジェンダー格差解消のために報道が果たすべき使命は大きいはず。しかし、取材する記者やディレクターのジェンダーバランスに偏りがある日本のマスメディアでは、ジェンダー関連の報道を出すことそのものに、高いハードルがあるとも言われています。職場のジェンダーギャップの問題は、報道機関で働く私たちにとってもまったく他人事ではないのです。
国際女性デーは、女性の地位向上を目指す日。
今回のブログでは、既存のマスメディアを飛び出して、新たな挑戦を始めた女性記者たちを紹介します。
 引用)生活ニュースコモンズnote
引用)生活ニュースコモンズnote
2023年7月14日、オンラインのメディアプラットフォーム「note」のサイトで、小さなミモザの花を青空に掲げた写真とともに、新しいウェブメディアが産声をあげました。
「大切なことを、伝えていきたい」のタイトルで始まるあいさつ文を一部、引用します。
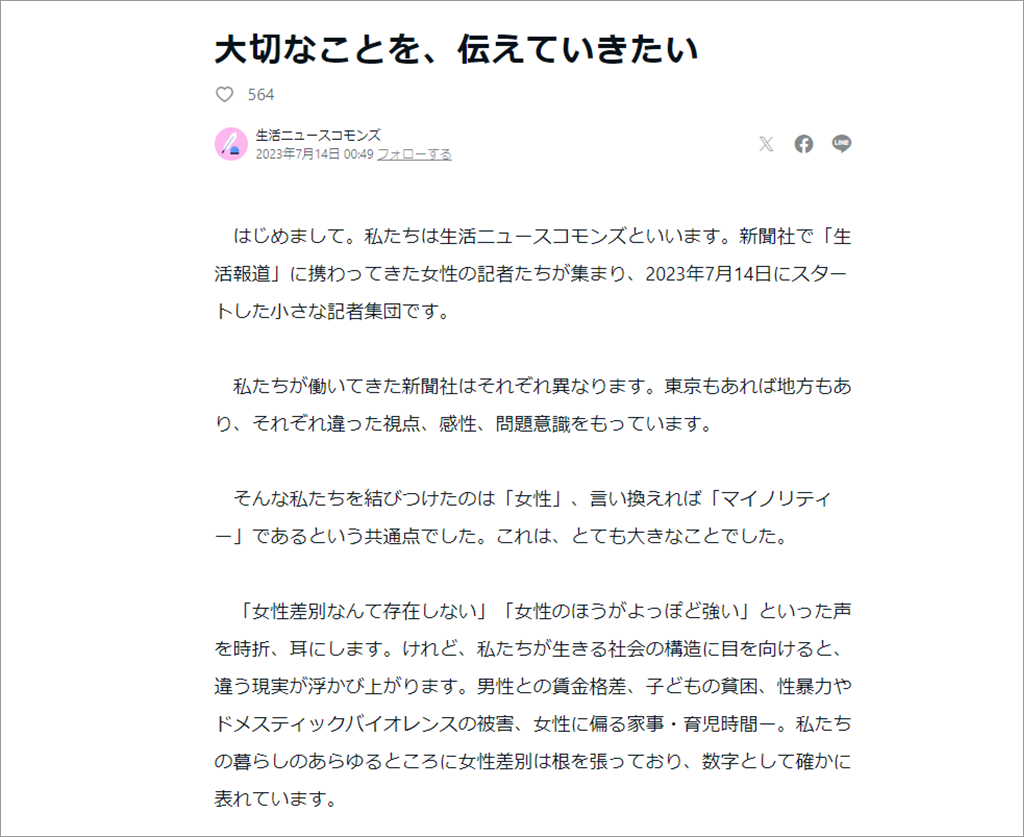 引用)生活ニュースコモンズnote
引用)生活ニュースコモンズnote
「生活ニュースコモンズ」1) は、東京、横浜、広島、秋田などを拠点とする5人の“小さな記者集団”から始まりました。配信を始めて半年あまりで、これまでに投稿された記事は90本以上にのぼります。ひとり親家庭の貧困の実態や、セクハラ、性暴力といった問題のほか、元日に発生した能登半島地震の厳しい避難生活についても、独自の取材をもとに伝えています。
 引用)生活ニュースコモンズnote
引用)生活ニュースコモンズnote
記事に共通するのは「弱い立場に置かれている人の声、生活者の視点を大切にしたい」という取材者の思いです。
1月11日に掲載された、ひとり親家庭に関する記事の内容を見てみましょう。
 引用)生活ニュースコモンズnote
引用)生活ニュースコモンズnote
この記事では、シングルマザーを支援するNPO法人のアンケート調査をもとに、▽ひとり親家庭に支給される児童扶養手当の支給額が過去40年間で35%しか増額されておらず、物価高で生活が追い詰められている実態や▽最低賃金は過去40年間で244%増となった一方、児童扶養手当の所得制限が低く据え置かれているため就労を制限せざるを得ない切実な悩みなどを報じていました2) 。
アンケートに回答したひとり親世帯の当事者は約2,400人。支援団体は、子どもの貧困対策を恒久的に拡充する必要があると指摘しています。
この記事が出る1か月ほど前に、政府は次元の異なる少子化対策の実現を目指して「こども未来戦略」をまとめました。新聞社やテレビ局も大きく報道しています。たとえばNHKは、12月22日のNHK NEWS WEBで、児童扶養手当について「満額を受け取れる年収の上限を今の160万円未満から190万円未満に引き上げるなど、経済支援の拡充策が盛り込まれています」と紹介したほか、年間3兆6,000億円程度とされる財源の内訳を伝えました3) 。
新聞は、ひとり親家庭の実情を伝えていたのか、記事検索サイトで【こども未来戦略】と【ひとり親】のキーワードを入れて調べてみました4) 。筆者が確認したところ、ひとり親の声を紹介していたのは、12月12日付けの毎日新聞朝刊と、12月23日付けの産経新聞朝刊、それに12月31日付けの中日新聞朝刊の3紙のみでした。このうち、毎日新聞と中日新聞では物価高に不安を抱くシングルマザーの切実な声だったのに対し、産経新聞は、制度を歓迎する母親のコメントが掲載されています。いずれも、紹介していた当事者の数は1人でした。
紙幅の制約で文字数に限りがある紙媒体の新聞と、文字数に制限はないオンラインメディア。その違いはあれ、「生活ニュースコモンズ」が詳しく報じた、ひとり親世帯の困窮は、オールドメディアではほとんど可視化されることのない私たちの社会の実相です。記事の後半では、子どもの貧困対策に取り組む支援団体が、児童扶養手当そのものの増額や、より大幅な所得制限の緩和を求める要望書をこども家庭庁や厚労省に提出したものの、「こども未来戦略」では増額も緩和も限定的であったと言及していました。
「生活ニュースコモンズ」の“小さな記者集団”とは一体、どのような人たちなのでしょうか。
創設者の一人が、毎日新聞の記者として長く生活関連の報道に携わってきた吉永磨美さんです。
2020年から2022年まで、新聞労連で女性として二人目の中央執行委員長を務めた吉永さん。在任中は、ジェンダー表現に危機感を抱く全国の新聞記者と共に「失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック」(小学館)を刊行しました。
このガイドブックでは、ノーベル賞の受賞報道で散見される“妻の内助の功”といった表現や、インターネット記事のPV稼ぎを目的とした釣り見出しなどの実例を踏まえて、偏見や差別を助長するメディア表現をわかりやすく指摘していて、報道機関の意識改革にも一役買っています。
そんな吉永さんが、25年間勤めた 毎日新聞を辞めたのは、組合の専従を終えて記者職に復帰して1年足らずのことでした。決断の背景には組合活動で出会った、女性記者たちの存在があったと言います。
 吉永磨美さん
吉永磨美さん
吉永磨美さん
「多様性を認め合う社会に時代はアップデートしているのに、マスメディアだけは今も男性主流の組織です。社会部のデスクが5~6人中、女性は1人しかいない、あるいは1人もいないという新聞社がいまだにあります。新聞労連にはジェンダーや格差の問題を報道したいと思っても、デスクにニュース価値が低いと判断されて、報道しにくいと訴える女性記者が何人もいました。なかには諦めて辞めていく人もいます。その人たちが転職してメディア以外で働くのはジャーナリズムにとって大きな損失です。人材流出を食い止めたいという思いもあり、日々の生活から出てくる疑問をニュースにする新しいメディアを立ち上げることにしました。記事を書いているのは、全国紙や地方紙で、医療や福祉、人権の問題を取材してきた女性たちです。男性中心の新聞社では、扱いが軽くなりがちな生活者目線の報道に正面から取り組んでいます。
 引用)ポリタスTV「わたしたちの手でつくるわたしたちに必要なメディア」
引用)ポリタスTV「わたしたちの手でつくるわたしたちに必要なメディア」
画面左:宮崎園子さん 右上:吉永磨美さん、右下:阿久沢悦子さん
去年10月、吉永さんは、『生活ニュースコモンズ』の仲間の一人である阿久沢悦子さんと共に、YouTube配信のオンラインメディア『ポリタスTV 』に出演しました。議論のテーマは「わたしたちの手でつくる わたしたちに必要なメディア」。なぜ新聞記者を辞めたのか、旧来メディアにどんな問題を感じるのか、ディスカッションの全容は今もアーカイブで見ることができます5) 。
この配信で聞き手を務めたのはフリーランス記者の宮崎園子さん。2021年に19年間勤めた朝日新聞を退職し、広島を拠点にオンラインメディアで記事を執筆しています。「生活ニュースコモンズ」の目指すジャーナリズムは、オールドメディアのみならず、これまでのオンラインメディアにもなかった新たな試みと受け止めています。
宮崎園子さん
「私たちは記者である前に生活者なんですけど、新聞記者の仕事をしていると、男性中心的な組織の中で生活者としての視点を、ある種かなぐり捨てないとやっていけないという違和感がありました。『生活ニュースコモンズ』の記者の多くが、吉永さんや阿久沢さんのように子育て経験のある女性記者なんですよね。生活者の実感に基づいて取材していて、切り口も新鮮だし、一読者としても面白い記事が多いです。私自身も広島で子育てをしていて、地方の教育行政の問題とか書きたいことはいろいろあるのに、既存のオンラインメディアには出し口がないことが悩みの種でした。でも『生活ニュースコモンズ』なら生活者としての視点で書きたいことが書けそうな可能性を感じています。」
 引用)3月8日に新たに立ち上げられた「生活ニュースコモンズ」のウェブサイト
引用)3月8日に新たに立ち上げられた「生活ニュースコモンズ」のウェブサイト
https://s-newscommons.com/
「生活ニュースコモンズ」として初めて迎える3月8日の国際女性デー。この日を節目に、“小さな記者集団”は、次のステップに進みます。より多くの人が読みやすいメディアにするために、これまでのnoteでの記事配信から、独自のウェブサイトでの配信に切り替えることにしたのです。サイトを立ち上げるための資金はクラウドファンディングで集めました6) 。「生活ニュースコモンズ」には、参考としているオンラインメディアがあります。
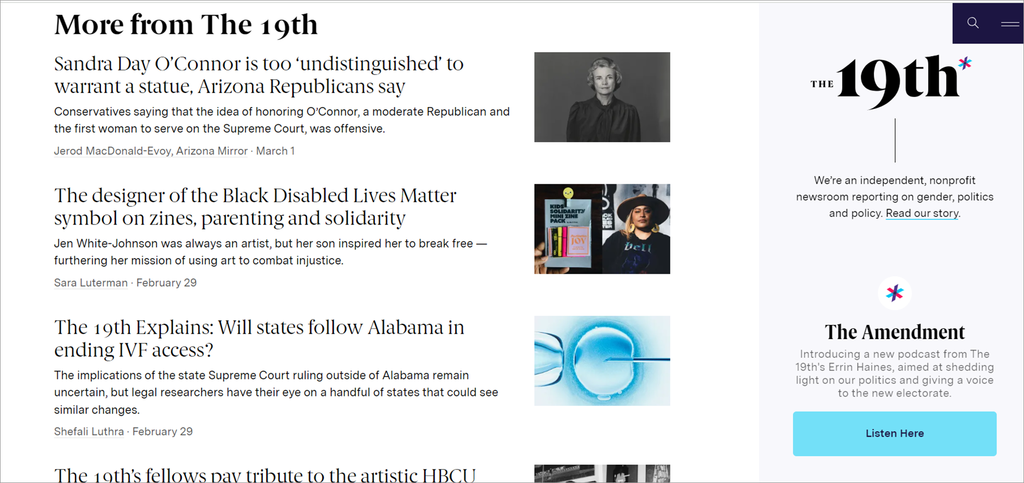 引用)the 19th
引用)the 19th
「The 19th」7) はアメリカ・テキサス州を拠点とする、非営利のオンラインメディアです。女性のみならずLGBTQ?の人々や社会的地位の低い人々が民主主義の参加者となるために必要な情報を提供し、力を与えることを目的に、ジェンダーの不公平や不公正を可視化し、女性や性的マイノリティーの人々の生活に影響する問題について、深く掘り下げて報道することをミッションに掲げています。
もうひとつ、「The 19th」が大切にしているのが、市民との対話とコミュニティーを作るためのデジタルプラットフォームとなること。公式サイトの「Our Mission(私たちの使命)」のページには、「有権者の人種やイデオロギー、社会経済、ジェンダーの多様性を反映し、共感をもってすべての人を取材する」として、「『The 19th』には、卑劣な言動やチアリーディング、オピニオン、的外れな記事や虚偽・誇大広告はありません」と皮肉を交えて伝えています。
ところで、国際女性デーの起源を知っていますか。19世紀後半から20世紀初頭にかけてアメリカの女性たちが参政権を求めて大規模な集会やデモを行ったことをきっかけに8) 、女性の地位向上を呼びかける動きが世界各地で活発になりました。この動きはアメリカで婦人参政権が認められたあとも続き、国連が1975年に3月8日を「女性の社会参加や地位向上などを訴える日」として正式に制定したのです9) 。オンラインメディア「The 19th」の名称は、婦人参政権を認めた合衆国憲法修正第19条(the19th Amendment)にちなんでいます。
ジェンダー視点のジャーナリズム。そして、市民とのコミュニティーとしてのデジタルプラットフォーム。吉永さんは、「The 19th」が実践するジャーナリズムを「生活ニュースコモンズ」で目指したいと考えています。
吉永磨美さん
「『the19th』は、生活者としてのジャーナリズムを実践しています。記者の大半は女性で構成されていて、ジェンダー視点の報道を発信することで、埋もれていた問題を可視化し、社会にもいい影響を与えています。私たちが目指すのも、『the19th』のようなジャーナリズムです。『生活ニュースコモンズ』の「コモンズ」には“共有財”や“公園”という意味があるんですね。新しく立ち上げるサイトでは、人々が集う公園のように、ジャーナリストも市民も、さまざまな立場の人が集まって、価値観や問題意識、疑問を分かち合える場を作りたいと思っています。半径5メートルの場から見える課題をボトムアップ型の切り口で追求することで、誰もが声をあげやすいプラットフォームにしていきたいです。」
メディアの中にあるジェンダーの課題を考えるとき、私には繰り返して思い起こす言葉があります。去年2月の文研ブログでも紹介した北欧の二人の女性ジャーナリストの言葉です10) 。
| 「メディアは単に社会を反映するだけではなく、私たちが何をニュースとして取り上げるのか、誰に取材するのか、どんな視点で伝えるのかによって社会をかたちづくりさえします。」 |
| (アイスランド国営放送RUV編集局長ソーラ・アルノルスドッティルさん) |
| |
| 「ジェンダー平等を達成するうえで子育てに関連する社会的支援は重要な施策です。こうしたトピックを頻繁に取り上げることが、社会の共通課題であるとの意識を共有していくうえで不可欠です。そのためには、メディアはどのように世界を描くのかを考えなければなりません。その意味でもメディアの役割は重要なのです」 |
| (北欧最大の日刊紙・ヘルシンギンサノマット紙のアヌ・ウバウトさん) |
「生活ニュースコモンズ」の新たな挑戦は、北欧の女性たちが示したメディアの役割に対する一つの解のように感じられました。
翻って、既存のマスメディアを顧みると、取材や制作に関わる記者やディレクターのジェンダーバランスに偏りが認められる現在、残念ながらこうした役割を十分に果たしているとは言えません。しかし私は、既存のマスメディアに身を置く人間の一人として、また、メディアの中のジェンダーや多様性の課題を研究する立場として、できることはまだあると考えます。
オールドメディアにできない報道があるとするならば、それはなぜなのか。そしてマスメディアに足りていない視点は何か。新たなジャーナリズムのかたちを目指す「生活ニュースコモンズ」の挑戦は、これからのメディアの在り方に一石を投じるものとして、既存のマスメディアに携わる者たちにとっても目が離せない存在になりそうです。「どのように世界を描くのかを考え」、「社会をかたちづくる」メディアの役割を担うために、マスメディアとしてできることを、私自身も考え続けていきたいと思います。
1)https://note.com/commons2023/
2)https://note.com/commons2023/n/nb5387c9910e8
3)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014296621000.html
4)日経テレコンで、2023年12月1日~2024年1月31日の期間で検索
5)ポリタスTVの全編はこちら https://www.youtube.com/watch?v=K8ODeL6tRkg
6)https://camp-fire.jp/projects/view/716877
7)https://19thnews.org/
8)https://www.loc.gov/item/today-in-history/march-08/
9)https://www.un.org/en/observances/womens-day/background
10)https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/480010.html






 3月8日は「国際女性デー」。
3月8日は「国際女性デー」。