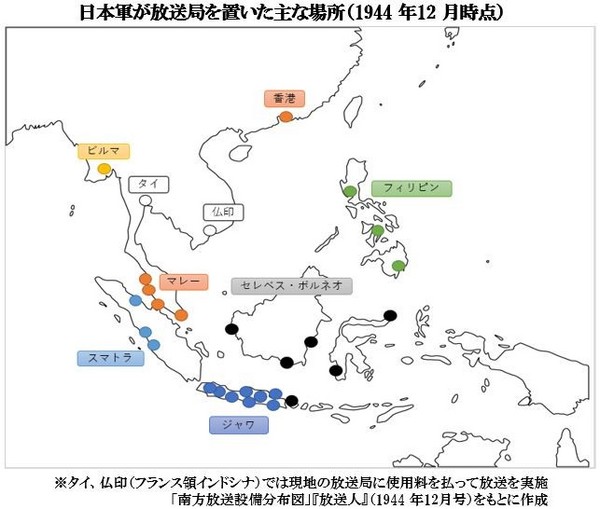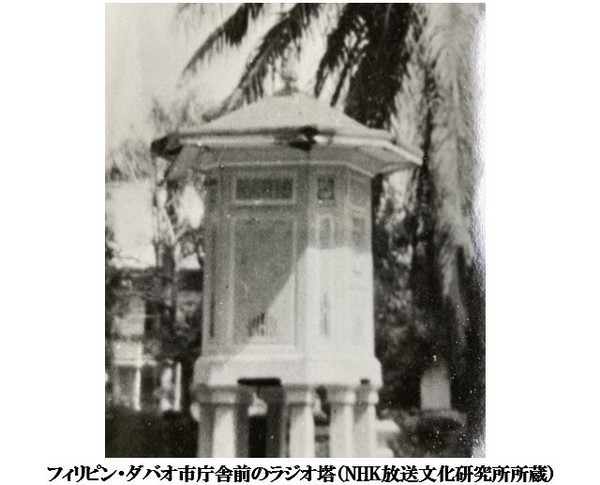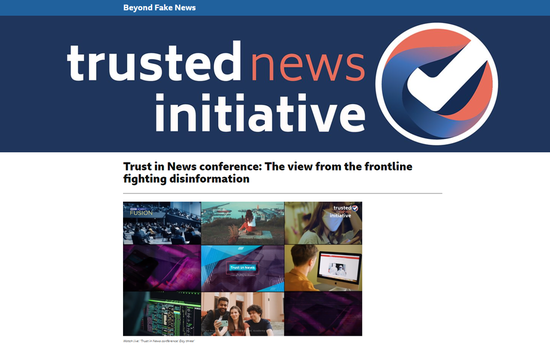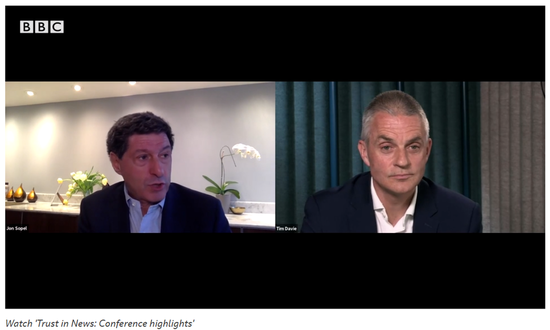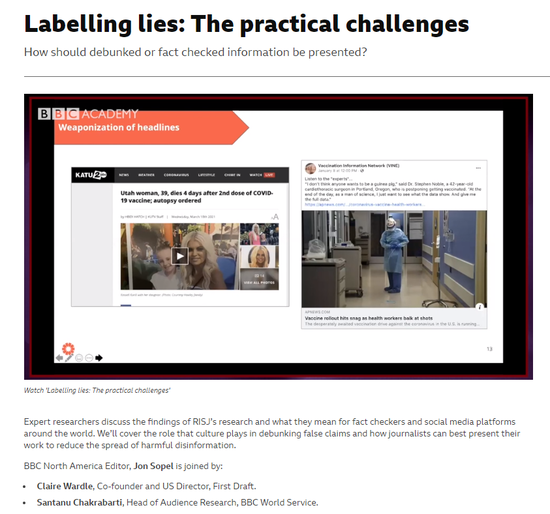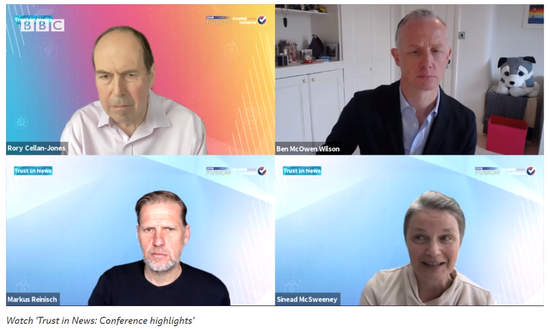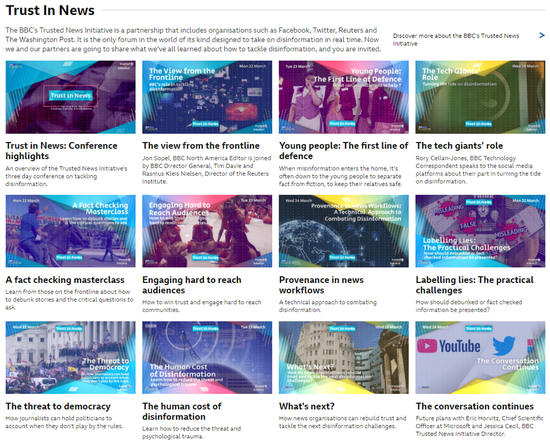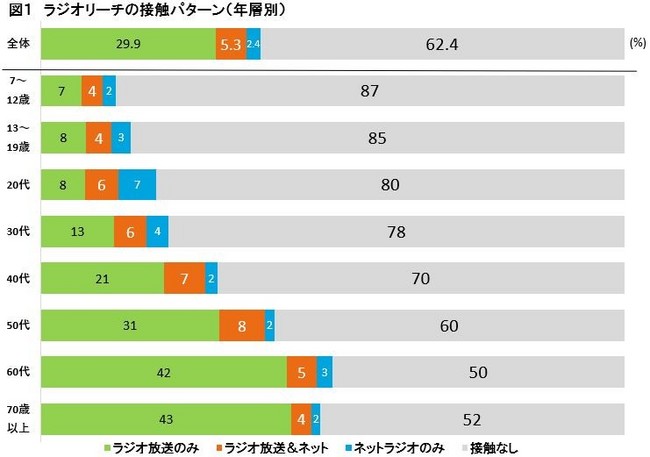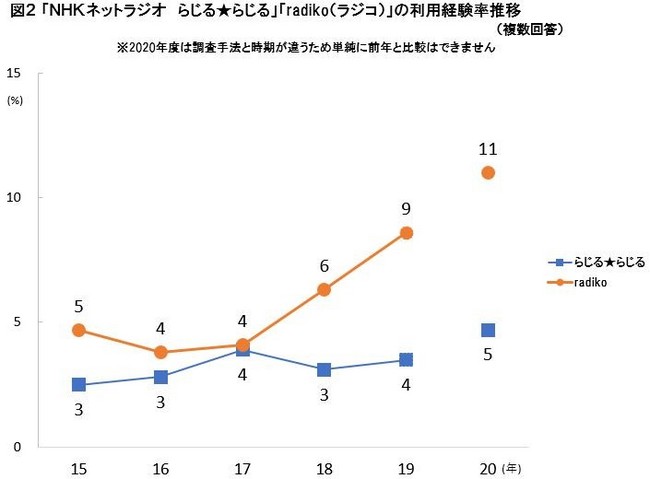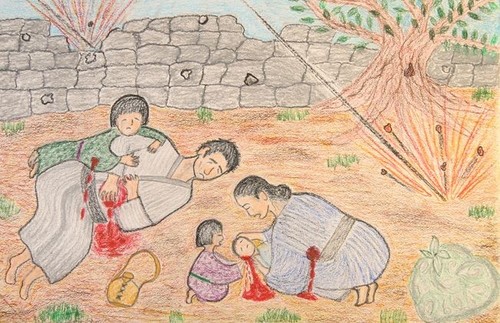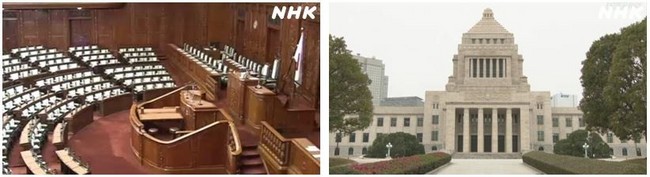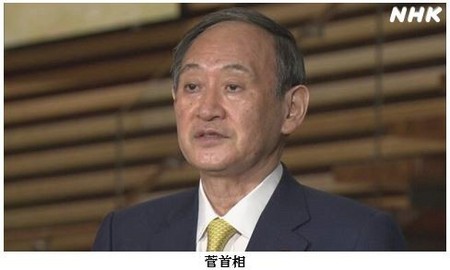メディア研究部(メディア動向) 村上圭子
フジテレビ(以下、フジ)系のリアリティー番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020(以下、『テラスハウス』)』に出演中だった木村花さんがSNS上で誹謗(ひぼう)中傷を受け、それを苦に自ら命を絶ってから1年弱が経ちます。母親の木村響子氏(以下、響子氏)は、「放送倫理・番組向上機構(以下、BPO)」の放送人権委員会に対して、「娘の死は番組の“過剰な演出”がきっかけでSNS上で批判が殺到したためだとして、人権侵害があった」と申し立てていましたが、このほど(3月30日)委員会決定が公表されました1)。
委員会では、「人権侵害があったとまでは断言できない」とする一方で、「出演者の精神的な健康状態に対する配慮が欠けていた点で、放送倫理上の問題があったと判断」する「見解」を示しました。既にこの内容については多くのメディアがニュースとして取り上げているので、ご存じの方も多いと思います。ただ、決定文は60ページに及び内容も多岐にわたっており、参加した記者会見でも共有すべき論点が多く含まれていると感じたことから、本ブログでは短いニュースでは十分に伝えきれない“メディアのあり方”という観点で、私なりにまとめておきたいと思います。
1)双方の主張は平行線のまま
私は2020年10月に「『テラスハウス』ショック①~リアリティーショーの現在地」という論考を発表し2)、ブログでも論考をサマライズしたものを書きました3)。今回のブログでは「リアリティー番組」で統一しますが、呼称も流動的で、フォーマットも固定化しておらず、定義も非常にあいまいな番組群です。私はこの論考で、世界各地のリアリティー番組をタイプ別に分類した上で、「制作者が用意したシチュエーションに、一般人や売り出し中のタレントなどを出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化を引き起こす何らかの仕掛けを用意し、その様子を観察する」ということを共通項としました。『テラスハウス』においては、6人の若い男女が共同生活をするおしゃれなおうちと車を用意するというのが、制作者が用意したシチュエーションと仕掛けです。欧米では、かなり過激なシチュエーションや仕掛けが用意されている番組も多いので、日本のそれとは大きく異なるように見えますが、欧米にも『テラスハウス』のようなタイプも存在しており、日本だけが特殊だという見方に偏りすぎると、特に出演者への対応策を講じていく上で見えてこないものがあるのではないかと私は考えています。これについてはまた後ほど述べます。
この論考を執筆したのは2020年の7月頃でしたが、ちょうどその頃、響子氏はBPOに申し立てを行い、フジテレビは社内横断メンバーによる検証報告を公表したばかりでした。双方の事実関係を巡る主張は大きく食い違っており、また響子氏のフジに対する不信感も非常に強く、直接的な対話も全く行われていない状況でした。そのため論考では、『テラスハウス』自体については扱いましたが、花さんを巡る動向の詳細に触れることはあえて避けることにしました。また「欧米ではリアリティー番組出演者の中に自ら命を絶った人達が数多くいる」という断片的な報道が、花さんの死後、繰り返されていました。そこで、まずはリアリティー番組とは何かを理解するため、約20年の発展の歴史や、日本ならではの特徴についてまとめることを試みました。そして、報じられていた欧米の出演者の死亡例や精神疾患例についても、その実態や背景、対策について可能な限り調べて取り上げました。
それから約半年の間、ネット上の誹謗中傷に対する対応策の議論は大きく進み4)、新たな裁判手続きを定めたプロバイダー責任制限法の改正案が今国会に提出されています。また、花さんに対する悪質な書き込みをしたとして、これまでに2人が書類送検されています5)。こうしたことを通じて、SNS活用におけるリテラシー向上の重要性についても社会全体で少しずつ共有されてきているように思います。
ただ、響子氏とフジの関係については、その後もほとんど変わることはありませんでした。そのことについてはとても残念に思っています。そんな中で進められてきた、BPOによる審理と関係者ヒアリング。決定文には、「委員会の事実認定は困難」という文言が繰り返し登場し、本決定を取りまとめることがいかに難しかったかがうかがえます。
2)花さんの死までの経緯を時系列で確認
とはいえ、今回の決定文で初めて事実関係が確認されたものも少なくありません。双方の主張が対立しているものも含めて、改めて花さんが亡くなるまでの経緯を時系列で確認しておきたいと思います。なぜなら、今回の委員会の審理では、番組に人権侵害があったかどうか、放送倫理上問題があったのかどうかを判断するのに、花さんが亡くなるまでの経緯の検証にかなりの重きが置かれていたからです。決定文の中では散発的に書かれている内容を拾いあげて私なりにまとめ直してみました。
<2019年>
8月29日 花さん、フジとの「同意書兼誓約書」に署名
(制作プロダクションのプロデューサーと1時間かけて読み合わせ。SNS炎上
のリスクなどについて記載。また、「心のアンテナの感度レベルを1から5や10に
や10にするつもりで、豊かな感性を(以下、略)」など番組制作に臨む心構えも
記されていた。加えて、出演者が条項違反した場合は、番組制作費用などの
損害を賠償することなどの規定もあった。)
9月2日 花さん、テラスハウスに入居
12月3日 第20話で花さん初登場
<2020年>
1月21日 “コスチューム事件”撮影
(花さんが洗濯機に置き忘れたプロレスの試合用コスチュームを男性出演者A氏
が誤って乾燥させ、縮んで着られない状態となってしまった。花さんにとっては、
東京ドームのリングでも着た大切なもの。花さんはA氏に怒りをぶつけ、
ごめんとしか言わないA氏に対し、被っていた帽子をとって投げ捨てた。)
1月22日 花さんの友人が、花さんから、制作スタッフから「ビンタしちゃえば」と指示
があったと聞かされる(※フジ側はこの内容を否定)
1月23日 “事件”の相手であるA氏、テラスハウスを退去し出演も終了
1月下旬 花さん、友人に番組に起因した誹謗中傷をネット上で受けて悩んでいると相談
2月15日 未公開動画撮影
花さん、撮影中に過呼吸に陥る。
響子氏側は、花さんはその場から逃げたのにカメラに追い回されたと主張。
フジ側は、花さんが落ち着いてから撮影を継続したと主張している。
3月28日 コロナで撮影中止に。テラスハウスでの共同生活も休止し、花さんは自宅へ
3月31日 Netflixで第38話(「コスチューム事件」)配信
SNS上及びダイレクトメールで花さんへの誹謗中傷が多数あらわれる。
花さん、自宅で自傷行為を行い、その写真を友人に送信し自身のSNSでも公開。
SNS投稿で花さんの行為を番組スタッフが知り、電話及びLINEで連絡。
4月1日 花さん、プロレス仲間と共に整形外科を受診する。
その後、4月中旬まで自傷行為を繰り返す。下旬までプロレス仲間宅に同居。
4月4日 制作スタッフから番組責任者(フジテレビ)に報告。
制作責任者は花さんと直接連絡はとらず、社内でもその事実を共有しなかった。
制作スタッフは花さんにテラスハウスでの生活再開を提案(実施されず)
4月8、9日 制作スタッフ自宅訪問。メンタルクリニック診察を提案(実施されず)
4月19日 制作スタッフが花さんにSNSアプリ削除を提案(削除するも、その後復活)
4月28日 FOD(※フジテレビの動画配信サービス)で配信
5月3日 花さんが自身のSNSアカウントを再開していることが確認される
5月14日 YouTubeで未公開動画を3本配信
(花さんが、第38話で起きた“事件”の背景について視聴者に十分伝わっていないと
不満をもらしていたとして、制作スタッフは、配信されていない内容をきちんと
伝えて花さんの評価を回復できるのではと考えて実施を決定したとしている。
一方、花さんは動画作成や内容について意見を求められたことはなく、公開も
突然の出来事だったという。)
5月中旬 配信後、再びSNS上で誹謗中傷が増加し、花さんが「未公開でまた荒れ始めた」
と制作スタッフに報告。
配信後、A氏から花さんに連絡あり。コロナ禍が落ち着いたら食事を約束。
花さん、自身の卒業プラン(テラスハウス退去)を制作スタッフに提案。
5月19日 フジテレビ系地上波で放送
花さん、制作スタッフとLINEでやりとり。非難のダイレクトメールがあったことを報告。
今後の撮影再開を前提とした相談を行う
5月23日 花さん亡くなる
3)権利の侵害はあったのか?
委員会決定は、人権侵害の観点と、放送倫理上の観点の2つに大別されています。以下、それぞれ内容の主要なポイントを押さえておきます。まず権利侵害はあったのかについてです。
*視聴者の行為を介した人権侵害に関する放送局の責任は?
申立人である響子氏は、Netflix配信後に花さんが数多くの誹謗中傷にさらされていたにも関わらず、その後も、未公開動画の公開や地上波での放送を行うことは、花さんに対する誹謗中傷を誘発させ精神的苦痛を与えることになることは疑いようがなく、こうしたことから人権侵害は明らかである、と主張しました。
これに対し、フジは2つの点から反論しました。花さんに対して各種の対応を行っていて漫然と放送を行ったわけではないこと。また、放送に起因する誹謗中傷が含まれる可能性が認識可能な場合に局の責任が免れない、ということになると、放送局の表現の自由や報道の自由が不当に制限されることになるため安易には認められない、という主張です。
委員会では、放送局の表現の自由の重要性、責任を負うべきは非難を行った者であること、違法な書き込みの多くは放送の趣旨や内容と関係ないところにまで及び、放送による権利侵害と別な問題であると考えられることなどから、違法性を含まない内容のリアリティー番組の放送に関してネット上で誹謗中傷がなされることについては、放送局に人権侵害の責任を問う事は困難だとしました。
*具体的な被害(花さんの自死)は予見可能だったか
ただ委員会では、同一の番組が放送だけでなく配信でも行われることが増えている中、今回のケースではNetflixで先行配信された時から花さんは誹謗中傷を受けていたため、フジが「特段の対応をすることなく漫然と実質的に同一の内容を放送・配信することは、(中略)人権侵害の責任が生じうる」とし、先行配信から地上波放送までの間のフジの花さんへの対応のあり方を検討しました。
まず、Netflix配信後の誹謗中傷を苦に自傷行為を行った花さんに対して制作スタッフが行った対応について検証し、委員会は一定の対応がなされたと捉えました。次に、その1か月半後に未公開動画を公開したことについては、響子氏側は「制作陣が炎上を盛り上がりと感じ、動画を出せばおいしいと思った」と考える方が自然であると主張、一方、フジ側は配信された番組内容に対する花さんの不満・要望にこたえるために制作したものと主張し、見解は対立していました。委員会としては、響子氏の主張は採用できないものの、フジ側にも配慮に欠ける点があったとしました。そして、最終的に地上波で放送するに至ったフジの判断については、花さんの態度が前向きになった兆しが複数見受けられたことなどを総合的に判断したことには一応の慎重さがうかがえるとし、人権侵害があったとまでは断定できないとしました。
*「本人の意思に反するような言動を強要されたことによる権利侵害」はあったのか?
平たく言えば、フジから花さんに対して“やらせ”のような何らかの強要があり、それに従わざるを得なかったのかどうか、ということです。この点については、特に双方の言い分が真っ向から対立しており、その中で委員会としての判断が行われました。委員会としては、制作スタッフから「ビンタしちゃえば」と指示されていたかどうかは不明であるが、それに類する指示があったことは否定できないとした上で、仮にこうした指示があったとしても花さんは実際にビンタをしていないこと、また、映像に収められている花さんのA氏への怒りは相当程度に真意が表現されていると理解されることから、フジからの花さんに対する「提案やアドバイス」「演出や指示」は、花さんの「自由な意思決定の余地が事実上奪われているような例外的な場合に当たるという意味での自己決定権や人格権の侵害があるとは言えない」としました。また、損害賠償の規定が盛り込まれた同意書兼誓約書については、「出演者を過度に緊張させたり、精神的に拘束したりする背景となる可能性があり、適切とは言えない」としながらも、やはり権利の侵害があるとは言えないと判断しました。
4)放送倫理上の問題はあったのか?
このように、委員会では人権侵害は認められないと判断した上で、放送を行う決定の際の配慮が十分だったかについて、放送倫理上の問題として検討しています。
まず委員会として、リアリティー番組が、「出演者自身が誹謗中傷によって精神的負担を負うリスクがフィクションの場合よりも格段に高く」、「出演者がしばしば未熟で経験不足な若者」であり、「状況を設定し、さらに出演者を選んで制作・放送しているのが放送局」であることから、局には「出演者の身体的・精神的な健康状態に特に配慮をすることが求められる」いうことを認識の前提としています。
その上で、未公開動画撮影の際の花さんの心的状態のシグナルを見落としていたこと、自傷行為が繰り返されるようになってから地上波放送まで1か月半しかたっていないこと、コロナ禍の緊急事態宣言という別要因によって花さんが不安な状態におかれていたこと、これらから、「いわば「素人判断」で意思決定をするのではなく、木村氏の精神状態を適切に理解するために専門家に相談するなどのより慎重な対応が求められたのではないか」としています。そして、こうした対応がなされなかった背景として、制作担当者(イースト・エンターテインメント)側と制作責任者(フジ)、また制作責任者とフジ社内での情報共有が行われなかったことがあるのではないかと指摘しました。
一方で、申立人の響子氏側が強く主張していた、制作側による過剰な編集、演出があったのではないか、という点については、問題はあるとは言えないとしました。また、フジが検証を十分に行わなかったことに対する批判については、委員会の検証のあり方の審理はかなり距離があるとして委員会としての判断を避けました。
5)今回の決定の意義と課題
以上、委員会決定の内容に寄り添いながら、その内容をまとめてみました。ここからは、決定の意義と課題について、私なりの意見を提示してみます。
*決定の意義について
まず、放送番組の制作や視聴において、配信サービスやSNSが密接不可分であるという今日的状況を踏まえ、局の責任の分界点や所在がどうあるべきかが本格的に議論された初のケースであったということ、これは今回の最大の意義だと思います。加えてリアリティー番組の特殊性についても深く考察された上で、出演者に対する精神的なケアの重要性と制作する放送局の責任が明確に示されたということも重要なポイントだったと思います。通常は当該局に対するものである委員会決定の結びのコメントが、今回はフジだけでなく放送界全体に向けられているというのも、委員会としての強いメッセージの表れだと思います。更に会見では、ABEMAのように、最近は配信サービスにおいて多くのリアリティー番組が制作されていることを受け、そうした事業者にも、この決定を読んで考えてもらいたいとのコメントもありました。
*決定の課題について
この委員会決定後、申立人の響子氏は記者会見で、「人権侵害が認められない結果について、すごく歯がゆく悔しい思いです。」「フジテレビには誹謗中傷対策をするだけでなく、出演者をコマの一つではなく、ひとりの人間として大切に扱ってほしい」と述べています6)。
前述したとおり、委員会決定には何度も「事実認定が難しい」という文言が登場しており、特に響子氏が最も強く主張している点、「娘は番組の過剰な演出によって凶暴な女性のように描かれた」か否かについては、対立する双方の主張が列挙されるに留まったと強く感じました。特にフジに対しては、局の表現の自由を尊重するというBPOの立場からか、踏み込んだヒアリングがなされているとは正直感じられませんでした。
「放送の自由・自律とBPOの役割」という論考7)で、文研・メディア研究部の塩田幸司氏はこれまでの委員会決定を読み解き、「メディアの言論・表現の自由を守りつつ、人権など市民の権利を擁護しメディアの質を高めるというジレンマの中で、BPOの各委員会が放送現場を委縮させないようにメディアの自律性を最大限尊重するという謙抑性を持ち続けていた」としています。今回の決定も、全体的にはその謙抑性を強く感じる内容でした。私はそのこと自体を否定するつもりはありませんし、その謙抑性こそが、NHKと民放連が設立した第三者機関として、自律的に運営するBPOの重要な立ち位置だとも思っています。そのため、今回の委員会決定が、番組を端緒とした誹謗中傷によって娘を奪われたと感じる母親の思いに到底応えられる内容でなかったことは、BPOという組織の宿命だと指摘されてもやむを得ない部分もあるかと思います。
一方で、制作者側へのヒアリングについては、もう少し謙抑性を排して臨むべきではなかったか、それを排して臨んでいたらもう少し異なる決定になったのではないか、という印象を私は持っています。いくつか感じる点はあるのですが、ここでは1点だけ述べておきます。
例えば、未公開動画制作に関して制作スタッフが発した「通常は、出演者からの『ここを使って欲しい』『ここを使って欲しくない』などの要望は受け付けていません」という発言ですが、通常のニュース取材やドキュメンタリーにおいては当てはまるけれど、リアリティー番組という特殊な番組制作においてはどうなのでしょうか。若い一般の出演者と制作者が一蓮托生の状態の中で関係を構築しながら台本なきドラマを紡いでいく、その難しさを魅力に昇華させていく力量が問われるのがリアリティー番組の制作現場だと私は思っていました。最近ではある種のドキュメンタリーにおいても、出演者と制作者が、撮られる側と撮る側という立場を超えて、相談し、共闘しながら作品を作り上げていく現場も増えてきています。そうしたことを鑑みても、この制作スタッフへのヒアリングでの言葉は、あまりに浅薄すぎると感じました。更に、通常は出演者の要望を受け付けていないものの、「花さんが3月31日に自傷行為に及んでいたこともあり、その心情に配慮することは重要であると考えて」未公開動画を制作し公開したということですが、そのプロセスで制作スタッフは花さんに一切意見を聞かず、動画の公開すら花さんにとって突然だったということにも大きな違和感を覚えました。もしも制作スタッフが心情に配慮することが重要だ、と心底思っていたとするならば、「配慮に欠ける」以上に「制作者本位」であったのではないか、そこには「動画をだせばおいしいと思った」という気持ちが本当に潜んではいなかったか……。委員会は響子氏の思いを背負い、もう一歩踏み込んだヒアリングを行うべきではなかったかと感じています。
また、委員会決定では、制作担当者、制作責任者、フジの上層部の中の意思疎通のあり方に問題があったとの指摘がありました。現場は親身にケアを行っていたが、フジはどこまで責任を果たしていたのか、そんなトーンが委員会決定の文言でも会見でも感じられました。そのため私は会見において、花さんに向き合っていた制作担当者と、最後まで花さんと直接連絡をとらなかったフジの制作責任者の双方のヒアリングを通じて、花さんへの思いに対する温度差を感じなかったか、制作現場はNetflix配信後の花さんの状態を見て、その後の配信や放送を行うことをためらってはいなかったか、と聞きました。しかし、具体的な答えを得ることはできませんでした。私がなぜこの問いをしたかと言えば、気持ちの浮き沈みを繰り返す花さんに寄り添い、その心情をくみ取ることを最優先に考える現場であれば、これ以上、配信や放送を重ねることで花さんを傷つけたくないと考える人がいてもおかしくない、そう信じたいという思いがあったからです。フジに直接取材ができていないので、まだ私はこの点については納得できていません。
なぜ私がこの問題にこだわるかというと、それは出演者のケアを誰が行うのか、という問題に直結するからです。親身に接してくれている制作者が、実は自分を「コマの一つ」としてしか見ていなかったら、「ひとりの人間として大切に扱う」意識が欠落しているとしたら、出演者は完全に逃げ場を失ってしまいます。更に、損害賠償をさせられるかもしれない同意書兼誓約書にも自己責任でサインをしてしまった、ということも、特にプロダクションに守られているわけではない一般人やセミプロのような若者であれば、重圧としてのしかかってくるかもしれません。
先ほど私は、リアリティー番組の制作については、通常の取材や番組制作以上に、局において出演者の精神的ケアの責任がある、という今回の委員会決定には意義があると述べました。ただ今回の決定では、ケアの具体的内容までは言及されていません。出演者にとって制作スタッフは味方なのか敵なのか、実はここが、今回の問題の最も大きな本質なのではないかと私は感じています。
真実を暴くための報道の現場では、たとえ相手の尊厳を傷つけたとしても伝えなくてはならないことも時にあります。また、ドキュメンタリーの撮影の現場では、取材者と被取材者の関係は信頼と緊張の繰り返しの中で進んでいきます。ドラマのような完全なフィクションの現場を私は経験していませんが、強い信頼関係のもとに制作が進められている現場が多いと聞きます。では、リアリティー番組はどうなのか。制作者の心構え次第なのか、それとも、制作当事者は出演者本位で考えることは構造上難しいため、精神的ケアは別な担当者を置くか、もしくは完全に制作体制とは切り離し、制作スタッフの対応に対する相談も受け付けられるような医療や苦情の窓口を設けるべきなのか……。
リアリティー番組の最初の自殺者は、私が調べた限りでは1997年のことですが、その男性は亡くなる前に妻に対して、「(制作者は)私がやった良い部分をカットし、私をバカのように見せた」と語っていました。この問題は、古くて新しい、リアリティー番組そのものが抱える宿命なのかもしれない、と私は考えています。
なお、この点については、4月5日から、イギリスの放送・通信分野の独立規制機関であるOfcomが、放送局がこれまで以上に出演者に対して保護をするように義務付けた新たな規定を発効させています8)。これは、イギリスで絶大な人気を誇るリアリティー番組『ラブ・アイランド』で、出演者3人、その恋人を加えると4人が自ら命を絶った事実を受け、広く意見を募った上で設けられた規定です。2020年10月に論考を書いた時にはまだ意見募集が終わったばかりで詳細に触れられませんでしたので、本ブログで次回、このイギリスの状況について改めて報告したいと思っています。
6)フジテレビに対して思うこと
フジはこの委員会決定を受けて、「今回の決定を真摯に受け止め、今後の放送・番組作りに生かしてまいります。番組制作に伴うSNS上の対策や課題については新設したSNS対策部門を中心に組織的に取り組んでいく所存です」とコメントを発表しています。ただ、現在も配信されている『テラスハウス』の今後についてや、それ以外のリアリティー番組を今後制作するのかどうかについては、言及を避けています。
『テラスハウス』は2012年に始まってから、世界各国で多くの人達を魅了してきました。BPOの青少年委員会のホームページには、2012年の中高生のモニター報告に、以下のような一文があります。「(鳥取・中学2年男子)僕が最近はまっているテレビ番組は、『テラスハウス』(フジテレビ/山陰中央テレビ)です。今までの番組とは一風変わった番組で、そのアイディアは素晴らしいと思います。青春まっただ中の中高生には人気が高く、見ていて胸がときめきます。アイディアでテレビの未来は大きく変わると思います。」
フジは今後、花さんや響子氏、花さんを取り巻く多くの関係者はもちろんのこと、こうして番組を楽しんできた視聴者に対しても、真摯に向き合うべきではないかと私は思っています。また、今回の委員会決定を公表した放送人権委員会ではなく、同じBPOの放送倫理検証委員会でこそ審議すべきではないか、という声は会見でも聞かれましたし、今からでも審議すべきと主張する専門家もいます9)。私は、SNSと最も親和性の高いリアリティー番組の課題から、制作者、出演者、視聴者との関係を再構築することが、これからのメディアのあり方を考えるために重要だと考えています。そのためには、今回の委員会決定でこの議論が終わることはとても残念なので、もしも放送倫理検証委員会で審議されるのであれば、それを歓迎する立場ですが、こうした議論の枠組み以上に大事なのは、当事者であるフジが、そして制作責任者や制作担当者個人が、きちんとこの現実に向き合うことだと考えています。今回の経験を社会で共有することが、今後のメディアのためにも、そしてコンテンツを制作する自局の、自身のためにも必要だという意識になってもらいたい。それまで私は、このテーマについて取材を続けていきたいと思っています。
1) https://www.bpo.gr.jp/?p=10741&meta_key=2020
2) https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/20201001_6.html3) https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/435552.html4) 総務省においては、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」で議論が重ねられ、
2020年12月に最終とりまとめが公表された。この取りまとめをもとに、
今国会では法改正案が提出されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724725.pdf
5) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210405/k10012956671000.html
6) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210330/k10012944601000.html
7) https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/pdf/20190130_2.pdf
8) https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/new-protections-for-people-taking-part-in-tv-and-radio-shows
9) 時事ドットコムニュース「問われるBPOの存在意義 フジテレビ「テラスハウス」に「人権侵害なし」決定」(上智大学・水島宏明氏)
https://www.jiji.com/jc/v4?id=210331bpoterrace0003