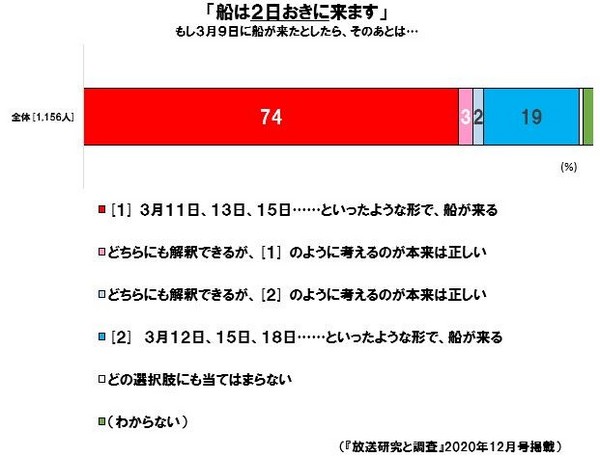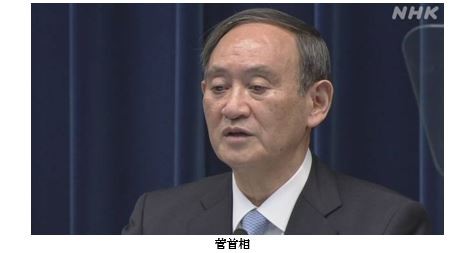#312 失われた人生をどう伝えるか イギリスのコロナ報道から
メディア研究部(海外メディア) 税所玲子
新型コロナウイルスが世界的に広がって1年あまり。「放送研究と調査」で海外のコロナ報道について執筆するため、新聞やネットで情報収集を続けていましたが、ふと気が付くとじっくり読み込んでしまう記事がありました。それは、コロナで亡くなった方について写真や家族・友人のコメントなどを添えて描かれた「失われた人の物語」。匿名が多い日本ではあまり見ないアプローチです。どんな狙いでこうした記事は書かれているのでしょうか。イギリスの例から考えます。
亡くなったトム・ムーアさん ツイッターより
2021年2月2日、100歳の男性がコロナに倒れました。亡くなったのは、トム・ムーアさん。「キャプテン・トム」との愛称で親しまれた退役軍人です。去年4月、100歳の誕生日までに自宅の庭を100往復するとの誓いをたて、コロナ禍で多忙を極める病院への寄付金を募りました。第2次大戦の勲章を付けたブレザーを着込み、歩行器を頼りに懸命に歩く姿は、イギリス人の心を鷲づかみにし、目標額1000ポンド(約15万円)とはけた違いの約330万ポンド(約49億円)が集まりました。「砂糖を沢山いれた甘いティーが好き」「孫のおもちゃの修理は天下一品」。女王からナイトの称号を受けたことよりも、トムさんの素朴な人柄を伝える記事に目がとまり、その訃報に、しんみりしたものでした。
「キャプテン・トム」ほど脚光を浴びなくとも、イギリスのメディアには、コロナで亡くなった人の「顔」と「物語」が多く登場します。
BBCニュース ウエブサイト「Coronavirus: Your tribute to those who have died」
公共放送BBCは、ウェブサイトに“Coronavirus: Your tribute to those who have died”という特設ページを開設。亡くなった750人の写真と、家族や友人が寄せたメッセージを掲載しています。それぞれの写真が順番に大写しになる仕掛けとなっていますが、中でも目を引くのは「全員をご覧いただくには312時間かかります」との注釈です。「世界最悪水準となったイギリスの犠牲者10万人を超える」と、原稿に書いた一文の持つ重みに、はっとさせられました。
9月15日付ガーディアン紙 「Lost to the virus」
また有力紙「ガーディアン」も“Lost to the virus”というタイトルの連載を組んでいます。例えば、2020年9月15日に掲載されたメルビン・ケネディーさん(67歳)。ジンバブエを逃れイギリスにわたり、ロンドンバスのドライバーとして働きながら家庭を守り、最愛の妻を病で亡くした後には、残された2人の娘に愛情を注いだ男性の人生が、見開き4ぺージにわたってつづられています。同時に、十分な感染対策が取られず、多くの犠牲者が出た公共交通機関の勤務の過酷さもあぶり出しています。
このようにイギリスのメディアは、大半の人たちの名前を出して報じていますが、その意図はどのようなものなのでしょうか。私はある出来事を思い出しました。それはイギリス人フォトジャーナリスト、ポール・コンロイさんをインタビューした時のことです。コンロイさんは、サンデー・タイムズ紙の記者マリー・コルビンさんと、2012年、内戦下のシリアに潜入取材しました。滞在先に撃ち込まれたロケット弾でコルビンさんは亡くなり、その物語はのちに映画化されました。コンロイさんは、人間は単なる数ではない、といって紛争地を取材し続けたコルビンさんの思いについて「ニュースを常に人間化(humanize)しようとしていた」と説明してくれました。「家族とか子どもとか、おじいちゃんとか、読者が、自分の身近な人に置き換えられて初めて思いを寄せられる。そのことで、シリアでの悲劇を、何とかしてやめさせる方法はないかと思う人が多くなることを願っていた」と。
確かに記事は、具体的な情報があったほうが記憶に残るようになるし、のちのち振り返ったときにも、検証可能なものにもなります。一方で、日本で見られるように、取材を受けた人が中傷や差別を受けることもあり、被害から人々を守るメカニズムが十分でないのも事実です。実名報道が一般的なイギリスでさえ、「キャプテン・トム」の家族はネット上での誹謗中傷に苦しんだと明らかにしています。また、ガーディアンの記事でも、「個人的な情報を削除し、置き換えました」と発行後に修正した記事もあり、プライバシーとの難しいバランスを模索しながら取材していることが容易に想像できます。
正解はあるのだろうか、と思いながら、ふとテレビに目をやると、ワイドショーがコロナの変異種で亡くなった人の話を伝えていました。人のシルエットのアイコンに、「70代、男性、渡航歴なし」のキャプション。亡くなった方はどんな人生を送り、どんな夢を持っていたのかな・・・そんな思いが頭をよぎります。