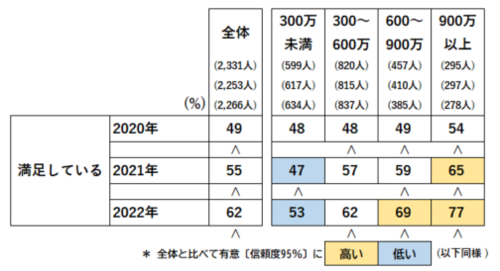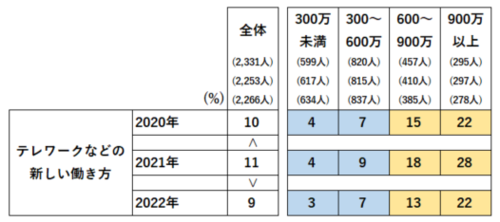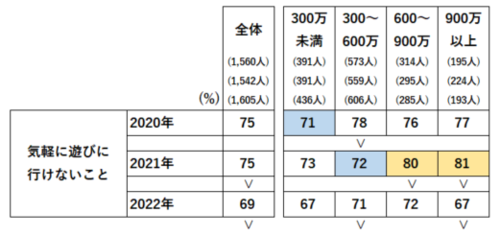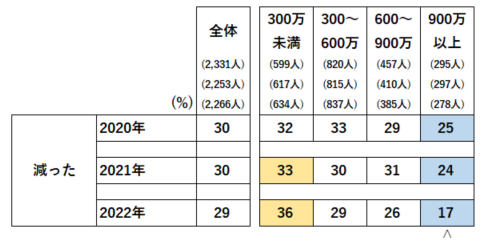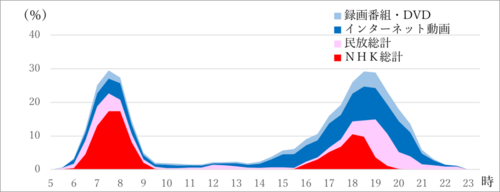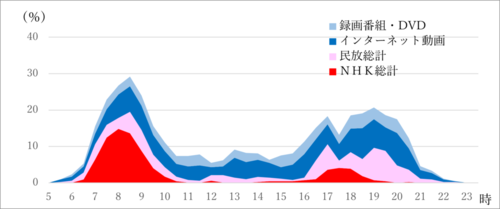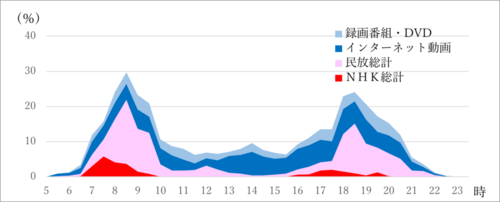NHK放送文化研究所 研究主幹 島田敏男
昨年末に強制捜査に着手した東京地方検察庁特捜部は、関東で正月の松があける7日に池田佳隆衆議院議員(安倍派)を政治資金規正法違反容疑で逮捕しました。特捜部は池田容疑者が収支報告書の不記載や虚偽記載によって得た裏金の額が多いことや、証拠隠滅の疑いを把握したことから逮捕に踏み切ったと伝えられています。
 逮捕された池田佳隆衆院議員
逮捕された池田佳隆衆院議員
この問題では、最大派閥・安倍派の歴代事務総長経験者などが、次々に東京地検から任意の事情聴取を受ける事態となりました。自民党の政治とカネを巡る問題、とりわけ規正法のもとで企業献金に代わる方法として温存されてきた「パー券売り」にメスが入ったことは画期的です。
ルールを守っていればまだしも、永田町の相場で1枚2万円のパーティー券をどこに大量に買ってもらい、どのように使ったかが闇の中に隠されたままであることが許されるのかという問題です。
政治資金として集めた金は課税対象にならないという特典は、「議会制民主主義を育てる財源」だからというのが政治資金規正法の建前です。つまり国会議員という「選良」が行うことだからという、性善説に基づく仕組みなのです。それが無残に裏切られ裏金化されていた点に、国民の強い怒りが噴出したのは当然です。
この国民の怒りの声を背に受けて、検察当局も「公開ルールの順守を怠った形式犯」では済まされないという判断に至ったと見ることができます。億単位の賄賂が介在するような贈収賄事件とは異なるにしても、政治の信頼を失墜させる罪の重さに異例の捜査が行われたのは当然でしょう。

そして捜査が続く1月12日(金)から14日(日)にかけてNHKの月例電話世論調査が行われました。昨年12月の調査では、自民党が2012年に政権に復帰して以降の11年間で最も低い「支持率23%」を記録していました。
☆あなたは岸田内閣を支持しますか。それとも支持しませんか。
| 支持する |
|
26%(対前月+3ポイント) |
| 支持しない |
|
56%(対前月-2ポイント) |
昨年後半から下降傾向が続いていた内閣支持率は、いったん下げ止まった形です。しかしながら統計上は支持も不支持も前月からの変化に有意差はありません。つまり誤差の範囲内の変化だということです。
今回は能登半島地震という大きな自然災害があり、被災地の救援や復旧にあたる政府の対応に期待が寄せられていたという事情もあります。
☆あなたは能登半島地震への政府のこれまでの対応を評価しますか。評価しませんか。
評価する声が過半数に上り、岸田内閣に対するアゲインストの風を和らげている面もうかがえます。
とはいえ、自民党が政治とカネの問題で失った信頼を回復するのは容易なことではないでしょう。次の数字を見れば一目瞭然です。
☆派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、自民党は「政治刷新本部」を立ち上げ、再発防止策などの検討を始めました。これが、国民の信頼回復につながると思いますか。つながらないと思いますか。
つながらないと回答したのは与党支持者で66%、野党支持者で88%、無党派で85%となっています。与党を支持する人たちでも、厳しい受け止めが3分の2に上っています。
 自民党「政治刷新本部」(1月11日)
自民党「政治刷新本部」(1月11日)
「政治刷新本部」に対しては、派閥が生んだ問題を派閥均衡のようなメンバーで議論するのは陳腐だという指摘や、パーティー券の裏金を受け取った安倍派議員も含まれているのはいかがなものかといった批判が出ています。
☆あなたは政治資金規正法を改正し、ルールを厳しくする必要があると思いますか。必要はないと思いますか。
こちらについては与党支持者、野党支持者、無党派のいずれを見ても、ルールを厳しくすべきだという答えが8割から9割に上っています。
問題はパーティー券を購入した相手と金額を明らかにする徹底した情報公開と、事務所の会計責任者が違法行為をした場合に議員本人の責任も問う連座制の適用にまで踏み込むことができるかです。これが最低限のラインだと思います。
では今回の問題の土台にある自民党の派閥について、国民はどういう見方をしているのでしょう。
☆あなたは自民党の派閥のあり方についてどう思いますか。
| 今のままでよい |
|
5% |
| 存続させても改革すべき |
|
40% |
| 解消すべき |
|
49% |
自民党支持者が大多数を占める与党支持者では「存続させても改革すべき」が5割に達して多数ですが、野党支持者と無党派では「解消すべき」が5割超から6割に上っています。

派閥連合体として国会で多数派を形成し、長く政権を担当してきた自民党にとって、党内で競い合うことが活力の源だという従来の考え方を変えるのは簡単ではなさそうです。ただ、それでは自民党が自ら失うことになった信頼の回復をどこまで図ることができるかも不透明です。
一方で、派閥は残しても政治資金規正法のルール強化が進むことになれば、これまでのように表に出さない政治資金の確保は困難になります。野党議員と比べ、地元に大勢の私設秘書を抱えて議席を守ってきた活動スタイルにも影響が出るでしょう。
あれやこれや考えると、直ちに政権交代が起きるような展開はないにしても、自民党の信頼や資金集めがやせ細っていくことを懸念する声は消えそうもありません。ある自民党の閣僚経験者は「次の参議院選挙は来年2025年夏。衆議院の任期満了は2025年10月。それまでには潮目の変化があるだろう」と期待交じりで語ります。
野党がバラバラだから怖くない、というのが自民党関係者に深刻な危機感を生じさせていない最大の要因でしょう。それが岸田自民党全体の「鈍感力」の核になっているように見えます。しかし、信頼回復のないまま党としての勢いがやせ細る展開になるならば、少数与党に甘んじ、結果として野党側の結集を促す事態も否定できません。

今年9月の自民党総裁選への対応も含めて、岸田総理がどういう展開を目指そうとしているのか現状でははっきりしません。
まず当面は、今月26日からの通常国会前に「政治刷新本部」が打ち出す最初のメッセージを国民がどう受け止めるかです。これが最初の関門として立ちはだかっています。
 |
島田敏男
1981年NHKに入局。政治部記者として中曽根総理番を手始めに政治取材に入り、法務省、外務省、防衛省、与野党などを担当する。
小渕内閣当時に首相官邸キャップを務め、政治部デスクを経て解説委員。
2006年より12年間にわたって「日曜討論」キャスターを担当。
2020年7月から放送文化研究所・研究主幹に。長年の政治取材をベースにした記事を執筆。
|