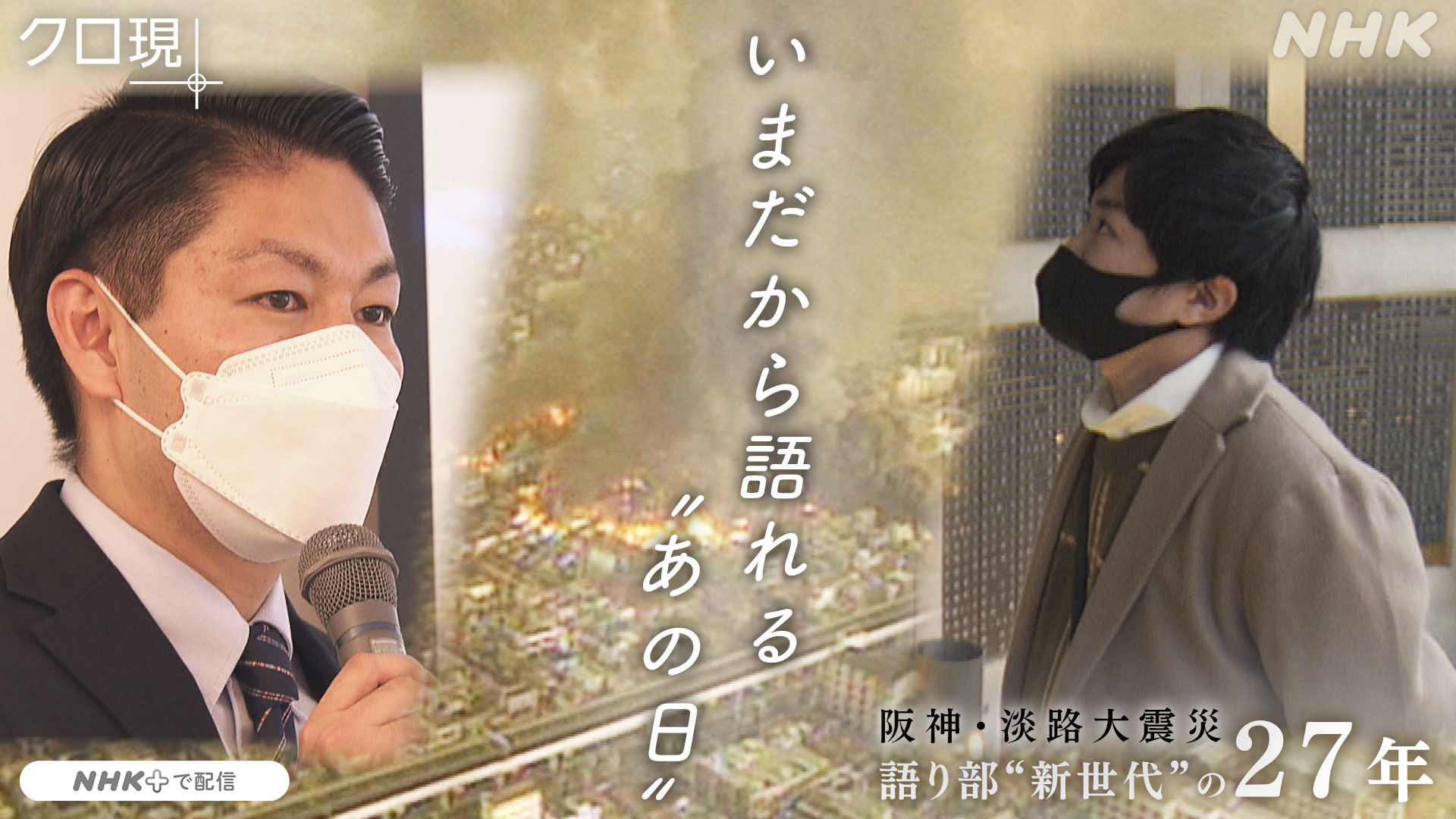
いまだから語れる“あの日” 阪神・淡路大震災 語り部“新世代”の27年
阪神・淡路大震災当時、子どもだった世代が震災体験を語り始めている。7歳の自分をおいて逝った両親を「恨んできた」という男性。この冬、学校で初めて震災体験を話す。弟2人の焼死体を目にし、その後弟の存在を「隠し続けてきた」という男性は、語り部となり消防団の活動に力を入れている。あの日に生まれた男性は、生きる意味を探し続けてきた27年間を語る。悲しみと向き合いながら、懸命に語 ...
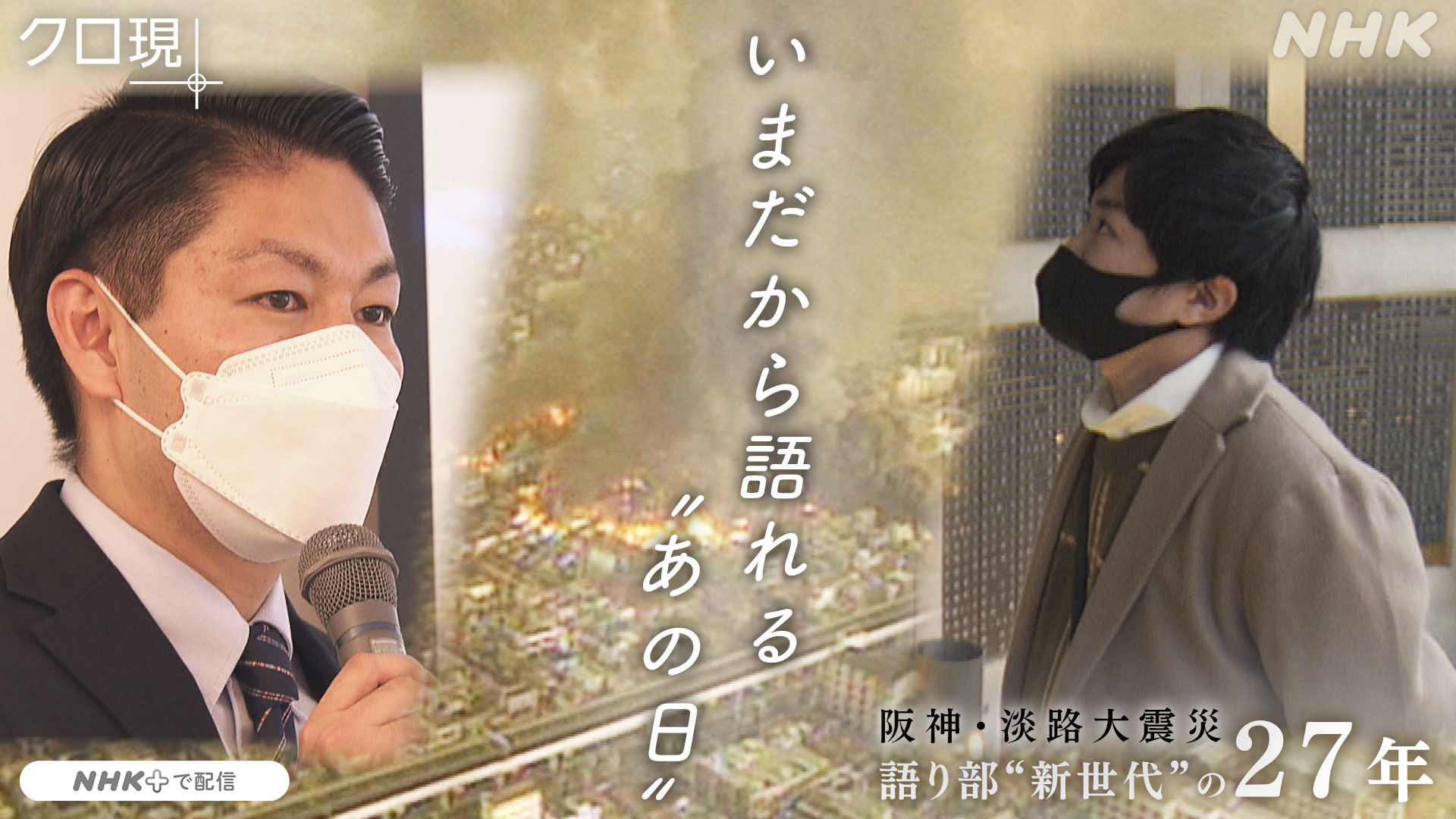
阪神・淡路大震災当時、子どもだった世代が震災体験を語り始めている。7歳の自分をおいて逝った両親を「恨んできた」という男性。この冬、学校で初めて震災体験を話す。弟2人の焼死体を目にし、その後弟の存在を「隠し続けてきた」という男性は、語り部となり消防団の活動に力を入れている。あの日に生まれた男性は、生きる意味を探し続けてきた27年間を語る。悲しみと向き合いながら、懸命に語 ...

阪神・淡路大震災から20年、NHKではこれまで継続的に行ってきた被災者・遺族へアンケートを改めて実施。寄せられた928の回答からは、20年経った今被災者が直面する現実が浮かび上がっている。震災当時“働き盛り”だった世代が、いま経済的な困窮に陥り、さらに“心の復興”も実感できずにいるのだ。当時、“働き盛り”世代は、自力で自宅や事業を再建することを求められた。定年前後の年 ...

16年前の阪神・淡路大震災の時、発生した負傷者は4万3千8百人。しかし多大な犠牲者と復興の陰に隠れ、社会的な注目が集まらなかった。去年、兵庫県が、震災で負傷し、障害を負った人たち328人を対象に実態調査をしたところ、16年たった今も、苦しみを抱える人が数多くいることが分かってきた。大災害という異常事態の中、生活再建と治療を迫られ、支援も無く孤立してきた実態が浮き彫りと ...

阪神・淡路大震災の後、家を失った人たちのために建てられた災害復興公営住宅。現在、2万5000世帯、およそ4万2000人が暮らしている。自力再建が難しい高齢者が多数入居したため、高齢化率は46%(神戸市)に及んでいる。住民の多くは抽選によって、住み慣れた土地を離れ、今の住宅に入居した。そのため、今も孤立する高齢者がいる。 しかし行政では震災10年を機に、住民が自分たち ...

この1月17日で阪神淡路大震災から7年。 街の復興が進んだ被災地 神戸では、震災の記憶の風化が心配されている。こうした状況に危機感を持った被災者たちが、震災の記憶を伝える様々な活動を始めた。 被災者自らが当時の体験を話す語り部グループの取り組み。震災で傷ついた商店街のアーケードをモニュメントとして街に残そうとする商店主たちの試み。番組では、震災の悲しみを乗り越えて ...

25万棟の家屋が大きな被害を受けた阪神大震災。家を失った人々は、十分な支援がないまま、自宅の再建を迫られた。震災から6年、被災した人たちは、住宅ローンなど多くの借金を抱えて苦しんでいる。去年10月におきた鳥取県西部地震では、被災地ですでに住宅の再建が始まっている。鳥取県は、住宅を失った世帯に300万円の支給を決定し、成果が出ている。突然の災害で家を失った時、国や自治体 ...

5年前の阪神大震災は、木造住宅の耐震性を問い直すきっかけとなった。横浜市が行った耐震診断では、70%を超える家が、大地震が来ると危険だと判定された。いま住んでいる家は安全か、どうしたら地震に強い家ができるのか、木造住宅の耐震性を徹底検証する。

阪神大震災で多くの中小企業が深刻な被害を受けた。あれから5年、厳しい経営を迫られる被災地の中小企業の実情と課題を検証する。

阪神・淡路大震災から4年になる。仮設住宅そして被災者向けの公営住宅では、今著しい高齢化が起きている。 今晩は、震災から4年、被災地が今抱える高齢化問題に迫る。

阪神大震災で被害を受けたマンション再建の問題点を探る。

6400人余りの人が亡くなり、25万戸が全半壊するという大きな被害が出た「阪神大震災」から、明日で丸2年を迎える。仮設住宅は2年で解消する予定になっていたが、現在も3万7千世帯、およそ7万人の人が不自由な生活を強いられている。今夜は、ポートアイランド第2仮設住宅から、中継で被災者の現状を伝える。

阪神大震災で、突然かけがえのない肉親を失った多くの人々。1年以上経った今もその死が受け入れられず、悲しみのあまり心や身体の不調を訴える人も出ている。 どうすれば心の傷を癒すきっかけがつかめるのか、周囲の人たちはどう接すればよいのか、被災地で始まった心のケアへの取り組みをリポートする。

阪神大震災では住宅20万棟が全半壊したが、その再建は進んでいない。借地や借家の権利関係や建築基準などの法律が、住宅再建の壁になっている。震災から1年を迎える被災地の苦悩をリポートする。

1年前の阪神大震災で570人のこどもたちが親を失った。地震は彼らの生活を大きく変えた。心の深い傷を乗り越えようと懸命に生きている震災児の姿を追う。

今夜は、1年前の阪神大震災で浮き彫りになったヘリコプターによる救急医療である。救急治療を必要とする負傷者が数多く出た阪神大震災。命を救うために一刻を争う中で、最初の3日間でヘリコプターによって運ばれた患者はわずかであった。なぜ、ヘリコプターは十分活用されなかったのか、見直しが始まっているヘリコプターによる患者の搬送をめぐる課題を探る。

神戸を中心に大きな被害をもたらした阪神大震災。被害の実態を把握するのに時間がかかり国の救援活動が遅れたと指摘された。また家族や知人の安否をなかなかつかめない人も大勢いた。情報不足の克服に向けた新しい取り組みを伝える。

神戸市は8月20日で小中学校などの避難所を閉鎖し被災者に対する食事の支給を打ち切ることにした。被災者も避難所を出て仮設住宅に移りたいのだが郊外の仮設住宅では通勤や通院が不可能、近くのは競争率が激しくて当選しない。近くの1Kの間取りではこどものいる家族には狭すぎる。実態のリポートと被災者へのアンケートそれに神戸市長へのインタビューで構成。

阪神大震災から5か月、被災地では復興が進む一方で、今もおよそ2万5千人の人々が避難所での生活を余儀なくされている中、将来に絶望した被災者の自殺があいついでいる。せっかく生き残った人が、なぜ死を選ばなければならないほど追い込まれていったのか、その背景を探る。

危険箇所1800…阪神大震災の被災地で土砂くずれによる二次災害の危険性が指摘されている場所の数である。しかし、自治体による防止対策が進んでいるのは、わずか60箇所に過ぎない。住民の不安が高まるなか、どうやって梅雨期を乗り切ればいいのか、神戸市六甲山付近を中心に懸念される土砂災害の危険性を検証する。

阪神大震災は地域の医療にも大きな打撃を与えた。地震から3か月、全国からの医療ボランティアがつぎつぎと被災地から撤退している一方で、大きな被害を受けた医療機関の再建は進んでいない。生まれつつある医療の空白がもたらす問題に迫る。

阪神大震災で父親、母親或いは両親を失った、いわゆる震災遺児は500人以上にのぼることが分かった。大震災から2か月たった今、親を失った子供たちは精神的、経済的いたでにどう立ち向かおうとしているのか。そして何を支えに生きていこうとしいるのか。親を失った子供たちが直面している現実を伝える。

大きな被害をもたらした阪神大震災。この大地震で、どこの活断層がどのように動いたかなど、地震についての調査が進められている。 今夜は、新たに明らかになった事実を中心に、活断層や地盤が揺れるメカニズムを探っていく。

神戸市は、阪神大震災で被害の大きかった六つの地域で、災害に強い街づくりをめざしての復興計画案を発表している。しかし、計画に基づいた区画整理や再開発計画の実行に当たっては、土地や建物について個人の権利が制限されることになる。街の再建はどのように進められようとしているのか、その波紋を追う。
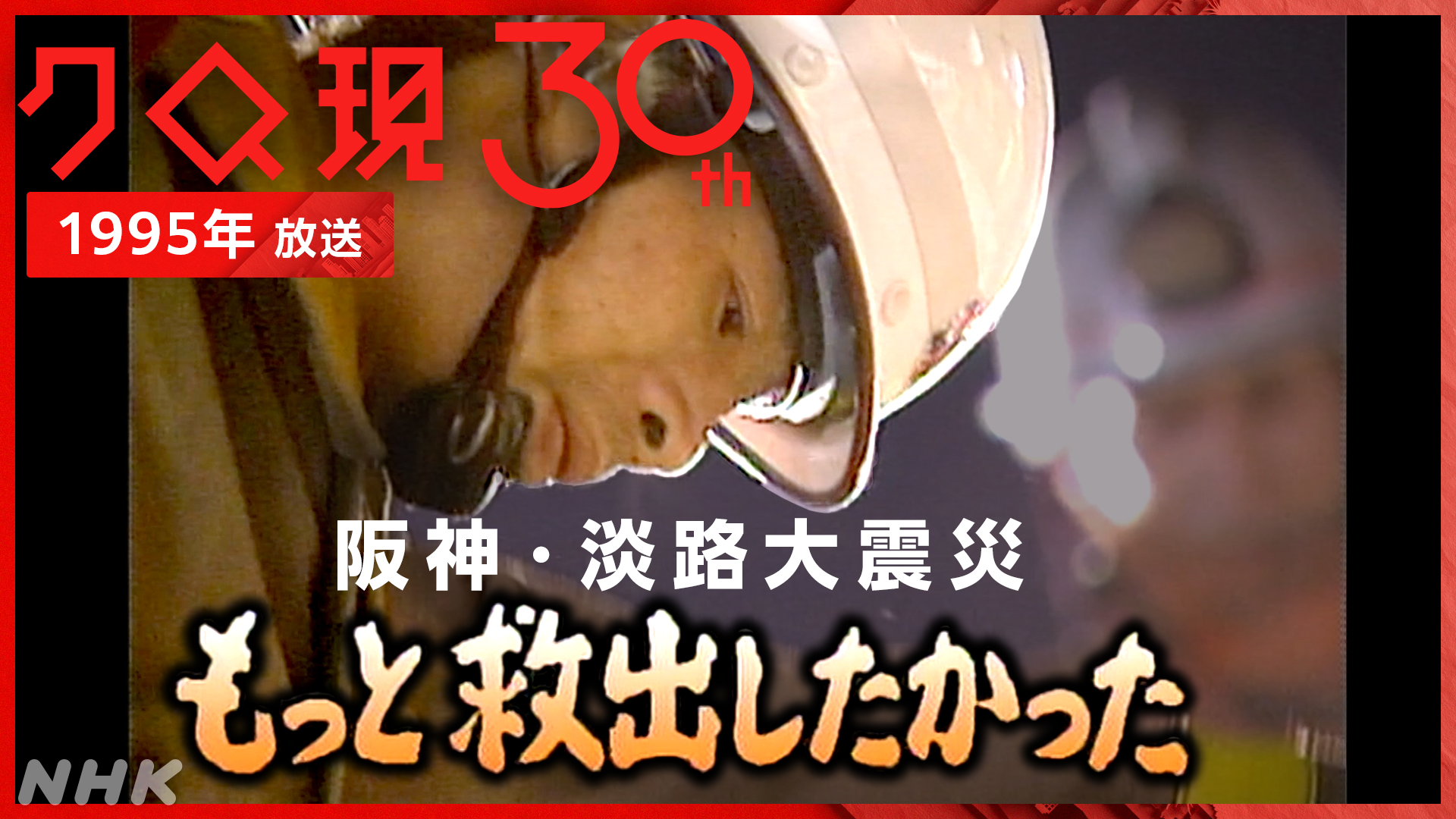
今夜は神戸市消防局の署員たちが書いた手記を基に阪神大震災でどのような救助活動が行なわれたのか見る。阪神大震災では多くの人たちが壊れた家やビルの下敷きになった。その救出に当たった消防署の隊員たちが震災から一ヵ月半過ぎようとしている今、手記を書き残そうとしている。 番組では、がれきの中で隊員たちは生と死の場面にどう立ち向かい、どのような壁にぶつかったのか検証する。 ...

阪神大震災の被災地では今、壊れた家屋や傾いたビルの取り壊しが行なわれている。しかし住民にはそれぞれ様々な事情があり、取り壊しが簡単には進まないのが現状だ。被害の激しかった地域で、復興に向かう人たちが抱える問題について考える。

阪神大震災で命は助かったものの、長引く不自由な避難所暮らしで体が弱り入院するお年寄りが相次いでいる。しかし病院は満床状態が続き、適切な治療が受けられない人も多い。被災地の高齢者が直面している厳しい状況を伝える。

阪神大震災では、地下にも被害が続出した。神戸高速鉄道の駅では、天井を支える柱が長さ100メートルにわたって折れ、駅が崩れるという大きな被害を受けた。地震には強いと言われてきた地下で、なぜこのような被害が出たのか。今夜は、地下鉄崩壊の謎に迫る。

今夜は阪神大震災で壊滅的な被害を受けた地場産業を取り上げる。全国一のケミカルシューズの生産地神戸市長田区では、靴製造メーカーの大多数が操業不能に陥った。工場や機械を失い資金ぐりがつかない苦しい経営者が数多くいる。地場産業への深刻な被害は何をもたらすのか。再建は可能なのか。再建に向けて立ち上がろうとしている企業を取材。

今夜は、阪神大震災で被災した子供たちを取り上げる。阪神大震災で、大切な肉親を奪われ家や教科書を失った子供たちが大勢いる。また被災地では、まだ授業が再開されない学校も数多くあり、子供たちは厳しい環境の変化の中での生活を余儀なくされている。番組では、長引く被災地の生活の中で、子供たちはどのような暮らしをし、何を求めているのかを探っていく。

大震災で全壊したり被害を受けたりした家屋は10万棟にのぼる。壊れた家やマンションを再建出来るのか。また、借りていた家や土地はどうなるのか。我が家を取り戻すため被災者の人たちが直面する問題に迫る。

阪神大震災に見舞われた方々に、何かしてあげたい。被災地に集まった大勢のボランティアが、今不自由で不安な生活を強いられている被災者を支えている。また、被災者同志で助け合い、いたわりあう姿も数多く見られる。 今夜は、苦しみに直面した被災地での思いやりとボランティアのあり方を見る。

阪神大震災では、大勢の被災者の消息がわからなくなった。連絡がとれないためである。肉親や友人の安否を気遣いその行方を探し求める家族や友人の姿を追う。

大地震が全国の物資のおよそ10%が通過する神戸を直撃。高速道路をはじめ鉄道、神戸港が大きな被害を受け、その影響はアジアなどへも及び始めている。物流の混乱を企業はどのように乗り越えようとしているのか、その現状をリポートする。

阪神大震災で高速道路や新幹線の高架橋がなぜ数多く落下したのか新しい事実が明らかになった。大きな地震が起きても心配はない安全だと思われていた日本の高速道路や新幹線の高架橋が多くの箇所で破壊された。破壊はなぜ発生したのか。 番組では、新しい調査結果に基づいてその原因を検証する。

1月17日に発生した「阪神大震災」は、人々の生活を根底から崩した。現在も、避難所で暮らす人々は29万人余り。水道やガスといった生活に欠かせない都市機能が寸断されている中で、多くの人たちが生活の知恵を生かし協力しながら、なんとか日々をやりくりしている。 番組では、困難に立ち向かう人々の姿を、現地からの報告を交えて伝える。

阪神大震災の際に火災が広がったのはなぜか、何回も火災が起きたのはなぜかを、被災者や消防関係者の話をもとに検証する。

阪神大震災で、最大でマグニチュード6にもなると予想されている余震。いったい、いつ、どの程度の余震が起きるのか、不安を抱えての復旧活動が続けられている。崩れかけた家やひびの入ったマンションが倒壊する危険はないのか、立ち入っても大丈夫なのか、専門家による建物のチェックが始まった。余震による二次災害をどう防ぐのか具体的に見ていく。

現在、死者3597人、行方不明者659人。一昨日未明、阪神地区を直撃したマグニチュード7.2の地震で犠牲になった多くの人が、倒壊した建物の下敷きになった。建物の倒壊はなぜ多発したのか、また、人々がなぜ逃げ出せなかったのかを探る。