
攻防!ハンバーガーの値段 業界の“舞台裏”で何が
日本は賃金と物価の好循環を生み出せるのか?身近なハンバーガーの価格をめぐる“攻防”から、そのヒントを探ります。かつてデフレの象徴とも呼ばれたハンバーガーの価格は、ここ数年急上昇。ある大手チェーンは好調な業績を背景に、この春大幅な賃上げに踏み切りました。一方、郊外の店舗では今も比較的安い商品が売れ筋となるなど、個人消費が力強さを欠いているとの指摘も。好循環が実現するには ...

日本は賃金と物価の好循環を生み出せるのか?身近なハンバーガーの価格をめぐる“攻防”から、そのヒントを探ります。かつてデフレの象徴とも呼ばれたハンバーガーの価格は、ここ数年急上昇。ある大手チェーンは好調な業績を背景に、この春大幅な賃上げに踏み切りました。一方、郊外の店舗では今も比較的安い商品が売れ筋となるなど、個人消費が力強さを欠いているとの指摘も。好循環が実現するには ...

今、学校の食事が揺れています。1食250円ほどで提供されてきた小学校の給食は、物価高の影響で鶏むね肉やもやしなどの安価な食材を多用。広島では調理を担っていた民間事業者が破綻し、高校の食堂や寮で食事がストップする事態に。そうした中、給食の費用をユニークな予算で補助し、学校給食を支えると同時に地域づくりに活用する自治体も現れました。給食費無償化の動きも広がる中、子どもの“ ...

全国各地で進められている再開発に異変が!?高層ビルの建設で“新たな面積”を生み、その売却で地権者が“持ち出しゼロ”で街を更新できるはずが・・・。新幹線の開業にあわせ“100年に一度”の再開発に乗り出した福井市では想定外の“費用負担”に直面。さらに再開発によって人口が急増するさいたま市が見舞われている“しわよせ”とは―。地域にメリットをもたらすべき再開発、思わぬ“負荷” ...

ガソリン価格は今後どうなっていくのか?過去最高値を更新したレギュラーガソリン価格は国の補助金延長によって値下がりを始めたが、家計への負担を気にする声は今も続いています。原油価格は高止まりを続け、既に6兆円余が計上された補助金はさらに膨らんでいく可能性も。中東情勢の影響は?公平な税負担のあり方は?化石燃料への依存から脱することができず目の前の対応に追われる日本、この危機 ...

都内のある家庭ではポータブルの太陽光パネルと蓄電池で電気代が去年の半額に。屋根にパネルを設置した賃貸マンションも人気です。今、太陽光発電は蓄電池と組み合わせた「自家消費」がトレンド。東京都では大手事業者にパネル設置を義務化。沖縄・宮古島では740世帯のパネルと蓄電池を一括管理し、電力を安定させ台風にも備える先進的な取り組みまで進んでいます。費用対効果は?廃棄の問題は? ...

卵高騰の原因は、円安にウクライナ侵攻などによるエサ代の高騰に鳥インフルエンザの感染拡大。専門家によると、値段は元のようには戻らないおそれが出てきているといいます。さらには卵の生産の土台を揺るがす、鶏卵業者の廃業が後を絶ちません。なかには活路を見いだすために、生卵を海外に輸出する業者も!安価で安全で味も優れていて高い評価を得ている日本の卵。これからもおいしい卵を食べ続け ...

食品の値上げが相次ぐ中、食費の節約志向が高まっています。そこに意外な落とし穴が。食事がパンや麺類など炭水化物に偏り、体や筋肉を作るたんぱく質が不足するなど、いつの間にか“低栄養状態”に陥る人が少なくないことがわかってきました。さらに持病を悪化させる危険も…。“値上げ時代”、私たちは節約をしながら、どう健康を守ればいいのか?必要な栄養を確保する簡単なコツとは?専門家と具 ...
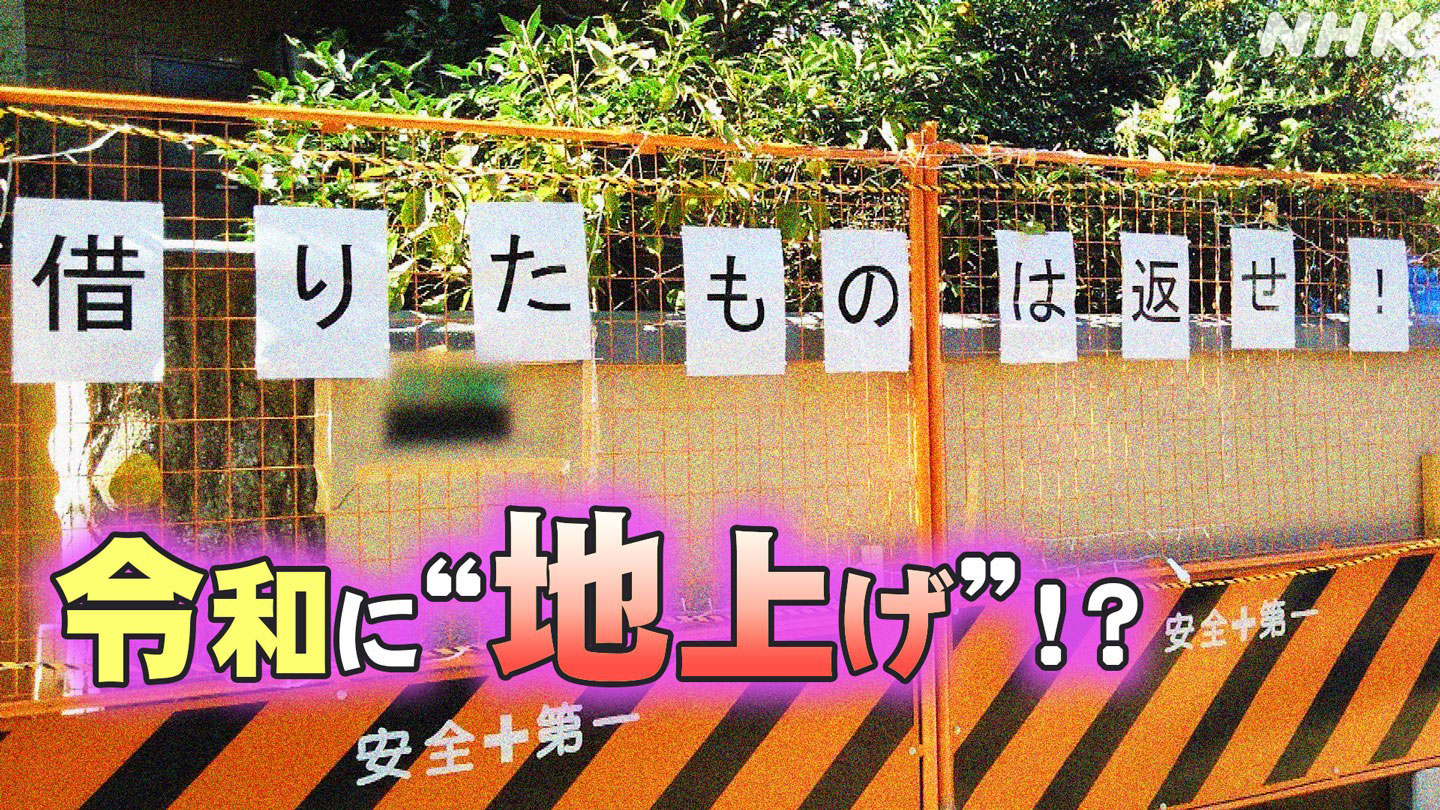
バブル期に大きな社会問題となった悪質な“地上げ”が今、形を変えて各地で相次いでいる―。情報の真相を独自追跡。“地上げ"にまつわるトラブルの相談を受ける弁護士たちは、かつてとは異なる“新たな手口”に直面していました…。なぜ、令和の時代に地上げが?不動産業界の関係者たちが明かしたのは、現代に地上げが求められる“理由”でした。都市部を中心に価格高騰が続く不動産業界。その裏側 ...
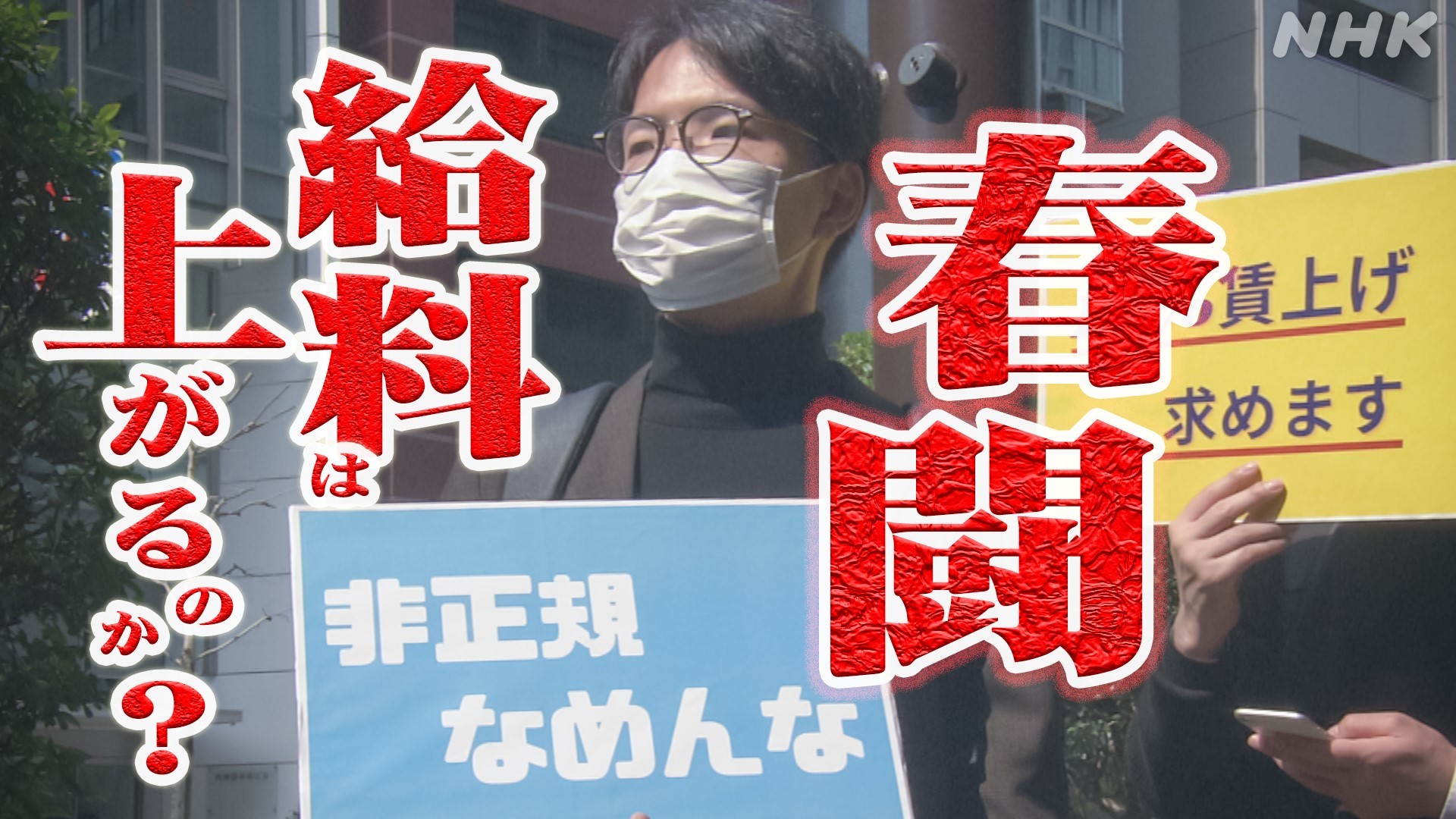
3月15日は集中回答日でした。大手企業を中心に賃上げムードで、賃上げ率は3%台を超える勢いです。しかし、実質賃金はむしろ下がっており、働く人の7割を抱える中小企業ではベアを予定していないという企業も少なくありません。そうした中、非正規雇用の従業員たちも立ち上がり、“横でつながる非正規春闘”という新たな動きも出始めました。物価高が続く中で、私たちの賃金はどうなるのか。そ ...

今、使い終わった食用植物油を分解しSAF(サフ)と呼ばれる航空燃料に作り変える動きが広がっています。環境負荷が低いとされ、この燃料を使わないと海外の空港に離発着ができなくなる事態も懸念されています。一方、SAFの原料となる廃食油の争奪戦が世界で激化。廃食油を飼料にしてきた日本の畜産業界に影響が。環境大国ドイツでは脱・飛行機が加速、寝台列車が再注目され始めました。廃食油 ...
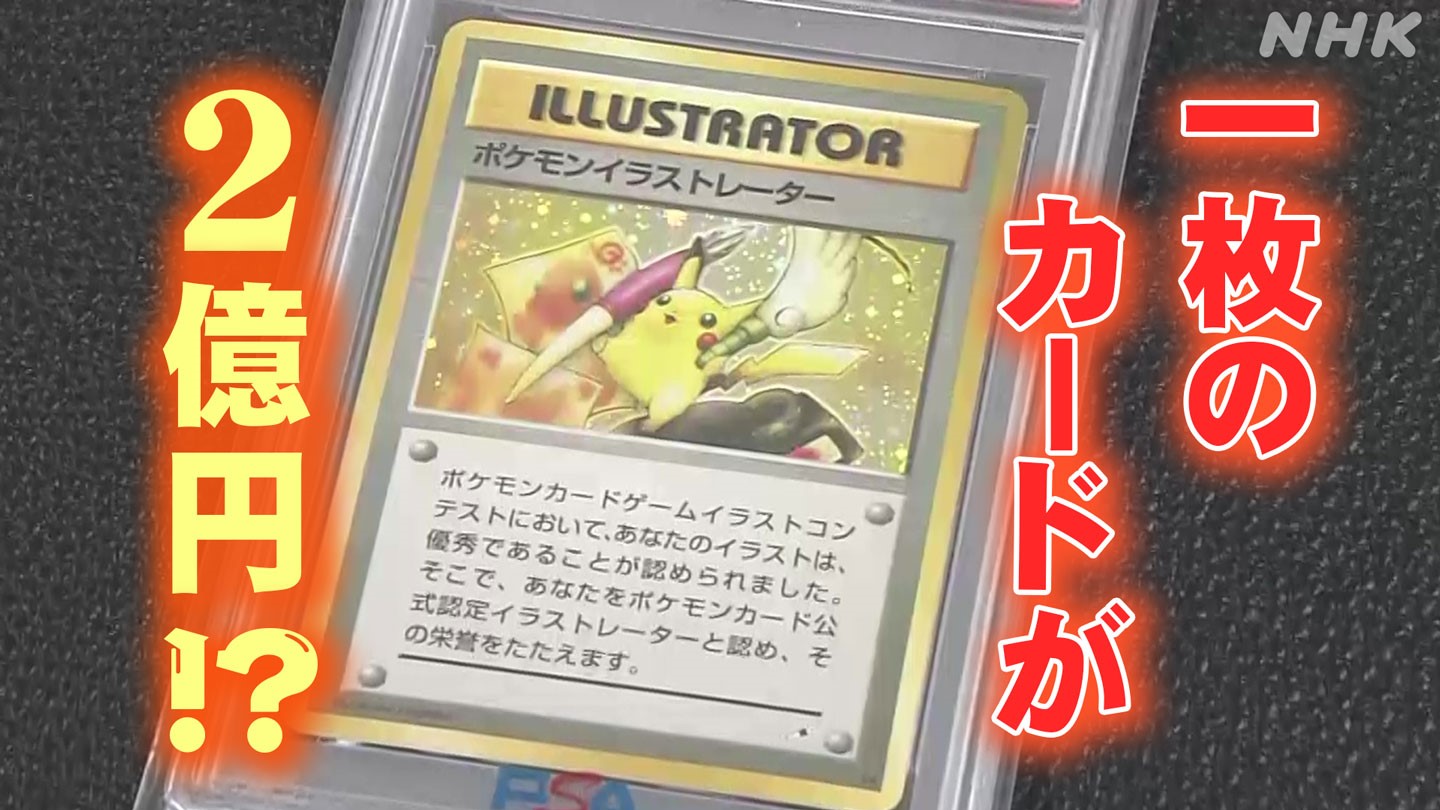
1枚で数億円のものまで!?子供も大人も楽しめるゲーム「トレーディングカード」、略して「トレカ」。その価格が今、驚愕の高騰を見せています。中古市場では、いまや数万円のカードは当たり前で、億単位の値段がつくものも。カードの売買で巨額の利益を稼ぎ出す"トレカ投資家"まで現れました。秋葉原では、コロナ禍で生じた空き店舗に専門のショップが次々と出現し…。価格高騰の裏にいったい何 ...

日本の国民食「カレーライス」に大異変が起きています。外食カレーの全国平均価格は、過去最高の721円に上昇。家庭用のルーの値上げも止まらない。背景には、世界規模で進む原材料費の高騰があります。異常気象によるインドのスパイスの収穫減、ウクライナ危機によるブラジルの鶏肉争奪戦、世界的なコンテナ船物流の混乱…。5,000品目以上が値上げされる2月、ひと皿のカレーから、驚きの世 ...

身近な牛乳をめぐって、いま“異変”が―。私たちが直面する牛乳・乳製品の値上げ。背景にあるのは世界的な飼料高騰です。エサを輸入に依存してきた日本の酪農はかつてない危機に直面。「生き延びられないかも」と語る大規模酪農ファーム経営者。1頭10万円だった子牛が500円に…。廃業せざるをえない若き酪農家たちも。生産のために必要な物資の多くを海外に依存する現実、そして価格に転嫁で ...

東京は今、200以上の高層ビルが建設される大改造のまっただ中にあります。渋谷では100年に1度の大規模再開発が進行中。東京駅周辺ではロボットが行き交う未来型ビルが完成します。虎ノ門でも外資企業を呼び込もうと国際競争力を兼ね備えた街作りが行われています。しかし高層ビルの建設ラッシュには、オフィスの空室率上昇やさらなる温暖化のリスクもあります。東京は今後、どのような都市に ...

12月から始まる“冬の節電要請”、相次ぐ電気料金の値上げ、実現が急がれる脱炭素社会・・・。エネルギーをめぐる状況が激変する今、活発化しているのが“原発活用”に向けた動きです。政府は、原発事故のあと繰り返し「想定しない」と説明してきた原発の新増設について、年末までに検討すると発表。「既存原発の再稼働」「運転期間の延長」などはどうなるのか?私たちの暮らしに直結するエネルギ ...

2夜シリーズ「異例の物価高」。第2夜は、物価高を乗り越えるためには、何をすればいいのか考えました。鍵のひとつとなるのが、賃金の値上げです。政府は、新卒の給与をアップさせた企業に対して法人税を減税する「賃上げ促進税制」の適用拡大を検討。企業が蓄積しているお金“内部留保”が過去最高に達するなか、賃上げは実際に取り組むことはできるのか。経済ジャーナリストの荻原博子さんや成田 ...

10月に6700品目以上の食料品が値上げされ、家庭や企業を直撃。異例の物価高は、いつまで続くのか、どうすれば乗り越えられるのか、2夜連続で特集しました。第1夜は、物価高の原因を苦境であえぐ現場から探りました。食料品・飲食業界では、食用油の原料の需要が高まっているだけでなく、原産国が輸出制限に踏み切ったことで価格が高騰。“物価高倒産"は、過去最多を更新しています。物価高 ...

猛暑の夏や、寒さ厳しい冬、突然「電気」が来なくなったら…。原油や天然ガスなどの資源高の直撃を受けて“新電力”事業者が相次いで撤退し、前触れなく「サービス停止」を突きつけられる個人や事業者が急増しています。さらに火力発電所が減少し、この夏や冬に「計画停電」が行われる可能性まで議論に。なぜ、いま電力が足りないのか?不足はいつまで続き、暮らしにどんな影響が?日本の“電力クラ ...

20年ぶりの急速な円安に高騰していく物価・・・。日本経済をこれまでにない急激な変化が襲っています。私たちは、この波にどう立ち向かえばよいのか。旅行、日常生活、そして資産の3つの分野の第一人者が独自の視点で視聴者の質問に徹底的に答え尽くします。海外旅行先の定番・ハワイでは物価高であらゆるモノの値段が高騰。ハワイの免税店では日本で普通に買った方が安いという不思議な現象が起 ...
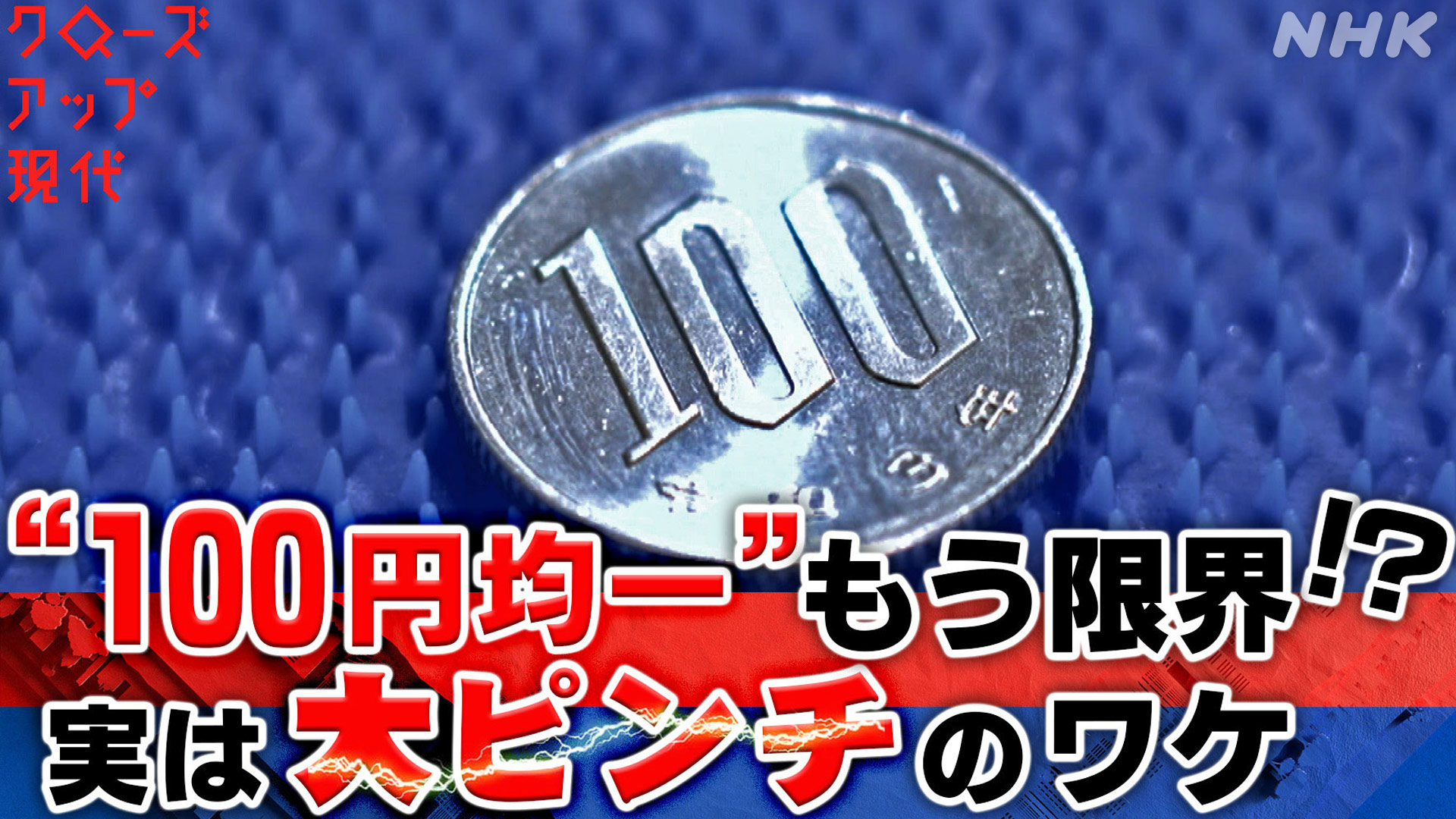
コロナ禍でも成長を続ける100円均一ショップ。しかし今、そのビジネスモデルが存亡の危機に立たされています。物価や人件費の高騰で、いくら売っても100円では利益が出なくなっているのです。一方、消費者の「100円で買いたい」というこだわりは根強い。岐路に立つ大手チェーンの戦略は?ネットで話題の分解人が100円商品を徹底検証。そして、長年100均業界を支えてきた中国の驚くべ ...

まさに“値上げの春”。カップラーメン、ティッシュペーパー、ガソリン…かつてない勢いで食品や日用品・光熱費などの価格が引き上げられています。 スーパーとメーカーの間では価格をめぐる綱引きが勃発。このまま物価が上がり続けると、暮らしにどれほど影響が出るのか?そして、家計を守るカギの「賃上げ」は今後どうなるのか?

いま世界で現代アート作品の高騰が続いている。5月、アメリカの作家が製作した「ウサギの彫刻」がオークションにかけられ、存命作家史上最高額の100億円で落札されたのだ。アメリカでは、ギャラリー経営者や評論家、コレクターたちが協力して有望なアーティストを発掘し市場価値を引き上げるシステムが構築されていて、そこに世界の投機マネーが流れ込んでいるという。一方で中国は国が旗振り役 ...

「75歳以上には、保険で使える薬を制限すべきでは?」ある医師の“警告”が波紋を広げている。1回の点滴に100万円以上もするがんの新薬が保険適用されたため、何万人もの患者が使えば医療財政が破たんするというのだ。「年寄りを助けて未来の患者を見捨てるのか」「命を金ではかる気か」…医療現場や省庁、製薬会社、そして患者までも巻き込んだ議論が起こっている。私たちは望む薬を飲めなく ...

漁獲量の減少によって、アジやホッケなど食卓の魚の高騰がつづいている。原因とされるのは、海水温上昇など海の異変と乱獲。追い詰められた漁業者は、収入を確保するため小型魚や幼魚まで捕る「負のスパイラル」に陥っている。漁業復活には、資源を守ることが急務だ。今年、国は絶滅危惧種に指定されたクロマグロの幼魚の漁獲量を半減する規制を導入した。すでに多くの魚に漁獲規制を導入し、資源回 ...

じわじわと食品の価格が上がり続けている。今月1日に大手食品メーカー数社がパンやパスタなど小麦製品の値上げに踏み切ったのをはじめ、大豆、卵なども値上がり傾向にある。世界的な食料不足で輸入穀物が高騰しているのだ。背景には中国・インドなど新興国の需要急伸があり、国内の食品メーカーや畜産農家の間では、このまま穀物相場の「高止まり」が続くとの危機感が広がっている。そんな中、大手 ...

「このままでは10億円以上の赤字を飲み込むしかない。」建築用の鉄材を扱う業者が嘆く。今年に入り、鉄鋼の原料価格は去年の2倍以上に急騰。デフレも追い打ちをかけ、モノ作りの現場から悲鳴が上がっている。さらに、鉄の価格を決める国際ルールが根底から覆り、混乱が広がっている。これまで鉄の原料、鉄鉱石の価格は日本の鉄鋼メーカーと海外の大手資源会社の間の“話合い”で“年に1度”決め ...

北海道洞爺湖サミットで、温暖化や原油の高騰とともに主要議題に上る食糧高騰の問題。新興国の需要増加や投機マネーの流入に加え、食用のトウモロコシが自動車用のバイオ燃料の生産に大量に使われていることも原因だとされている。世界最大のトウモロコシ生産国アメリカでもバイオ燃料政策の見直しを求める声が上がり始めているが、エネルギーと農業の両方の問題を解決するために導入された政策だけ ...

最近パンの値上げが相次いでいる。食用油の価格の急な値上がりがその理由だ。乳牛や鶏などの飼料も高騰、経営危機に陥る農家が増えている。穀物の国際価格の異常な値上がりが、少しずつ目に見える形で私たちの生活に影響を及ぼし始めている。背景にあるのが”バイオ燃料ラッシュ”だ。アメリカでは中部穀倉地帯にバイオエタノール工場が続々建設され、輸出用より高値でトウモロコシを買い付けている ...

高圧電線が数キロにわたって切り取られ盗まれる。神社の屋根を葺いていた銅板が全部はがされる。工場のアルミホイールが大量に持ち逃げされる…。耳を疑うような金属の盗難事件が最近相次いでいる。背景にあるのは、スクラップ金属の異常ともいえる高値。国際価格の急騰、中国の需要の急増を受け、スクラップ業者が廃品や廃棄された電化製品を買い集めては、大量に中国に輸出している。高騰を加速さ ...

医療費の負担が増える中で、医療機器の内外価格差に注目が集まっている。医療機器の多くは欧米からの輸入品で、生産国と日本での価格に大きな開きがあるためだ。内外価格差の背景には、過去の貿易交渉を機に外国側から日本市場への参入に関して、働きかけがあったことも一因とされる。国産の優れた医療機器を開発することで、医療費を削減しようという動きもあるが、シェアの確保は容易ではない。医 ...

今空前の焼酎ブームが続いている。都会には次々と焼酎バーが登場し、産地では焼酎工場が大幅な増産を続けている。特に芋焼酎が人気だ。そのため、原料になる芋が不足し、中国から冷凍芋を輸入したり、芋の生産をする建設業者も現れた。また、1本3、4万で取引される”プレミア焼酎”も現れ、安く大量に仕入れ、高値で転売するブローカーも登場している。 去年は、偽物がオークションで取引され ...

過去最高水準で推移する原油価格。大型ハリケーンの影響もあってニューヨークの先物市場で1バレル50ドルに迫っているのをはじめ、ロンドン市場でも取り引き開始以来の最高値を更新した。 9月15日のOPEC総会では、1日百万バレルの増産が決まったが、高騰を抑えることはできなかった。今回の空前の原油高騰は、OPECの供給余力が限界にきている事に加え、中国等で原油の需要が急増し ...

この1年原油価格が高騰し、世界経済に深刻な影響が出ている。ドイツでは自動車の燃料価格が大幅に上昇、トラック運転手や農家が、全て燃料にかかる高い税金を下げて欲しいと政府に訴えている。10年前の湾岸危機以来の高値が続く原油価格。そこには、巨額の資金を元手に原油相場を動かす投機筋の姿が見え隠れしている。番組では、投機筋や産油国の動きを通して原油価格高騰の背景を探る。

小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物市況は、今年史上空前の高騰、世界最大の穀物輸入国・日本を直撃した。すでに一部食品の値上がりが見られる。産業界と食品市場の実態をリポートする。

マンション販売に明るさがみえてきたのをよそに、公団住宅は大量に売れ残っている。過去3年間に売り出した公団住宅の15%が空き室のまま。かつて人気の的だった公団住宅の不人気の原因と公団住宅がかかえる課題をリポートする。

去年11月建設省の道路審議会は、いつかは無料になるはずだった高速道路の通行料金を永久に取り続けるべきだという答申を出した。現在全国6000kmに及ぶ高速道路。料金制度の見直しの背景には何があるのか、波紋を呼んでいるこの動きに迫る。

円高の中で進められてきた日本企業の海外移転・進出も、思惑が外れて撤退を余儀なくされた企業が急増している。日本の製造業の海外進出の明暗を分けたのは何か、その背景を探る。

冷夏の影響で異常な高値を続けているキャベツに焦点をあてる。