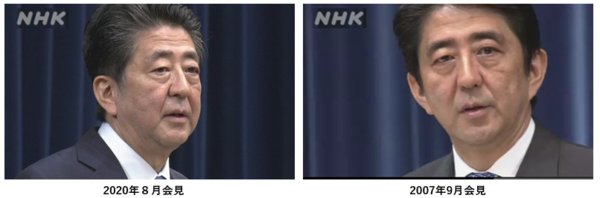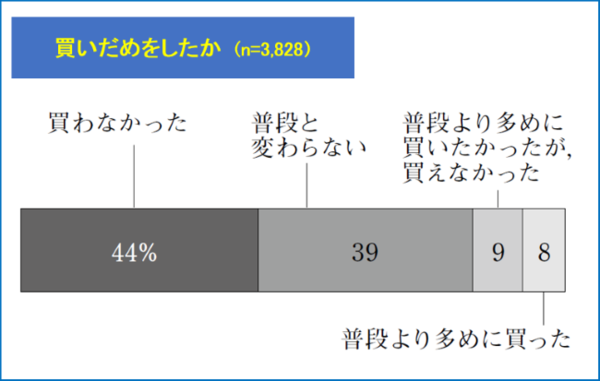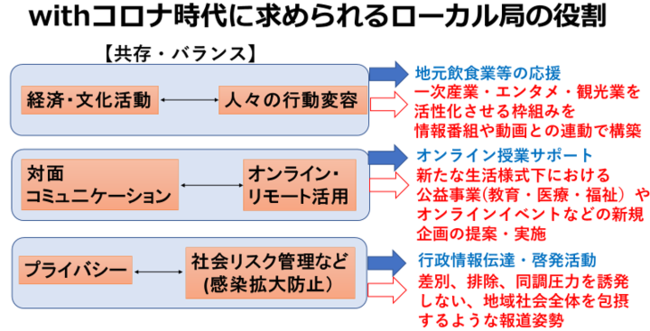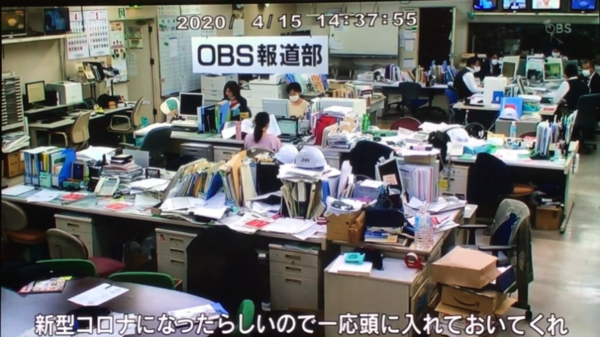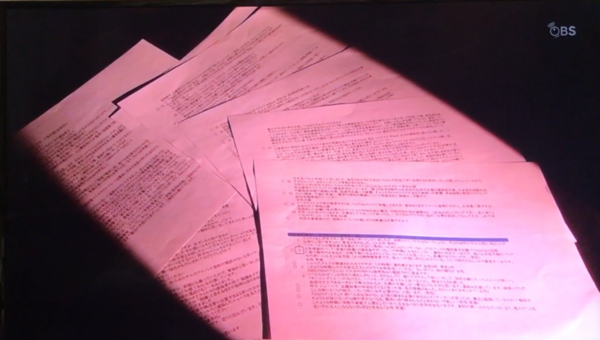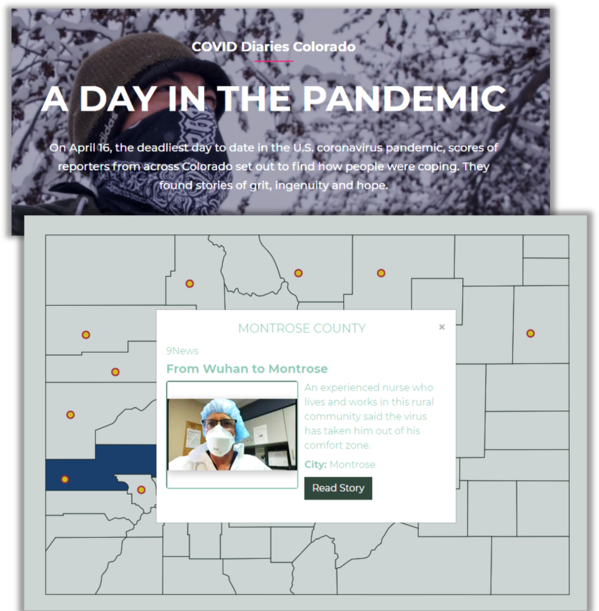#270 『テラスハウス』ショック ~リアリティーショーの現在地① 木村花さんの死から3か月が過ぎて~
メディア研究部(メディア動向) 村上圭子
5月23日、フジテレビ系で放送していたリアリティーショー『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020(以下、『テラスハウス』)に出演中だった22歳の女性プロレスラー、木村花さんが亡くなりました。花さんはSNS上で番組の内容を発端とする誹謗中傷を受けており、それを苦に自ら命を絶ったとみられています。その花さんの死から3か月が過ぎた8月26日、ABEMAが制作する恋愛リアリティーショー『いきなりマリッジ シーズン4』に出演していた23歳の濱崎麻莉亜さんが自ら命を絶ったことがわかりました。麻莉亜さんはAmazonプライムのリアリティーショー『バチェラー・ジャパン シーズン3』にも出演していました。現時点で、彼女の死が番組と関係があるのかについて詳細はわかっていませんが、2件続いたリアリティーショーの出演者の死という事実について、社会は重く受け止めなければならないと思います。
このような問題が繰り返されないためには、何を考え、どのような取り組みを行っていかなければならないのでしょうか。私は以前から、リアリティーショーの持つ光(発展)と影(課題)に関心を持っていたにもかかわらず、特に“影”の部分についてこれまで考察を行ったり問題提起をしたりしてこなかったことに忸怩たる思いを抱いています。出演者が自ら命を絶つという痛ましい事例は、すでに欧米では繰り返し発生し問題となっていました。にもかかわらず教訓が生かしきれなかったのだとしたら……悔やんでも悔やみきれません。
同時に、こうした痛ましい問題を眼前にすると、議論はどうしても、リアリティーショーは今後一切制作すべきではない、とか、SNS上の言論の規制を強化すべきだ、といった“極論”に流れがちです。しかしこうした時にこそ、複雑に絡み合う問題の背景を冷静かつ丁寧に検証することで、実効性のある対応策を導き出したり、メディアが抱える本質的な問題に粘り強く迫ったりする機会にすべきだと考えています。
このテーマについて、私は今後、腰を据えて考えていきたいと思い、まもなく発行される「放送研究と調査」10月号からシリーズで連載していきます。本ブログでは2回にわたり、その内容の一部をお伝えしたいと思います。
*リアリティーショーの歴史をひも解く
10月号では、リアリティーショーの誕生から今日に至る歴史を、欧米と日本を比較しながらひも解いてみました。
リアリティーショーは「リアリティー番組」「リアリティーテレビ」などとも呼ばれますが、明確な定義はなく捉え方もさまざまです。ただ、そのように呼ばれる番組群の特徴を見てみると、「制作者が設けたシチュエーションに、一般人や売り出し中のタレントなどを出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化をひき起こす何らかの仕掛けを用意し、その様子を観察する」というのがおおよその共通項と言えるのではないかと思います。『テラスハウス』でも、番組冒頭で毎回、タレントのYOUさんが「この番組は、男女6人がひとつ屋根の下で生活をします。番組が用意したのは、すてきなおうちと、すてきな車だけです。台本は一切ございません」という定番セリフを言っていますね。フィクションとノンフィクションの境界のあいまいさが、ドラマでもドキュメンタリーでもないこのリアリティーショーの最大の特徴であるといえましょう。
<光と影の20年>
こうした特徴の番組群がポピュラーになったのは、いまから約20年前、2000年前後です。ヨーロッパで生まれ、アメリカに渡ったリアリティーショーは、瞬く間に全世界に広がりました。そして当初から、各国において特に若い層を中心に爆発的な人気を博し、軒並み高視聴率を叩き出す、放送局にとっては“ドル箱コンテンツ”となります。その反面、視聴者が出演者の様子を“のぞき見”るという倫理的な特質や、出演者に葛藤を与える仕掛けをするという“社会実験”的な側面、出演者の心を“虚実皮膜”の状態に長時間置くストレスの課題が絶えず指摘され、批判もされてきました。番組で演じる“リアル”と自分の人格の“リアル”とのギャップを埋められず、放送中、あるいは放送が終わってからも、アイデンティティの崩壊を食い止められない出演者も少なくなく、それは出演者が自ら命を絶つという最も痛ましい形で表出していくことになります。
当時の記事やリポートからは、リアリティーショーに対して各国の視聴者が熱狂し、放送局が興奮し、社会が大きく困惑する様子をうかがうことができます。まさにリアリティーショーの歴史とは、“光と影”が表裏一体となって織りなしてきた歴史といってもいいでしょう。
<日本の系譜>
しかし日本では当初、リアリティーショーを巡る熱狂も困惑も無縁といっていい状況でした。2001年には欧米の番組が購入・放送されたり、その日本版も制作されたりしたのですが、大きなインパクトはなく、むしろ視聴者からは敬遠される方向にありました。他方で、1990~2000年代の日本では、日本テレビ系の『進め!電波少年』やフジテレビ系の『恋愛観察バラエティー あいのり』などのバラエティー番組が人気を博していました。2つの番組とも、リアリティーショーの特徴とも共通する、「制作者が設けたシチュエーションに、一般人や売り出し中のタレントなどを出演させ、そこに彼らの感情や行動の変化をひき起こす何らかの仕掛けを用意し、その様子を観察する」内容だったのですが、何が異なっていたのでしょうか。『電波少年シリーズ』のプロデューサーだった土屋敏男さんは自身のブログで、こうした番組群はバラエティー番組の中から誕生しており、それは「ドキュメントバラエティ」というジャンルであること、「アンチクライマックス性、アンチドラマ性」が日本の特徴であり、ドラマティックに作り上げる欧米のリアリティーショーとは異なる系譜を持つものであると述べています1)。
そんな中、2012年に『テラスハウス』が誕生します。企画を提案したフジテレビの太田大プロデューサーは、雑誌のインタビューにおいて、これまでのドキュメントバラエティに対するアンチテーゼともとれる考えを述べており、同時に、「欧米のリアリティーショーみたいな番組」を常々制作したいと思っていたとも明かしています。ただ、『テラスハウス』は単なる欧米リアリティーショーの輸入ではなく、「もっとリアルな,ドキュメンタリー性を重視」したものにしているとのことでした2)。そうした意味からも、『テラスハウス』は初めての“日本型リアリティーショー”といえるのではないか、というのが私の見立てです。
ドキュメントバラエティにしても日本型リアリティーショーにしても、日本では木村花さんの死以前には、欧米のように出演者が自ら命を絶つという痛ましい問題が起きることはありませんでした。ただ、両プロデューサーがいみじくも強調していたように、日本では欧米に比べてドキュメントにこだわったが故に、やらせ疑惑というような批判は後を絶ちませんでした。これが欧米と異なる日本における“影”の部分ともいえるかもしれません。ただこれについても、制作者・出演者・視聴者の三者のぎりぎりとも絶妙ともいえるバランスのもとで番組が成り立ってきたのではないかと思います。
*制作者・出演者・視聴者の関係性の変容
しかしこの三者の関係性は、SNSが普及してから大きく変容したと言えます。SNS以前は、その良し悪しはともかくとして、制作者が出演者・視聴者をコントロールすることが可能な時代でした。しかしSNSの普及によって、三者の関係性はフラットになっていきます。そのことは、制作者が視聴者との距離を縮めて番組を盛り上げる可能性を広げましたが、同時に、出演者と視聴者が(制作者がコントロールできないところで)直接つながっていくことにもなりました。特にリアリティーショーにおける出演者は、売り出し中のモデルやタレントなどが少なくありません。彼らは番組に関する内容はもちろんですが、それ以上に自身の“リアル”な胸の内や活動内容を発信します。フォロワーは、番組に出演している姿を見てファンになった人もいれば、番組以外の彼らの活動を通じてつながった人達もいます。SNSの世界においては、リアリティーショーの制作者が作った“リアル”と、彼らの活動の“リアル”に境目はなくなり、視聴者は時に番組を視聴する以上に高い熱量で出演者とつながっていくのです。
同時にSNSは広く一般に開かれる匿名が許される空間でもあるため、出演者に対する強いアンチのコメントの書き込みや,視聴者以外の“通りすがり”による悪質な“落書き”,ストレスを発散したり炎上を目的としたりする“誹謗中傷”にも遭いやすい環境です。出演者たちはリアリティーショーに出演して急に有名になってしまい、“たたかれる”ことに対する免疫も十分に用意できない中でその環境にさらされるわけで、かなりのストレスだということは想像に難くありません。
このように、出演者と視聴者という関係性を超えてしまったところで起きてしまうSNS上の様々な問題に対して、制作者はどこまで関われるのか、そして関わるべきなのか……。こうしたことが問われているのが、今のリアリティーショーを巡る状況ではないかと思います。
*花さんの死から3か月の間に起きたこと
花さんの死後、フジテレビは、『テラスハウス』の収録と放送、自社の運営する動画配信サービスFODでの配信を中止し、7月31日には社内横断メンバーによる検証報告3)を公表しました。報告では、制作スタッフにはSNSの炎上は予見できず、炎上を煽ろうとするような意図はなかったこと、SNSで花さんに対して批判的なコメントが増えてからは、スタッフは彼女と電話やLINEで連日連絡を取りあい、自宅にも複数回訪問するなどしてきたこと、しかし、ケアや健康状態への認識には結果的に至らぬ点があり力が及ばなかったことが記されていました。それに対し、花さんの母親の木村響子さんは、「外部の人による調査ではなく、公正かつ真摯に調査が行われたとは感じられない内容4)」だと不信感を募らせています。響子さんは7月15日、放送倫理・番組向上機構(以下、BPO)に番組に人権侵害があったと申し立てる書類を提出しました。BPOが審理するかどうかの判断はこれからです。現時点では両者の言い分は大きく食い違っていますので、10月号の「放送研究と調査」ではこの件についてはあえて触れていません。議論の行方を見守りつつ、取材を深めていきたいと思っています。
3か月の間に最も進んだのが、SNS上の誹謗中傷への対策ではないかと思います。総務省では以前から「プラットフォームサービスに関する研究会」と「発信者情報開示の在り方に関する研究会」という2つの研究会で議論が行われていましたが、花さんの死後、より積極的に議論が進められてきた気がします。まず、8月末に出された研究会の中間取りまとめ5)を受けて、インターネット上の誹謗中傷の被害にあった人が匿名の発信者の特定を行いやすくするための省令改正が行われました。被害者は誹謗中傷の書き込みをした発信者に対して損害賠償などの法的請求を行うことができますが、その前提として発信者を特定しなければなりません。しかしそうした書き込みをするアカウントは匿名のことが多いです。そのため、権利が侵害されたことが明らかであり、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに、被害者はプロバイダーに対して発信者情報の開示を請求することができ、これを受けたプロバイダーは原則として被害者の意見を聴取した上で、開示をするかどうかを判断することとされています。これがプロバイダー責任制限法における発信者情報開示制度というものですが、今回の改正で、開示対象に発信者の電話番号が追加されることになったのです。今後は、この制度のプロセスが被害者にとって多くの時間・コストがかかり負担になっており、権利回復のための手続を断念せざるを得ないこともあるとの指摘に応え、新たな裁判手続の創設など、更に踏み込んだ議論が行われる予定です。また9月1日には、プロバイダーの自主的取り組みやユーザーのリテラシー向上の啓発活動などをまとめた「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ6)」も公表されています。このテーマはリアリティーショーを超えた議論ではありますが、SNS上の表現の自由の今後を考える上でも重いテーマであり、また制作者・出演者・視聴者の三者の関係性を考える上でも重要な内容となってくるため、今後「放送研究と調査」で執筆すべく、取材を進めていきたいと思っています。
次回のブログでは、リアリティーショーを巡る海外の最近の動きについて報告します。
海外では30人以上の出演者が自殺したなどと報じられていますが、実際にどういう人たちがどういう背景のもとで亡くなったのか?イギリスでは放送局がリアリティーショーを制作する際に遵守すべきことを放送規則に加えようという動きがありますが、その最新動向はどうなっているのか?などについてです。
1) T_producer「ドキュメントバラエティとリアリティーショー①②」(『note』2020年5月29日、6月9日)
https://note.com/t_shacho/n/naac4a83fd770?magazine_key=mc08264c4a9a0
https://note.com/t_shacho/n/ne2b834ce6b7e?magazine_key=mc08264c4a9a0
2) 「ネットで火が付いた!「テラスハウス」のサクセスストーリー【フジテレビプロデューサー・太田大】」(『ザ・テレビジョン』2018年7月18日)
https://thetv.jp/news/detail/154545/p2/
3) フジテレビ「「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」検証報告」(2020年7月31日)https://www.fujitv.co.jp/company/news/200731_2.pdf
4)「テラスハウス問題の検証結果 木村花さん母「不信感しかない」」(『NHK NEWS WEB』2020年7月31日)
5) 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」(2020年8月31日)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/02kiban18_02000104.html
6) 総務省「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の公表(2020年9月1日)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/02kiban18_02000105.html