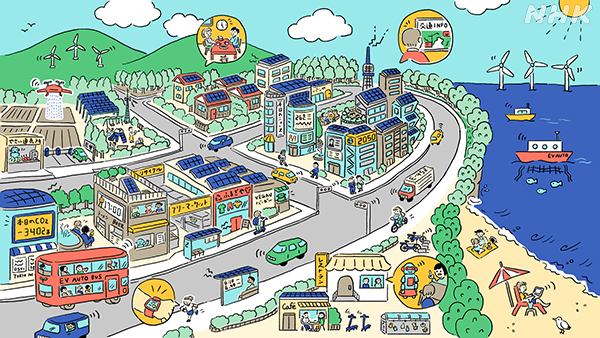「世界で何が起きているのか」桑子が行く“気候変動”の現場
2023年、わたしたちは観測史上最も暑い夏に直面。世界各地で災害が多発しました。
国連のグテーレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代に入った」と発言し、科学者たちは人類の存続に関わる脅威が迫っていると警告しています。
干ばつ、水不足、洪水、猛暑…いま世界中で起きている“気候変動”。
今回、その最前線でもあるヨーロッパとアフリカの地を訪れ、私、桑子が感じたことを写真とともにまとめました。
(クローズアップ現代 キャスター 桑子 真帆)
ヨーロッパ史上最大規模の森林火災 ギリシャの現場へ
私が最初に訪れたのは、ことし 8月に山火事が起こったギリシャ・エヴロス地域。熱波や乾燥などのため、燃え広がる火を止めることができなかったといいます。

案内してくれたのは、山火事の被害を受けたルトロス村の村長コスタス•ノティスさんです。

村を見渡せる場所に立つと、山火事から3か月がたったいまも、焼け焦げた痕跡がありました。
全体が焼けて巨大な黒いかたまりと化した山や、火が通ったところだけが黒くまだら模様になった山があちらこちらに。


山火事がいかに広範囲に及んでいたかを感じさせられました。
養蜂業や農業、酪農業など自然と密接に関わり合いながら暮らしてきた村の人々。
幸い、声をかけ合い避難を進めたことで、村のすべての人の命が助かりました。

しかし、村長のノティスさんは「草がなくなり放牧はできない。樫(かし)の木がなくなり、はちみつもとれない。職がないと若者たちは村から出ていく。この先、村はどうなってしまうのか…」と表情を曇らせました。
村の存続にまで関わりうる山火事。影響の深刻さを感じました。

取材をする中で、ひとりの男性に出会いました。
酪農家のコスタス・ピストラスさんです。

当時、火はものすごい速さで迫ってきたといいます。
-
 コスタス・ピストラスさん
コスタス・ピストラスさん -
「煙の中で家畜たちが逃げていくのを見ました。扉のところまですでに火が来ていたので、私自身も危険な状態でした」
懸命に消火を試みたものの火の勢いは止まらず、畜舎や倉庫は全て焼失しました。

焼け跡に無残に転がっていたのはヤギの骨。
-
 ピストラスさん
ピストラスさん -
「このあたりはヤギの骨でいっぱいです」
飼っていたヤギ85頭のうち、助かったのはわずか6頭。
生活に大きな打撃を受けました。
いま、ピストラスさんが新しく建てている畜舎を見せてもらいました。
すると、目にとまったのは「黒い柱」。再建に、山火事で焼けた木を使っているのです。

「ギリシャでは、『あらゆる物事には、どんなに悪く見えても、必ず何か良いこともある』と言うんだけど、まったくそのとおりです。大惨事から幾ばくかのものでも守り切って、得られるものがあれば得る。それでなんとかするしかない」と話すピストラスさんに、身体に気をつけて少しでも状況が良くなりますようにと声をかけることしかできませんでした。


火は、17日間にわたって燃え広がり、約1000㎞²が焼き尽くされました。
森林はいまどうなっているのかー
自然環境気候変動庁のハリス・パパレクサンドリスさんに案内してもらいました。

木を触ってみると、ポロポロと灰が落ちてしまいました。

-
 ハリスさん
ハリスさん -
「触ってみると中まで焼けていることがわかります。木に緑の部分が残っていないということは、呼吸ができず光合成ができません」
次の世代に命をつなぐ松ぼっくりも真っ黒焦げに。

この森が元に戻るのにはいったい何年、何十年かかるのだろう…。
気が遠くなるような思いにかられながら、焼け焦げた木の根元付近に樫の木の新芽が顔を出しているのを見つけました。周辺には花のつぼみも。

「自然は何千年と再生を繰り返してきた。これは未来への小さな希望です」と、案内してくれていたハリスさんの表情が初めて緩みました。

しかし、自然の回復力にばかり頼っていてはいけません。
「もしまた山火事が起きたら、ダディア森林はなくなってしまう。気候変動に対応しない限り、森林のみならず人間の生活環境や社会経済活動にも深刻な影響が及ぶ」と語気を強めるハリスさんの言葉が重く残りました。
「ここで暮らせない」セネガル 進む砂漠化
次に私が訪れたのは、セネガル北部にある人口900人ほどの小さな村、ダガ村です。

この地方は、雨が少なくなり、大地の砂漠化が進んでいます。

この村では、これまで、インゲン豆や落花生などを栽培し生計を立ててきました。
しかし、雨が少なくなり、砂漠化が進んだことにより、いまは作物がほとんど育たなくなっています。
若者たちに話を聞くと、「1年のうち畑仕事ができるのは、雨季にあたるたった2か月の間。ここで暮らし続けることがますます難しくなっている」と苦しい胸の内を語ってくれました

セネガルではこの70年で降水量が30%以上減少。
森林伐採などに加え、雨が降らないことで農地の6割以上が砂漠化したといいます。

収穫量が激減する中、故郷を捨てざるをえない若者が相次いでいます。
この村でも、ことし8月にひとりの男性が海を渡ってスペインを目指しましたが、途中で命を落としました。
亡くなったのは、ラミーン・サンブさん。

3人の子どもに加え、親戚も養っていました。
作物が育たず、収入は5分の1にまで激減する中、スペインへ向かうこと決心。家族を養うため働く場所を求めていたとみられています。
しかし、乗り込んだ船の中で、水や食料もなく衰弱死してしまったのです。
妻のファトゥさんは「雨さえ降ってくれれば、夫は村を出て行くことはなかったのに。子どもたちをどう養っていけばよいのか…」と涙を流していました。

深刻な干ばつや災害によって住み慣れた土地を追われる人たち=“気候難民”と呼ばれる人たちが世界で増え続けています。
日本では豪雨が頻発し、川の氾らんや土砂災害が繰り返されています。
しかし、セネガル北部では逆に雨が降らなくなり、暮らしそのものが成り立たなくなっています。地球の異変を感じざるをえません。
アフリカ 未来に託すプロジェクト
気候変動にどう立ち向かうのかー
いま、アフリカでは乾燥に強い木々を植えて砂漠化を食い止める「グレート・グリーン・ウォール計画」が進んでいます。

アカシアなど、雨が少ない土地でも育ち、強風と砂から土地を守る木を植樹しています。


このプロジェクトは、アフリカを東西に横切るように巨大な緑の壁を築く計画で、国際連合や世界銀行の支援を受け、11か国で進んでいます。
私が訪ねたセネガル・ンディアレニュ村では、植林に加え、農地に水を供給するかんがい設備が整えられ、作物を自分たちで育てています。

この日は、村総出でたまねぎの苗の植え替えが行われていました。
畑に水をためる設備ができたことで、砂地でも農業ができるようになっています。

農業を担うのは村の女性たち。
ある女性は「自分たちに役割があることが生きがいにつながっています。子どもたちがこの村で暮らし続けられるように、この取り組みを次の世代に受け継いでいきたい」と話していました。

炎天下の厳しい暑さの中でも、互いにことばを交わしながら生き生きと作業している姿が印象的でした。
取材を終えて
ギリシャ、セネガル、ケニアとおよそ2週間にわたって気候変動の現場を取材してきて、私が実感したのは、良くも悪くも世界はつながっているということです。
故郷を追われる気候難民も森林の消失も、遠くに暮らす私たちの活動がきっかけとなって負の連鎖を起こしてしまっています。
人の手で起こした負の連鎖をどう止めるか。それは、やはり人の手しかないのではないかと感じます。
この地球規模の危機に対して、果たして世界は同じ方向を向いて進めるのでしょうか。
ひとりひとりがどう行動に移していけるか。いまが正念場だと感じました。
みんなのコメント(24件)
-
 感想オーロラ2023年12月21日
感想オーロラ2023年12月21日 - 今後気候難民が多数出る、いうのは情報としては知っていましたが、既に船で国を出ざるを得なかったり、家族が見捨てられて子育てに困る母親などを映像で見て、いよいよ、突入しているのだと、ゾクっとしました。水不足、食料不足が、政情不安をもたらす。奪い合いや戦争が増えていくことになる。日本も、対岸の火事ではない。
-
 提言Thai suke2023年12月21日
提言Thai suke2023年12月21日 - すでに10年以上前からこういう事象は起き始めています。
各区国で脱炭素など環境問題に取り組んでいますが、それだけの問題でしょうか。自動車業界に従事しておりますが、産業を続けている以上は、生活環境が良くなる地域とそうでない地域の格差がありクリーンなエネルギーという事もその製品を作るための影響はとても大きいです。
問題提起はとても簡単な事ですがどのように対処し、やめるべき事を明確にする事が大切です。
急務であるのであれば具体案が必要で。被害を受けている国を報道しても意味がない。生活の中で何をやるべきかを訴える事が必要だと思う
-
 質問yoshi2023年12月21日
質問yoshi2023年12月21日 - 彼らは自分で灌漑しよう気はないのか
今純水はフィルターで簡単に作れる
頼るのではなく自力解決の精神が必要だ
-
 提言かずき2023年12月1日
提言かずき2023年12月1日 - 日本を含めた先進国は、このような立場の弱い人々が苦しむ現状に強い危機感を持って行動するべきです。
日本はまず、NDCを大幅に引き上げなければならないと思います。そして、2030年までに石炭火力発電を廃止すると明言すべきです。そうでないと、1.5度目標達成は困難でしょう。
政府や企業には、本気で気候変動対策をしてほしいです。
-
 感想地球沸騰化さん2023年12月1日
感想地球沸騰化さん2023年12月1日 - 地球沸騰化シリーズを見た。国谷さんって、すごかったんだなって、改めて思った。国谷さんのインタビューが見たい
-
 感想きんたろう2023年11月30日
感想きんたろう2023年11月30日 - 内容はBSで放送されたものが多かったと思います。こういった番組をもっと地デジで放送してほしいです。知ることは大事ですが、個人にできることは限りがあります。例えばパーム油問題。RSPO商品を探しても種類は少なく値段も高く日常的に使えません。そもそもプラ容器です。研究者の方が色々な提唱をしても企業や政府、何より国民が日々の生活を見直さなければ“地球沸騰化”は免れないのではないでしょうか。大手日用品メーカーの方が「彼ら生活がかかっているから環境の話だけでやれるわけがない」と話していました。現場を知る人がこんな姿勢なら企業が変わるはずがありません。他人事ではないはずです。
-
 提言puzzzle2023年11月30日
提言puzzzle2023年11月30日 - 世界で取り組まなければならない喫緊の課題です。国内外における気候危機の状況を伝える専門の番組や報道番組での一枠(例えば気象情報に続けて)などで、常に伝え続けることも検討いただきたいです。
-
 感想のんのん2023年11月28日
感想のんのん2023年11月28日 - 気候変動による難民がこんなにいたなんて、ショックです。
明日をもわからない命すれすれの生活を余儀無くされているこうした人々を、私たちはどう支えていけばいいのでしょうか。
ひとつ言えるのは、いまウクライナで、ガザで戦争をしている場合でなんかないこと。戦争こそが気候変動を生む温床であるのですから。
もっと人間は賢くあっていたい。お互いに武器を捨て、富める国々の人々は貧しい人々に手を差し伸べていけたらいいのに。そんな夢を抱いています。
-
 感想さの2023年11月28日
感想さの2023年11月28日 - 温暖化によって森林火災が起き、さらにCO2が増えて温暖化になる、という負の連鎖が起きているのだなということがよく分かります。
しかし、これを見た視聴者ができることは多くはありません。当然、アフリカまで直接出向いて緑化活動をしようとか、国連で温暖化防止のためのさらなる法を提出しようということはできません。このような国際情勢に目を向けた番組を作ることも大事ですが、私たちにもできることを番組として放送することも同じくらい大事でしょう。公共放送NHKとして、放送するべきことは、「私たちができる5つのこと」の方ではないでしょうか。左上のQRコードで少しだけ伝えるのではなく、テレビという膨大な情報を伝えることができるメディアで伝えてほしいと思います。
-
 感想web3Arts2023年11月28日
感想web3Arts2023年11月28日 - いつも、お世話になります。人類の未来の分岐点に佇む待ったなしのテーマなので、微力ながらオウンドメディアを使い、あまねく産業界に警鐘を鳴らしています。昨夜の番組構成、とても貴重でした。COP28を契機に、国民運動としての気運を醸成したく、引き続きよろしくお願いいたします。