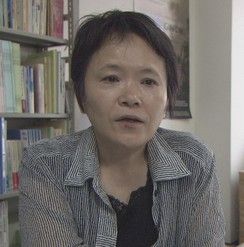2014年08月11日(月)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(7)
番組ディレクターの松原です。
「たとえ人生の99%が不幸だとしても、最後の1%が幸せならば、その人の人生は幸せなものに変わる」
私は、マザーテレサのこの言葉を信じられませんでした。
まだ子どもだったころ、いつか必ず死ぬという事実に気づいた夜、眠れずに天井のシミをずっと見ていて朝が来たのを覚えています。つまり、死とは怖くて冷たいものでした。
でも、“みとりの村”永源寺では、本人が望む最期を、家族が看取る「最後の1%」があったように思います。最後の時間を共に過ごすことで、命は尽きても、目に見えない意志や想いが、看取った家族に受け継がれていく。それを、マザーテレサは「幸せ」と呼んだのでしょうか?

”看取りの村” 滋賀県東近江市、永源寺地区
最後に、松玄太郎さん、左近セツさん、左近治之助さん、そして家族の皆さま。
様々な人に命と向き合う機会を与えて頂き、本当にありがとうございました。

66年間連れ添った妻を看取る夫

大好きな祖父の最期に寄り添う孫
◆“みとりびと” ―看取(みと)りの時間に伝えあうこと―
本放送8月5日(火)、再放送8月12日(火)
本放送:夜8時00分~8時29分
再放送:午後1時10分~1時39分(夏の高校野球のため、放送時間変更)
2014年07月24日(木)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(0)
ディレクターのKです。
6月10日にハートネットTV「60歳からの青春」で取り上げた精神科の長期入院の問題を、今夜(7/24)の「クローズアップ現代」で特集することになりました。
依然、多くの人が、入院が必要ないにもかかわらず行き場なく精神科病院に入院せざるをえない実態が続いています。
先日のハートネットTVでは大きな反響をいただきまして、さらに様々な立場を追加取材し、「どうすれば長期入院を減らせるのか?」をジャーナルに考えていく方向性にしています。
この問題を再び取り上げることができ、ディレクターとして大変うれしく思っています。
精神疾患の患者は300万人を越え、もはや他人ごとではない精神医療の問題。
何十年も続いた構造的な問題に頭を抱えることばかりですが、自分らしく、自由に、誰かとともに生きる意味は何なのか。
考えていただくきっかけになれば幸いです。
2014年7月24日(木)放送
クローズアップ現代「精神科病床が住居に?長期入院は減らせるか」
◆関連番組
60歳からの青春~精神科病院40年をへて~
◆関連ブログ(出演者インタビューや取材記など)
・岡崎 伸郎さん:「精神障害の問題では日本はもはや"周回遅れ"」
・山本深雪さん:60歳からの青春 ―精神科病院40年をへて―、に寄せ
・緊急取材中―精神科病院・20万人以上が1年以上の長期入院という現実―
2014年07月10日(木)

7月10日放送の「2014 介護百人一首 夏編 その二」のなかで紹介した短歌を、その詠み手やご家族の写真とあわせて掲載します。
(番組で紹介した順です)
【続きを読む】
2014年07月09日(水)

7月9日放送の「2014 介護百人一首 夏編 その一」のなかで紹介した短歌を、その詠み手やご家族の写真とあわせて掲載します。
(番組で紹介した順です)
【続きを読む】
2014年07月08日(火)
7月9日放送「2014 介護百人一首 春編 その一」
7月10日放送「2014 介護百人一首 春編 その二」
にご出演された、小説家の姫野カオルコさんにメッセージをいただきました。

【続きを読む】
2014年06月23日(月)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(0)

6月25日放送(7月2日再放送)
シリーズ 選ばれる命
第4回 反響編
ご出演のブルボンヌさんにメッセージをいただきました。
《ブルボンヌさんプロフィール》
ゲイ、女装パフォーマー/ライター。LGBTの存在を社会に発信し続けている。NHK第一ラジオ「午後のまりやーじゅ」木曜日パーソナリティー。
――収録の感想を教えてください。
私もセクシュアルマイノリティーという少数派のひとりですが、そういう立場からすると、“普通”とされているものと違う部分を持って生まれてくる子どもを「それでもいいよ」と愛情深く育てて生活されているご夫婦というのは、確かに“救い”なんです。
だけど、私たちが「そうしてほしい」と言えば言うほど、いま苦労されている当事者の方や、葛藤の中で中絶を選択された方たちの行為を否定してしまうことにもなりかねない。だから、この問題は「どんな子でも産んで育ててね」とポジティブに表現するだけではダメなんだと思いました。
実は、今回収録するにあたってこれまでのシリーズ3回分を拝見したんですが、本当に心がかき乱されて、「私の中での答えはこれだ」というものを持って収録に臨むことができなかったんです。そのくらい複雑で難しく、答えなんて簡単に出ない問題だと痛感しました。
詳細は「続きを読む」をクリックしてください > > >
【続きを読む】
2014年06月23日(月)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(0)

6月25日放送(7月2日再放送)
シリーズ 選ばれる命
第4回 反響編
ご出演の荻上チキさんにメッセージをいただきました。
《荻上チキさんプロフィール》
1981年生まれ。評論家。ニュースサイト「シノドス」編集長。メディア論をはじめ、政治経済や福祉、社会問題から文化現象まで幅広く取材し分析。著書に『ウェブ炎上』『ネットいじめ』『僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか』など。
――収録の感想を教えて下さい。
「産む・産まないは女が決める」と言ってきた一方で、障害者運動が「障害があるからといってその子を殺めることは許されない」と言ってきたように、いろんな当事者のニーズがぶつかり合い、悩みながら進んできた面があるんですね。
それに対して何が一番いい答えなのかというのを当事者の外部が結論を出すことは非常に難しいと思います。「これが答えだ」というのは、個々人が置かれている状況などによっても異なってくる。だからこそ、「何が答えなんだろうか」、「自分はどうするんだろうか」、「自分が決めたことをどう受け止めたらいいんだろう」と悩みながら語り合える“場”があることこそ重要です。倫理面での議論も重要ですが、番組の中で紹介したドイツの事例のように、「相談ができる体制」を整えていくことも重要になってくる。出産はただでさえ誰にとっても一大イベントなわけですから、それをサポートする体制づくりと、今までの出産に対する倫理の面での議論がまだまだ成熟する必要があると感じました。出産・育児等を「個人の選択の問題」だけに押し付けることなく、葛藤を前に相談できる体制は、すべての「親になる人」にとっても重要だと思います。
詳細は「続きを読む」をクリックしてください > > >
【続きを読む】
2014年06月23日(月)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(0)

6月25日放送(7月2日再放送)
シリーズ 選ばれる命
第4回 反響編
ご出演の久保純子さんにメッセージをいただきました。
《久保純子さんプロフィール》
元NHKアナウンサー。2011年~2013年夫の転勤に伴って渡米し、8月に帰国。現在、モンテッソーリ幼児教育の教員免許を取得中。二児の母(長女と次女)。
――お話を聞きながら涙ぐむ場面もありましたが、どのような思いが込み上げてきましたか。
正しい答えがない中で、赤ちゃんことを思って中絶の選択をして、心も体もボロボロになりながら「それで本当に良かったんだろうか」とずっと自分を攻め続けてしまう母親の苦しさ。それに思いを寄せると、やはり、心穏やかにはいられませんでした。
決して他人事ではありませんし、中絶を経験されたお母様、お父様方のことを思うと、本当に、苦しいです。
詳細は「続きを読む」をクリックしてください > > >
【続きを読む】
2014年06月20日(金)
- 投稿者:web担当
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(0)
ハートネットTV、WEBライターです。
今回の収録は、今月シリーズでお伝えしてきた『選ばれる命』の『反響編』でした。
3回のシリーズ放送を観て、「これは思っていた以上に重い…。」と感じたこのテーマ…。
スタジオゲストのブルボンヌさんが、「こんなに答えが出ない問題ってあるの?」とおっしゃっていましたが、私もまさに同じ思いです。
寄せられた体験談は痛みや葛藤でいっぱいで、聞いている方も胸がえぐられるようです。
出生前検査で赤ちゃんに障害があるとわかり中絶を決断された方の話もありました。「(結果を受け、悩んだ末に)お腹でつながっている赤ちゃんと、自分の意思でサヨナラするのは本当につらい…」と、中絶を選択した母親たちを慮る久保純子さんの“母”の涙…私も、子供が二人いるので、ひとごととは思えません。

収録の風景。難しいテーマでしたが打ち合わせ時から議論が尽きることはありませんでした。
【続きを読む】
2014年06月09日(月)
- 投稿者:番組ディレクター
- カテゴリ:ハートなブログ
- コメント(2)
6月10日放送(6月17日再放送)
60歳からの青春 ―精神科病院40年をへて―に寄せ
NPO大阪精神医療人権センター 副代表 山本深雪さんにお話を伺いました。
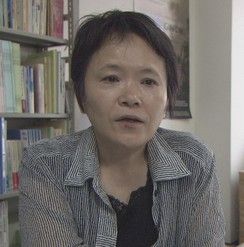 《山本深雪さんプロフィール》
《山本深雪さんプロフィール》
NPO大阪精神医療人権センター 副代表
1997年から、大阪府内の精神科病院を訪問、入院患者の声を聞く活動を続けている。入院経験のある当事者でもある。
――今回の番組では、原発事故をきっかけに地域で暮らすことになった男性を紹介しています。
たまたまのできごとでハコモノがなくなった。そうしたら、その方の居場所をみつけなくてはいけない、ということでまわりの人が熱心に動いてくださった、結果的にその方らしく無理せずに暮らせるグループホームに出会うことができた。
・・・その話は、すごく比喩的というか、そんな風に一人ひとりが支援されたら、うまくゆくのにな、と思います。
病棟の中にいると、その人の本当の顔が見えない、だからその方を何とかしなくちゃいけない状況にあるんだ、ということに気がつかない、あるいは気づいていても知らない顔ができてしまう。ハコモノがなくなってしまうと、どうしよう、どこで暮らす、どういうサポートがあったら暮らせるだろう、という話に転換してゆく、それができた、ということなのだと思います。その方のようなサポートが地域に用意されたら、社会的入院をしている人たちが人生をあきらめなくてすみます。
【続きを読む】