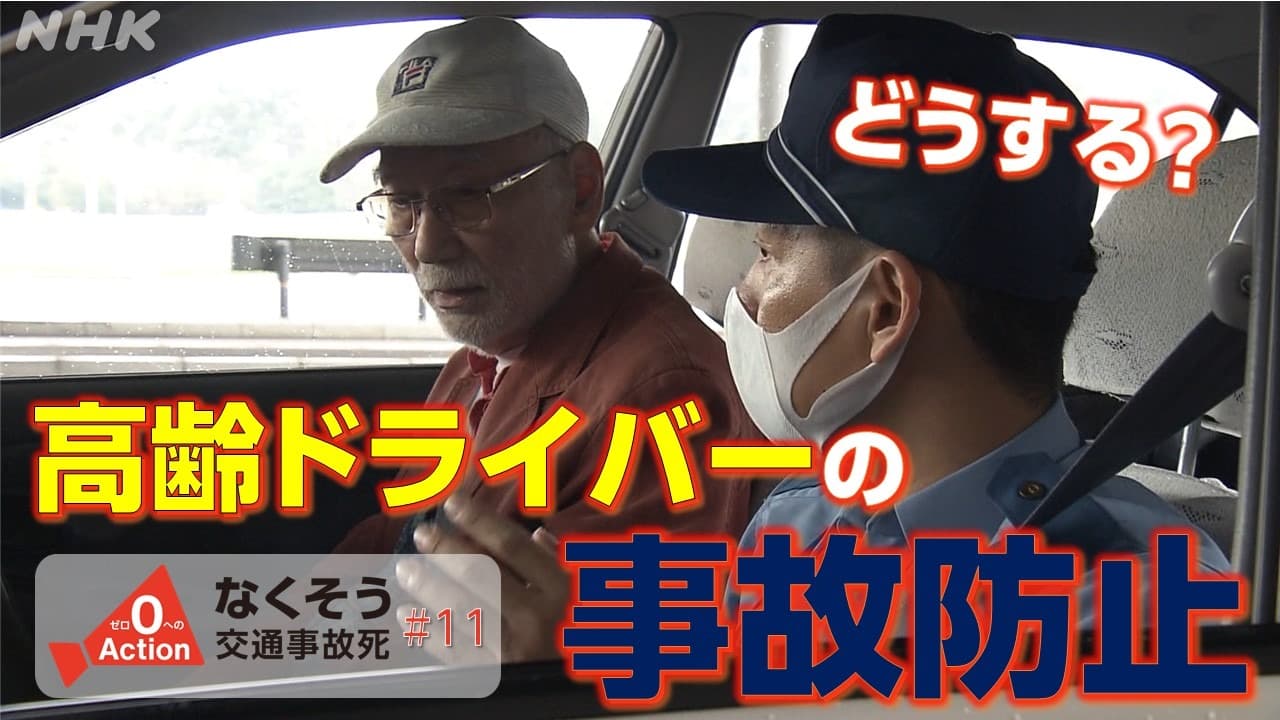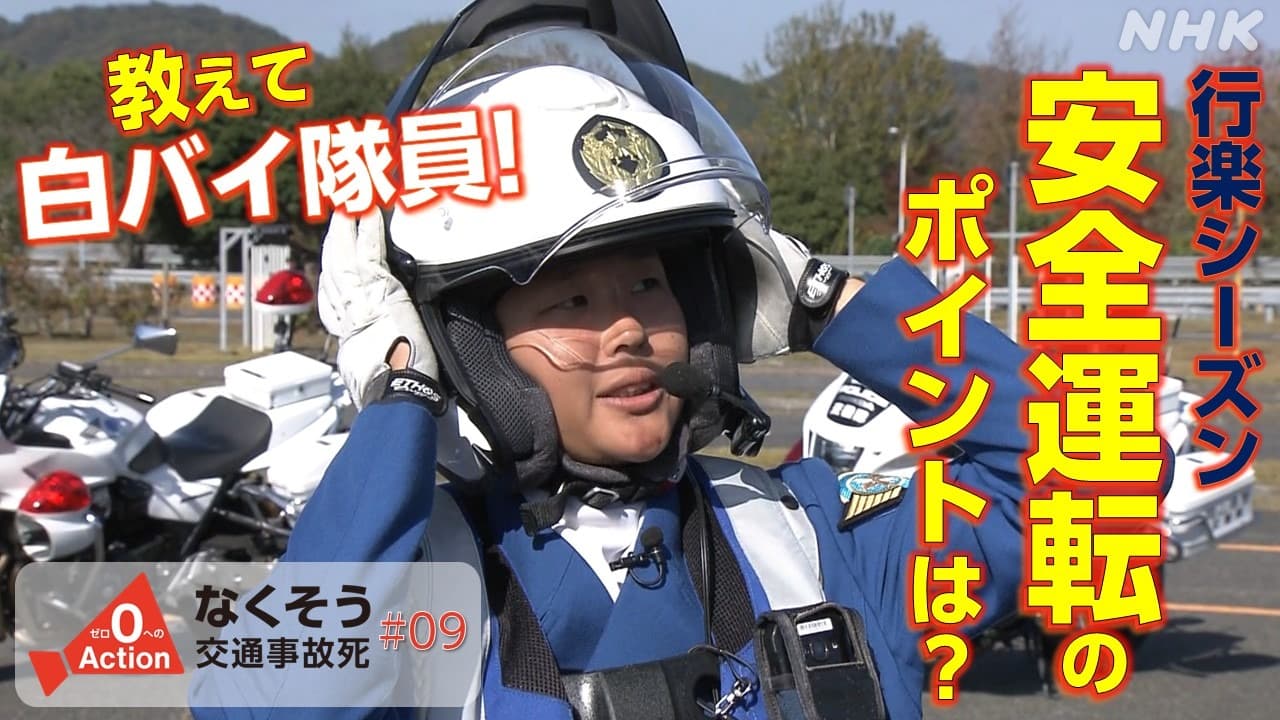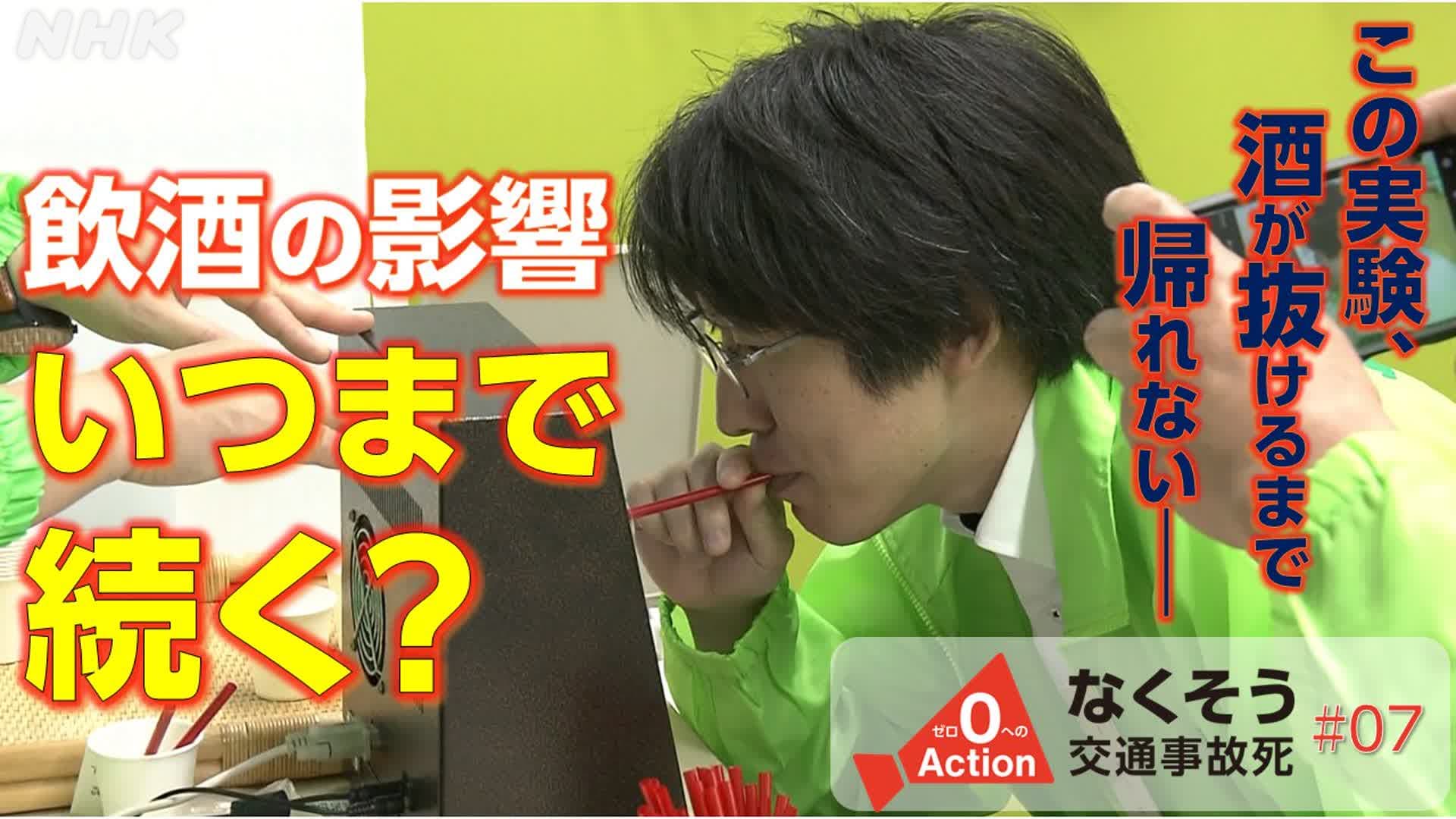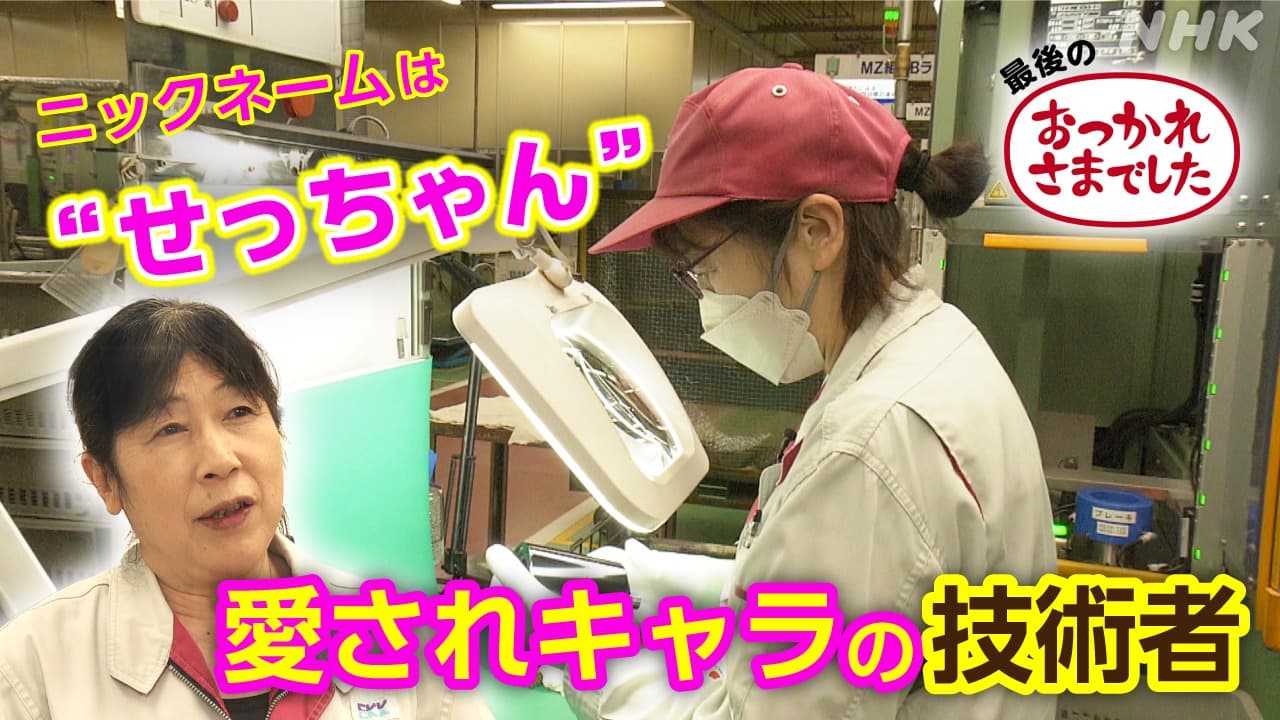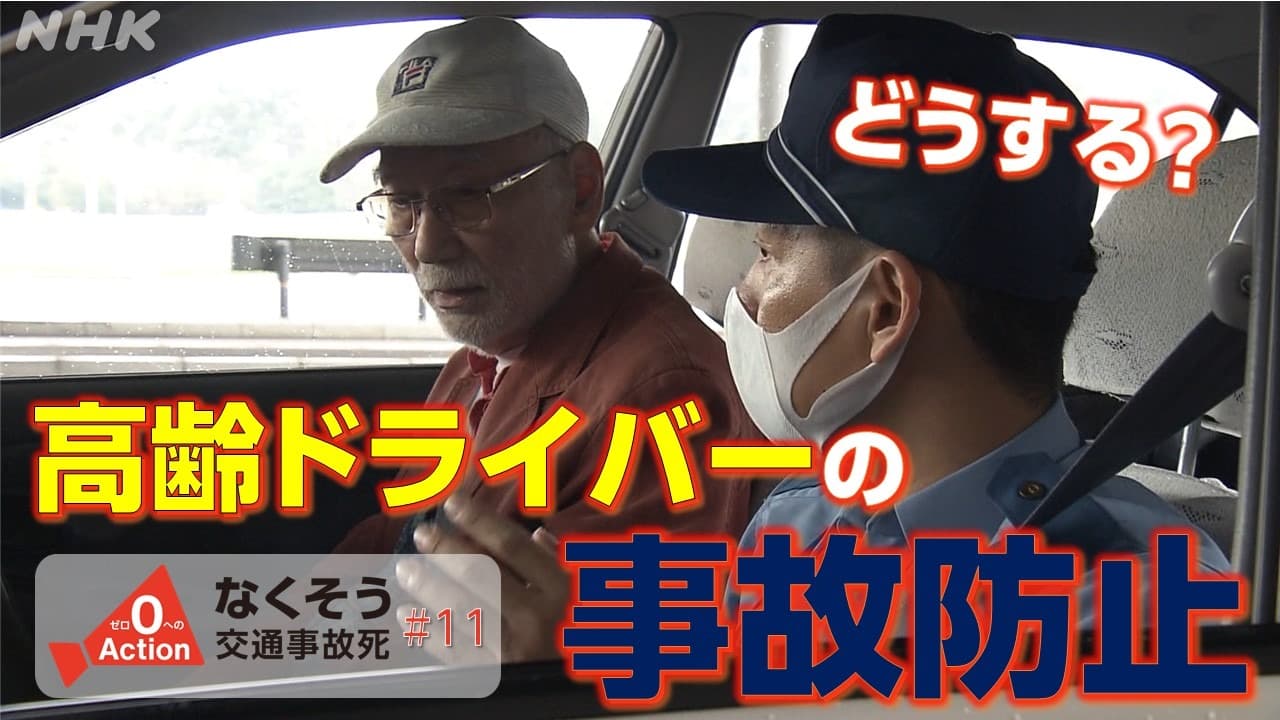岡山発 ②用水路ラビリンス 防げ転落事故! 敵は「慣れ」...?
- 2023年12月06日

令和4年、人口10万人あたりの交通事故による死者数がワーストになった岡山県。
事故ゼロを目指そうと、夕方のニュース「もぎたて!」のなかで「ゼロへのアクション~なくそう交通事故死」のシリーズを展開しています。
今回、岡山県の交通事情をめぐる3つの「ヤバい」を岡山県出身でSTU48の沖侑果さんと考えます。2回目は「用水路ラビリンス」です。
(岡山局ディレクター:大井屋奏 鈴木花 記者:美濃田和紅 映像制作:岡夏帆)
用水路がなぜ迷宮なのか

沖侑果さん
岡山県って、そこら中に用水路があるイメージ。落とし穴みたいに突然、現れますよね
岡山県出身の沖さんもそう感じる用水路。岡山の人にとっては身近な存在ですが、どのくらいの長さがあるのでしょうか。

実はその長さ、岡山市だけでおよそ4000キロ。直線距離でベトナムにいくことができます。次いで用水路の長いのが倉敷市で、その2000キロをあわせるとインドに到達します。
でも、なぜこんなに用水路が多いのでしょうか。

橋本成仁
教授
遠浅の海だったのを江戸時代に干拓して、広大ないい農地をつくり、水を供給するための用水路ネットワークがきちんと張り巡らされました。そこに家が広がったわけですが、昔からのインフラである用水路もそのまま残っているということですね
危険が潜む用水路

用水路とともに発展してきた岡山県。しかし、その「多さ」と「近さ」ゆえの危険が潜みます。
毎年、用水路への転落事故が多発。岡山市内だけでも、昨年度は47件起きました。
こうした事故の多くは、夕方から夜にかけて起きています。

取材で夜の用水路にやってくると、道路との境目が分かりませんでした。慣れ親しんだ道でも、ちょっとした不注意で転落のおそれがあることが分かります。
岡山市が危険な場所を洗い出したところ、なんと2500か所以上見つかりました。そこで、転落防止の柵や反射板、夜間に光る目印など安全対策を施しました。
しかし、用水路は何千キロもあるので、まだ注意が必要な場所があるかもしれません。

例えばこちらの場所。数年前に柵が設けられるまで、突然道が途切れて用水路が現れる、危ない場所でした。実際に事故も起きた場所だということです。確かに危ない......。

何か考え事をしながら動いていると、「あっ」ということがあるかもしれないですね
未然に防ぐ取り組みも
地元の声がきっかけで、令和5年、柵が完成した場所もありました。子どもの通学を心配した保護者が町内会長に相談し、町内会長が地元の人や行政、水路の管理者と話し合ったということです。

柵があるのとないのでは、全然違います。柵がないと怖く感じませんか?

ずっと自分がそこに住んでいるという人になればなるほど、おかしな状態だとは思えない。外から来ても、何年かするとこれが普通になってきちゃうんです。恐ろしいことに。慣れが人間の感覚を変え、危険を察知する能力を下げていきます
橋本教授によれば、救急車が出動する転落事故は、年で平均すると県内で1日1件程度です。しかし、人に言わずにその場を立ち去るケースが多くあるのではないかと指摘します。当然、そうした人たちの存在は、統計上の数字には上がってきません。
あなたが毎日通るコースは大丈夫ですか?
「普通」を疑うと、「危険」が見えてくるかもしれません。

自分は今広島に住んでいます。岡山にいる時は全然何とも思ってなかったんですけど、広島に行ったらあそこまで深いものとか全然なくって!だから改めて見て、岡山はやっぱり用水路が多いんだなと思いました
柵以外の対策は?
すべての用水路に柵をつけたらいいのでは? 取材していて、そんな声も聞きました。
しかし、距離は何千キロもあります。そして側道が狭い場合は、車や農業用トラクターの通行の邪魔になってしまいます。
そうした場所には、ライトで光る「反射板」や、夜は自然に発光する「蓄光素材の目印」など、狭いスペースでも道路と用水路の境が分かるよう、対策が進められています。


使ってない用水路はなくすことはできないんですか?埋めたりとか......
そのように考えますよね。
橋本教授によれば、用水路は水源から海までつながっているため、一部分をなくすということができないとのことでした。「フタをすればよいのでは」という意見もよく出るそうですが、水温が下がって農業に支障が出たり、掃除や管理がしにくくなったりするということです。

福祉大学
金光義弘
名誉教授
生活インフラが発達して便利になればなるほど、リスクも大きくなります。
インフラを補強するため、人間の目で危険箇所に気づいたり、先ほどの発光物を活用したりするなど、知恵を働かせることが重要です
番組制作を終えて

「当たり前」の怖さを実感した取材になりました。岡山に来て約1年。当初「こわっ!!」と思っていたはずなのに…すでに用水路の近さに慣れつつあった自分が怖い。これを機に岡山歴の長い先輩方もご一緒に、意識アップデートしましょう!

取材させていただいた岡山大学の橋本成仁さん。印象に残ったのが、「慣れが危険察知能力を下げていく」こと。ハッとさせられました。たしかに、赴任した当時は岡山の用水路の多さ・大きさに驚いていたなあ、と。用水路に限らず、何事も慣れは危険のもと。そのことを肝に銘じて生活を送りたいです

私自身も中学時代、用水路に自転車ごと突っ込みました...。当時は「恥」だと思っていたので、周りにも秘密にしていました。同じような体験をした人も多いはずです。現状を変えるため、町内会長や役所に相談するなど、危ないと思った時点で行動に移してくだされば幸いです...!

初めて岡山に来たとき用水路の多さに驚いたのですが、今はすっかり見慣れてしまい、危険性も感じなくなっていました…。橋本先生の言葉を聞いて、改めて身の回りに潜む危険について認識することができました