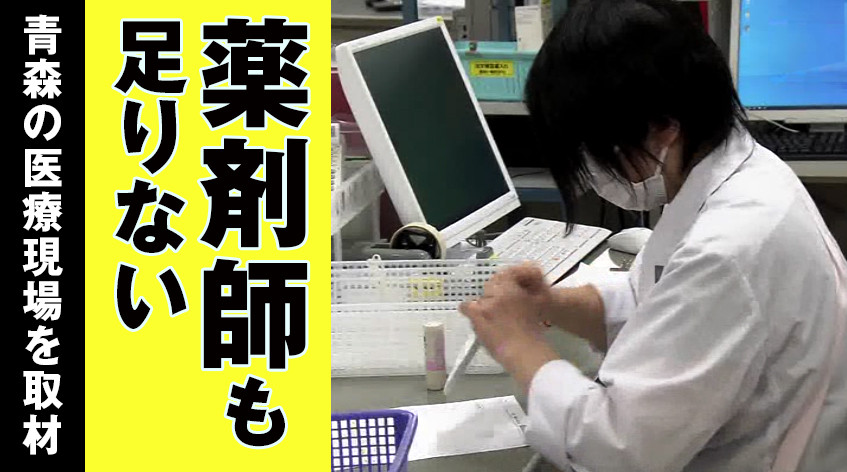ホームページ移転のお知らせ
 編集部
編集部
2023年05月10日 (水)

移転先はこちら↓
https://www.nhk.or.jp/aomori/lreport/article/001/48/
2023年12月より、ご覧の「NHK青森コンテンツサイト」は「NHK青森WEB特集」に順次移転しております。
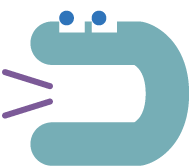 編集部
編集部
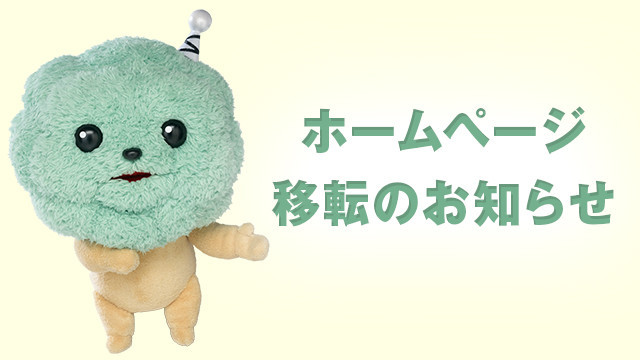
 編集部
編集部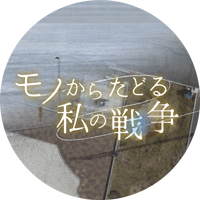 「モノからたどる私の戦争」編集部
「モノからたどる私の戦争」編集部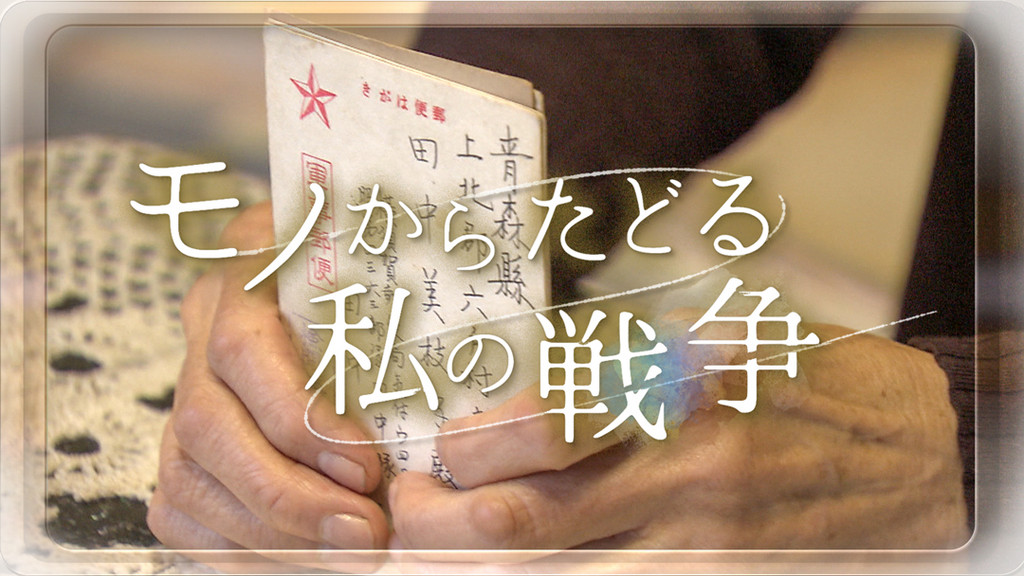
 諸冨泰司朗(記者)
諸冨泰司朗(記者)
 本橋 彩子(キャスター)
本橋 彩子(キャスター)
 編集部
編集部
 小原敏幸(記者)
小原敏幸(記者)