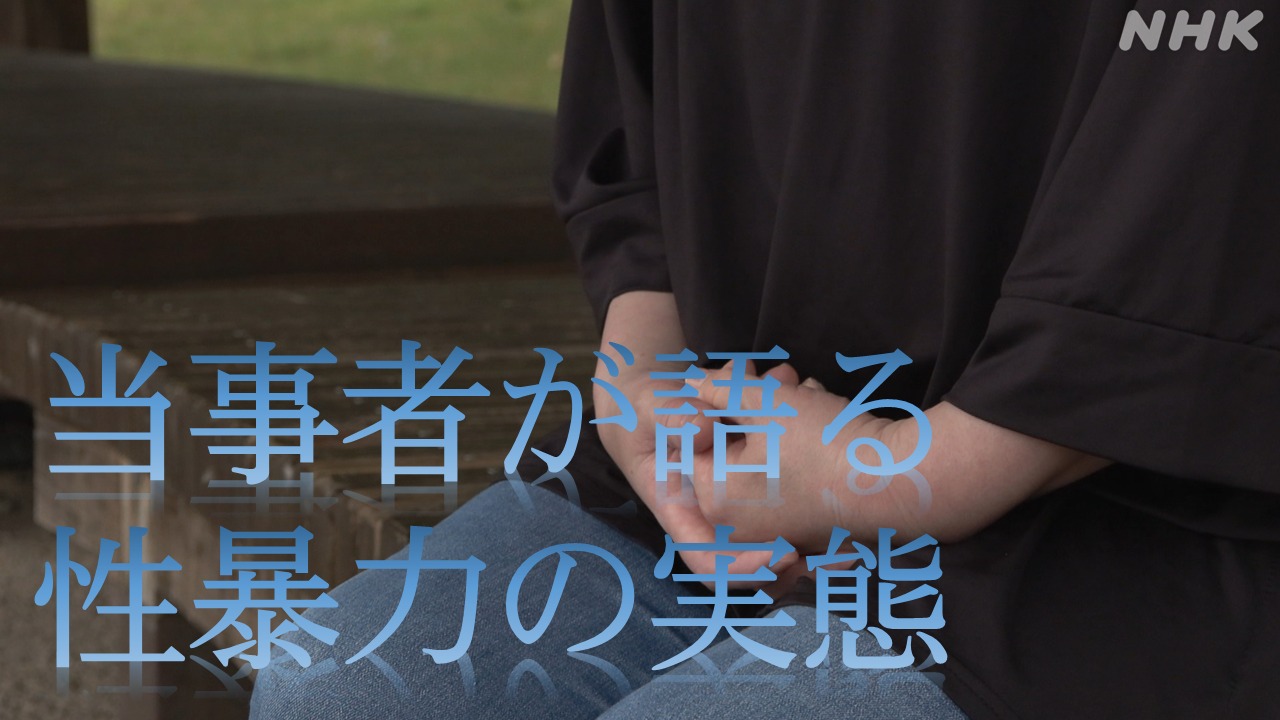ことしのジェンダーギャップ指数富山の順位は?防災の課題は?
- 2024年04月01日


3月8日は国連が定める「国際女性デー」。
NHK富山放送局では、「あなたと変えたい」をテーマにジェンダーに関するテーマをお伝えしています。

国際女性デーにあわせて発表された、都道府県ごとの「ジェンダーギャップ指数」から富山県の課題について考えます。
これは、大学教授などでつくる「地域からジェンダー平等研究会」が、地域ごとに強みや弱みを知ってもらい具体的な取り組みにいかしてもらおうと、おととしから発表しています。
こちらが富山県のことしの順位です。

順位が低いほど性別による不平等や格差が大きいことを示していますが、教育分野は4位、行政分野は8位と去年から順位を上げています。一方、政治分野は44位と下がっています。
どうしてこのような結果になったのでしょうか?政治分野の全国順位のもととなった主なデータです。
政治は全国ワースト4 女性議員の少なさ課題

県選出の国会議員は、女性はゼロ。県議会議員と市町村議会議員の女性の割合は全体の1割程度でした。去年は統一地方選挙があり、鹿児島県議会で女性議員が倍以上に増えるなど他の都道府県で変化があった一方で、富山県では女性議員の数が変わらず、去年よりも順位が下がりました。また、知事や市町村長をつとめた女性がこれまでにいないことも、全国順位が上がらない要因になっていると考えられます。政治に多様な意見を反映させるためにも、女性議員が少ないのは課題です。
4位の教育分野 富山県は校長や教頭への女性登用進む
一方で、4位の教育分野についてもとになったデータです。

富山県は、教育分野では校長や教頭への女性の登用が比較的進んでいて、小学校の校長は男性100人に対して女性は76人と男女の割合が近づいています。
子どもと接する学校の校長先生の男女格差が少ないと子どもの考え方にも影響します。調査した専門家はハラスメント対策にも目が届きやすくなると指摘しています。
防災のジェンダーギャップは?

行政分野の指標の1つ、防災の政策に関わる県内の市町村の防災会議のデータです。防災会議のメンバーのうち、女性の割合は1割とこちらも少なくなっています。全国的に見ても少ない水準です。
ことしは能登半島地震もありましたが、災害の現場に影響はあったのでしょうか。地震の発生直後から避難所運営にあたった氷見市の防災士の女性が現場で感じた課題を聞きました。
能登半島地震 避難所のジェンダー課題は?

3月3日、市役所に集まったのは氷見市の防災士たち。
地震発生直後から避難所の運営にあたり現場で感じた課題を共有しました。

防災士の柳田ゆかりさんです。
この会議で柳田さんが指摘したのが、女性や子ども用の備蓄の不足。
柳田さんが1月1日から避難所運営にあたった氷見市の南部中学校です。

指定避難所となっているこの中学校には、800人もの人が押し寄せました。

避難している中には小さいお子さんとか赤ちゃんとか外国人の方もいらっしゃったので、途中でミルクはないですかと聞かれました。

地震発生からおよそ1時間後、柳田さんは、最初に備蓄倉庫の鍵を開けました。

中には非常食やストーブはありましたが、赤ちゃんの食料は粉ミルクのみ。
哺乳瓶は見つからず最終的にミルクを必要な人に渡せませんでした。

ミルクはあるけれども哺乳瓶がないのでどうされますかと言ったら、哺乳瓶がないんだったらいいですと、断られた方もいました。

さらに、生理用のナプキンは1袋で10枚ほどしかなかったといいます。

感覚的に1袋だけで小さい袋だったので、これではすぐになくなってしまうなと感じました。子どもの用品も女性の用品も少なかったです。はるかに少なかったです。

また、別の避難所で居住スペースに使われたのは段ボールの仕切り。市は見守りをしやすくして災害関連死を防ぐためテントではなく段ボールを使用したといいますが、幅広い世代が避難する中着替えなどプライバシーの確保も課題だったといいます。

テント式ではないので、上からのぞこうと思えばのぞけるというのが難しい部分があった。
日頃から地域の防災活動にあたり災害の発生時には避難所運営などにあたる防災士。女性の資格取得者は男性の4分の1以下と少ないのが実情です。

柳田さんは、防災に関わる女性が増えることで、災害時に女性や子どもが何が必要になるのかという視点で備えができるのではないかとしています。

男性とはまた違う目線で、女性が避難所にいると避難者が相談しやすいということもあると思います。自分たちの気づきを市に提案していきたい。
実際に避難所では備蓄の不足など課題がありました。
ただ氷見市の担当者によりますと、防災備蓄倉庫には最低限のものが入っているため、まずは各家庭で食料や防寒具など非常時に持ち出す袋の準備しておいて、避難するときには持ってきてほしいとしています。
まず自分でも備えをした上で、行政の備蓄にもジェンダーの視点を入れた見直しが必要です。

指標をまとめた上智大学の三浦まり教授は、「災害の影響は男女によって異なるため、それをふまえた防災対策や、避難所運営を心がける必要がある。防災分野は構造的に男性が多いため女性を増やす努力をしないと自然増が極めて難しい」と話していました。
今回取材した災害の現場でも女性や子ども用の備蓄が不足していてジェンダーの課題が浮き彫りになりました。政策を決めるメンバーには多様な視点が必要だと改めて感じました。みなさんも身の回りのジェンダーバランスについて考えてみてはいかがでしょうか。