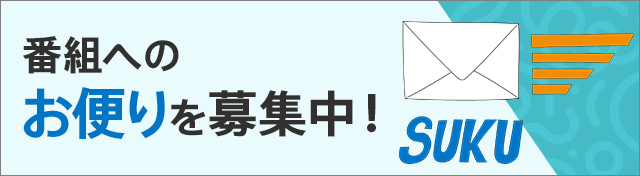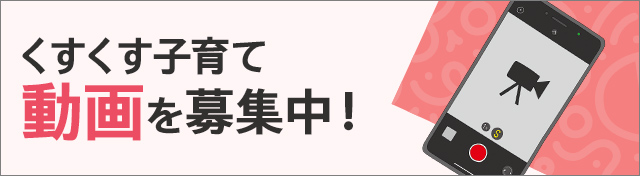2022年6月、東京都が育児休業の愛称を「育業」に決定し、育児にしっかり取り組む期間であると呼びかけ話題になりました。一方で2023年1月には、岸田首相が「育休中の人などの学び直しを後押しする」と応じた国会答弁に批判が集まり、育休のあり方について議論が高まりました。
では、実際に育休を取得したママは、どのような育休を過ごしたいと考えていたのでしょうか。ママ、子どもにとって、どんな育休が望ましいのでしょうか。育休の取得経験のある専門家と一緒に考えます。

「育休の理想と現実(2)パパパの言い分編」はこちら
専門家:
天野妙(みらい子育て全国ネットワーク代表)
小﨑恭弘(大阪教育大学教授)
育休は休暇だと思ってた!
1人目が生まれたとき、育休中に資格の勉強や部屋の模様替えなど、いろいろやろうと意気込んでいました。勤めていた職場に、育休中に勉強して資格を取得した先輩ママがいたんです。夜勤もある不規則な仕事で、仕事をしながら勉強するのが難しく、私も育休中にスキルアップしたいと思いました。
でも、ふたを開けてみると資格なんかとんでもない状況でした。3時間おきの授乳で常に睡眠不足。そばにいないとすぐ泣き出すので、家事すらはかどりません。自分の時間はどこにもないんです。体も心も余裕がなく、1年1か月の育休はあっという間に過ぎていきました。育休は、休みではなく、仕事を休んで育児に専念する期間だと思い知りました。
いろいろできる人がいるのに、自分はできていないと自分自身を責めて、そのイライラが子どもの接し方にも出てしまうこともありました。あとで話を聞くと、資格を取得した先輩ママには、同居の家族からのサポートがあったそうです。状況も違うので、うまくいかないのは当然だったんです。
その3年後、2人目の育休は、育児以外のことで頑張るのをやめました。いろんなことをしようとすると、気持ちが追われて、子どもとあまり向き合えないと思ったんです。1人目の経験で、育休の時間を子どもとゆっくりたのしもうという気持ちになれました。
(お子さん4歳2か月・5か月のママ)
鈴木あきえさん(MC)
このママの気持ちが痛いほどわかります。私も朝の15分ドラマですら見る余裕がありませんでした。録画したとしても、見る時間がありませんでしたね。
すくすくファミリー(ママ)
1人目の育休を取得するとき、DVD鑑賞や裁縫など、ゆっくり自分の趣味の時間を過ごそうと思っていました。でも、そんな余裕はなかったです。初めての育児で、何が正解かわからない中、必死に試行錯誤する毎日でした。2人目、3人目のときは、赤ちゃんのお世話に加えて上の子どもたちの育児もあったので、さらに大変でした。仕事復帰までのTODOリストを作っていましたが、全く予定通りに進まず「明日こそやろう」の連続でした。
すくすくファミリー(ママ)
1人目を出産する前は、絵本の中の世界のような育児をすることを想像してました。
―― 天野さん、小﨑さん、みなさんの話を聞いていかがですか?
キラキラして見えるのは、その人の一部分
 天野妙さん
天野妙さん
私も同じように、キラキラした人を見て、つい「私には能力がないんだ」と思い込むことがありました。でも、キラキラして見えるのは、その人の一部分だと認識できれば、気持ちも変わっていくと思います。また、初めての育児はできないことがあって当然です。野球部に入ってすぐにうまくバットが振れないことと同じなんです。
妊娠出産前に、育児のイメージを持てるように
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
妊娠出産前に、子育て体験イベントに参加するなど、育児のイメージを持てるといいですね。最近では、自治体がプレパパ・プレママセミナーなどを行っています。また、赤ちゃんのいる家庭に遊びにいくのもよいでしょう。先輩パパ・ママと関わって、赤ちゃんや、赤ちゃんのいる生活に触れてください。全国のパパ・ママたちには、ぜひ先輩パパ・ママとして、子どもたちと接する時間や機会を増やしてあげてほしいと思います。
パパの育休、ちゃんと子育てしてほしい!
パパの勤務先の会社では、育児休暇が義務づけられています。そのため、次男が生まれたとき、パパはしぶしぶ1週間の育休をとりました。でも、長男の面倒を頼んでも、ただ動画を見せるだけ。長男と外へ遊びに行っても、「ママじゃなきゃダメだって」と1時間もたたずに帰ってくる。次男の寝かしつけを任せてみると、「おっぱいがないとダメだね」と言って、すぐにギブアップ。育児はおろか、家事も自分のことも、すべてママ任せです。感情的になって「2人の子どもなんだから、ちゃんと子育てしようよ!」と言ったこともあります。
私の仕事はフリーランスで、フルタイムで働いてるパパと比べると収入は多くありません。そのせいか、パパから「家にいるんだから、家事とか育児はママの担当だよね」という圧力を感じます。パパの「名ばかりのとるだけ育休」に、今でもモヤモヤしています。
(お子さん2人のママ)
すくすくファミリー(ママ)
パパに1日、育児・家事を丸投げしてみると、全体の流れをわかってもらえるかもしれませんね。
すくすくファミリー(ママ)
パパは育休中、家事に慣れていない分、臨機応変が苦手でしたね。
―― 天野さん、小﨑さん、みなさんの話を聞いていかがですか?
育休を通して、多様な視点を身につけることが大切
 天野妙さん
天野妙さん
パパが会社から求められて育休をとって、「名ばかり育休」になっている状況がたくさんあると耳にしています。そもそも、政府も含めて、育休取得促進を進めているのは、男女の性別役割分業感を払拭するためでもあります。そして、イントラパーソナル・ダイバーシティー(個人の中に多様な視点や価値観・役割を持つこと)を身につけることも大切です。
例えば、平日の昼間の公園はどんな感じなのか、スーパーの牛乳が昨日より20円高くなっているなど、会社と家の往復だけでは知ることができません。そういった、いろんな視点や価値観への理解の促進も含めて仕事を休むことを、企業側からも伝えてほしいと思っています。
家族でリスクヘッジを
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
ママが感じているモヤモヤの要因のひとつには、パパとママの経済格差があると思います。しかし、この先パパがママよりも収入が多いという確証はありません。やはり、夫婦や家族でリスクヘッジすることを考えれば、パパも育児と仕事ができる、ママも育児と仕事ができる、そのほうが豊かで安全に生きていけると思います。
―― モヤモヤしているママは、パパにどんなふうに伝えたらいいでしょう?
親の先輩としてパパを育てるつもりで
 天野妙さん
天野妙さん
「パパに育児・家事を丸投げしてみる」という話がありましたが、私も夫に任せてプチ家出をしたことがあります。私はこれまでに3育休をとっていますが、実は、夫はとったことがありません。不満だってありました。結婚して21年になりますが、はじめはお湯も沸かせない夫だったんです。
でも、今では私が2泊3日の出張で家をあけても、夫が家庭を回せるようになりました。もちろん、そうなるまでに時間はかかりました。
妊娠期間を考えれば、母親のほうが親として10か月先輩です。先輩としてパパを育てるつもりで考えるといいかもしれません。時間はかかりますが、それが最短距離だと思います。
人間関係にもメンテナンスが必要
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
子どもが生まれて、環境が変わる大きなタイミングです。ここで、人間関係にもメンテナンスが必要だと思います。私が所属するNPOでは、「OSを入れ替える」という言い方をしますが、環境の変化に合わせて、新しい心構えや意識(OS)を作っていくわけです。気づいた人にしか変えることはできません。
でも、残念ながら、気づいてないパパが多いのです。めんどうなことだと承知していますが、気づいたママがパパを育てていくことを意識してほしいと思っています。
子育てのタイミングを考えて育休をとってほしい!
2人目の子どもが生まれてから半年間、パパが育休をとってくれました。一緒に育児をしている実感をえられて、とても助かって感謝もしています。でも、パパの育休明けが、ちょうど新年度のはじまりの4月でした。上の子の小学校入学、下の子の保育園入園が重なって大変だったんです。仕事への復帰時期は、子育てのタイミングを考えてほしかったです。
(お子さん2人のママ)
―― 育休からの復帰時期について、どう考えますか?
育休取得は家庭第一主義で
 天野妙さん
天野妙さん
おそらく4月の復職は、パパの仕事や会社にとって都合がよかったのでしょう。とはいえ、育休明けのタイミングでママに苦労をかけることにつながっているので、会社や自分の都合だけでなく、家庭第一主義で考えることが大事だと思います。
復職と子どもとの生活の優先順位を意識する
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
復職も大事で、子どもとの生活も大事。この優先準備をどう捉えるのか意識するとよいでしょう。育休は突然はじまるものではないので、考えておくとよいのではないかと思います。
パパの育休、もっと取りやすくなってほしい!
パパは育休をとる予定だったのですが、急遽仕事が忙しくなってとれるような状況ではなくなり、そのままとることができませんでした。仕事によってはとりにくい場合もあると思いますが、もう少し多くの業種で育休をとりやすくなってほしいと思います。
(お子さん2人のママ)
鈴木あきえさん(MC)
番組には、このママと同じように、「パパに育休をとってほしいけど、忙しいことがわかっているので言えない、あきらめたほうが楽だ」という声がたくさん届いています。
夫婦でじっくり話し合うことが大事
 天野妙さん
天野妙さん
とても難しいですよね。ただ、最初から「夫はいつも残業ばかりで忙しい、育休は無理だろう」と思い込んでいる場合があるかもしれません。また、我慢して何も言わないと、この先の夫婦関係に影響することもあります。「私のわがまま」ではなく「子どもの育ち」を考えて、勇気を出して、夫婦でじっくり話し合ってください。その結果、育休がとれないとしても、話し合ったこと自体が大事だと思います。
パパの育休、取らずに乗り切った
パパの会社は不規則な仕事が多く、以前は育児に時間を割くのも難しい状況でした。転機になったのは、2020年、3人目の子どもが生まれたとき、新型コロナの流行でリモートワークがはじまったことです。パパは、このリモートワークをフル活用して、子育ての時間をしっかりとれるようにしたんです。

基本的に、夕方5時から夜9時までを「家族の時間」にして、なるべく家事と育児に集中します。夕食の準備や子どものお風呂、寝かしつけなど、育児と家事に一番手がかかる時間帯に、夫婦一緒に過ごせるようにしました。一緒にすることがとてもありがたくて、夫も変わって、家族の関係性もよくなったと感じます。
4人目を出産してからは、産後ケアのボランティアや、ファミリーサポートなどにも頼りました。ほかにも近所の方など、いろんな人に助けてもらっています。
(お子さん4人のママ)
古坂大魔王さん(MC)
わが家もスケジューリングを大事にしていましたね。朝起きる時間を決めて、夕方は6時前に帰ってくる。できれば5時半、園の迎えに行く。それから9時までは仕事をしない。それを週に3回と決めていました。2年半ぐらい続けています。
―― 天野さん、小﨑さん、このような働き方と育児についてどう思いますか?
育休をきっかけに働き方を変える
 天野妙さん
天野妙さん
育休をとっても、そのあと長時間労働に戻ってしまったら、元の木阿弥になってしまいます。そのため、育休をきっかけにパラダイムシフトを起こして、働き方まで変えることを目指していただきたいと思っています。例えば、男性も時短勤務の制度を利用できます。このパパのようなリモートワークもあります。近所の方のサポートや、外部のサービスを活用することも重要です。
「助けて」と言える力、受援力を身につけて
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
育児のために、パパもママも、まわりの人たちも巻き込む、まさに「チーム育児」ですね。ママだけが育児するのではなく、みんなでするわけです。私も近所に住んでいた友だちの母親にいろいろとお世話になったことがあります。
そのように、まわりの人たちに「助けて」と言える力を身につけてほしい。最近では「受援力」と言われています。子どもは人と人をつなぎます。そのパワーをうまく使える家族・親になってほしいと思います。
育休・ここが不満!
「育休・ここが不満!」というテーマで、みなさんの話を聞きました。
育休で保育園の時間が短くなる!
育休中、保育園に預けられる時間が短くなるのが困る。パパに頼めていた送迎がママの担当になって大変でした。
鈴木あきえさん(MC)
自治体によっては、育休中は上の子どもを保育園に預けられなくなるなど、地域差がありますよね。
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
いろんなところで問題になっています。実は、育休中でも一定の保育が認められていますが、地域によっては待機児童の課題もあり、なかなか解消できないのです。
 天野妙さん
天野妙さん
とても気持ちがわかります。この逃げ道を探るとすれば、例えばパパが時差出勤して、朝の送りを担当するのもひとつの方法です。また、外部のサービスを利用したり、近所の方の力を借りたり、同じ育休中のママ友の力を借りてみたりできるとよいのではないかと思います。
育休で収入が減ってしまう!
フリーランスなので育休中の補償がありませんでした。フリーランスにも育休の給付金があると助かります。
育休で半年を過ぎると、給付金の割合が下がるのは困ります。せめて1年間は同じ割合で支給してほしい。
鈴木あきえさん(MC)
やはりお金の問題が気になりますよね。育休で収入が減ってしまうことが大きいと思います。
 天野妙さん
天野妙さん
現在、政府が「骨太の方針」という方針を定めているところで、その中で自営業者・フリーランスの方々の所得補償について議論が進んでいます。また、育児休業の2か月間は、育休給付金の給付率を100%にすることも検討されています。そのように、少しずつですが変わってきていると思います。
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
日本の育児休業制度は、世界的に見ると優れているといわれてます。育休がない国もたくさんある中、期間が長く、給付率も世界一だといいます。基本的に育児休業中は社会保険料が免除され、手取りは休む前の8割程度になっているので、育休を自分たちの生活を見直すタイミングにしてほしいと思います。
育休を夫婦で話し合うきっかけに
 天野妙さん
天野妙さん
育休は、自分たちが何を大事にするのか、どうして働いているのか、何でお金が必要なのか、子どもにどんな教育を受けさせたいのか、自分たちがどういう親でありたいかなど、そういったことを話し合う絶好の機会です。実際に育休をとれるかどうかに関わらず、話し合うきっかけにしてほしいと思います。
また、パパが育休をとることで、ママの産後うつの抑制にもつながります。子どもが生まれるときは、ぜひ育休について話し合ってください。
育休はすてきな家族になるための助走期間
 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん
育児は、自分たちの都合だけで進めることはできません。妊娠のタイミングや出産のタイミングもそうです。出産が予定より早くなることもあります。いろんなことを「チーム家族」で頑張って乗り越えていくような家族をつくっていってほしいと思います。まずは子どもの育ちを大事に、育休を、これからすてきな家族になる助走期間だと考えてみましょう。


 天野妙さん
天野妙さん 小﨑恭弘さん
小﨑恭弘さん