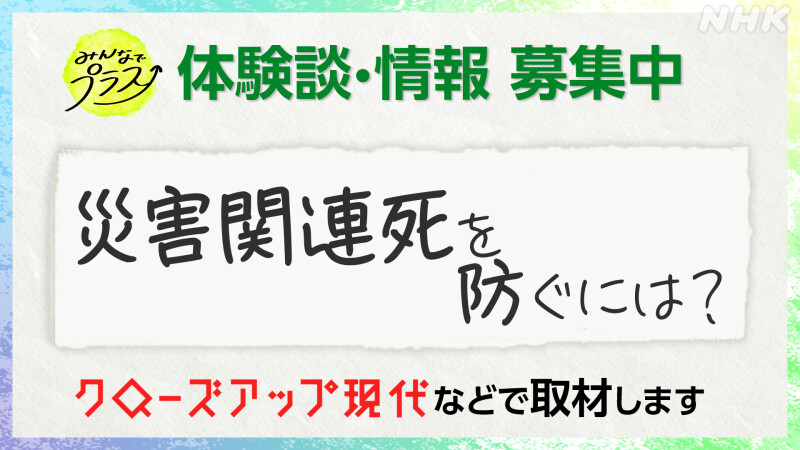2024年1月19日
18コメント
-
 はなえむ
はなえむ - 母は若年性アルツハイマーですでに寝たきり。二人暮らしをしてくれていた父が昨年急に認知症が進みました。様子を見に行った後、なんとなくワサワサした気持ちで帰るのですが、そんな時、阪急電車のラッピング電車を目にすると、夢中になって動画を撮り、気分が上がります。今は ちいかわ や ミャクミャク列車が走ってます。