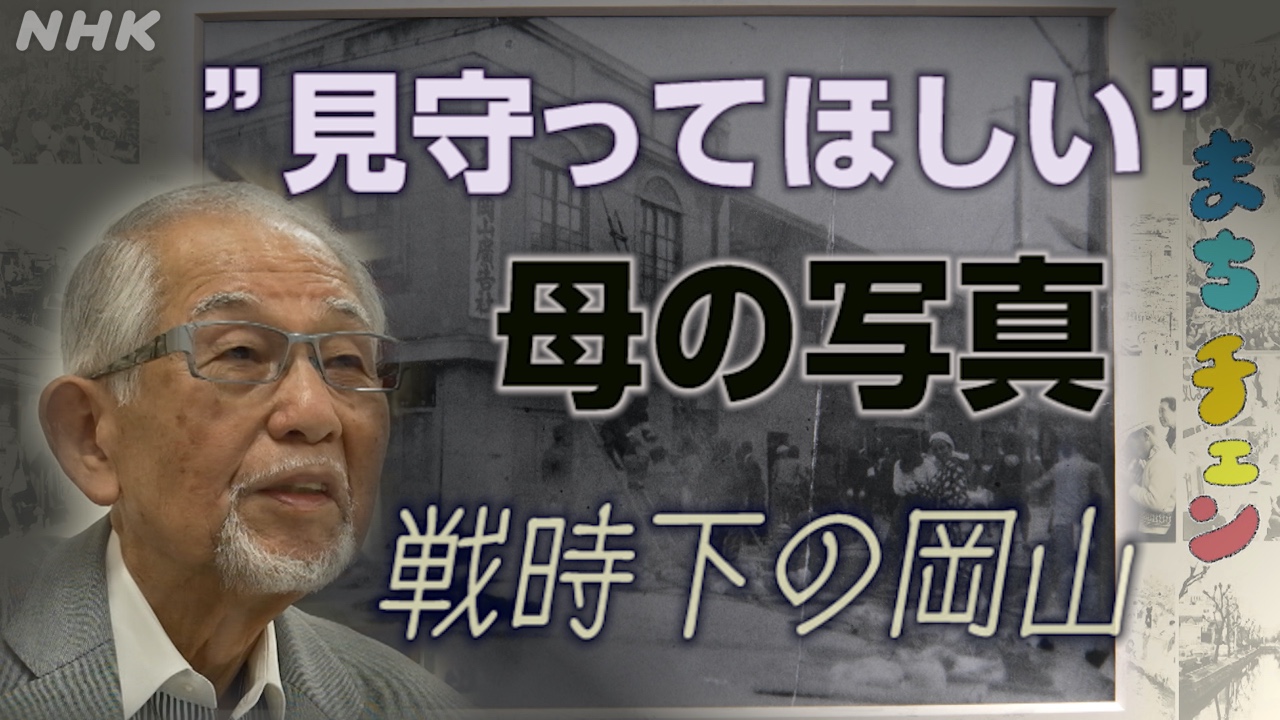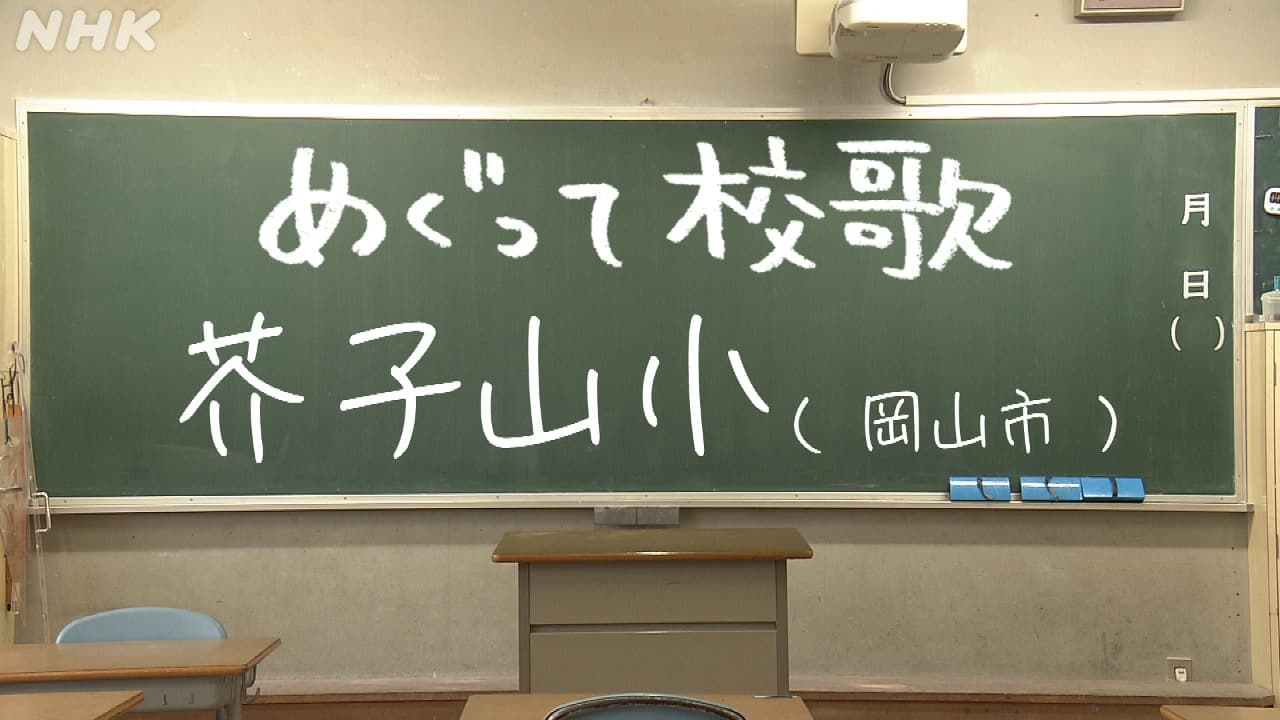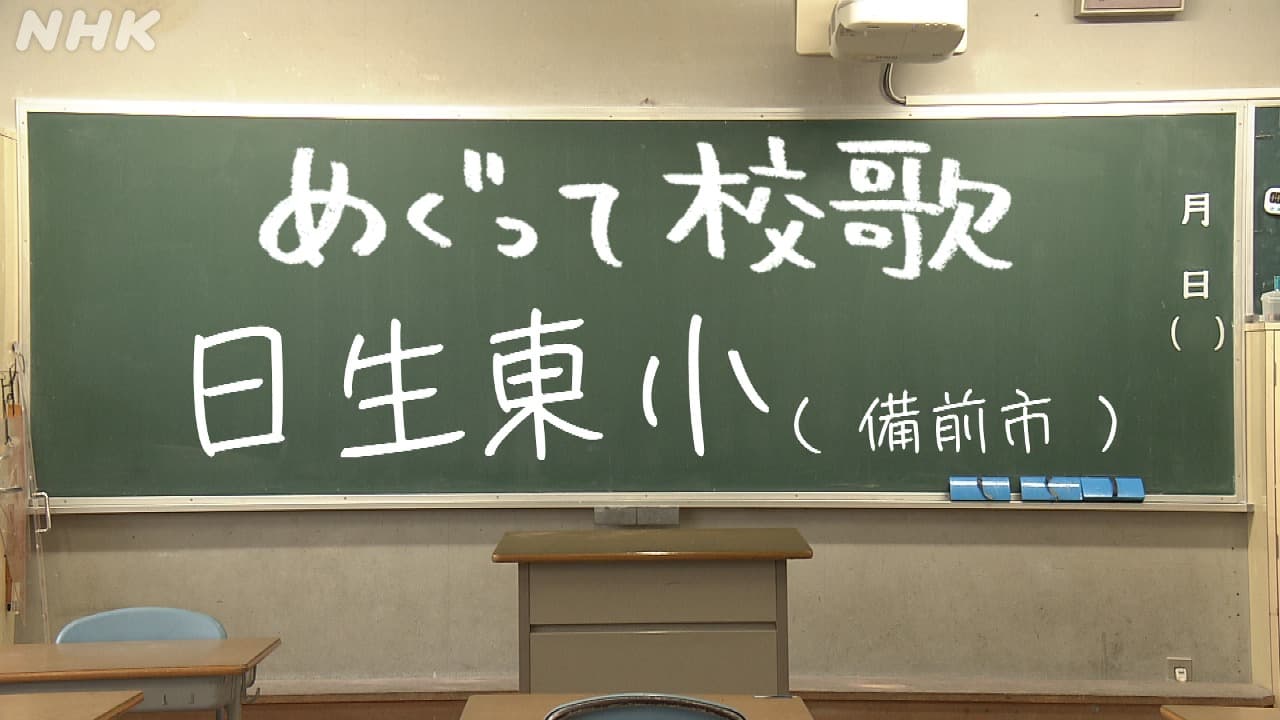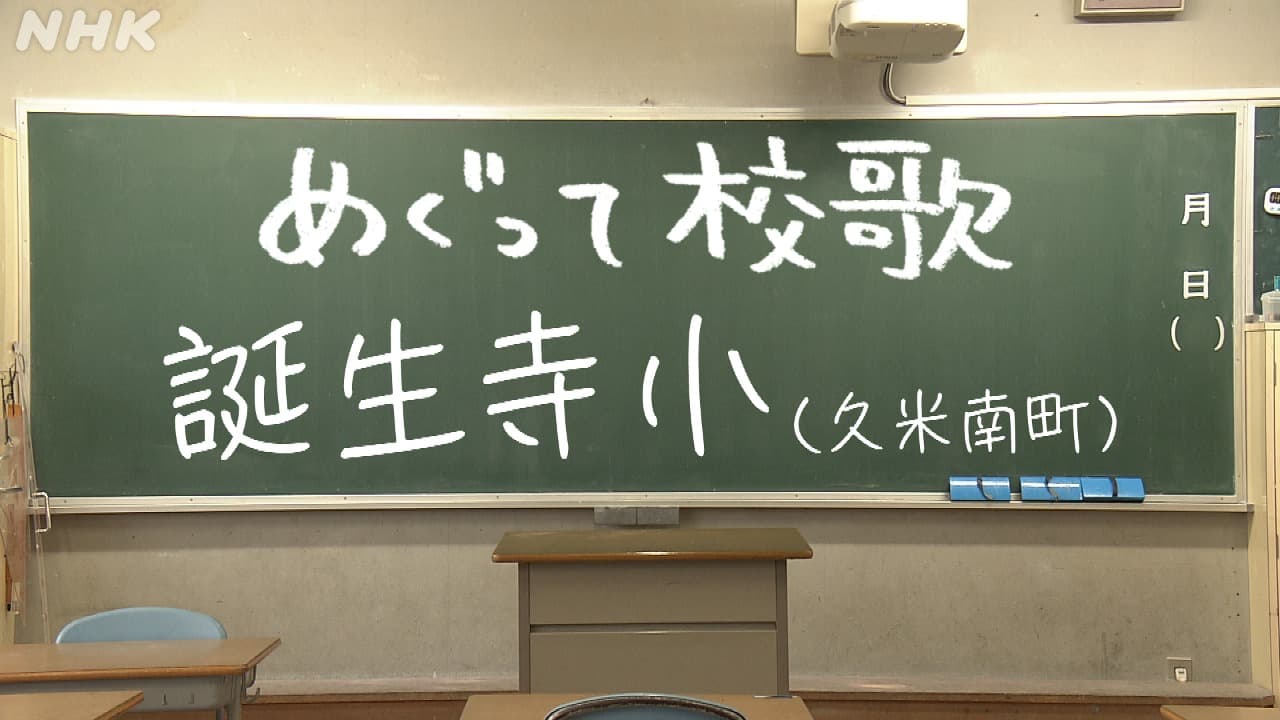岡山発 司令官の孫 岡山で“沖縄戦の情報提供を”
- 2024年01月31日

太平洋戦争末期の沖縄戦について調べている旧日本軍の司令官の孫で70歳の男性が岡山市内で講演しました。岡山県によると、県内出身者の沖縄戦での戦没した人は確認されているだけで、中国地方で最多の1847人。「岡山の人も関わった沖縄戦の歴史を平和のために知ってほしい」と男性は訴えています。
(岡山放送局記者 入江和祈)
祖父は沖縄戦の司令官

令和5年12月、岡山市北区の公民館で約20人を前に話をしたのは、東京の牛島貞満さん(70)。牛島さんの祖父は、旧日本陸軍の第32軍司令官、牛島満です。20万人を超える人が犠牲になった沖縄戦で軍を指揮しました。牛島さんは約30年前、沖縄を訪問し、それをきっかけに、祖父のことや沖縄戦について調べています。
岡山で講演した訳は?

牛島さんが岡山県にやってきて話をしたのには、理由がありました。
それが首里城の地下にある第32軍司令部壕の存在です。岡山と深いつながりがあるのです。

牛島司令官は昭和20年5月22日、この第32軍司令部壕を放棄し、島の南部への撤退を決めました。この撤退により、南部に避難していた民間人も戦闘に巻き込まれました。

この判断が沖縄戦をさらに悲惨な状況にしました。

牛島さんは、司令部壕について分かりやすく伝えようと、全長3メートルもの大きさがある手作りの模型を用いて、詳しい構造や、牛島満司令官がどこで指揮をとっていたかなどを説明しました。
この壕を造ったのは「第2野戦築城隊」という部隊です。牛島さんが国立公文書館の文献を調べると、この部隊は岡山県で編成され、隊員576人うち183人が岡山県の出身者だったことがわかりました。183人のうち、故郷に戻ったと考えられる人は47人。戦死率は74.3%でした。

悲惨な歴史を語り継ぐには、司令部壕の保存や公開をする必要があると考えてます。当時の状況をより明らかにするために、出征した隊員についての資料や証言などの情報を求めています。
火災で焼失した首里城の正殿の再建が2026年の完成を目指して進められていますが、沖縄県によりますと、それにあわせて、地下の司令部壕も一部公開する予定だということです。
少しでも実態に迫りたい

牛島さんは、岡山県遺族連盟などの協力を得て、今の岡山市東区の出身で船大工だった隊員を知り、紹介してもらった遺族に話を聞くことができたと話しました。
そして、編成された部隊が、どのような作戦に参加して動いていたのかが書かれている行動履歴と、隊員の名簿を読み解きました。めまぐるしく戦況が変わるなかで、隊員たちは警備をしたり、戦闘に関わったりと、かわるがわるさまざまな役割を担っていたと、講演会のなかで牛島さんは報告しました。

戦争の歴史というのは戦闘部隊を中心に描かれていることが多いが、実際は陣地を構築したり、道路を作り直したり、さまざまなことが組み合わさって戦争が起きている。工兵隊の部隊も詳しく調べていく必要がある。
これからも沖縄戦の実態に迫ろうと調査を続ける牛島さん。情報があれば寄せてほしいと呼びかけています。

国内最大の地上戦の歴史を知ることが、今後の平和をつくる上でとても大事だ。沖縄戦の重要なポイントである司令部壕をつくった人たちは岡山県出身の方々が多く、どんな方々だったのかということは沖縄で十分に調べられていません。資料もないので、ご遺族にたどり着いて調べていきたいと思う。