
【第4回】発災時 データで命は守れるか ~自治体編~



二瓶(東京理科大学):ご説明ありがとうございました。令和2年7月豪雨時の説明で、「様々なインフラが使えなくなる」というのが連鎖的に起こっていたと話をされていましたが、それは事前にどれくらい予測できていたんでしょうか。

三家本(熊本県危機管理防災課):過去にも大雨が降った場合には、停電はよくあることですので、その辺りはだいたい認識をしておりました。また特に、NTT回線の、特に有線についてもよく落ちるんですが、携帯電話が意外と弱かったというのが実情です。携帯電話も、基地局をやられた場合がありますし、電気が通じませんので、各市町村の担当者も充電ができなくなり、7月4日、土曜の夕方くらいからですね、電池切れで携帯電話自体が使用できないというのもありました。当時は、KDDIと災害対策本部の携帯電話がまだ繋がってたんですが、結局充電が切れてしまって使えなくなったということで、7月4日の夜くらいからですね、ほとんど携帯電話も使えなくなりました。そこは我々も予期していませんでした。また衛星携帯も持っていまして、また各通信業者からお借りして配ったんですが、これもやはり天気が相当、雲が厚いとなかなかうまく繋がらないということがわかりましたので、特に携帯電話の脆弱性について痛感しました。携帯電話は脆弱なんですが、しっかりと基地局に、中継機材等を持っていけばすぐに回復するということで、逆に復旧性も一番早いということが分かりましたので、天気が良くなれば、ヘリコプターを使って、中継機材等を運んでいけばですね、早く回復することが分かりました。逆にNTT回線や電力線についてはやはり、道路が直らないと修復できないというところも今回強く感じたところです。

二瓶(東京理科大学):そうすると、どこを強靱化しておくといいのかというと、どこでしょうか。

三家本(熊本県危機管理防災課):一番最後まで生き残ったのは行政防災無線ですね。アンテナが、中継局さえ生きていれば無線が飛びますので、これが非常に強かったなということです。これは県と市町村でも無線の中継ネットワークを作ってましたので、これが使えたということと、それから市町村と住民の方々も無線を使っていろいろ連絡をやりとりしていましたので、これは非常に強靭性があるなあと。ただやはりデータが送れないということと、なかなかいっぺんに多くの情報を流すことに困難があります。なので、課題が残りましたが、無線については期待感がありました。自衛隊は多重無線を持っていますので、無線を通じてデータを送るなどの機能がしっかりできていますので、かなりお金がかかる世界ですが、無線を通じたいろんな情報のやり取り等をもっとパイプを太くできればよいなと。しかし現状については、携帯の基地局が使えなくなればダウンしてしまいますので、やはり長いレンジ、つまり長い距離を飛ばせるような、中波以上の無線を使う機能があれば、非常に災害時でも、抗堪性、強靭性はあるのではと感じております。
二瓶(東京理科大学):分かりました、ありがとうございます。

畑山(京都大学):最近、準天頂衛星が上がっていて、Q-ANPIというシステムが実験的に使われていています。孤立集落と連絡を取ろうという際の1つの手段として、準天頂衛星を使った通信はアリじゃないかと思いますが、この辺りは、熊本県では実験的なことをしていますでしょうか。
三家本(熊本県危機管理防災課):Q-ANPI については避難所管理をしています、県で今、実用試験に協力しています。
畑山(京都大学):使えそうでしょうか。それとも防災行政無線があれば、いらないのではという意見もありそうですが。
三家本(熊本県危機管理防災課):今、被災地の県南では防災行政無線をまさに強化する、あるいは複数の支援を使うという話も進んでいますので、それを進めていくのか、Q-ANPIを入れるかについては結論は聞いていませんが、検討をしているというふうに聞いております。
畑山(京都大学):デジタル行政無線はあちこち置いておくわけにはいかないものだと思いますので、できれば、どこかに集約して、Q-ANPIと連動したようなシステムになるといいのかなと思っています。
関本(東京大学):三家本様、ありがとうございました。
関本(東京大学):続いての議題に行きたいと思います。「検討会の知見取りまとめ資料・今後の方針」につきまして、よろしくお願いいたします。
捧(NHK):産学官民連携で、「こういったことが実現可能なんじゃないか」というお考えがある方はいらっしゃいますでしょうか。
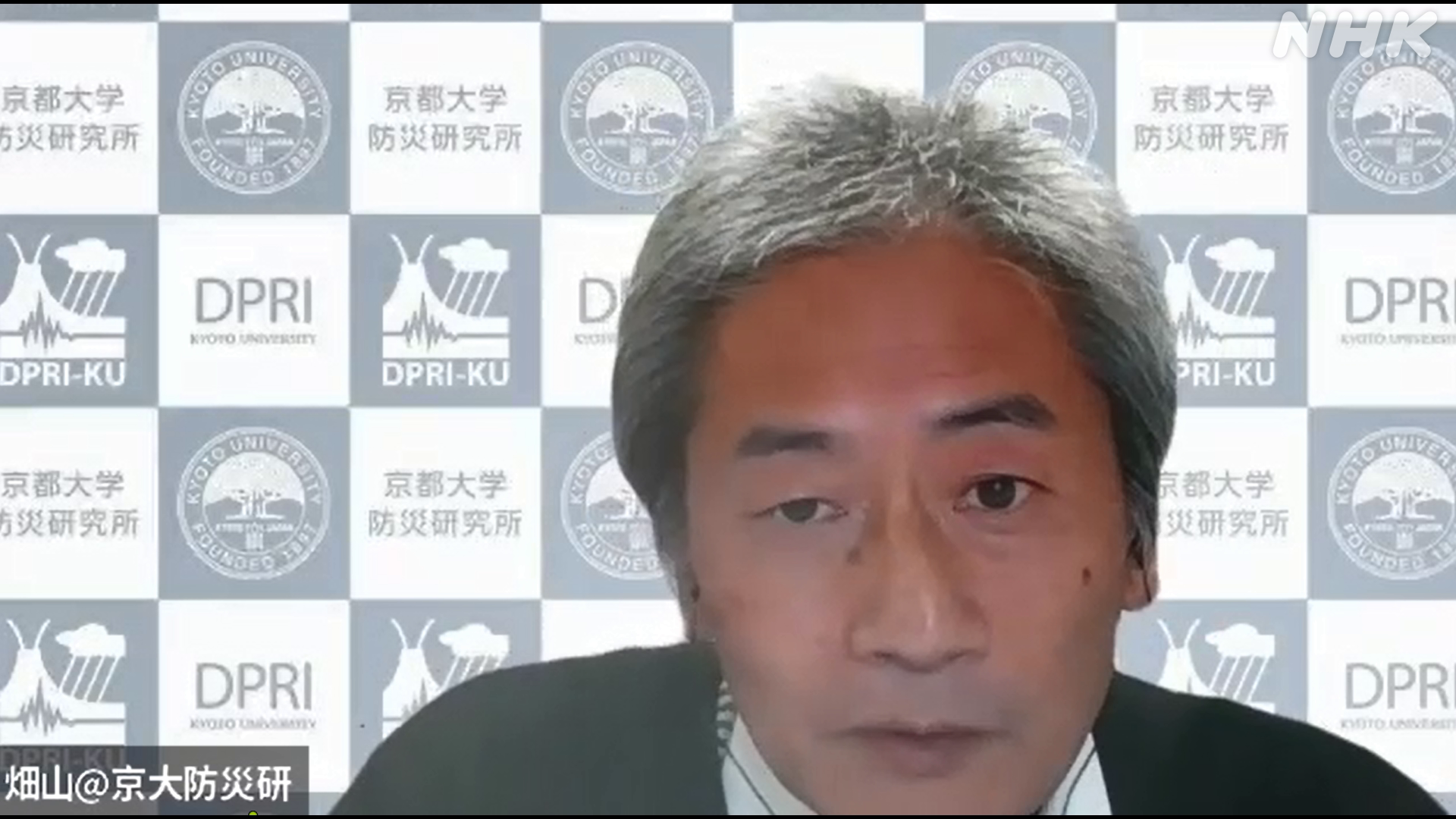
畑山(京都大学):人流データは非常に魅力的でですね、我々も、令和2年7月豪雨のデータを使って分析したりしています。災害研究の世界で、「このデータはどう使えるか」というのを検討している中で、人の行動、災害時の行動は研究している人は多い。多くの場合に、「避難した」とか「避難しなかった」というアンケートをとって、それが何に依存しているのかといった要因分析をするんですが、そこから、態度変容させるための要素を引っ張り出して、どういうキャンペーンをしたらいいのか、どういう情報をどう出せばいいのかなど研究をしています。しかし、そもそもその研究、そこで出てきた避難のモデルというのが、どれほど現実を表してるのかという評価はされていないんです。浸水のモデルを作ったら、本当に今回の浸水はこのモデルで説明できたかということを検証されると思います。それは事後に、浸水エリアをしっかり皆さんで調査されて、それから実績を作って、それで自分のモデルにどういうパラメーターを設定したらそういうことが説明できるかという話をされて、モデルの妥当性を検証されますが、避難のモデルは実はそれがないんですよ。なぜそれがないのかと長年思っていますが、「答えがないから」だと思っています。浸水エリアなら調査すればわかるんですけど、「人がどう動いたか」って実はなかなかわからない。ですが、それがモバイル空間統計などの人流データが答えになりうるんじゃないかというのを最近議論しています。例えばそういったデータを答えにしたようなプラットフォームを作って、多くの人たちが様々な分析を出してくる。避難の行動などの検証もプロジェクトを作れないか。いま関係者でそういったものを作ろうと動いています。どういうデータがどう揃うと、どういうことを推定できるかってちょっとずつ変わってくるので、できるだけ多くのデータが集まったプラットフォームを作りたいんですね。例えば令和2年7月豪雨の再現でも構わないし。これから先の話もやりたいんですが、まずは過去の象徴的な災害のデータを集めて、再現できる形を整えつつ、その間を繋ぐ推定モデルを評価していくというのを、考えているところです。これをうまくやると、研究者はモデルの評価ができるし、もう一つは、人の行動ってあまり変わらないので、よく見ていくと、「避難所に人を派遣しなきゃいけない時間帯はどの辺なのか」とか、そういったタイムラインも、人の動き自体からわかるので、読めるようになってくるんじゃないかと思っています。そういうところに繋がるプラットフォームと研究評価を、産官学民連携でできないかと考えています。

関本(東京大学):畑山先生が土木計画の中で研究会等もされていますし、災害時の行動変容を実際の実データ、事故の実データでちゃんと検証する、1つではなく複数の事案で行うのも大変重要と思います。