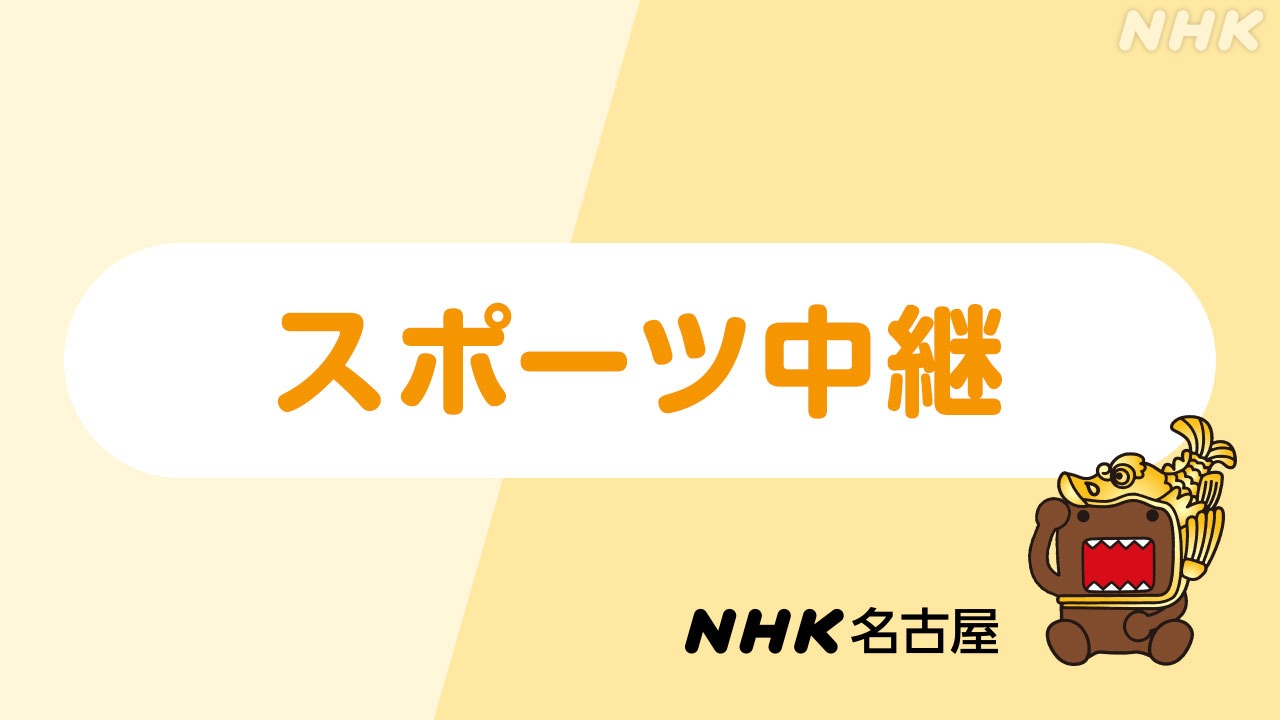聖火トーチ「心臓部」は愛知製
- 2024年05月15日

7月に開幕するパリオリンピック。その聖火トーチの心臓部を作ったのは、実は愛知県豊川市のメーカーなんです。東海地方の「すごい」を紹介する「東海すごいぜ!」。今回は、フランスに送られた聖火トーチの3つの「すごい」を取材しました。
聖火トーチの「心臓部」を製造したのは豊川市のメーカー
これがそのトーチ。
実物を持たせてもらうと…。


持つとずっしりします。重さは1.5キロ。
聖火ランナーとして走るとなると結構体力がいります。
この聖火トーチの心臓部を製造した愛知県豊川市のメーカーです。

本業は登山やキャンプで使うコンロやランタンなどの製造をしています。
過酷な環境でも炎が燃えるとして、エベレストを目指す登山隊などにも採用されています。

選ばれたのが「すごい」

愛知の中小企業が聖火トーチ作りに選ばれたのがまず「すごい」。
でも、いったいなぜ選ばれたのでしょうか?

新富士バーナー 山本洋平さん
パリの組織委員会の方から突然メールが届きまして、トーチの燃焼部を作ってくれる企業を探しているが参加する興味はないかと。
私どもはもともと、東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレー用トーチも製造しておりましたので。
東京オリンピックのトーチに関わった実績が評価されました。
担当したのは、トーチの炎を出す燃焼部とガスボンベです。

今回はトーチおよそ2000セット分を納入。
ひとつひとつ手作業で丁寧に組み立てます。
水中で内部に空気を送り込んでみて、ガスが漏れないかもチェックします。

トーチの肝となる燃焼部。
与えられた開発期間はわずか1年だったといいます。


非常に光栄ではあったんですけれども(準備の)期間も短かったものですから、どこまで完成度をあげられるか、そこが不安なことでもありました。
聖火が消えないつくりが「すごい」
二つ目の「すごい」は、雨が降っても風が吹いても消えない、このトーチづくりです。

課せられたのは、1時間に50ミリの大雨や、時速60キロの突風の中でも聖火が消えないトーチをつくること。

ここからのぞくと、そのカギが見えるというのですが炎しか見えません…。
実は外から見える炎とは別に、トーチ内部にいわば「種火」があります。


聖火を象徴する赤い炎を守るために種火を作っておく必要があるんです。アウトドア用のランタンに使われている技術なんです。
これがそのランタン。

点火するとまず青い炎がつきます。
この炎の温度は1500度ありますが、そのまま熱すると、プラチナでできた網目状の部分が 赤くなってきます。

プラチナの表面では200度ほどの低い温度でも燃焼が続くので、炎が消えにくくなります。

この仕組みをトーチ内部にも取り入れることで、激しい雨や猛烈な風でも聖火が消えないトーチが完成しました。
炎のかたちが「すごい」
3つ目の「すごい」はトーチから出る炎のかたちです。

今回取材したのはギリシャでの採火式より前。
本番まではお見せできないということなので、絵に描いてもらうと…。

これが山本さんが実験で見た炎のかたち。上ではなく横から炎が出ています…。

ランナーが走ると、赤い炎が横にたなびいて見えるようにしたいとパリから要望がありました。
その仕掛けが、トーチの裏側にあるこの細長い穴です。


ここから赤い炎が出てきて、旗のようにたなびくような設定になっています。色・形状、そういうところにすごく細かい指摘がありました。聖火にすごく価値があるものだという情熱も感じましたし、そういうものを実現できるところにすごくやりがいがあったなと思います。
4月、ギリシャで採火式が行われ、聖火トーチも初めて披露されました。
パリオリンピックの聖火リレーは5月8日からフランス国内で始まり、合わせておよそ1万人の聖火ランナーが開会式が行われるセーヌ川へとつなぐ計画です。

山本さん
何よりも無事に走り切ってほしい。最後、聖火台に無事に点火してほしいなと思っています。
ちなみに今回は1本の聖火トーチを10人ほどのランナーが共同で使う予定です。
東京オリンピックの時の1万3000本に対してパリでは2000本に減らしています。
資源をムダ使いしない「SDGs」も今回のパリ大会のメッセージになっています。