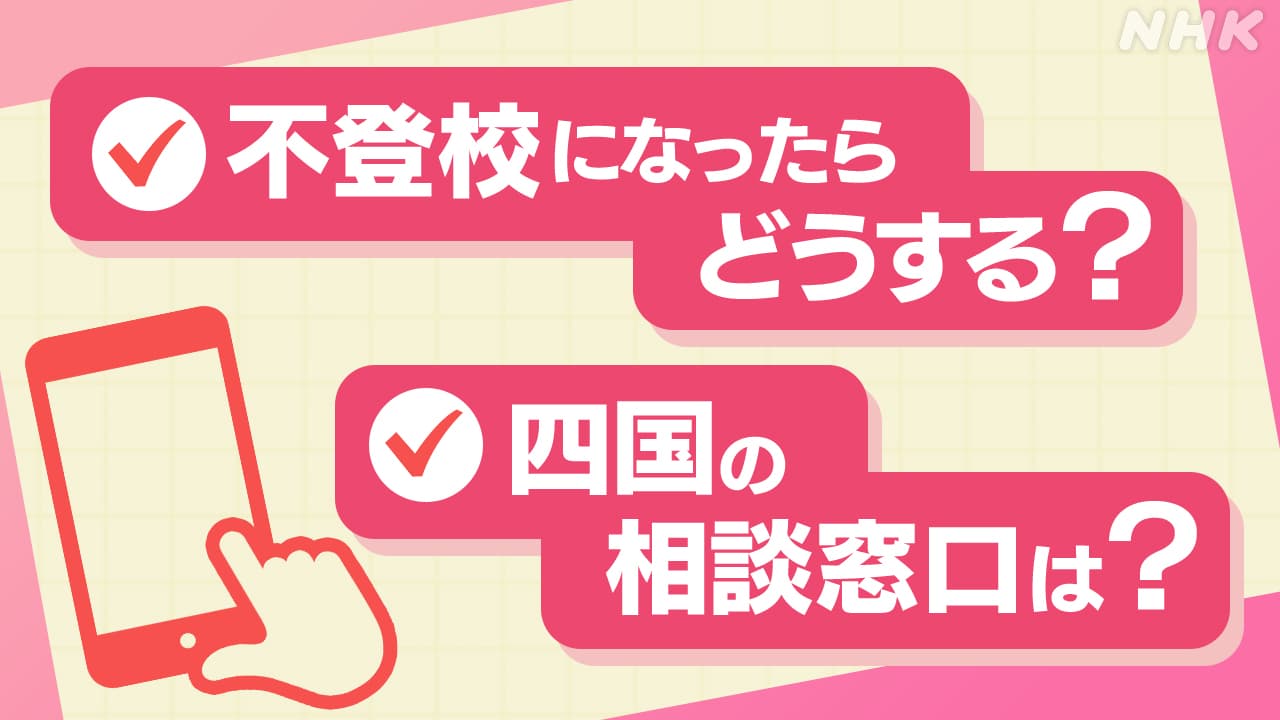愛媛県松山市の高校に新設 “不登校経験者が通いやすい”コース
- 2024年05月27日

2022年時点で四国の小中学生の不登校の生徒は7500人以上。
5年間で2倍に増えています。
フリースクールなど、“学校以外”に様々な選択肢が広がる中、不登校経験を積極的に受け入れ、入学希望者が急増している高校が松山市にあります。
どんな学校なのか、取材しました。
(NHK松山放送局ディレクター 大久保凜)
入学希望者が急増する新設コース
その学校は、松山市にある私立の松山学院高校です。
130年前に創立され、普通科のほかに調理科や福祉科があります。

その普通科の中に2年前、新設されたのが今回取材した“Newコース”。
過去に不登校を経験した生徒のみを受け入れる、全国でもユニークな取り組みです。
3年目を迎えた2024年の新入生の数は初年度の4倍近い169人が入学。
コース全体でも生徒数は300人以上になりました。
いったいなぜ、こんなに人気なんでしょう。
“自分のペース”が守られた学校生活
学校の始業時間の朝8時半。
Newコースの教室に、生徒は4人しかいませんでした。

授業が始まると、ぽつりぽつりとやってくる生徒たちの姿が。
「今来ました」と彼らがコース専用の職員室の入り口で中に呼びかけると、教員が「おはよう!よう来たね」とにこやかに出迎え、教室へと向かう後ろ姿を温かく見送ります。

「遅いじゃないか!」「なんで遅刻したの!」ととがめる声は一切聞かれません。
むしろ一緒に教室まで付き添ってあげることもあるくらいです。
一度不登校を経験すると、生活のリズムが崩れて朝起きづらい生徒が多く、決して本人の“怠け”や“サボり”ではないと学校側も受け止めているためです。
そのため、このコースでは各自で自分の体調を見ながら自主的に登校してもらうようにしています。

Newコース長 尾下桂子さん
「遅れてくる理由は聞かないですね、コントロール(本人の自己管理)だから。自分で“今日はこの時間割りやけん、この時間に来よう”ってしている子が多いので、そうやってコントロールしながら授業に参加していく。無理のないように。(教室も)だいたいは行けるんですけどちょっと不安そうな子には『行こうか』って声かけていきます。その子の状態に合わせています」
一度教室に行けたとしても、50分の授業の間、長時間座り続けることにも苦労する生徒もいます。
そのため、コースではクラスとは別の教室が用意され、休憩したり、自習したり、オンラインで授業に参加したり、自由に過ごすことができます。

生徒との距離感と信頼
学校で取材を続けていると、教室の外にあるベンチで教員と生徒が話し込んでいる姿をよく目にしました。
これも、生徒たちが通いやすくする工夫の一つです。
教員たちはなるべく生徒の近くにいて、気軽に声をかけるよう務めています。

そして学校生活や体調、進路のことで悩みがあったら、こうして隣に座ってゆっくり話を聞きます。
こうすることで信頼関係を築き、徐々に心を開いていってくれるといいます。
教員たちは生徒同士のコミュニケーションにも一役買っています。
この日の昼休み。
空き教室をのぞくと生徒たちのランチに担任の教員も混じっていました。

はじめのうちは話しかけるきっかけがつかめなかったり、会話が続かないことも多いため、教員が輪に入って手助けするんだそうです。
この日は「好きなアイドルな誰か」と教員が切り出すと、それをきっかけに生徒同士が会話を始めました。

Newコース担当教員 新開多恵さん
「“お昼のランチ”は一緒にご飯を食べるイメージはすごくあるんだけど、じゃあ誰とどこで食べたらいいかってところから始まって、そこでじゃあ先生きっかけを作ろうと、一緒に食べることが多いですね。コミュニケーションの仕方がわからないだけで、私がしゃべっているのを見ながら同じことをしてみたり、いろんな子に話を振ってみたり、少しづつ話せるようになってるから、きっかけづくりが必要なのかなと思います」
高校卒業の単位を未来への切符に
ここまで“通いやすさ”にこだわる理由の一つに、高校卒業に必要な単位を取ってもらうことがあります。
そのため必修科目は生徒たちが集まりやすい2限目以降に設定し、夏休みなどの長期休みの間には学力の遅れを取り戻せる補習も充実させています。
なぜ、このようなコースを作ったのか。
コースを立ち上げた校長の吉田慎吾さんに聞きました。
吉田さんは長年、中学校の教師をしていました。
不登校の生徒と関わる中で、出席日数が足りないなどの理由で高校進学の道が限られてしまうケースをいくつも見てきたといいます。

「私が中学で教えていた当時は子どもたちが高校へ行きたいと思っていても預かってくれる高校がなかったんです。保護者の方にも生徒本人に申し訳ないなと思いました。“未来に向かって羽ばたきなさい”っていう切符を渡したかったので、自分がこの立場(高校で働く立場)になったらうちにおいでっていってあげられるようにしたいと思っていました」
自分の気持ちが話せるように
このコースに通う2年生の岡山優希さんです。
中学3年生の時に不登校を経験しました。
きっかけは苦手なクラスメイトがいたこと。
それでも学校には時々行きましたが、クラス替えで仲がいい友人とも離れてしまい、行けなくなりました。
高校進学を検討した時、通学できることが選ぶ決め手になったといいます。

「最初は通信制とかも考えていたんですけど、やっぱり学校ちゃんと登校したいなって気持ちもあって。『行きたい』って気持ちは結構強かったんだと思います」
それでも入学当初は人と接することが苦手で、数週間は自席から動けずに固まっていたそうです。
教員や同級生と会話を積み重ねる中で、次第に自分の気持ちを怖がらずに伝えられるようになりました。今は将来の目標も見つかって、毎日充実しているといいます。

Newコース2年生 岡山優希さん
「先生がみんなと話せる、友だちを作れる機会を設けてくれて、そこから同じ趣味が見つかったりして話せるようになっていったと思います。自分の中でとどめていたちょっとした悩みも、この学校に来て先生に話しやすくなってあんまりため込まなくなりました。卒業後は情報系の大学に進学したいです」
3年目を迎えたNewコース。
来年の春、初めての卒業生が誕生します。
取材後記
Newコースを取材する中で、一度は不登校になっても、「もう一度学校に行きたい」と願う生徒がこれだけたくさんいるんだということを知りました。
とくに印象的だったのは、このコースの職員室の様子です。次から次へと生徒がやってきて、先生に悩みを相談したり、時には雑談をしたり。生徒にとって温かく、安心できる教員がいるこの場所がよりどころになっているんだと実感しました。
来年の春には1期生たちが卒業します。一度不登校を経験し、その上で“学校に通うこと”を選び、3年間の学校生活を経て最後に何を思うのか。みんなどんな道を選んでいくのか、今後も取材を続けたいと思います。
特集の内容は下記の動画でもご覧いただけます。