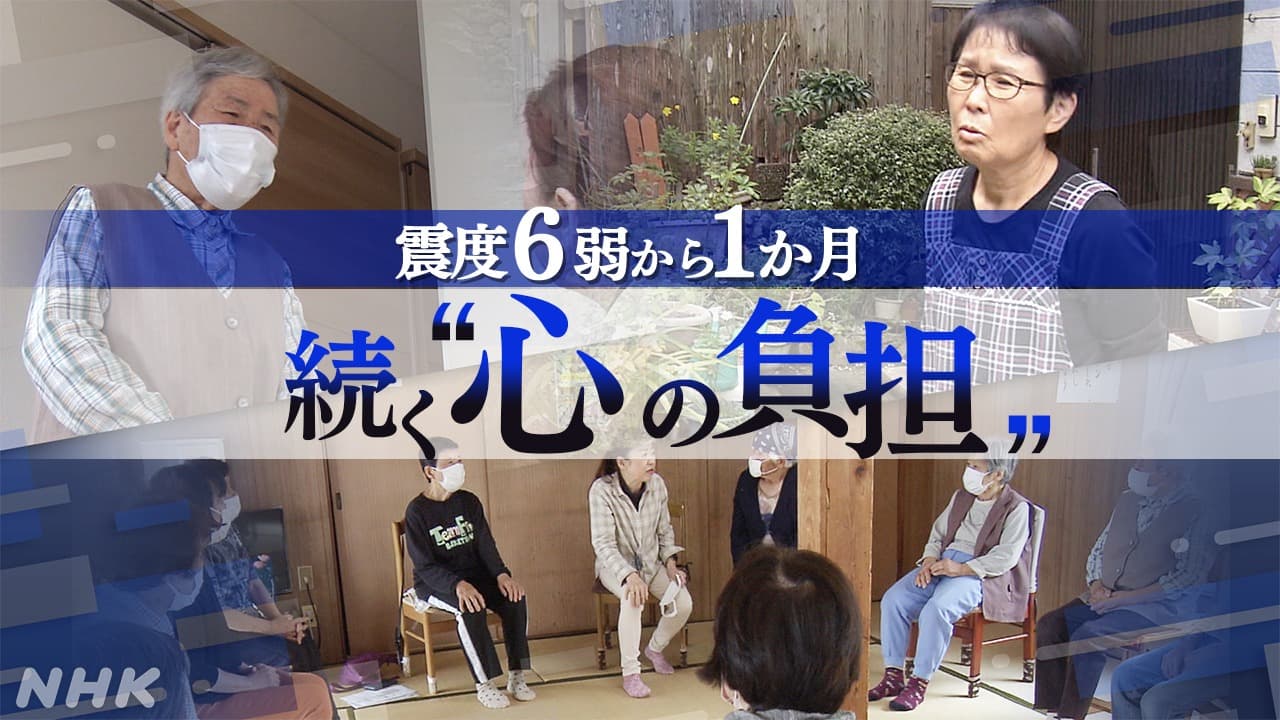不登校になったらどうする?四国の相談窓口は?
- 2024年05月10日

新年度になって1か月が過ぎ、学校やクラスの雰囲気に合わせることに疲れが出たり…
学校に行く気になれなかったり…
5月の大型連休明けは、不登校になりやすい時期の1つ。
もし自分の子どもが不登校になったら、どういった支援があるのか。
四国の最新の取り組み、そして各地の相談窓口を調べました。
(四国らしんばん 『不登校急増 “登校ありき”はもう古い!』 取材班)
詳しくはNHKプラスでご覧いただけます。

文部科学省は、不登校の定義を「病気や経済的な理由などを除き、1年のうち30日以上欠席している状況」としています。
小中学生の不登校の数は年々増加していて、四国では令和4年度が7,597人。
前年度より1,000人以上増え、5年前のおよそ2倍となっています。

お子さんの不登校に悩む保護者からは、こんな声も。
「『学校に行きたくない』と言われ、どうすればいいかわからず、つらい」
「誰に相談すればいいかわからない」
「このまま不登校だと、子どもの将来が心配」
「学校に無理にでも連れていったほうがいい?」
いったいどうすればいいんでしょうか。

まず紹介するのは、不登校になり、自宅から出ることが難しい子にも支援を届けたいという思いから、2023年に始まった取り組みです。
愛媛県の「メタサポキャンパス」です。

インターネット上の仮想空間・メタバースに「学びの場」を作り、自宅からでも学びや他者とつながる機会を持ってもらおうという狙いです。
愛媛県内の小中学生47人がアバターを作り、家にいながら利用しています(2024年3月時点)。

アバターとはオンライン上の空間で操る、自分の分身のこと。
本物の自分の姿に似せる必要はなく、性別、体型、顔だち、髪型、服装など、たくさんの選択肢から好きなものを選んで組み合わせます。
毎日自由に変えることができるため、キャンパスに通う楽しみの1つになっています。
利用できるのは、平日9時から16時まで。
学年別にオンライン教材が用意され、小学生は4教科、中学生は5教科を学ぶことができます。
キャンパスでの活動状況は在籍する学校にも共有され、校長の判断で出席扱いになります。

「自力では問題が解けない!」
そんな時は、教員免許をもつ愛媛大学の5人の大学院生が、チャットや音声、Webカメラを使って教えてくれます。
さらに子ども達の交流を生む、ユニークな部屋も用意されています。
音楽や料理、映画など、互いの好きなことをシェアできます。

子どもたちに人気で、のぞいてみるとたくさんの書き込みがありました。

ほかにもメタバースならではのイベントを次々と実施して、子どもたちの交流が広がっています。

(愛媛県教育支援センター 指導主事 坪田 朋也さん)
「今後子どもたちも、社会に出ていく1人になりますので、小学生~中学生の間に、人と関わる楽しさであるとか、喜びであるとか、そして学習等を積み重ねることによって、自分自身への自信であるとか、そういうところを積み重ねて成長してもらいたいなと感じています」
メタサポキャンパス利用の対象となるのは、以下の条件に当てはまる児童生徒です。
(1)愛媛県内の小・中学校に在籍
(2)在籍校がメタバース上の学びの場による支援が適当であると判断
(3)本人と保護者が利用を希望している
(4)自宅にアプリを起動できる機器・通信環境が整っている
機器を所有していない児童生徒への支援については、愛媛県教育支援センターに相談してください。
<愛媛県教育支援センター 電話📞089-963-3113(内線:122)>
なぜ、こうした新たな支援が積極的に行われているのでしょうか。
その理由の1つは、2016年に文部科学省が出した通知にあります。
平成28年9月14日「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方 (1)支援の視点より
不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。また,児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること

不登校の児童生徒数が年々増える中、すべての子どもたちが十分に学べる機会を得ることができるよう、不登校児童生徒の状況に応じた支援等を行うことができるよう努めてほしいと、文部科学省が全国の各教育現場に依頼したのです。
これを受けて、“登校ありき”ではない支援が広がっていくようになったのです。
愛媛県フリースクール等連絡協議会の窓口や、不登校支援機関「ホームスクール愛媛」の理事長を務める川内真紀さんに監修いただき、不登校支援の様々な受け皿をまとめました。

まずは【外出はできるし、人と話したり関わりたい気持ちはある】お子さんの場合。
「教育支援センター」や「フリースクール」といった支援があります。
学習活動・体験学習・スポーツなどを通して、社会的自立につなげることを目指します。

「教育支援センター」は自治体の教育委員会などが運営する公的機関で、学校に登校ができず悩むお子さんが通えるスペースを用意し、学習支援やイベントなどを行います。
「フリースクール」は主に民間が運営をしていて利用料がかかります。
自治体によっては一部助成があるところもあります。
カリキュラムや運営方針はフリースクールによって違うため、見学などをしてお子さんに合うフリースクールかどうか慎重に見極めることが大切です。
「教育支援センター」や「フリースクール」の多くは自分のペースで勉強や好きなことができるようにサポートをしてくれます。
つづいて【家の外にあまり出られない】場合。
「ホームスクール」や「オンラインスクール」という手があります。
主に自宅で自分のペースで勉強するというものです。

川内さんが運営するホームスクール愛媛では自宅を支援者が訪問し、お子さんや保護者の悩みを聞いたり学習支援をしたりしています。
オンライン教材を使うことで学習の記録が残るようにし、その記録を在籍校に伝えることで出席扱いを受けています。
ホームスクールに限らず、どの支援・受け皿を選択しても、在籍する学校の校長が認めれば出席扱いになります。
【学校には行けるけど、自分のクラスには入りづらい】という場合には、自分のクラスとは別の部屋・教室に通う「別室登校」や「スクールカウンセラー」などの受け皿があります。
一方で別室には行けても自分のクラスには行けず、友人とのコミュニケーションに悩んだり十分に学ぶことができなかったりするなど課題を抱える子どもたちも多くいます。
別室登校をする子どもたちにもっと寄り添えるようにと、高知県で3年前に始まったのが「校内サポートルーム」です。
個別に指導を受けられる特別な教室で、専任の教員が配置されています。
教員はクラスに常駐し子どもたちの些細な変化を見逃さずにひとりひとりに合わせて成長をサポートします。
この専任の教員との関わりが、大きく変わるきっかけとなった生徒がいます。

中学2年生から校内サポートルームに通い始めた、りょうすけさんです。
小学3年生のときから学校に行くことをためらうようになり、登校する日はあっても、教室に入ることは難しかったといいます。
そんなりょうすけさんが変わるきっかけになったのが、当時校内サポートルームを担当していた竹村三枝さんです。

りょうすけさんと毎日過ごす中で、竹村さんはりょうすけさんの工作への強い関心に気づきました。
「サポートルームで使用する棚を作ってほしい」とお願いすると、りょうすけさんは進んで引き受けてくれたといいます。

さらに、りょうすけさんはサポートルームのみんなを喜ばせようと、ゲームセンターさながらの力作を披露。りょうすけさんのつくったゲームは生徒たちの注目の的になりました。


このことが自信となり、りょうすけさんは本格的にものづくりを学びたいと工業高校への進学を決断。
将来はものづくりの楽しさを教える人になりたいと、考えています。

「竹村先生はずっと見てくれていたので自分のことをわかってくれる感じでした。 物を作るのが好きやって、それ分かったうえで頼ってくれて、今があるのも竹村先生のおかげだと思っています。 これからは大学に行って、できたら教員になりたいと思っています」

サポートルーム専任教員(当時) 竹村三枝さん
「仲間のすごーい!という反応が子どもたちの笑顔が次へ次へとつながっていく。生徒たちの活動の原点になっていると思います。 サポートルームにくる生徒の中には、集団生活が苦手っていう生徒もいますし、学習面でなかなかしんどくて勉強が無理だって学校から足が遠のいていった生徒もいますし、人それぞれなのでその原因を私たち教師がきちんと理解してあげて、それぞれの子どもに応じた支援をしていく、それが大事だと思っています」
こうした別室登校に専任の教員を配置する取り組みは、教員の業務量が増えることにもつながるため、
どう継続できるかが課題となっている一方で、 高知で17校、愛媛で10校、香川で9校、徳島で5校が実施していて、四国各県で広がっています。
不登校の受け皿を選ぶ中で気をつけたいのが【体や心に強い反応が出ている場合】です。
「夜眠れない」「朝、気分が悪い」など、顕著な症状が出ている場合は「医療」とつながってください。

子どもの精神疾患や発達障害などのケアに注力した児童思春期外来という窓口が全国の医療機関で開設されています。
薬の処方や、心や生活を整えるプログラム・グループ活動などを実施することで、症状を改善させていきます。
そして受け皿を選ぶ際には、お子さんの気持ちを優先することも大切です。
お子さんが何に悩んでいて何を望んでいるのか。
学校に行けない理由が自分でもわからずに悩む子どもたちも少なくありません。
まずはお子さんの気持ちに寄り添い、お子さんにあった受け皿を一緒に選んでいくことが求められます。
不登校が長く続いたとしても、その後、希望の進学先や就職先に進んだ人も多くいます。
お子さんのケアも大切ですが、保護者の心や体のケアも重要です。
長年不登校に悩む家庭を支援してきた川内さんは、「保護者へのケアが、ひいてはお子さんのケアになる」と現場経験から感じたと言います。
ぜひ相談できる第三者を見つけて悩みを打ち明けてみてください。
愛 媛
■愛媛県総合教育センター
電話相談…下記の番号に電話をしてください。
電話📞089-963-3986(教育相談室直通)
来所相談…事前に予約が必要です。上記の番号に電話をして予約してください。
<相談日及び時間>
・月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
・8:30~17:15
💻愛媛県の相談窓口詳細はこちら(外部サイトに移動します)
児童・生徒の教育相談 | 愛媛県総合教育センター (esnet.ed.jp)
■メタサポキャンパス
<問い合わせ先>
愛媛県教育支援センター(愛媛県総合教育センター)
電話📞089-963-3113(内線:122)
💻メタサポキャンパスについてはこちら(外部サイトに移動します)
メタサポキャンパス | 愛媛県総合教育センター (esnet.ed.jp)
高 知
■高知県心の教育センター
電話📞088-821-9909
<相談日及び時間>9:00〜17:00 (第2・4・5土曜日、第5日曜日、祝日、年末年始はお休み)
スクールカウンセラーによる電話相談のほか、来所しての相談も可能です。
💻高知県の相談窓口詳細はこちら(外部サイトに移動します)
心の教育センター|高知県(pref.kochi.lg.jp)
徳 島
■徳島県立総合教育センター特別支援・相談課
電話📞088-672-5200(相談専用)
メール📩 tokubetsushien@mt.tokushima-ec.ed.jp
<相談日及び時間>平日9:00~17:00
💻徳島県の相談窓口詳細はこちら(外部サイトに移動します)
教育相談 - 徳島県立総合教育センター (tokushima-ec.ed.jp)
■LINE相談 「とくしま(生徒の心の相談)2024」
<相談日及び時間>18:00~21:30
💻LINE相談について詳しくはこちら(外部サイトに移動します)
ホーム - 徳島県立総合教育センター (tokushima-ec.ed.jp)
香 川
■香川県教育センター
【子育て電話相談】📞087-813-2040
(対象:おおむね18歳までの子どもの保護者、学校(園)関係者/相談時間:9:00~21:00)
【子ども電話相談】📞087-813-3119
(対象:おおむね18歳までの子ども/相談時間:9:00~21:00)
メール相談も可能です。
💻香川県の相談窓口案内はこちら(外部サイトに移動します)
相談窓口 | 香川県教育センター (kagawa-edu.jp)