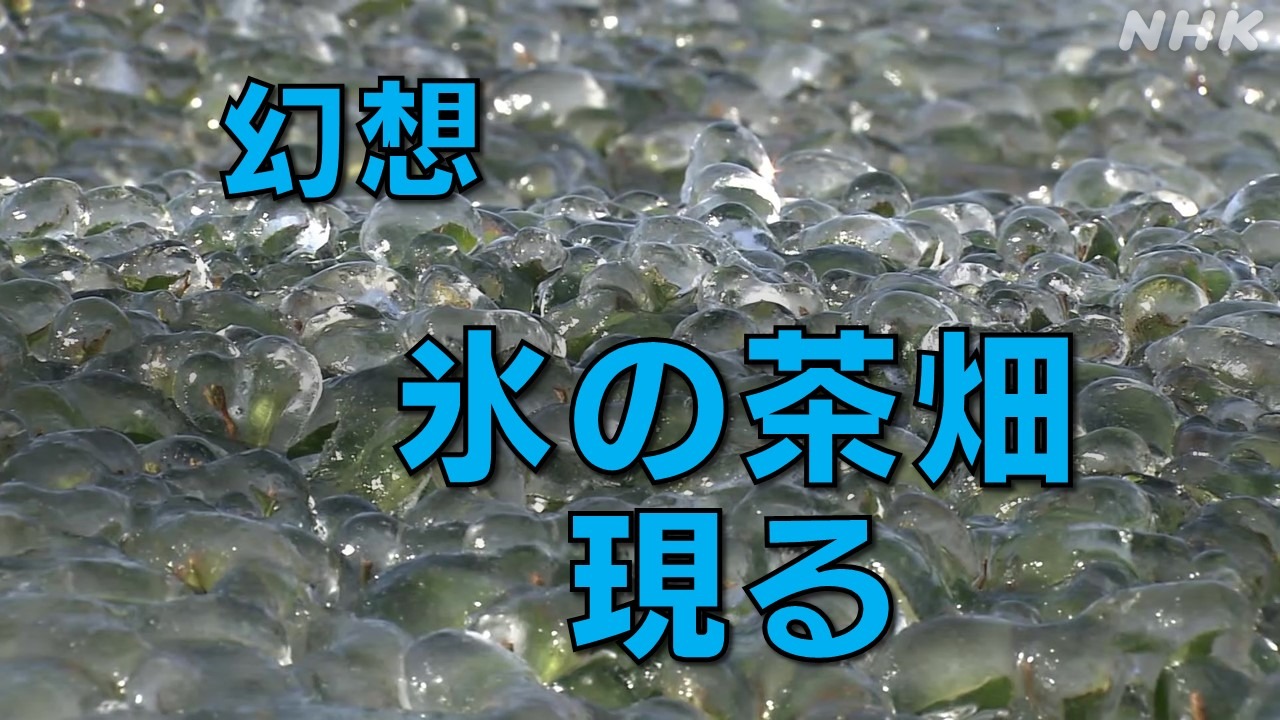【解説】旧優生保護法 熊本地裁の判断は
- 2023年02月01日

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたと熊本県内の70代の男女が国に賠償を求めた裁判で、熊本地方裁判所は1月23日、「この法律は差別的な思想に基づく、非人道的なもので、憲法に違反する」と指摘し、2200万円を支払うよう国に命じました。
同様の裁判で国の賠償責任を認定する司法判断は3件目となります。
裁判の争点と、熊本地裁の判決について解説します。
訴えを起こしていたのは、
熊本県に住む渡邊數美さん(78)と、76歳の女性のあわせて2人です。

2人は、昭和30年代から40年代にかけて、本人や家族に障害があることを理由に、旧優生保護法によって不妊手術を強制されたとして国にそれぞれ3300万円の賠償を求めていました。
裁判の争点は

大きな争点は
▼相手の不法行為から20年が過ぎると裁判で賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」の規定が適用されるかどうか、
でした。
これについて、双方の主張です。

▼原告側:国の政策などによって作られた、差別や偏見によって裁判を起こすことが困難だった
▼国側:裁判を起こした時点で手術から20年が経過し、賠償を求める権利は消滅している
熊本地裁の判断は
判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は次のように指摘しました。

旧優生保護法は差別的な思想に基づき、子孫を残すという生命の根源的な営みを否定する、極めて非人道的なもので、憲法に違反することは明らか国の賠償責任を認め、原告2人にあわせて2200万円の賠償を命じました。
その上で、少なくとも平成31年の国の救済法の成立より前に提訴した原告は、賠償を請求できると判断しました。
では、最大の争点となっていた「除斥期間」の規定の適用について、裁判所はどう判断したのでしょうか。
判決は、4つのポイントから判断しました。
【①被害の甚大さ】
「国が人間の尊厳を侵害する明らかに違憲な旧優生保護法を制定し、生殖機能を奪うという極めて強度な人権侵害を行った事案で、差別され、手術を受けさせられた原告らの身体的・精神的損害は甚大」
【②国の責任は】
「昭和23年の旧優生保護法の制定当初から昭和40年代まで優生手術を積極的に推進し、学校教育でも優生思想を助長・促進して、偏見や差別を社会の広範囲に浸透させた」
「優生手術による人権侵害が甚だしいことを認識したあとも適切な対応や救済措置をとらず、差別や偏見を正当化・固定化させてきた」
【③裁判を起こす難しさ】
「国の一連の対応が著しく不十分な状況のなかで、優生手術を受けさせられたことを社会に公表し、国に損害賠償を請求するのは、事実上不可能だった」
「熊本県には優生手術の資料が残っていないなど、証拠資料の散逸・消滅を招いた責任は国側にあり、『除斥期間』を適用する前提の一部を欠く」
【④憲法との関係】
「明らかに憲法に違反する法律を制定し、それに基づく政策によって原告らに重大な損害が生じた以上、最高法規である憲法に規定された国への損害賠償の権利を、民法が定める『除斥期間』で妨げることには慎重であるべき」
裁判所はこの4点を踏まえ、
「優生手術を受けた人に『除斥期間』の規定を適用することは、民法の信義則や解釈の基準などから見逃しがたい重大な問題が存在する」として、「少なくとも一時金の支給を定めた法律が成立した平成31年4月24日の前に裁判を起こした原告らに、『除斥期間』を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と判断しました。
原告は


▼渡邊數美さん(78)
「ようやくこの日を迎えました。これまで辛い人生で、自分の体が恥ずかしく、ひた隠しにしてきたが、生きていてよかったと初めて思いました。判決までとても長かったです」
▼原告の女性(76)
「とてもうれしく思います。料理が得意なので、もし家族がいれば家族団らんの時間を持ちたかった。優生手術を受けたことで家族を得られなかった残念な気持ちが思い返されます。国には控訴しないで頂きたいと思います」

▼東俊裕弁護団長
「争点への見解も明快で、違憲性について、旧優生保護法が目的と手段、ともに極めて差別的な考えで行われたことを前提に指摘している。また、原告らが受けた手術は人権を侵害するような国の政策のもとで行われたものであることから『除斥期間』の規定を適用してはならないというこちらの主張をくみ、この規定をそもそも適用しなかった熊本地裁独自の画期的な判決だったと思う」
「賠償額の差を除いて、裁判所は問題に正面から向き合ってくれた。提訴にまだ至っていない人についても、後に続くことができるような結果だった」
国は

▼厚生労働省「国の主張が認められなかったものと認識している。今後、判決内容を精査し関係省庁と協議したうえで適切に対応したい」
全国の裁判への影響は
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国に賠償を求めた裁判は、これまでに全国あわせて10の地方裁判所と支部で起こされています。
このうち、これまでに言い渡された1審の判決では仙台、大阪、札幌、神戸の地方裁判所が、この法律は憲法に違反するとの判断を示しましたが、賠償を求める訴えは「除斥期間」の適用などを理由にすべて退けられています。
一方、2審では2022年、大阪と東京の高等裁判所が憲法違反と判断した上で、国に賠償を命じる判決を言い渡しています。
同様の裁判は2月以降、6月までに1審が静岡、仙台で、2審が札幌、大阪、仙台で判決が予定されていて、判決への影響が注目されます。
※追記※
2/3、国側は福岡高等裁判所に控訴しました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20230203/5000018187.html