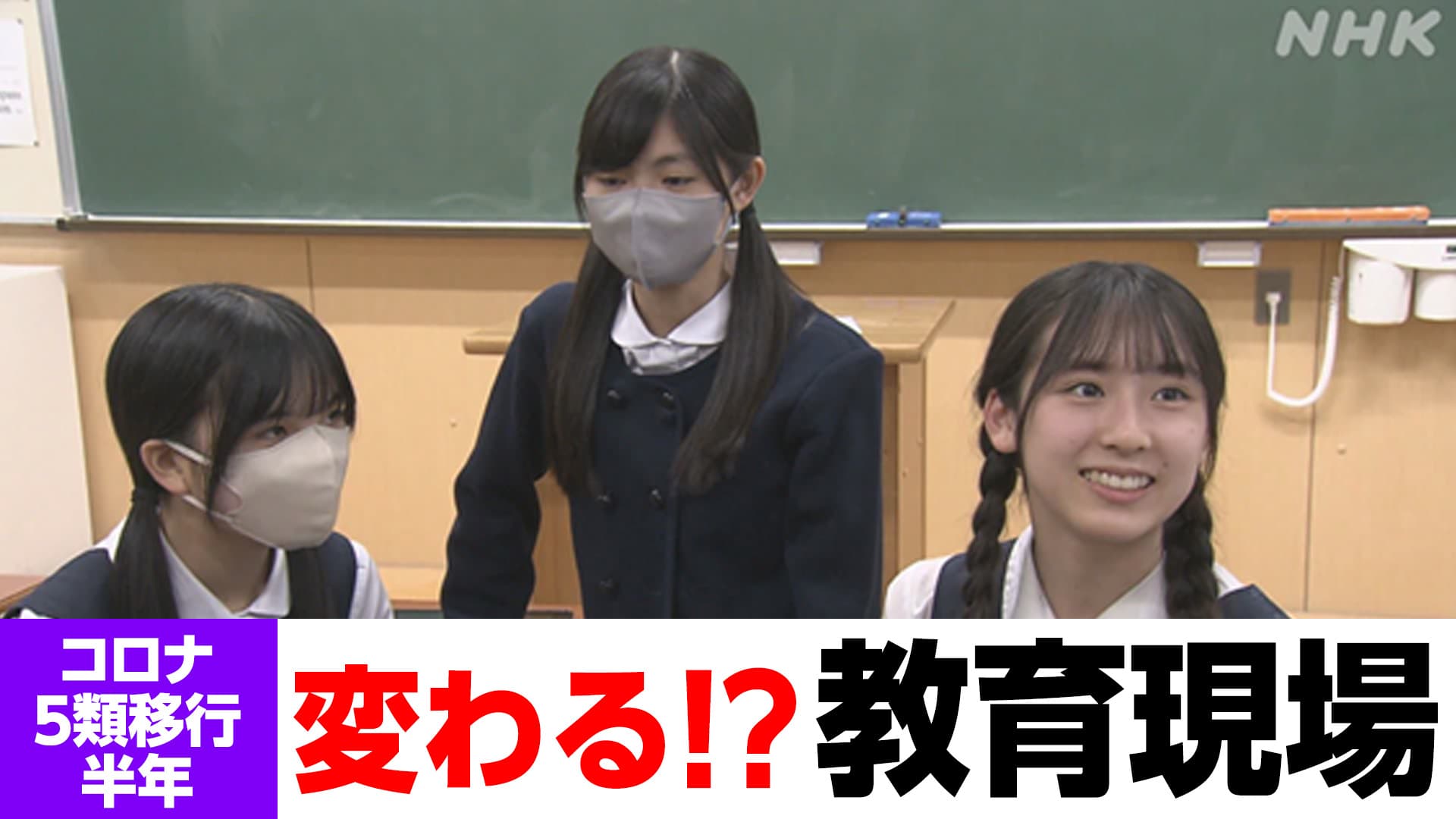九州沖縄からボナペティート
- 2023年12月21日
イタリアンシェフ、サルバトーレ・クオモさん(51)。日本に本場イタリアのピッツァを広めることに尽力し、手掛ける店は世界のイタリアンレストランベスト50にランクインするトップシェフです。
いま大分県日田市に拠点を置き、日々九州沖縄の食材を集めては料理を作っています。
サルバトーレさんは、今年春から沖縄の歴史ある製粉会社とともに新たな挑戦を始めました。
製粉会社の高い技術で"最高"のピッツァ生地を作ること。そして、その生地に九州沖縄の"最高"の食材たちを載せること。
トップシェフが作り出す九州沖縄ならではの、究極のピッツァ―。一体どんなものになるのか、その挑戦をおよそ半年間追いかけました。

九州沖縄が好き!サルバトーレさんの思い
サルバトーレさんは、日本にピッツァを広める活動を30年間続けてきました。
その間、15年もの年月を九州や沖縄で過ごしてきました。
30代なかばで沖縄に5年ほど暮らし、2011年に福岡市百道に移り、そして2021年からは大分県日田市の山間にラボを構えています。

―九州沖縄のどこが好きで拠点を置いているのですか
「コンパクトだけど本当に何でも揃ってると思う。温度も関係してる。一定の場所にいくと、土の温度の変化がすごくて、マイナス5度とかから昼間は20度超えるような寒暖差がある環境がある。大分県竹田市にはサフランが育っていて、最近では九州でトリュフが発見されたと聞く。僕はそういう宝だらけの場所にいたいっていう単純な理由です」
――今回作ったピッツァに九州沖縄でのサルバトーレさんの過ごした思い出もつまってるんですか?
「つまってる。料理にはいろんな物作りをしている人たちと接触することがね、ものすごく大事なことだと思う。で、聞くこと。思ったらともかく聞く、思いついたら行動するようにしてる。実はインタビューの前にマスタード作ってたんだよね。ごめんね、待たせてるのに」

―待ってるのに!笑
「ごめんね。九州にいると毎日どんどんどんどんいろんな食材出てくるから。
夜、頭ん中考えちゃうんだよ。あんなことやんなきゃいけないって思ったらやっぱすぐ作らなきゃって、忘れちゃうんだよね」
思いついたら即行動、常に料理のことを考えているサルバトーレさん。普段から運転しながら九州沖縄の食材で何を作ろうか考え、思いついたらすぐにキッチンに向かうことで、アイデアを形にしているそうです。

“豆腐ようをピッツァに!” 沖縄での思い出が核に
沖縄の食との出会いは“沖縄そば”からでした。30代なかば、沖縄に住み始めたころ、休みの日は1日中北谷の海でダイビングをして、そのあとに近くの店で沖縄そばを食べていたのだそう。
そこから沖縄の食が好きになり、イタリア料理にも取り入れるように。その代表が豆腐ようだったといいます。


今回のピッツァに登場した豆腐よう。実は思いついたのは新メニュー発表の2週間前でした。
リモートでサルバトーレさんとスケジュールを打ち合わせ中、突然「豆腐よう使ったら面白いかもね」と一言。
ディレクターの私を含め、打ち合わせに参加していた秘書の方や現場の料理人たちも、「なぜ豆腐ようをピッツァに…?」となりました。

―なんで豆腐ようをピッツァに使おうと思ったのですか?
「ゴルゴンゾーラのパスタを作りたくて、でもゴルゴンゾーラどこのスーパーに行ってもないわけ。どうすれば、、。その時に使ったのが、豆腐ようだったの。ゴルゴンゾーラはかびの発酵の香り、豆腐ようはお酒の発酵の香り。全然種類違うけど、不思議と「これは似てる、使える」と思ったね。それからゴルゴンゾーラの代わりに、豆腐ようのパスタを家で作ったりしてたよ。最初は結構苦手だったんだけどね、慣れてくると好きになった」

果物豊富うきは市のいちじく 生産者の思いに応える
トッピングに使われるのは、九州沖縄の食材たち。
その1つが、皮ごと丸々食べられるいちじく「とよみつひめ」。2006年に新たに品種登録されたもので、平均糖度が17度という甘さとトロッとした食感が特徴です。実は世界中に500種類以上あるいちじくですが、日本生まれのいちじくは貴重だといいます。

とりわけ今回サルバトーレさんが感動していたのが、「皮ごと食べられる」ということでした。

いちじく農家・吉瀬さん
「皮ごと食べた方がいちじくを感じられる。自分たちはやっぱり、皮ごと食べてもらってもいいように、農薬とかも極力控えてるんですよ」
サルバトーレさん
「イタリアのいちじくって、皮むかないといけない。なかなかそのまま食べられないので、海外でも。やっぱりここまでストレートで、そのまま食べてくださいよって感覚でやれるっていういちじくなかなかないんですよね」
うきは市との出会い 食品ロスへの思い
サルバトーレさんがうきは市の果物を使い始めたのは今年から。きっかけは「食品ロスをなくすこと」でした。
日田市でジェラート屋さんを開いたサルバトーレさん。そこで使う果物には、表面が傷ついたり形が悪いというだけで規格外になってしまったものが含まれています。それは食品ロスをなくすため。今、うきは市の6次産業化に取り組む施設と協力して、規格外の果物を入手しています。

サルバトーレさん
「結局果物作ってる人って、規格外のものを作りたくてやってるわけじゃない。だから努力は規格外もそうじゃない果物も変わってないんですよね。それが例えば見た目で、これ駄目ですよみたいな話にされちゃったりとか。そこは、本当にいつもなんとかしたいなって思うんですよね。そこはやっぱり皆さんのかいてる汗、一緒なんで。うきは市は果物が美味しくて、1年通して何かしら果物がある。うきは市と協力して、規格外の果物を僕らが買い取って、ジェラートとか料理に変えるのが理想の形じゃないかな」

吉瀬さん
「葉っぱが風で揺れて実にこすれたら、傷がつく、傷がついたらもう2級品、3級品。すごいかわいそうなくらい、返品来ますよ」
サルバトーレさん
「僕は子どものときイタリアで育って、実は日本に来たとき、初めてニンジンがまっすぐだって分かった。知らなかったんですよ、まっすぐなニンジンがあるとかね」
吉瀬さん
「キュウリがまっすぐとかね」
サルバトーレさん
「やっぱり味がともかくメインっていうところが、そこはすごく重要なところ。形とかも当然あって、いいんですけど、とにかくおいしいものを提供するのが第一という考え方に、もう1回戻したいんですよね」
吉瀬さん
「下のランクになってしまったものの単価がちょっとでも底上げできたら、農家さんにとってすごく嬉しいこと、大事なことだと思います。だから頑張ってほしい」
“蜂蜜を作っているだけじゃなく、環境を作ってる”
トッピングに重要な役割を果たすのが、大分県日田市の蜂蜜。
サルバトーレさんが養蜂家・諌山洸武さんと出会ったのは日田市に来たばかりの3年前。"地元の蜂蜜"があると知り、直接家を訪ねて買いに行ったのだそう。
そこで諌山さんの蜂蜜の味にひかれ、以来ずっとお付き合いをしているのだとか。


諌山さんが蜂と向き合うときのこだわりは、「素手で作業を行うこと」。蜂を傷つけないためだといいます。

「1日に何回も刺されますけどね。笑。痛いです、今も。笑。
ゴム手袋してやると刺されなくていいんですけど、その分刺されないと思って、蜂を雑に扱っちゃうかもしれないので、なるべく素手で扱って丁寧に傷つけないように、怒らせないようにっていうのを心がけてやってます。蜂自体も刺すことで死んじゃうので。かわいそうっていうのが。1回刺したら蜂も死にます。なので蜂の命を絶たんように」
日田は杉が多く、花が特別多い町ではありません。それでも日田にこだわるのは、地元の味を出したいから。

―なんで日田にこだわっているんですか?
「日田の地元の味を提供出来たらなあって。好きだからですかね。生まれ育った場所だし、日田は寒暖差が激しくて、他の地域に比べたら辛いかもしれないですけど、そこでみんな、農作物作ったり、自分も蜂を育てたりして、なんか、いいなって。簡単じゃないから、なんかそこも面白い。難しいけど、やりがいはある土地だなって感じです。しかも日田の果物の交配を手伝っていると思うと、自分がやめちゃったりしたら農家さんも困るやろなって。日田の果物農家さんの力になっていることは嬉しいです」
諌山さんによると、蜂は40日程度しか生きられず、蜂が一生に集められる蜜はスプーン一杯分なのだそう。

―どういう思いで蜂蜜を作っているのですか
「貴重すぎる感じですね。蜂にとってはごはんであり、宝物であり、そういうものを頂いています」
“食材を翻訳する” 日本×イタリアの自分だからできること
サルバトーレさんを取材していて印象的だった言葉、それは「食材を翻訳する」でした。
父がイタリア人、母が日本人というサルバトーレさん。イタリア・ナポリで育ち、12歳の時、日本にやってきました。父は千葉県でイタリアンのレストランを開きますが、経営は思わしくなく、サルバトーレさんが18歳の時、病で亡くなりました。
経済的に苦しい日々。サルバトーレさんはアルバイトを幾つもかけ持ちし、1日24時間の内、20時間働いたこともあったそうです。
そして、23歳で自分のレストランを東京都内にオープンします。


当時、日本にはまだ本場のナポリピッツァが浸透していませんでした。その頃ひたすらナポリピッツァを知ってもらうため奮闘していた自分と、各地の生産者の姿が重なるのだといいます。
23歳で初めて持ったお店の跡地に連れていってくれました。
「ここが、サルバトーレのストーリーが始まった場所です。
(お店ができたのが)1995年なんで…28年経つ。3人兄弟で何かできないかって。」

多い時には200人の列ができたそう
「僕らの場合はタイミングよくメディアが取り上げてくれて、それまでのピザとイタリアンピッツァが何かが違うかということを証明してくれた。だから、話せる人、メッセージを伝えられる人っていうのがすごく重要で、メッセージを言えないままで終わってしまう場合もあって、僕もその可能性すごい高かった」
イタリアンの道を追求しながらサルバトーレさんが、ずっと考え続けてきたのは、「イタリアと日本の血を受け継ぐ自分だからできることは何のか?」。
そして辿り着いたのが、「食材を翻訳する」ということでした。
九州沖縄に拠点を移して15年。各地で生産者と会って、作る苦労を聞いて、料理に向き合う中で、意識の変化がおきているのだそう。

「自分が代表じゃなくて、この人達と一緒に出ていくような感覚になるんですよね。一緒に何か調理してるよって感覚になる。なんでこんな食材探すのとか言われるけども、言ってしまえばマニアックな世界観。僕もそうだけど、それを作ってる人、僕よりマニアックなわけですよね。だからものすごい時間を、いろんな人がかけて、1個のものを作り出して、僕のところに渡って。(僕は)それ以上のことをやってあげなきゃいけないじゃないですか」
“みんなの指紋がついたピッツァを”
そして完成したのは、九州沖縄の食材が満載の"究極のピッツァ"。
生地は沖縄にある創業69年の製粉会社が開発。そこに九州沖縄各地の食材たちが載りました。


「僕はイタリアンの歴史を変えられる人じゃないから、歴史はすでにあって、そこは僕が、こうだった、ああだったって語るべき人じゃないから。でも指紋として残すことは、多分僕はできると思う」と話すサルバトーレさん。
今回のピッツァに込めた思いを改めて聞きました。
「僕が好きな場所だから、九州沖縄が携わってくる。九州沖縄があって僕が通訳として立って、みなさんのところに渡す。 通訳ってそうでしょ。訳す人ってその人がしゃべってるけども、誰かのことばを使って会話をしてるので。同じことなんですよね。
基本的に僕なんだけど、後ろにはこれだけのものがありますよ、ということがちょっとでも分かってもらえたら非常にうれしいな。たくさんの時間とたくさんの人が、お客さんが食べるその一瞬のため、みんな働いてるので。果物を作る人もそうだし、粉を作る人たちもそうだし、チーズを作る人もそう。ピッツァを作る人もそうだし。やっぱ全部色んな人が、全部こういろんな人の手がそこに入ってます。責任をもらって商品を作って今度それを出して、代表として結局僕がそこが一番重い責任もらうわけやね。
みんなの時間とやってくれた事全部。そこはなかなかプレッシャーだけれども、まあ非常にありがたい仕事をさせてもらっています」

生産者の皆さんとサルバトーレさんの"指紋"がイタリアンの歴史に押された瞬間を見ているんだな、と感じた取材でした。
(NHK大分放送局ディレクター 鈴木萌花)