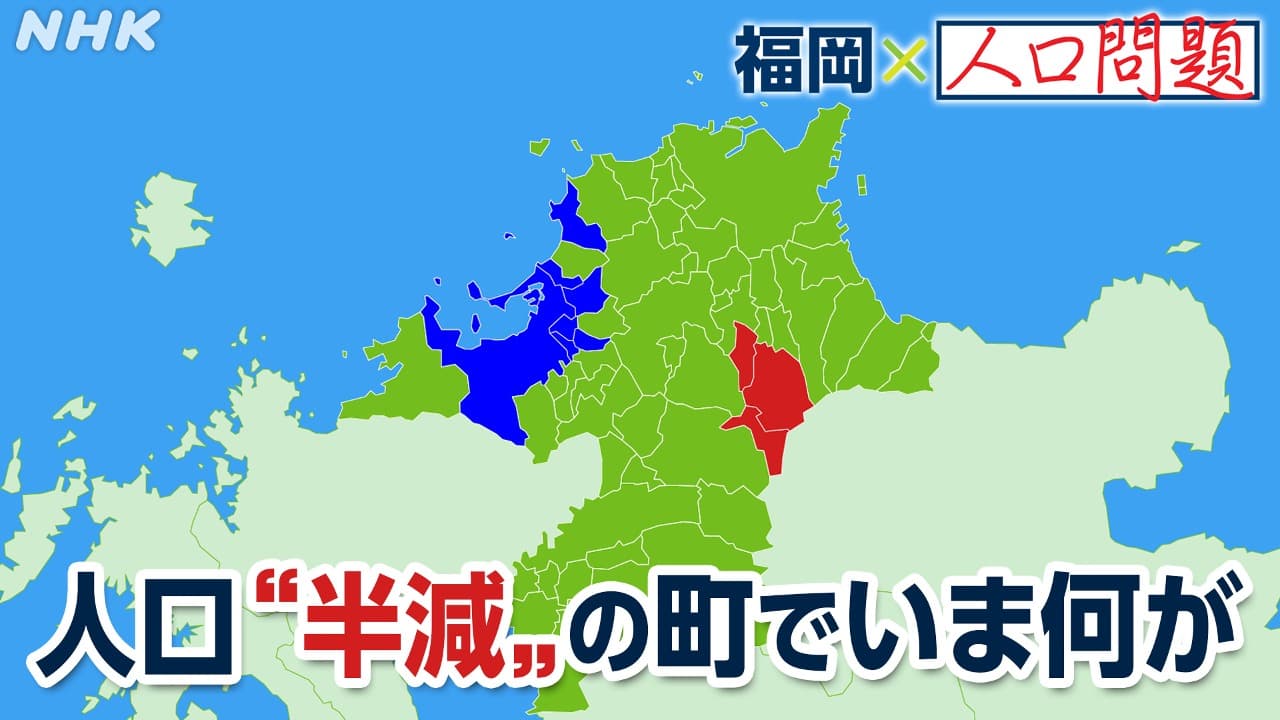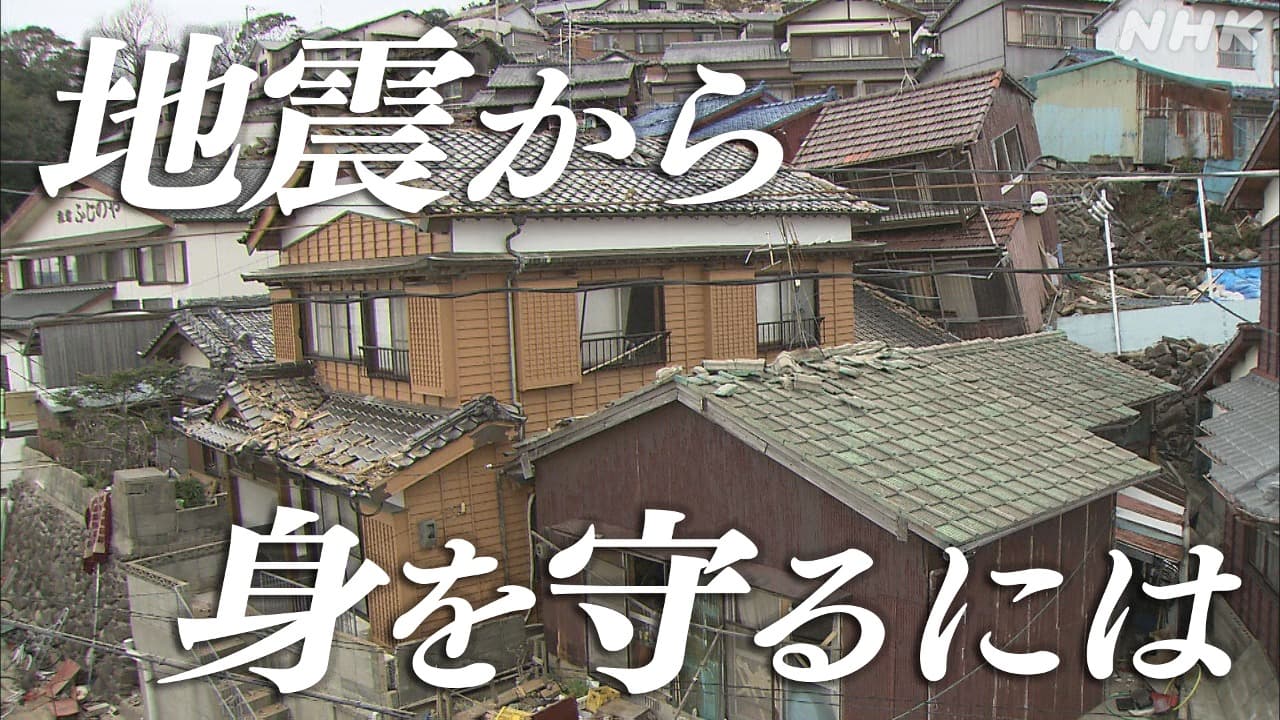「正義感」は、なぜゆがんだのか
- 2023年02月14日

「手っ取り早く制裁や威嚇を加えて服従させる目的で、成長途中の子どもに対する悪質な逮捕監禁を繰り返している。非人道的、常習的犯行で相応の非難を免れない」
2023年1月20日、福岡地方裁判所の法廷で裁判官が判決文を読み上げた。
中学生3人に対する逮捕監禁の罪に問われたのは障害児支援施設などを運営していたNPO法人の元理事長。言い渡されたのは懲役3年の実刑判決だった。
元理事長は、その3日前、取材に対し証言した。
「誰も助けられない人たちを自分が助けられるんだという、間違った正義感が自分の中にあったと思う」
なぜ、正義感は「暴力」に変わったのか。取材で感じていた疑問を本人に投げかけた。
(福岡放送局 記者 木村隆太)※2023年2月公開の記事の一部を修正しました。
元理事長による事件とは
2022年7月、警察は、福岡市のNPO法人の 理事長(当時)を逮捕した。
久留米市で障害児支援施設などを運営していた元理事長は、13歳から15歳のいずれも障害がある男子中学生3人に対する逮捕監禁の罪でその後、起訴された。

判決によると、このうち1人のケースでは、元理事長は、生徒の自宅を訪問し、ベッドの上にいた生徒の両手足を荷造りベルトや結束バンドで縛って「しゃべると殺すぞ」「暴れたら殴るぞ」などと脅したうえで、両目のあたりに粘着テープを貼り付け、頭に袋のようなものをかぶせて殴り、抵抗できない状態にして、自宅から連れ出した。
さらに、車で山道まで連行して「ここに捨てていくぞ」「ここに手足を縛って転がして埋めるぞ」などと暴行や脅迫をして、無理やり施設まで連れて行ったとされる。
裁判官は、懲役3年の実刑判決を元理事長に言い渡し、その理由を次のように述べた。
「発達障害を有する児童などの支援事業を手がける被告人が、児童に規律正しい生活を送らせるための指導や療育などと位置づけ、これにすがる親から報酬を受けて事業の1つにしていたと認められる」
「自傷や他害の危険がおよそ見て取れない被害者を様々に威圧して手足を拘束し、恐怖や屈辱を負わせる程度が強く、人格を無視している。指導や療育などの正当な理由を見出す余地はなく、手っ取り早く制裁や威嚇を加えて服従させる目的で、成長途中の子どもに対する悪質な逮捕監禁を繰り返している。非人道的、常習的犯行で相応の非難を免れない」
なぜ、違法な手法をとったのか
元理事長は、大学院で障害児教育を専攻してきたほか、卒業後は横浜の障害者施設で、自閉スペクトラム症がある利用者などと接してきた経験を持つという。
専門知識があり、30年以上もの間、障害児などを支援してきた経験がある元理事長が、なぜ暴力的な手法をとるようになり、それを繰り返し行っていたのか。
事件後も元理事長の社会復帰を求める署名がネット上で集まるなどの影響(詳しくは2022年12月23日公開の記事「誰か助けてください」https://www.nhk.or.jp/fukuoka/lreport/article/000/29/)がある中、事件をどう思っているのか、直接聞く必要があると考え、関係者を通じて元理事長にインタビューを申し込んだ。
判決日の3日前、元理事長は保釈中にインタビューに応じた。
判決の言い渡しを控えていたこともあるのか、元理事長は落ち着かない様子だった。
(元理事長)
「事件になった被害者の方々、当然被害を受けているということですので、そこについては大いに、真摯に反省をしているというところです」
元理事長は、はじめに反省のことばを述べた。
ただ、独自の手法による“療育”には理由があったと主張した。
ーなぜ違法な手法をとったのか?ー
「医療や心理、教育、福祉など様々な社会資源に皆さん(親)が頼ってきたけれど、やっぱり何も解決しない。様々なエキスパートやプロが対策を講じるなかで、子どもが働きかけにきちんと応じる状態ではなく、退行している状態だった。親から「助けてください」と差し出された手を私がとらなければ本当に社会から排除されてしまい、そうなれば、引きこもりになるか、家族の間で事件が起きてしまう可能性があった」
ー違法性は認識していたのか?ー
「違法なことであるということは当然、認識としては初めから思っていた。ただ、家族が社会生活を営めるのであればと思い、手をのばした」
ー恐怖を植え付ける以外の手法はなかったのか?ー
「緊急的に非合法な手段を使わざるをえなかった。本人が生きやすくなるために、やむをえずこの方法しかなく、あえて恐怖を感じさせる意図的な行為を行った。心の傷がゼロかというと確実にゼロとは言えないが、必要最小限だった。理論も実践もこの方法以外にいまだに考えつかない」
元理事長が療育に関わった経緯は
元理事長が障害児支援に関わるようになったのは次のような経緯だった。
大学時代に子ども相手にイベントなどをするボランティアサークルにいた際、自閉スペクトラム症の子どもに出会った。それをきっかけに、障害児とコミュニケーションを深めたいと大学院に進学し、障害児教育を学んできたという。
卒業後は、横浜市で当時日本でも先進的なプログラムを取り入れた施設の職員として、自傷や他害などの「強度行動障害」がある自閉スペクトラム症の人たちの支援に携わってきた。「国に認められた施設で仕事をしていたことが自信にもなっていた」と当時を振り返った。
その経験を生かそうと38歳で地元・福岡県に戻り、病院にいる自閉スペクトラム症の患者などの支援を始めた。口コミで元理事長の存在が知られるようになると、障害児を持つ親から依頼を受けて、ボランティアで個別に療育を始めるようになったという。
さらに、特別支援学校などにも足を運び、自力で排泄できない子どもなどの行動を改善したという。当時、学校や行政の関係者に対して「なぜちゃんと支援してあげないのだ」「不登校を解決してやる」「俺に任せろ」などと言い放つこともあったという。

当時の自分に対する周囲の評価について元理事長は「高飛車にみえたのか、専門家や行政、教育などの人たちからは良く思われていなかったと思う」と自己分析した。
親からは頼られて承認欲求が満たされる反面、学校や行政には「お金をもらっているのに何もしないのか。こっちはボランティアでやっているんだ」という思いになっていたという元理事長。
それなら自分でやるしかないという気持ちから、15年前にNPO法人を設立した。
証言「慢心やエゴ、間違った正義感があった」
ー違法だと認識しながら、なぜ、ブレーキはかからなかった?ー
「160日間ぐらい勾留されて、内省する時間を得るなかで、ほかに何らかの曇りがなかったか考えていくと、やはり、誰も助けられない人たちを自分が助けられるんだという慢心やエゴであったり、なんでこんな状況まで社会は放っておくんだという憤りであったり、片方には間違った正義感というもの、ゆがんだ部分も実は自分の中にあったなと思う」
ー反省の一方で正当性を主張するような、相反する感情を持っているようにみえるが?ー
「誤った正義感でやってしまったと思いながら、この子たちを助けるためにやったのだと。そう思うと、いやいや待て、それでも自分の中に慢心があったじゃないかと。その中をずっとループしていて、気持ちの整理がまだつかない」
事件の捜査が進み、裁判の審理を経た元理事長の心は、反省と自己肯定の相反する感情で揺れていた。自分の“正義”を否定されることにおびえているように感じた。
「社会的に容認されない行為」
元理事長の主張に対して、改めて有識者に聞いた。

ー事件の背景にはどのような社会構造があると考えているか?ー
「支援の相談には応じるが実際には動いてくれないという社会的な支援の脆弱性があり、頼るところがない親が元理事長を頼っていたと思います。社会的な支援がない中、親や子どもを救いたいという彼の思いが非常に強く、自分自身がやらなければいけないという“正義感”があったのだと思います」
ー恐怖を植え付ける手法をどう思うか?ー
「恐怖によるコントロールは手法としては、一時的にはコントロールできたとしても、恐怖の対象が居続けないといけないので長続きはしないと思います。子どもの人権もあるので、子どもを縛って拘束して連れ去って監禁するのは、本人なりの理屈があっても社会的に容認されない」
ー心の傷を最小限に留めることは可能だと考えるか?ー
「どれくらいの恐怖を与えたかっていうのは受け手側の話なので、それを恐怖を与える側が調整するのは難しいと思います。例えば、実際には自分は怒られていないけれども、先生が隣にいる子どもを叱責したことで学校に来れなくなる人もいますよね。恐怖の量は感じ方の問題なので、そもそも調整できないと思います」
「ひっ迫した状況の家族への支援体制を」

ー元理事長を頼った親やその子どもへの支援をどうすべきか?ー
「子どもだけを預かる支援にも限界があり、社会的な行動障害で引きこもったり、暴れたりしている子どもの家族に対する支援体制を整えなければならないですね。本当に追い詰められた人は一家心中しかないとか、私が殺されるか、私が子どもを殺すかというひっ迫した状況の人もいます。自治体が行動障害がある人やその家族向けに、支援体制がどうなっているかをリアルタイムで把握するシステムを作っていくことで、子どもの家族に対する支援体制を整える必要があると思います」
“第二の理事長”を生まないために
「どのような判決でも受け入れます」
インタビューにそう答えていた元理事長に3日後、懲役3年の実刑判決が言い渡された。
元理事長が懲役刑に服することで、障害児監禁事件には終止符がうたれる。
一方、事件の被害者や、障害児支援をめぐる社会の現状は深刻な問題を抱えたままで、福祉の手が届かずにいまも「助けて」と叫ぶ家族がいる。
その声を聞き、解決策を示すことができなければ“第二の理事長”は、また生まれると思う。