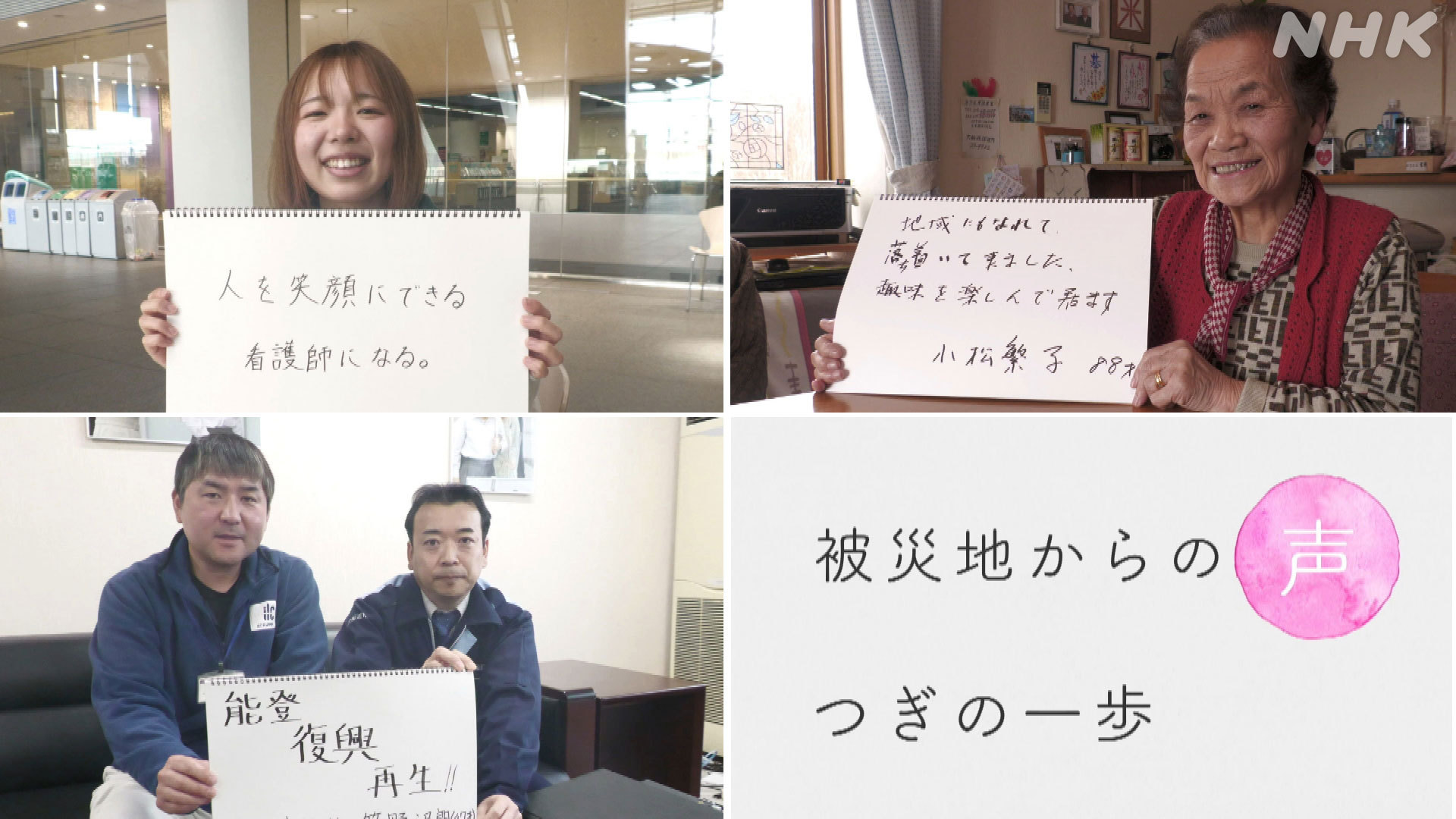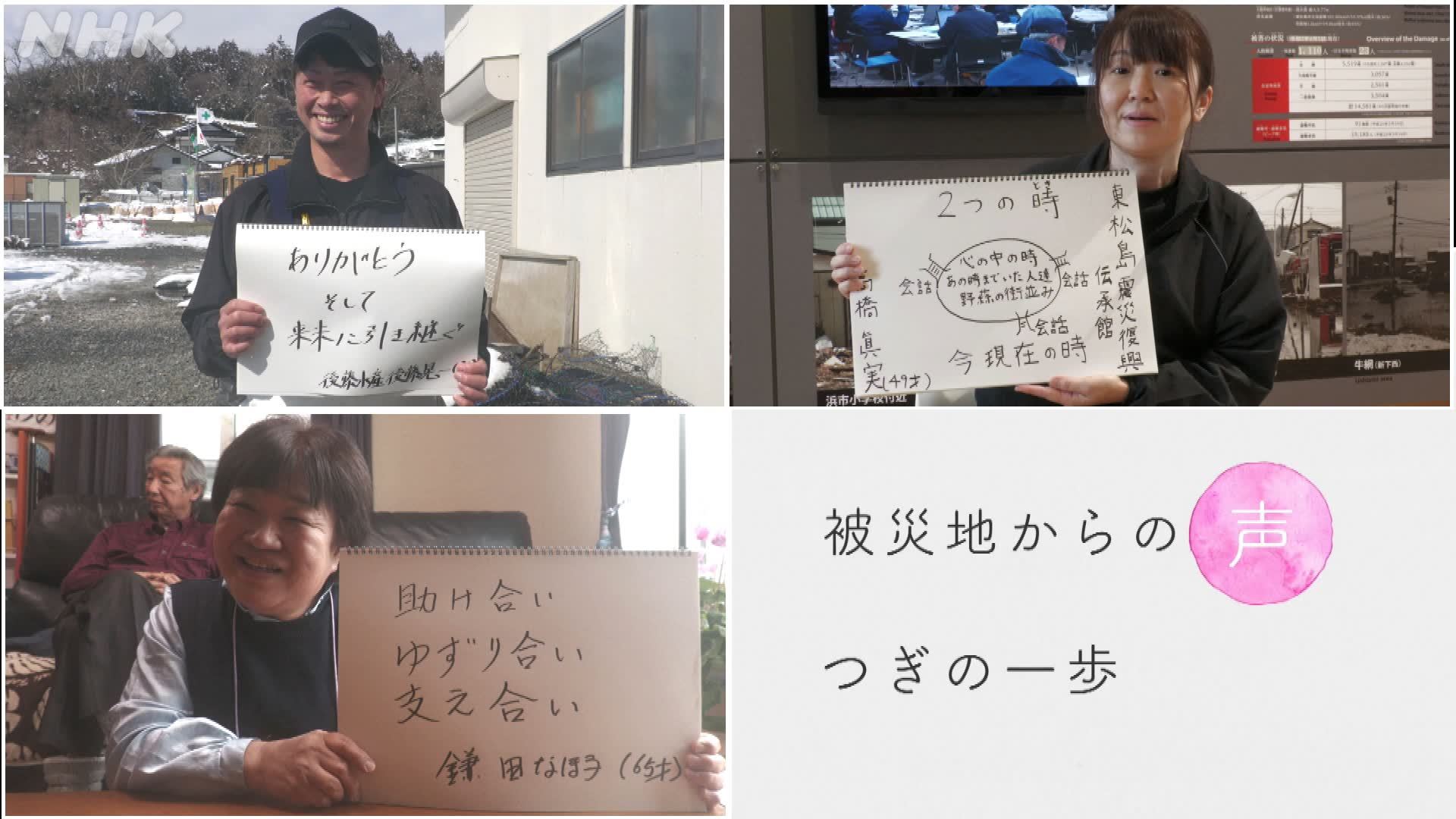【キャスター津田より】12月18日放送「首都圏編」
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回は年に一度お伝えしている、首都圏に避難した福島県の方々の声です。
原発事故による国の避難指示で、首都圏に住む息子や娘、親戚などを頼って避難し、そこで第2の人生を歩もうと決めた方々がいます。福島県の発表では、避難をきっかけに福島県外に住む人は、今も27000人以上います。そのうち半分の約15000人は、関東の1都6県(東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城)に住んでいます。ただ、この数字は、避難していることを当事者が自ら届け出るシステムを基にしていて(復興庁が県にデータを提供)、実態を反映していないという指摘も多くあります。
はじめに、東京都内で取材しました。4年前まで全町避難していた浪江町(なみえまち)の80代の男性はで、伝統工芸品『大堀相馬(おおぼりそうま)焼』の窯元で、国認定の伝統工芸士でした。自宅と工房は帰還困難区域にあり、窯の再開は諦めました。埼玉県など5カ所を転々として、現在は江東(こうとう)区のマンションで妻と2人暮らしです。ともに持病があるため、子どもが住む都内に永住を決めたそうで、今も窯元の組合には籍を置いており、過去の作品を浪江町の道の駅などで販売しています。
「もう年だからね。自分で(浪江に)行って何かするわけにはいかない…年寄りの10年はすごいよ。本当に東京は何一つできなくて大変だ。地下鉄に乗るにも、ずっと下まで行かなきゃいけないし。浪江にいたら、今の時期はルンルンだね。友達にイノシシの肉をもらったり、2月、3月になると川の魚を取って…。やっぱり自然が良かった。大堀は良かったなあ」
男性は、住民票だけは死ぬまで浪江町に置くことを決めています。

次に会ったのは、浪江町出身の23才の女性です。小学6年生で親族を頼って神奈川県へ避難し、その後、江東区の借り上げ住宅に移りました。女性の父親は若い頃、東京で会社員をしていましたが、Uターンして飲食店の3代目を継いだそうです。避難後、父親は以前いた会社に再就職し、葛飾(かつしか)区に自宅を新築しました。今は女性と両親、妹の4人暮らしです。浪江町の自宅と店は解体しましたが、女性は今も盆暮れの墓参りは欠かさず、将来、夜に人が集まれる店を浪江に作ることが夢だそうです。
「東京の人ってどんなだろうって思っていたけど、めちゃめちゃ冷たい…やっていけるか心配でしたね、中学の3年間は。まあ、いじめはなくて、田舎者ってちょっと言われるくらいで…訛りがとれてなかったんで、おかしかったみたいです。浪江はどんどん建物が無くなって、町が変わっちゃうんだって思うと寂しいです。楽しかった思い出が一番強くて、あんなふうに皆がお店で笑っていた姿が、町にまたいつか笑顔が戻る日が来ればいいなって思います。いつか自分がそういう店をつくりたいです」

そして、世田谷(せたがや)区では、浪江町から避難した60代のピアノ講師の女性に話を聞きました。講師歴は47年で、教え子には全国コンクールの入賞者も多く、執筆した4冊の教本は業界でベストセラーになりました。東京出身で、夫が転職してUターンしたのを機に、幼い息子2人と浪江町に移りました。町では27年にわたりピアノ教室を開き、実家の90代の両親も呼び寄せて暮らしていましたが、原発事故後は、入院中だった父(2013年に逝去)の転院先や、介護に適した賃貸物件を探すのが大変だったそうです。山形県や都内など6カ所を経て、7年前に世田谷区内に自宅と教室を構え、現在は夫と母との3人暮らしです。ウィーンでピアニストとして働いていた長男と、浪江町での教え子も講師として呼び寄せ、今では3人で100人を超える生徒を教えています。浪江町の自宅は解体して5台あったピアノも処分し、約60人いた生徒とは離ればなれです。避難でピアノを諦めた子も多いそうです。
「浪江は教室も少なかったので、熱心な、本気でやりたい人が来てくれて、浪江にいたから指導者として成長できたと思います。避難中、生徒とふれあわない生活がこんなにむなしいのかと感じました。でも、“生徒もピアノも全部失ったけど、先生には指導力が残っています”という知人の言葉に支えられて、仕事を再開したんです。10年経って、教える環境ができたことが本当に奇跡で、すごくありがたいと感謝しています。浪江で育てた生徒と東京で育てた生徒と、合同でコンサートを開きたいですね」

さらに町田(まちだ)市では、大熊町(おおくままち)から避難した60代の男性にも話を聞きました。大熊町には福島第一原発が立地し、ごく一部しか避難指示が解除されていません。男性は元々そば職人で、自ら図面を引いて大熊町に店を建て、材料も東京・築地(つきじ)から取り寄せるなど、本格的なそばを提供していました。原発事故後、義母と妻とともに県内外の4ヶ所を避難し、町田市に落ち着きました。男性は避難中の強いストレスで嗅覚と味覚を失ってしまい、23年間続けたそば職人への復帰は不可能です(奥様もPTSDで摂食・睡眠障害に)。職探しの結果、和太鼓教室の経営者募集の広告を見つけ、今は生徒数120人の教室を経営しています。大熊町の自宅兼店舗は、4年前に解体したそうです。
「本当に20年やってきて、ようやく“自分のそばです”って言えるそばができつつあったんで…そこは無念ですね。教室経営の説明の際に、夫婦で30~40分、太鼓を打たせてもらったんです。その時に家内が、被災してから初めて笑ったんです。“楽しい”って…。それで生きがいになったらいいなと思って、契約しました。太鼓って、非常にリフレッシュの源なんです。私は振り返らないですね。息引き取る時も、“あの時の試練、あれがあったから、今があるんだな”って思うんじゃないかな」

その後、埼玉県に移り、双葉町(ふたばまち)出身の方々から話を聞きました。双葉町は全住民の避難が続く唯一の自治体で、町の面積の95%が帰還困難区域です。原発事故の直後、町民は埼玉県加須(かぞ)市の支援でまとまって避難し、役場も加須市に置かれました。特に、旧騎西(きさい)高校の避難所には一時1400人が避難し、全国で最後まで残った避難所でした(閉鎖は2014年3月)。こうした事情から加須市に新居を構えた町民も多く、今も市内には約400人の町民が住んでいます。町の職員が常駐する役場の埼玉支所も、加須市内にあります。
まず、夫婦で加須市に暮らす60代の男性に話を聞きました。旧騎西高校や借り上げ住宅を経て、7年前に加須市内に中古住宅を購入しました。創業110年の水産加工会社の4代目で、帰還困難区域のため事業再開は断念しました。一緒に働くはずだった2人の息子も、茨城と埼玉でそれぞれ転職しました。加須市の町内会にも加入して温かく迎えられ、交流を深めてきたそうです。また、男性は埼玉に住む双葉町民が集まる「双葉町埼玉自治会」の設立に関わり、副会長を務めています。先月は双葉町へのバスツアーを企画し、避難指示解除された双葉駅前や、町の産業交流センターなども見学しました。
「65歳まで働いて俺は引退して、息子らには“小遣いだけくれればいいから”って伝えて、それで生活しようかと…今となっては夢だったんだけど。バスツアーの参加者の希望をとったんですよ。10年たつと、75歳で避難してきた人は85歳でしょう。どこか体が悪くて行けないとか、メンバーが減ってきた…10年ってこういうことなんだよね。町内に新しい建物はできている、それは分かるんだけど、ちょっと離れた所に入ると、“確かにこういう家があった”っていうのがみんな壊れかけたり、古びているわけ。草はボウボウだし。何も変わっていない、もっとひどくなっているというイメージが強いね」
最後に、加須市に双葉町出身の書家がいると聞き、訪ねました。70代の男性で、旧騎西高校から加須市の県営住宅に移り、5年前に自宅を新築して妻と暮らしています。原発事故当時、すでに子どもは独立し、妻の他に90歳の母親と、91歳の妻の母親の4人で暮らしていました。高齢の2人を連れての避難は壮絶を極め、妻の母は避難中に寝たきりになり、2年前に亡くなりました。自分の母親は100歳で、老人ホームで健在です。加須市に来た翌年、金泥(きんでい・金色の墨)で仏を描き、経文を書く作品に取りかかり、“十三仏”(人間の死後、仏になるまでの33年間を導く)を完成させるのがライフワークになりました。今年3月、旧騎西高校に双葉町民と加須市民との絆を記念した石碑が設置されましたが、刻まれた「希望」の2文字は、男性の筆によるものです。

「人生最大の落ち込みの中で、都内の書家仲間が展覧会を企画して、“先生、作品を出してください”って…。その落差といいますか、でも、それによって火がついたわけですよね。いま書けるのは何かと思った時に、岩手、宮城、福島で相当の方が亡くなっている、その鎮魂の意味で仏様を描こうと思ったんです。やりながらつらくなっちゃって、でも、やめるわけにはいかないです。10年を節目として改めて今後のことを考えた時、前を向いて頑張らなくちゃいけないとみんな思っていると思うんですね。だから“希望”という言葉は、今はベストじゃないかと思います」
今回の取材を通して思うのは、そもそもなぜ無理矢理、他県に家を建てて生活し、こういう思いをする方々がこの国にいるのか、10年経った今こそ、全国の皆さんが立ち返るべきだということです。