「答えのないものを、小説で問う」芥川賞作家・佐藤厚志さん インタビュー
昨年、『荒地の家族』で芥川賞を受賞した、作家の佐藤厚志さん。
出身地の仙台で今も生活し、東北を舞台にした小説を書き続けています。
芥川賞受賞からおよそ1年が経った昨年12月。佐藤さんの“小説にかける思い”を聞きました。
(仙台放送局ディレクタ-・見城佑衣)
「芥川賞作家」としての1年
―まず率直に、2023年はどんな1年でしたか?
| そうですね。慌ただしかったので、目の前のことをこなしていくうちに1年経ってしまったっていう感じです。小説を書くのが仕事ですけども、こういう仕事もやるんだなみたいな。いろんな文章を書くにしても、文芸誌だけに書くってわけじゃないので。 エッセイ(の依頼)はもうほんとに怒涛のようにきますね。なのでエッセイの締め切りを日々こなしていくって感じです。だから小説が進まないというか、なかなか手を付けられない。そんな1年でした。 |

―芥川賞を取ったことで、書くものに対しての影響はありましたか?
| やはり純文学ひとつで生活していくっていうのは難しいので、どうしても出版社も僕も、賞を目指すっていうところになっていくんですね。その分少し縛りがあるっていうかね。芥川賞というのは短すぎず長すぎずっていう分量で勝負するところがあるので、それに合わせて小説を書いて文芸誌に発表していくっていう。そういうのが定番の執筆スタイルになっていくんですけども、芥川賞っていうのを越えると、そこで自分の書くものというのは縛りが取れてね。何を書いてもいいっていう。長いのを書いてもいいし、短いのを書いてもいい。そこで自由は生まれるんですね。ただ自由が生まれる一方、今度じゃあ何書けばいいのかなっていう難しさも出てくるんですね。 幸い、自分は芥川賞の後に地元の新聞で小説を書かなきゃいけないっていう、そういう必要がありましたんで。必要に迫られて、深く考える暇もなく書いていったという状況でしたね。 |

昨年1月 芥川賞受賞会見
植木職人の日常から着想を得た『荒地の家族』
芥川賞を受賞した『荒地の家族』は、宮城県の亘理を舞台にした中編小説です。
東日本大震災で仕事道具を失った植木職人が主人公。家族とも別れ、喪失感を抱えながら、それでも生きようともがき続ける姿を描きました。
震災後の宮城を舞台にした小説として話題になりましたが、執筆のきっかけは身近な友人の日常の姿でした。
| 『荒地の家族』はまずね、植木屋さんが主人公の小説を書きたいというのが元々あって。僕の昔から知っている同級生が植木屋さん、造園業で働いていて、独立して一人でやっているっていうのをよく近くで見ていたので。長い時間を横で見てたから、それを小説にしてみたいなって思ってたのが傍らにずっとあったので、今回書いてみたっていう感じです。彼のね、そのまんまを書きたいって訳じゃなかったですけども、ただ、一つの題材としていいなっていう風に思ってただけですね。 |
―どんなところに「いいな」って感じたんですか?
| ものを作るっていうかね。職人が自分の日常として何かを作り上げていく仕事が好きなんでね。植木屋でも靴職人でも、お菓子作りの人でもいいんですけど、その人独自の何かを作ってる仕事っていうのがすごく面白いというか興味があるんで。たまたまその中で近くに植木屋さんがいたから、いいなと思っただけですね。 |
―職人の姿を小説で描いていくのが好きなんですね。
| それを小説に書くのが好きっていうよりも何だろうな。こう、物を分解してみるっていうのが好きですね。靴って普段履いているけど、中はどうなってるのかなみたいな。靴底を開けると、色んな底材の間にクッション、コルクとかが入っていたり。作りが実は複雑で、繊細なもので、今までの工夫が詰まっていて面白い。ひとつの仕事をひもといてみると、面白いっていうのはあるんで。何の仕事でも色々何かひもといてみたいなっていう欲望があります。 |
―『荒地の家族』の中で、御自身が気に入っている描写やシーンはありますか?
| 僕が気に入ってるっていうのは、ここがおすすめっていうのはないですね。結局、読んだ人がね、面白いところを拾って、そこだけでも何回も読んだりとかしてもらったら面白いですけども。わりと、筋肉描写とか肉体労働の描写とかは、原稿を出したその後にも更に足したんで。そこは面白く読んでもらえたら嬉しいかなぐらいのものです。 |
―肉体の描写にこだわる、その思いはどこからくるんでしょうか。
| それはね、物語が結局フィクションだからなんです。実在の場所を舞台にしてるとしても、そこは物語の中では架空の場所であり、架空の人物が動く。だから故に、リアルなものを織り込まないといけない。本当のことをね。それは身体的な感覚もそうだし、感情もそう。そういうリアルなのを込めなきゃいけないっていう思いで書いてます。 |
「痛み」を描くということ
『荒地の家族』に限らず、佐藤さんの小説には身体的・精神的な「痛み」の描写が多く登場します。
|
「顔面が潰れた感覚があり、祐治は両手で顔を覆ったまま、仰向けに倒れて動けなかった。」 佐藤 厚志『荒地の家族』 |

―佐藤さんの小説では精神的、身体的な「痛み」がとても緻密に描かれているように思います。
| やっぱり人の痛みっていうのは、本当に分かんないんですよ。共感はするけども、人がどんなに悲しんでいるかとか、どれだけ痛がってるかっていうのは掴めないですから、100%はね。掴めないから、それをできるだけ僕は、だからこそリアルに表現しようっていう努力をするんですけども、それでもやはり伝えられない。 痛みとかっていうのを書き込んでいくっていうのは、伝えたいっていうよりも自分がね、それを掴みたいっていうのもあるんですよね。伝えたいっていうのと同時に、それはどれだけね、痛いとか悲しいとかっていうのをくみ取れるかな、っていうことでもあります。双方向的に、描いたり感じたりしたいっていう、そういう思いです。 |
―小説を書くという行為自体が、「痛み」を分かろうとすることなんですね。
| そうですね。そういう能動的な気持ちっていうのはあります。書くっていうことを通して。 |
東北の身近な風景が、作品にあらわれる
―『荒地の家族』で印象的だったのは、「災厄」に見舞われる前と後の町の風景が鮮明に描写されているところでした。
| 考えて描くというよりは、見える風景をそのままできるだけ忠実に紙に下ろしていくっていうような作業の感覚なんですね。何か意図があって書くってことはあまりなく、つまり見える風景を描いていくっていう。見える風景っていうのは多分、亘理に小さい時に行ったときに見た風景とか、それから今に至るまでに見てきた風景の中で、心にとまってる風景がたぶん浮かんできたんだと思うんですね。それを捕まえてこう紙に降ろしていくってことです。 ただ、目に見えるものをね、全部書いたらもう読んでられませんから、そこから絞るんですけど、難しいんです。見えるものを全部書きたいっていう思いはありますけども、そこから切り取る、自分の中で風景をね。そこで描写していく訳ですから。まあ物語が大事ですから、読者の気持ちも考えつつ、くどくないようにね。バランスを見て書いてます。 |
―市井の人の日常生活をつぶさに追いかけている印象もありました。
| 日常を営んでいくっていうのは、それが第一義的なものですから。小説も、僕の中ではその延長にあって、毎日少しずつ原稿を書いてくっていうのが生活としてありますから。それが反映される形で小説が書かれてるのかもしれないんですけども。僕が書く小説の中に劇的な何か出来事は起こんないかもしれないですけどもね。日常の中にもやっぱりこうスリルとかはあってね。「会社に遅れる!」とか「もう間に合わない!」っていう時にね、知り合いに話しかけられたりして。「日常」っていっても、何もなく時間が過ぎていく訳でもないですから。何とかこう仕事をして、御飯を食べて生きてるっていうのがあるんで、それをそのまま描写していきたいという欲求があります。 |

佐藤さんの小説は、どれも宮城や東北を舞台にしています。しかしそれは、あえて東北を描き続けているというわけではないといいます。
| 単純に僕は仙台で生まれてね。ちっちゃい時は父親の転勤に合わせて転居というのも経験して。秋田とか岩手とかに住んだりっていうのがありましたから。もうわりと自分の中にある風景っていうのが東北に根差したものなんでね。で、僕が書く小説っていうものが、身近なところから題材を引っ張ってくることが多い。多いというか、身近なところからしか書けないっていうところがあるんで。必然的に地元を書いていく、大きな括りで東北っていうところを舞台にして、書きたいっていうよりも、それしか書けないかなっていう感じです。
根本的にはいろんな場所を書いてみたいっていう気持ちはありますよ。東京を舞台にしてもいいですし、外国でもいいですけども。やってみたいなって思いはあるけども、自分が書けるかっていったらね、分からないので。まずは書けるものを書いていくっていうことです。 |
小説に専念する新たな1年へ
長年、仙台市内の書店に勤めながら作家を続けてきた佐藤さん。
しかし、昨年の10月に書店を退職しました。
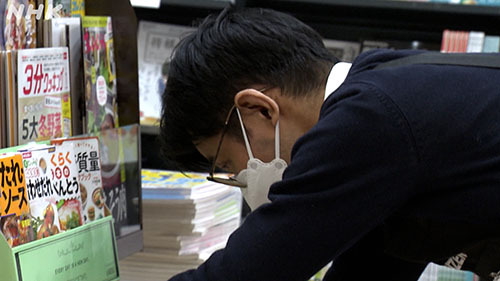
書店員時代の佐藤さん
―書店をおやめになるのは、いつ頃お決めになったんですか。
| いつかはね、小説一本で行かなくちゃいけないなっていうのはあったんですけど。2017年にデビューした時からね。というのは、プロとしてね、「小説を書いてます」ってこう、自分で納得できるようにね。どっかでは小説一本で行きたいなっていうのはあったんですけども。今年は決めたっていうよりも、今回はその必要に迫られてっていう感じですかね。どうしてもこなさなきゃいけない原稿が前にあって、そうせざるを得なかったっていう感じです。 |
―書店員をしながら小説を書くことに、こだわりをお持ちなのだと思っていました。
| 働いてるとね、色んな人と話す機会もあるし、今出てる新しい本もどんどんね、箱を開けて一番最初に手に取ることができるっていう。それは結構大きなメリットで。働きながら小説を書くのはいいなと思ってたんですけどね。働いてると、わりと体が活発に動く。そのテンションのまま、原稿に移行できるみたいなところもあったんで。リズムがあってね。1日仕事をして、その後に小説書いて…っていう流れがもう定着してたんでね。
そのまま、そのリズムでずっとやっていけたらいいなと思ってましたけど、さすがにね。1日にちょっとずつ書いて賄える原稿量というのは限られてますので、それで賄えなくなってしまって。できるだけ小説の時間を確保する為に、本屋の仕事は一旦やめたって感じです。 |

最後に、佐藤さんにとって小説とはいったい何なのか。
じっくりと言葉を選びながら、語ってくれました。
| 難しいんですけどね。根本的にはね、小説っていうのは、答えを出すっていうのが目的ではないですから。答えるっていうよりは、問う。問うっていうのが小説の目的であるんですよね。究極的に言うと、小説のテーマっていうのは死とかね。生とか、生きるっていうことに、突き詰めるとね、そうなっちゃいますから。根本が、答えのないものを問うてるっていうところが小説にはあるんで。小説っていうのはそういうものなんで。答えるっていうよりも問いを重ねていくようなものだと思ってます。 |

| 自分が一人で生きてるわけじゃないですから、どうしても何か頼ってね。今まで人類が発明してきたものを享受して、何でもね、文明の機器を享受してね。で、今、人に頼って生きてるっていうのもありますから。一人じゃ生きられないっていうっていう感じですかね。漠然としてるんですけど。なんて言ったらいいのかな。こう、今までの積み重ねを自分が享受してるゆえに、何か僕も自分のできることで役に立ちたいなっていうことなんですよね。何かそういう仕事ができたらいいなっていう、そういう気持ちです。 |
(2024年1月5日 『おはよう宮城』 で放送)








