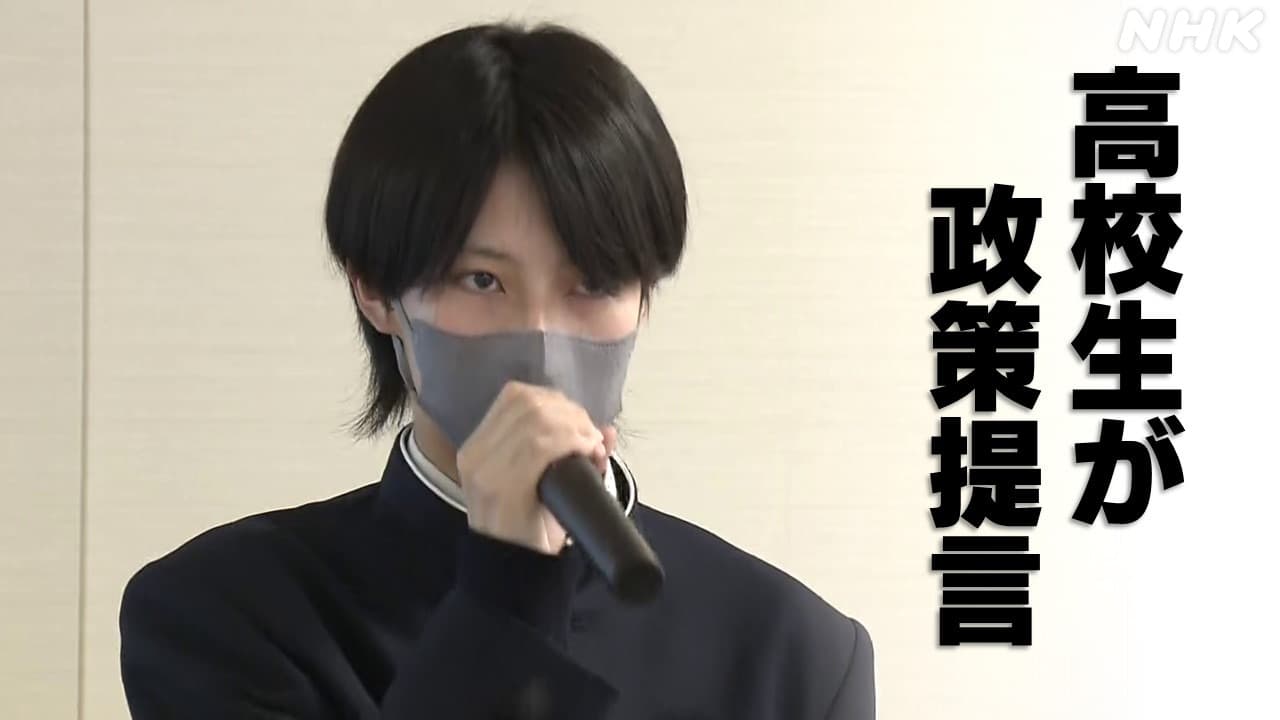健大高崎 青柳監督の原点は「内野より狭い空き地」と「同好会」
- 2024年04月23日

センバツ高校野球で群馬県勢初の頂点に立った指揮官の目には光るものがあった。胸中にあったのは、23年前、野球部創部当時の光景だった。整備が不十分で内野のノックをするのもやっとという「空き地」。そして、厳しい指導をすればすぐにやめていく「同好会」のメンバーたち。
高崎健康福祉大高崎高校、硬式野球部監督、青柳博文、51歳。
その指導者人生は、ことし開場から100周年を迎えた甲子園の「ひのき舞台」とは正反対の状況からのスタートだった。
(前橋放送局 記者 中藤貴常/2024年4月放送)
頂点から3日後、案内されたのは

群馬県内がまだ「健大高崎フィーバー」にあったセンバツ優勝の3日後。私(中藤)たちは快挙を伝える「緊急特番」を放送するために、青柳監督の取材を行っていた。学校として「初」の全国の頂点、しかも、群馬県勢としても「初」のセンバツの頂点。「初」ものづくしの背景には、指導者としてどんな歩みがあったのか、探るためだった。弱い雨が降るこの日、監督室から出た青柳監督が傘を差しながら案内してくれたのは、テニスコートだった。

健大高崎 青柳博文監督
「ここが原点です。ここからなんとか甲子園を目指そうと、創部当初、この場所で練習していました」
23年前、健大高崎硬式野球部の歴史は、当時「空き地」だったこの場所から始まった。セカンドベースまでの距離さえ確保できない狭さだったという。

「塁間を狭めて練習していましたね。“鳥かご”のようにネットを張り、その中でノックをしたり、狭いですけどバッティングをやったり…単純な練習をしていましたね」
“夢”と“厳しい現実”
青柳監督自身の野球人生は、華やかな歩みだった。

県内屈指の伝統校、前橋商業では甲子園に出場し、大学も強豪の東北福祉大学に進学。卒業後は軟式だったが、社会人の強豪チームでプレーした。引退後、県内の建設会社で働いていたところに打診を受けた。
「女子校だった高校が共学化に伴い、野球部を作る。監督を務めないか」
高校野球の指導者という“夢”がかなった瞬間だった。
「どこかでチャンスが巡ってきた時のためにと、選手を乗せるための大型バスの免許を取るなど準備を続けていました。声をかけてもらえたのは、とてもありがたかったですね」

ただ、2002年の就任直後に待っていたのは“厳しい現実”だった。先述のように専用のグラウンドはなし。メンバーはその前年にできた「同好会」の20人で、野球経験者は4人だけだった。

「言い方は悪いですが…絶望ですよね。現実を見て『ちょっとこれは厳しいな』と。正直そういう思いが強かったですね。自分だけ燃え上がって、周りだけ冷めているという感じですね」
厳しい指導、次々と去って行った部員たち

30歳で就任した“青年”青柳監督は、どんな指揮官だったのか。当時の部員の1人に話を聞くことができた。

「初代キャプテン」の倉持雄太さんだ。
「かなりの“熱血”という感じですね」
そう語り出し始め、さらに続けた。
健大高崎 初代キャプテン 倉持雄太さん
「僕は昔から野球をしていたので、甲子園に出場経験もある野球のいわばエリートが監督になってくれるということで、とてもわくわくしていました。ただ、周りのメンバーたちはその“熱量”についていけない人たちもいて少しギャップがあるような感じでした」
「同好会」は、小学校から野球をしてきた倉持さんが、学校が共学化された2001年に立ち上げたものだ。「かき集めた」という仲間が中学校でしていた部活動は、テニス部、卓球部、科学部…。「帰宅部」という選手もいた。野球に対する「向き合い方」や「意識の差」は異なっていても当然だった。倉持さんは、23年前、青柳監督の就任初日の様子を今もありありと思い浮かべることが出来るという。選手たちを教室に集めた青柳監督が「熱く」語り始めた。

「これから、甲子園を目指す」
「厳しく、行くぞ」
「まずは、坊主にすることから始めよう」
多くの選手の思いは、正反対だった。
「遊びで、やりたかっただけなんだけどな」
「そんなに、厳しくやりたくない」
「俺は、坊主にしたくない」
倉持さんによると、この初日のミーティングのあとだけで、なんと、部員の3分の1ほどが去って行った。その後も、少し厳しい指導をしただけで、やめていく部員が続いた。そして練習を「ボイコット」することもあった。青柳監督にもこの時のことを聞いた。「何回もあった」というボイコット。それだけでも傷ついた「心」をさらに傷つく出来事があったという。

健大高崎 青柳博文監督
「トイレの個室に自分が入っていると、部員たちがあとからトイレに入ってきて、僕の悪口を言うんですね。『練習が厳しい』とか『だるい』とか…悲しくて涙が出ましたね」
“健大高崎”は隠したい4文字
悲しい出来事は、それだけではなかった。バラバラだった選手たちの「心」を1つにしようと苦心する中で、まずは校名が入ったバッグをそろえることにした。しかし、ほどなく、青柳監督は、学校の外で思わぬ光景を目にすることになる。

健大高崎 青柳博文監督
「バッグにあった学校名を自転車のカゴで隠すんですね。自分が健大高崎の野球部であることを『恥ずかしい』と思っていたんです。その姿を見て、また涙が出ました。自分の学校にプライドを持てないというのは、非常に悲しいなと思ってですね…」
練習場所がない、選手の情熱がない、先は見えない。まさに、ないないづくしの日々だったが「1人でも部員がいるかぎり」と、なんとか心を保ち指導を続けた。
“右腕”が出来た

就任初日に発した「甲子園を目指す」ということばにうそはなかった。ただ「甲子園への道」は、当時も今も、それほど平たんではない。だからこそ、全国の球児や指導者にとっては「永遠の憧れの場所」でもあるのだが。
青柳監督の就任から5年間の夏の群馬大会の成績は次の通りだ。
初戦敗退、初戦敗退、3回戦敗退、初戦敗退、3回戦敗退。
しかし、その間に「甲子園」、しかも、この春の「頂点」までつながる大きな転機があった。創部3年目の2004年。みずからの「右腕」となる人材を探し続けていたところ、1人の人物にたどりついた。

生方啓介さん。今も野球部の部長を務めている。県立の沼田高校出身ながら、夏の県大会では決勝まで進んだ。他校の指導者をしていた生方さんの同級生の紹介でつながった2人。それ以降、磁石のS極とN極のように引き合い、一心同体、二人三脚、取り組んでいった。
「どうすれば勝てるのか」
「そのために、どんな指導すればいいのか」
時に深夜まで続いた2人だけのミーティングの時間は、青柳監督にとって今も貴重な財産だ。
止まっていた歯車が回り始めていった。
特別だった 2人だけの日々
その“右腕”となった生方部長は、深夜のミーティングをどう感じていたのか。
「覚えてないなぁ…」というのが第一声。
健大高崎 生方啓介部長
「あの選手をどうしようとか、ここを伸ばしてあげようとか、選手のことですよね。こんな練習がいいんじゃないかとか、あすはどうするかということを話していたのかな」
当時の2人の時間が「特別」だったことは全く同じだった。

「青柳さんと2人だけだったけど、本当に楽しくて。当時、沼田市に住んでいたので、深夜に帰ろうとしても、往復2時間かかるんですよ。でも車内でも翌日の練習の事ばかり考えていて。『とにかく勝ちたい』という一心でしたね」
「苦にも思っていなかったんじゃないかな」と続けたが、すぐにみずから否定した。

「でも、もう1回、同じことを今やれ、と言われたら絶対にいや、絶対にいや(笑)、戻りたくはない…ということはきつかったのかも」
一番身近に見ていた青柳監督は「どんな指導者なのか」と尋ねると、意外な2文字を口にした。
「大陸」
自身とは別の人の表現を借りたというが、自身の分析では「心が広い」、「基本的に優しい」、「やらせてくれる」、「言ったことをやってくれる」、「いつも見守られている」、「どっしりとした土台」…ゆえに「大陸」だという。
“機動破壊”で全国に旋風
2人が出会ってから3年目の秋に、ついに求め続けた「結果」が出た。2006年の秋の県大会で準優勝、初めて関東大会に出場したのだ。これを機に、学校のサポートが本格化する。よくとしには専用グラウンドができた。環境が整備されたことで、有望な中学生が県内外から集まってくるようになった。指導の体制も充実させていった。

そこで生きたのが、青柳監督の「サラリーマン経験」だった。「餅は餅屋」とばかりに、取り入れたのは、コーチの「分業制」だった。

「自分がすべてを管理するのではなく、会社のようにしっかりと役割を分けた方が効率がいい。会社で言えば、仕入れの担当、生産の担当…というように、高校野球でも投手担当コーチ、走塁担当コーチ…というように持ち場を任せる。自分は社長とまでは言わないですが、部長くらいの立ち位置でしょうか」

秋の関東大会出場後(2007年~11年)の夏の群馬大会の戦績は、以下の通り、ガラッと変わった。
ベスト8、3回戦、ベスト8、ベスト4、優勝(初)。
創部10年目の2011年にたどりついた初の群馬の頂点。そのよくとしの春にはセンバツ大会ベスト4。このころには「県内屈指の強豪校」と呼ばれるのに十分な実績を積んでいた。

常に1つ先、2つ先、3つ先の塁を狙い、走らなくても相手にプレッシャーをかける「機動破壊」は、全国でも注目を集めた。それは、この春の甲子園でもきちんと息づいていた、健大高崎の唯一無二のキーワードだ。

「選手の能力が今ほど高くない中で、打撃、守備、投手力は一気に高めることはできない。でも『走塁だけならどうにかなる』ということで、当時のコーチを中心に発案しました。長打を狙いたい中でイヤだった生徒もいたかもしれないですが、必死についてきてくれました」

OB500人の結集
それから13年でつかみとった「日本一」の称号。戦力は当時と比較しても格段に異なる。中学時代に日本代表を経験した選手をはじめ、全国から能力が高い選手が集まった。

青柳監督も大会前から「例年に比べて非常に力がある」とかつてない手応えを口にしていた。それでも、優勝直後の「お立ち台」で青柳監督が真っ先に口にしたのは、苦しかったあの日々を振り返った上での発言だった。

「23年前に野球部を創部して、いろいろな方々の支援の中でここまでやってこられて…。本当にいろいろなOBの顔が思い浮かんで涙が出ました」
3日後のインタビューでは、さらに重ねた。監督室にある写真やそこに記された名前を見ながらだった。

「甲子園優勝なんて、創部当時を考えると夢にも思わなかったですね。その瞬間、部長と抱き合うとOBへの思いや、思い出がこみ上がってきました。生徒には感謝していますが、その前に『歴史がある』ということだけは伝えたいですね。ここに全部のOBの名前があります。500人くらいでしょうか。そのOBたちの力の結集だということは、選手たちに伝えたいですね」
監督の“右腕”も涙
20年間、青柳監督のすぐそばに居続けた生方部長は、9回のマウンドにいた佐藤龍月投手が指を痛めていたことへの心配もあり「日本一になっても泣けねえな」と思っていたという。しかし、やっぱり泣いた。監督のもとに行った瞬間、涙が止まらなかった。思いは、2人が出会った時と、今も、一切変わりはない。

健大高崎 生方啓介部長
「勝ちたい、もう、勝ちたくてしょうがなかった。今もだけど、ずっとそれだけにこだわって、毎年、毎年、どうやったら勝てるか、強くなるかということを、ただひたすら考えてやって来た、青柳監督と一緒に。その積み重ねなんですよね」
初代主将がアルプス席で思い出したことば
初優勝の瞬間、健大高崎の初代キャプテン、倉持さんの姿は甲子園のアルプス席にあった。

お立ち台でOBに感謝の思いを語る恩師の姿を見て脳裏によぎったのは、20年前、その恩師に贈られた、ある“ことば”だったという。高校3年生の夏の県大会、初戦敗退のあと、ベンチに引き上げた時のことだった。
「お前たちが野球部をつくってくれたから今がある。自分が絶対にこれから野球部を強くする。だからこれからもずっと応援していてほしい」
共に涙を流しながら、交わした約束。20年の時を経た今、自分はアルプス席からこれ以上ない大きな声で声援を送り、恩師はそれに応えてくれた。

健大高崎 初代キャプテン 倉持雄太さん
「本当に有言実行したんだなと思いました。約束をかなえてくれましたね。まさか日本一強くなるとは思いませんでしたけど。優勝直後のインタビューでOBの事も話してくれて、相変わらず情に熱いというか、律儀な人だなと感じました」
夢、叶うまで挑戦
優勝からわずか5日後、この日からチームは全体練習を再開していた。取材をしていた私(中藤)はふと、いくつかある横断幕の中で、ひときわ古い、ボロボロになった1つに目が行った。

「夢、叶うまで挑戦」
この横断幕について青柳監督に尋ねると、感慨深い表情で語り始めた。

「実はこれ、創部当時から飾っていたものなんです。あの“テニスコート”のころからなので、最初の横断幕じゃないかな。500人のOBたちと共に歩んできた原点とも言えますね。これを見ると創部当時のことを思い返します。まさか日本一という夢をかなえることができるとは思いませんでしたけどね。ただ1つ言えることは、あの子たち、OBたちが、野球部が弱くても、何でも、はいつくばってやってきた結果があってこその今なんですね」

ただ、いつまでも過去を振り返っているわけではない。その目は、もう夏を見据えている。というのも、健大高崎が「夏の甲子園」に最後に出場したのは9年前。加えて、この夏は「打倒・健大」を合言葉に、ライバルたちが挑戦者として向かってくるだろう。その夏は、もうすぐだ。青柳監督の「叶えたい夢」に終わりはない。

「しかし夢というのは不思議なもので“かなえた”と思っても、次から次へと湧いてくるんですよ」
「次の夢は?」と当然の質問をした。

健大高崎 青柳博文監督
「もちろん夏の日本一、春夏連覇です」