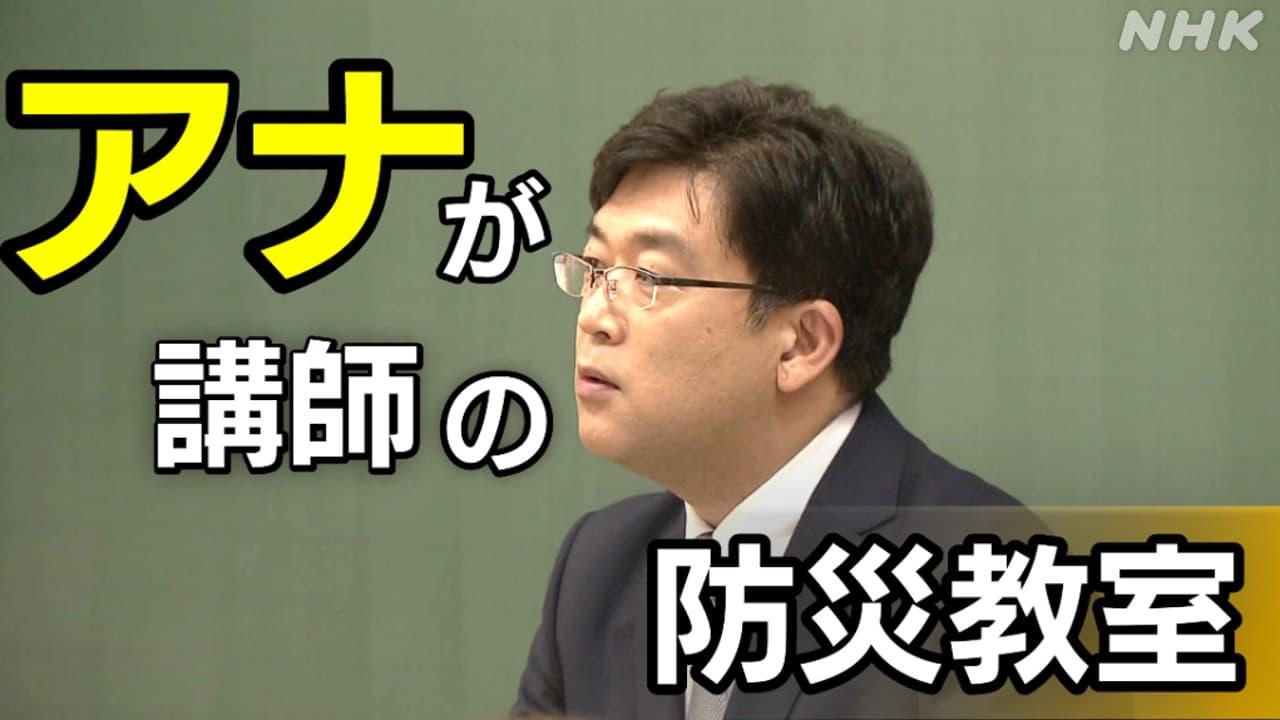えっ、富山に将軍がいたの?
- 2023年10月24日
※ 射水市新湊博物館 開館25周年記念特別展「海が支えた放生津幕府」より
えっ、富山に将軍がいたの?
知ってましたか? 富山に足利将軍が5年間もいたことを・・・。
まずは、こちらをご覧ください。

射水市新湊地区の内川にかかる放生津(ほうじょうづ)橋。そのたもとに立つこちらの銅像。馬にまたがるりりしい姿のこの人こそ、室町幕府10代将軍・足利義材(あしかが・よしき)です。
なぜここに、足利将軍の銅像が建っているのでしょうか。
実はこの人、5年間にわたり、この地に滞在していたのです。
「明応の政変」により放生津へ
いまから500年以上前、室町時代の明応2年(1493)、室町幕府を二つに分かつ「明応の政変」が起きました。当時10代将軍だった足利義材は、対立する大名・細川政元(ほそかわ・まさもと)らとの戦いに敗れ、いったんは捕らえられましたが、6月の暴風雨の夜に京都から脱出し、翌月、越中放生津(射水市)へとやってきたのです。
なぜ義材は、放生津へ逃げてきたのか。当時、日本海を行き来する船の拠点として栄えていた放生津。そこは、義材がともに戦い政変の中で自害した畠山政長(はたけやま・まさなが)の重臣である、神保長誠(じんぼ・ながのぶ)が支配していた場所でした。義材は長誠を頼って放生津へ逃げてきたと言われています。また、当時の越中には、将軍家の領地がたくさんあったほか、京都から離れていて、簡単には攻めてこられない場所だったから、などの理由もあると言います。
放生津へは、京都の幕府から義材に従う役人らもやってきました。義材はこの放生津に、将軍家の正式な旗である御幡(みはた)を立てさせ、自身の幕府の正当性を示したといいます。そして京都に再び戻る機会をうかがいつつ、5年間を過ごしました。

“放生津”とは、どんな場所?
"放生津”は、富山湾に面した港町で、湾内を行き来する船が多く出入りしました。もともとは漁港でしたが、鎌倉時代のころに港町となり、日本海交易で栄えました。
放生津の東には、放生津潟と呼ばれる潟湖がありました。その潟湖に流れ込む河川を通じて米などの物資が集められ、内川沿いの港町で荷揚げされた後、海を行く船に積み替えました。物資とともに人も集まり、放生津は港町から都市へと発展していったと考えられています。
放生津には鎌倉時代になると、越中の武士を管理する守護所が設けられました。そして室町時代以降は、越中の守護で京都に住む畠山氏に代わって、婦負(ねい)郡と射水郡を管理する守護代の神保氏が居城を構え、港町の物流も管理する中で大きな経済力をつけていったと思われます。

義材が富山に残した足跡をたどる
義材の没後500年と博物館開館25周年に際して、射水市新湊博物館で開かれている特別展「海が支えた放生津幕府」から、越中での義材の足跡や港町・放生津の繁栄を物語る品々を見ていきます。

「木造天神坐像」(もくぞうてんじんざぞう)です。魚津市の寺におよそ2か月間滞在した義材がお礼に奉納したと伝わり、寺の近くにある天神山(てんじんやま)の名前の由来になったとされています。

「青磁浮牡丹唐草文香炉」(せいじうきぼたんからくさもんこうろ)です。室町幕府が推進した明(みん)との貿易で輸入された品で、香炉を受け継いできた立山町の芦峅寺では、室町将軍が奉納したと伝えられています。

国指定重要文化財の「絹本著色法華経曼荼羅図」です。仏教経典の「法華経」の物語を描いた絵画で、全部で22幅あるうちの3幅が展示されています。こちらは、京都から船で放生津に運ばれたと考えられており、当時の放生津が日本海を行き来する船の拠点として繁栄していたことを伝える品です。ちなみにこの曼荼羅図については、放生津城主の神保氏が、越中と飛騨の国境を支配する武士を味方につけるため、その武士が信仰していた本法寺に奉納したという説があるそうです。

「禅僧連署書状」は、放生津の義材のもとへ保護を願い出た寺院に対しその許可が下りたことを、義材に仕えていた禅僧たちが証明した文書です。県内に唯一伝えられている、義材が放生津で行った政務に関わる文書です。

義材が放生津城に掲げた将軍家の正式な旗である御幡(みはた)を、想像して復原されたものです。二つの黒い線は「二引両(ふたつひきりょう)」と呼ばれる足利家の紋です。義材が立てさせた実際の御幡には、「八幡大菩薩」と書かれていたと考えられています。

射水市新湊博物館の松山充宏(まつやま・みつひろ)主査学芸員は、「足利10代将軍・義材が5年間富山県で政治を行っていたという史実を多くの人に知ってもらいたい。また、戦国日本史の大舞台となった放生津の歴史を体感していただければ」と話していました。
この展覧会は、11月26日まで、射水市新湊博物館で開かれています。
富山を離れて10年後、義材 再び将軍に!
放生津で5年間過ごした後、義材は福井県、山口県へと移り、富山を離れて10年後にとうとう京都へと戻り、再び将軍になります。鎌倉、室町、江戸と、3っつの幕府がある中で、将軍に2度なったのは、義材ただ1人だそうです。
※ちなみに義材は、福井に移動したころに、名前を義尹(よしただ)へ、そして京都に戻り再び将軍になったころに義稙(よしたね)へと改めています。

「塵塚物語」という説話集には、地方への流浪を余儀なくされ苦労した経験から、義材が“政治には慈しみの心が大切だ”と気付いたということが記されています。
その後義材は、抗争の中で再び京都を離れ、最後は四国の徳島県で亡くなります。
波乱の人生を送った義材の生き様、そしてその義材が5年間過ごした、当時の放生津の繁栄の歴史に、この機会にぜひ思いをはせてみてはいかがでしょうか。