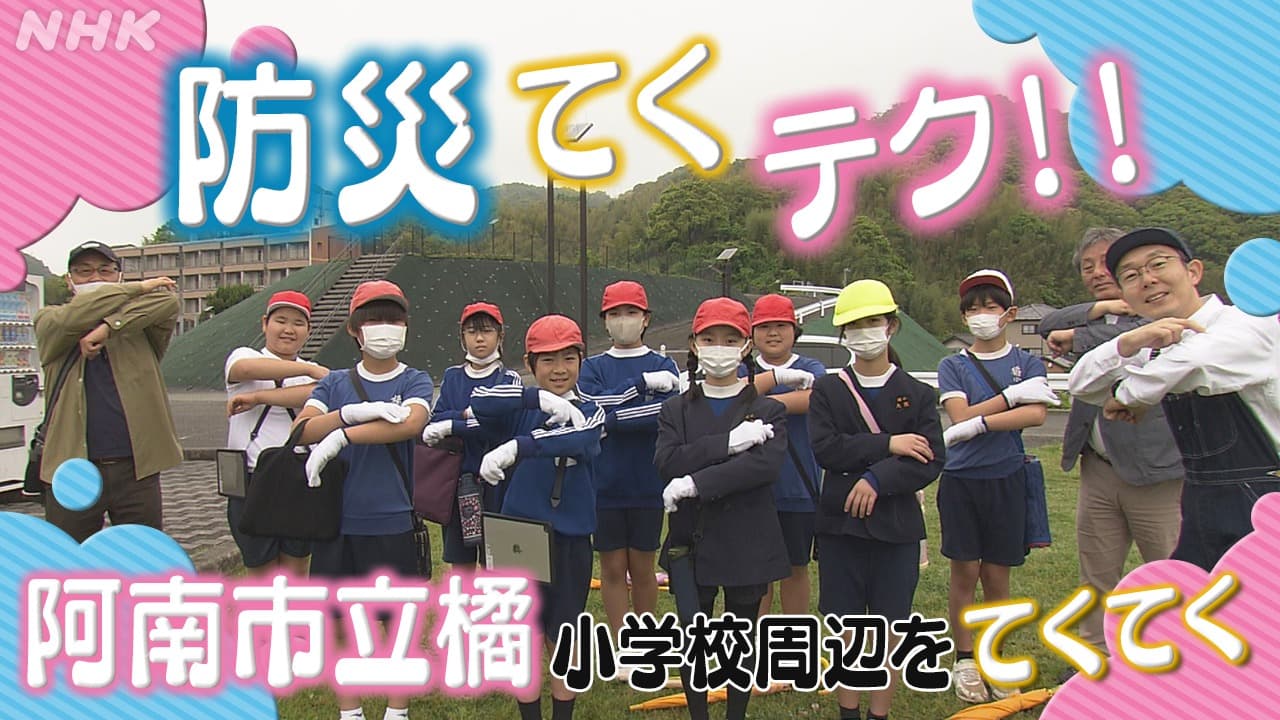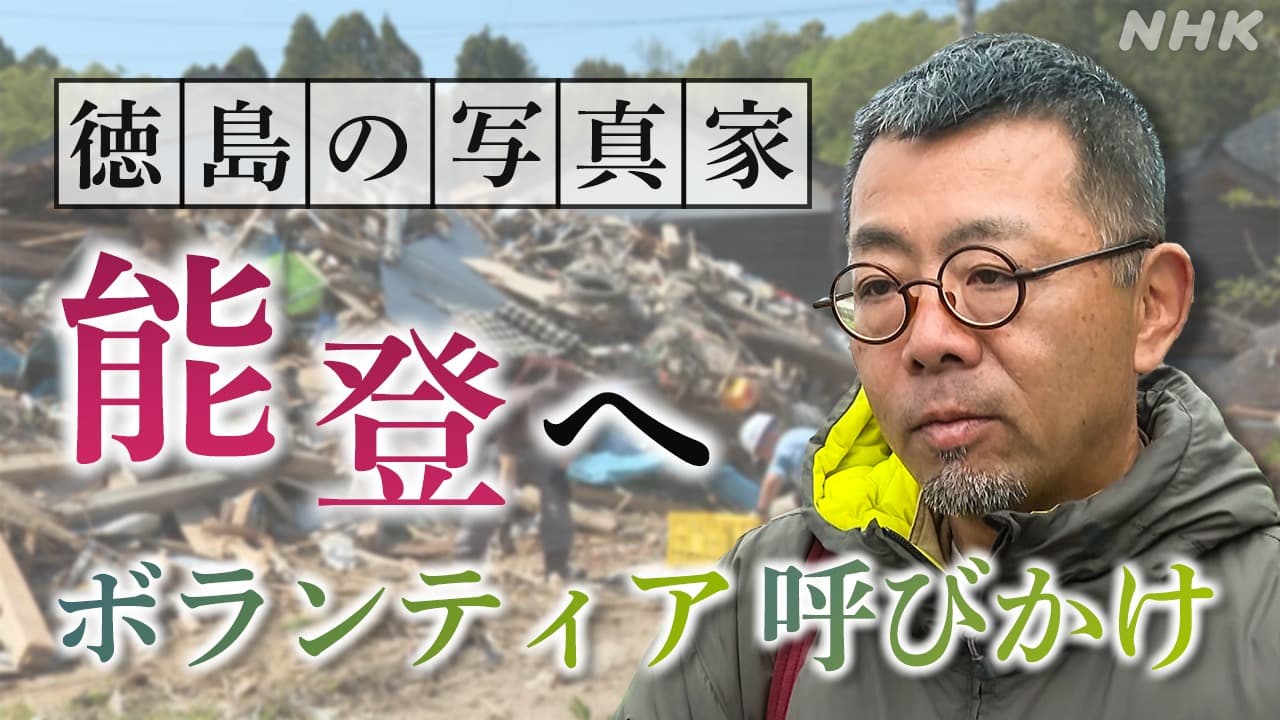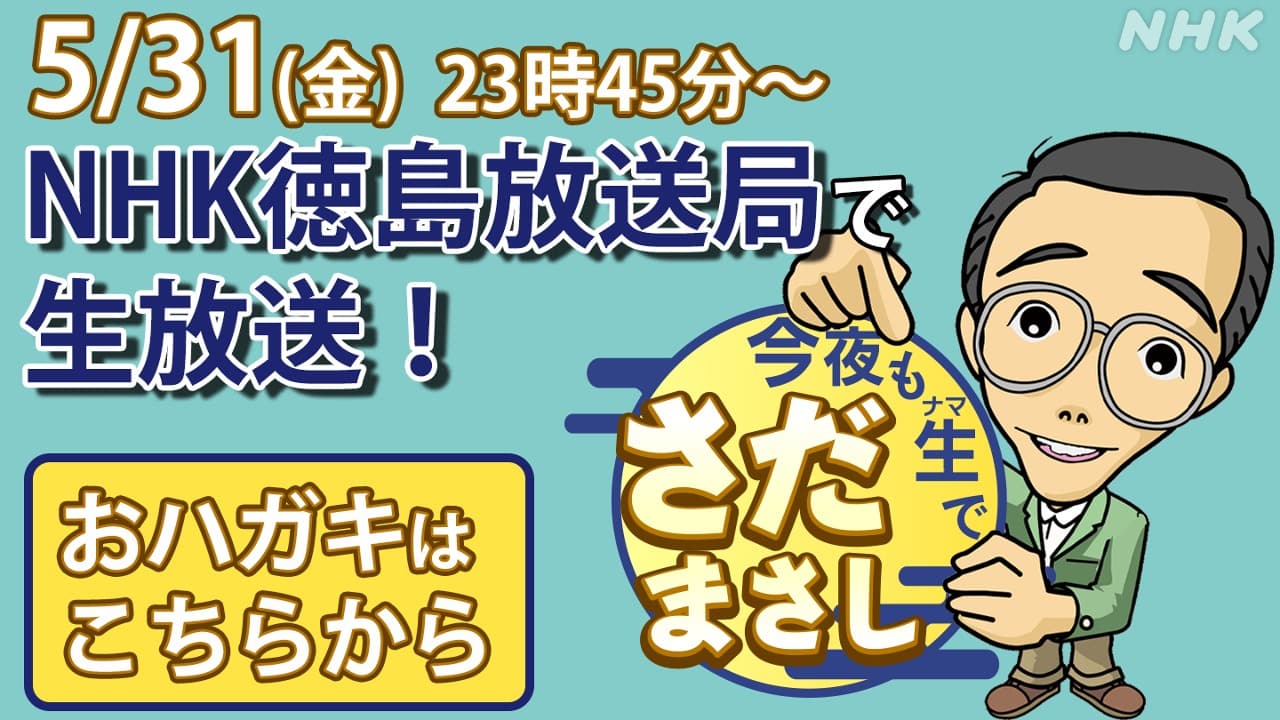後藤田知事 就任1年 災害への取り組み 道路寸断への対策は?
- 2024年05月17日

後藤田知事が就任してから5月18日で1年。
これにあわせシリーズで県政の課題を見つめます。
1回目は「防災」です。
重要性が増す幹線道路寸断への対策
徳島県の最も大きな課題の一つが「南海トラフ巨大地震」や「中央構造線断層帯」の地震への備えです。
4月に発生した豊後水道を震源とする地震では愛媛と高知で震度6弱、徳島県でも震度3を観測するなどいつ起きてもおかしくない大地震への備えの大切さを改めて考えさせられました。
また、ことし1月の能登半島地震では、幹線道路の多くが寸断され、救助などの初期活動が遅れたことが大きな課題となりました。

徳島県でも南海トラフ巨大地震で幹線道路の寸断が想定され、能登半島地震を教訓に初期対応の態勢の整備などが求められています。
ことし3月、能登半島地震の被災地を訪れた後藤田知事は幹線道路が寸断された現状を見て、徳島での対策の必要性を痛感したといいます。

後藤田知事
「能登半島という地形上の問題もある中で、そこには道路が3本走っているわけだが、それが発災後は道路が破損しデコボコになって、それが通れるようになるまでに相当な時間を要した。これから考えた時に、特に徳島の県南部は、幹線道路が3本どころか国道55号一本しかない。」
幹線道路が1本しかない県南部では、大地震が起きた際に、能登半島地震以上に道路の寸断の影響が深刻になるおそれがあります。
こうした道路が寸断された際に必要となるのは、緊急車両などを通せるようにすることです。
現場で作業にあたる工事関係者との連携も欠かせません。
5月10日には、徳島市で国と県それに県建設業協会の担当者の会合が開かれ、南海トラフ巨大地震が発生して道路が寸断された際の初期対応について、意見が交わされました。

南海トラフ巨大地震で幹線道路が寸断された際、協定に基づいて県内の各地区に割り当てられた建設業者がすみやかに対応することになっています。
そのためには、国や県、それに建設業者との日ごろの連携が初期対応において重要になります。
出席者からは、現場に速やかに向かう際の課題や復旧作業の手順を確認する重要性を指摘する意見が出されました。

後藤田知事「訓練を積み重ねていく」
南海トラフ巨大地震などで、幹線道路が寸断される事態にどう備えるのか。
後藤田知事は、復旧に向けた訓練を積み重ねる重要性を強調しました。

後藤田知事
「6月議会の補正予算で、市町村の要望、また県で広域的に準備すべきハード・ソフト、そしてまた今後も県の西部、南部で訓練も頻繁にやっていきたい。訓練したことがないことはできませんから、練習してないことはできません。今まで図面上でやってきたことを実際やってみようと進めています。」
徳島県は、南海トラフ巨大地震を想定して道路の復旧に向けた計画の見直し作業を進めていて、ことし3月に改定しました。
この中では緊急輸送を確保するために、復旧を優先させる道路をこれまでの78路線から3倍以上となる260路線に増やしていて道路の復旧対策の強化を図っています。
こうした計画を着実に実行していくために関係機関との連携が不可欠です。
県は、日ごろから工事関係者との協議の場を設けて課題を共有するとともに、道路の復旧に向けた訓練を行うことでいつ起きてもおかしくない大地震に備えることにしています。
後藤田知事には、国や市町村それに、工事関係者と連携を取りながら災害に強い徳島県を目指してほしいと思います。