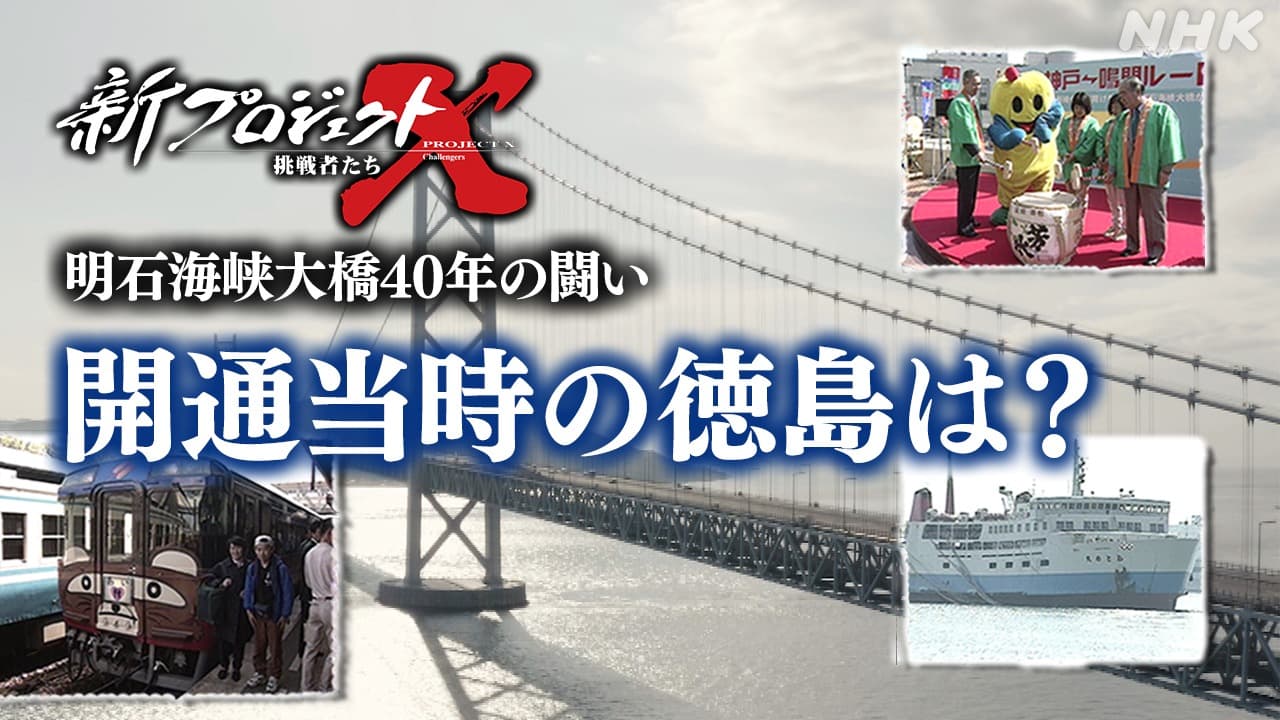徳島 阿南市立橘小学校 避難のときは○○ブロックに注意!
- 2024年05月16日

子どもたちや防災の専門家と地域を歩いて災害から命を守るための道を検証する「防災てくテク」。
防災の視点で自分たちの住む地域を歩くと違った見え方、発見があるかもしれません。子どもたちといっしょに防災のポイントを見ていきます。
阿南市立橘小学校5年生のみなさん、そして、徳島大学環境防災研究センターの上月康則教授といっしょにてくてくしました。
阿南市立橘小学校周辺をてくてく

橘小学校がある阿南市橘町は紀伊水道に面しています。
南海トラフ巨大地震で最大で震度7、地震後およそ19分で20cm以上水位が変化し、最大で8mを超える津波が押し寄せる想定です。いち早く高台に避難する必要があります。

今回は学校の近くの港から歩いて10分ほどの防災公園を目指します。
スタート地点の港では?能登半島地震でも注目された現象

スタート地点の港で、まず上月さんから注意点が。

上月康則 教授
(地震の)後にこういう海に面した場所は、どうなっているでしょうか?

島尾篤志さん
ここは埋め立てた場所もあるので地盤がすぐ軟らかくなると思います。

上月康則 教授
まさにその通りで、そういう場所でよく起きることは液状化。
細かい土と水が噴出してきます。

高橋篤史アナ
大和くんの膝ぐらいまで?
上月康則 教授
あるかもしれません。

能登半島地震でも注目された液状化。
上月教授が現地調査したときの写真です。
橘小学校周辺も同じような状況になって、避難に時間がかかることが考えられます。
住宅地の避難で注意! ○○が並ぶブロック塀
通学路でもある住宅地の中へ。


島尾篤志さん
この辺りの道はブロック塀が並んでいて、
瓦の家が多いから落ちてくるんじゃないかな?

上月康則 教授
ことし1月の能登半島の地震の時もほとんどのブロック塀が倒れていました。
ブロック塀の見方を教えると透かしがあるブロックがあるじゃないですか。
こういうものは鉄筋が入ってない。
透かしが並んでるようなブロック塀は大変危ないです。

上月康則 教授
揺れ続けている中で避難しないといけないので、島尾さんが言ったように瓦が落ちてくる。
電柱やブロック塀などにも気をつけて避難しないといけません。
さらに進んでいくと普段から津波の脅威を意識させる工夫を発見!

高橋篤史アナ
電柱の赤い印は津波がこの高さまで来ますよという印?

上月康則 教授
そうですね。ただ、古い想定ですね。

高橋篤史アナ
この地域の津波の高さは、今は8mを超える想定なので、あと1m高い津波が来るということですね。
みんな普段意識してこの印、見ていましたか?

大和尚矢さん
そんなところまで見ていませんでした。
高橋篤史アナ
気にしてみるのも上月さん、いいかもしれないですね?

上月康則 教授
いいですね。
普通、2mの津波が来ると、家が流され始めると言われています。
あそこまで来る津波は、家を完全に流していく。
それだけの力がある津波が来るんですね。
防災公園に到着! 複数の避難の道を想定せよ

坂道を登り、防災公園に到着です。標高は10mほど。

ここには地域の自主防災会で管理する防災倉庫もあります。

倉庫の中には水や

ビスケットなどの食糧

寒さをしのぐための毛布などが保管されています。いざというときも安心です。

最後に上月さんからみんなにメッセージです。

上月康則 教授
自分の命を第一に考えて、一番に近くて高いところに避難しましょう。
複数の避難路を用意しておきましょうと言われています。
この道がだめやったらこの道、この道がだめやったらこの道と安全なところを事前に選んで考えておきましょう。
今回の感想を代表して大和さんに聞きました。

大和尚矢さん
印象に残ったことや勉強になったことは、津波がたった2mでも来たら、建物などが流れ出すということです。
あと、電柱に赤い印が貼られてて、電柱でも津波の高さを表したりすることがあるんだなということが印象に残りました。
これからも自分たちの、そして、地域のみなさんの命を守るため、防災の学習を続けてほしいと思います。橘小学校5年生のみなさん、ありがとうございました。
高橋アナ 制作後記
今回、上月さんは
①液状化を想定しておく
②透かしのあるブロック塀に注意
③複数の避難路を想定しておく
という3つのポイントについて話してくれました。
そして、今回の避難場所の防災公園はこの地域で想定されている津波の高さより高い場所ではあります。
ただ、津波は想定を上回ることも考えられます。
防災公園のすぐ北の山側には標高20m以上の場所に御嶽神社がありますが、かなり道が細く、整備されていません。
上月さんは
「御嶽神社を避難場所とするならば、子どもやお年寄りも安全に避難できるよう避難路の整備が必要」と話していました。
みなさんも避難場所、避難ルートを複数想定し、実際に歩いて安全かどうか確認してください。