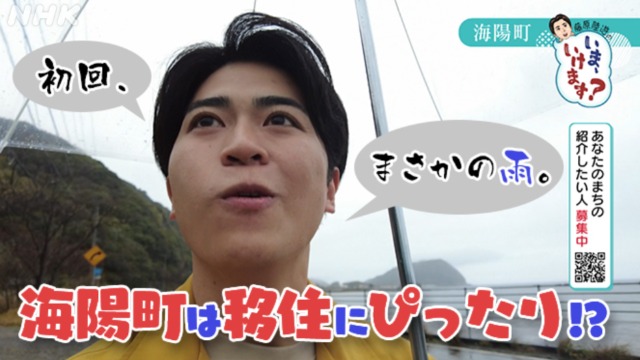部活はもう学校に頼れない
- 2023年01月11日
"学校から部活動がなくなる"
そんな日が来るのを目指して、今、全国各地で議論が進められています。国はこれまで教員が担ってきた部活動を地域のスポーツクラブなどに移そうと改革に乗り出しています。しかし一足早く移行を進める学校の現場からは、いくつもの課題が見えてきました。
指導するのはサラリーマン
部活動の地域移行に一足早く取り組んでいる学校が徳島市にあります。徳島県のモデル校に指定されている城ノ内中等教育学校です。

去年12月の休日に行われたフェンシング部の練習。この日、熱心に指導していたのは学校の教員ではありません。会社員の男性です。フェンシング歴は20年以上。学校には男性のほかに3人のコーチが県教育委員会から派遣され、休日の指導にあたっています。生徒たちも経験豊富な指導を好意的に受け止めています。

自分の弱いところや自分にあった練習方法を教えてくれます。
自分のやりたい練習にあった先生も選べるので環境に満足しています。

とにかく基本の基本、初歩の初歩をわかりやすく繰り返して指導しています。生徒たちの成長を感じています。
なぜ部活動を地域に?
部活動の地域移行が進められる背景には、喫緊の課題があります。教員の長時間労働です。OECD=経済協力開発機構が実施した調査では、1週間の勤務時間が日本は56時間に上り、48の国と地域の中で最も長くなりました。原因の1つとなっている部活動などの課外活動に費やす時間も平均のおよそ4倍に上り、こちらも最長でした。

課題も山積
しかし地域への移行には課題もあります。城ノ内中等教育学校では現在、外部コーチの人件費(1時間あたり1600円)は、国がモデル校の事業費として一時的に負担しています。ただ今後、全国で地域移行が実現したとき、外部コーチの人件費を誰が支払うかまでは決まっていません。保護者が負担する可能性もありますが、今でも練習に必要な剣やマスクなどの用具をそろえるのに10万円ほどかかるといいます。

顧問の仁木将之さん(29)は、さらに保護者の経済的負担が増えれば、部活動を諦める生徒が出てくるのではないかと心配しています。

「フェンシングをしたくてもできない子どもたちが出てきてしまうのを心配しています。地域に移行しても、フェンシングができる環境であってほしい」
さらに地域移行をめぐって練習場所の確保という課題も指摘されています。小松島市の小松島南中学校では、体育館が校舎の中にあることから、教員がいない休日に施設をどう管理するかや、生徒の安全をどう確保するのかについて模索を続けてきました。去年からは試験的に一部の部活動の練習場所を廃校になった中学校の体育館に変えることにしました。

今、この体育館を休日に利用しているのはバドミントン部だけですが、ほかの部の利用が
増えれば練習場所を確保できるか分からないといいます。さらに学校から離れた場所に外部コーチと生徒だけになる場合、けがやトラブルが起きた時の対応も課題です。

学校の施設以外で練習場所を確保するのは難しい現状です。トラブルへの対応も課題で、生徒がけがをした時に練習場所に顧問の先生がいれば、保護者にすぐ連絡できるのですが、地域の指導者だけしかいないとなれば対応は難しく負担になると思います。
もう学校に頼れない
指導者の人件費や施設の確保といった課題は全国各地でも指摘されています。国は、当初、休日の部活動を来年度からの3年間で段階的に地域に移行する計画でした。ところが国民から意見を募ると「指導者や施設の確保が難しい」といった声が相次ぎ、国は3年間で移行を達成するという目標の修正を余儀なくされました。課題が山積する現状にどう向き合うべきか。教育問題に詳しい名古屋大学大学院の内田良教授は、地域社会が一体となって議論を尽くすほかないと指摘します。

「数十年にわたって肥大化した部活動を教員がこれまでほぼただ働きで担ってきましたが、もう学校に任せることはできません。社会でどうやって子どもを育てていくかを考えなければいけない段階にきていると思います。なんとか部活動を回していくためにも、持続可能な部活動のあり方について保護者、地域の住民、民間企業のみんなが広く議論することが必要です」