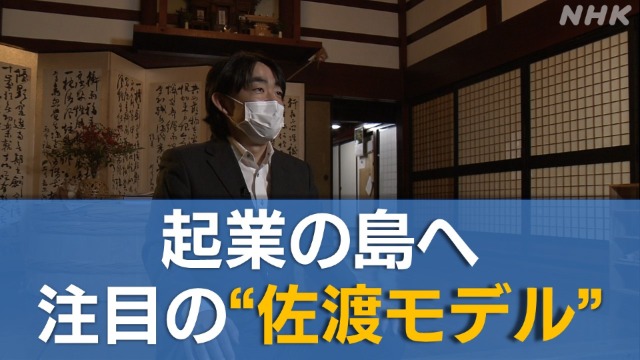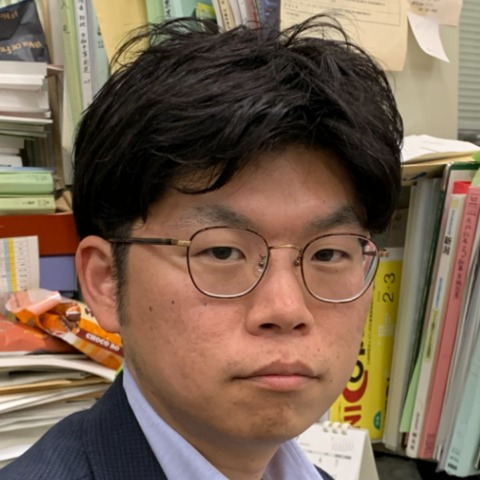不妊治療の保険適用 新潟県の状況は?経験者として取材した
- 2022年04月25日

「ピピピ!」私の家で毎朝鳴るのはスマホでも、時計でもなく、基礎体温計。
もぞもぞと妻が動いて体温を測る。こちらは気づかないよう装いつつ、様子を探る。
「はぁー、たぶん、生理来るわ…」
深いため息とともに舌打ちが聞こえたり、枕に顔を押しつけて泣いていることもあった。
一緒に悲しむべきか、励ますべきか。私はなんて声をかけたらいいのか分からないー。
不妊治療の保険適用が4月から拡大された。
保険適用でどう負担は変わるのか、課題は何なのか、経験者の1人として現場を取材した。
(新潟放送局 記者 野口恭平)
【自然にうまくいく…わけではなかった】

現在、36歳の私。
第1子は5年前に生まれていて、2人目を考え始めたのは4年ほど前。
「まだ若いし1人目と同じように自然な形でうまくいくかな」
なんてことを考えている間に、気づけば1年半が過ぎていた。
2020年2月ころから、基礎体温計を使ってタイミングを測り始める。
転勤とそれに伴う妻の退職を経て、この年の年末からは、クリニックに通っての不妊治療を開始。
検査では特段問題はないということで、医師の指導のもと妊活を続けていたが、なかなか妊娠の兆候はない。
妻の生理はかなり規則正しくやってくるため、毎月Xデーが近づくと、期待と不安の混じり合った思いでいっぱいになる。
その後、2021年秋ごろに人工授精へステップアップすることを医師に相談し、結果的にそこから2回の治療で妊娠に成功した。
振り返った今だからこそ言えるのかもしれないが、当時、先が見えない中、時間だけが過ぎていくのが本当に怖かった。
肉体的にも精神的にも妻はもっと苦しんでいたと思う。
【保険適用拡大 負担はどう変わる?】
とはいえ、もっともっと大変な境遇の人はたくさんいる。
今回、不妊治療の保険適用が拡大されたことを受けて、少しでも悩んでいる方の力になれればと現状を取材した。
まず、負担がどう変わるのか、簡単に説明したい。

一般的な不妊治療の流れでは最初に不妊の原因を検査する。
エコーを使って卵子の発育状況を見たり、精子の質や数は正常か確認したり。
また、子宮卵管造影検査で卵管が狭くなったりしていないかなどを調べる。
これは以前から保険が適用されていた。
青い線で囲まれている右側の部分が主な治療法。これに今回保険が適用されるようになった。
国の調査では、人工授精にかかる費用は平均でおよそ3万。体外受精の場合は平均でおよそ50万円。
今回、保険が適用されたことで、患者の自己負担は原則3割になる。
一方、年齢や回数に制限がある。
体外受精や顕微授精は、
▼40歳未満は子どもが生まれるまでに通算6回、
▼40歳以上43歳未満は通算3回まで、
これ以降、保険は適用されず、自己負担となる。
※人工授精やタイミング法は年齢制限なし
【現場一筋40年 ベテラン医師は】
専門家は今回の制度変更をどのように見ているのか。
約40年にわたり不妊治療に取り組んでいる「ARTクリニック白山」の荒川修医師を取材した。

年間1000人以上の患者を受け入れているこのクリニック。
3月、制度の詳細がまだ分からない中でも全職員が参加して勉強会を行っていた。
窓口でどのような説明をしなければいけないか、協力が欠かせないパートナーの同意を得るにはどうするか、患者の治療方針にどのような影響が出そうか・・・。
このほか、素人の私には難しい専門的なテーマも含めて真剣に話し合っていた。

その後も、ホームページで情報発信するなど制度変更に対応してきたという。
荒川医師にまず、保険適用拡大の効果について聞いてみた。

荒川修 医師
「人工授精をまずやってみようという人は不妊治療の中でも(症状が)軽い方。年齢も若いですし、お金がなくてできなかった人もいるかもしれない。こういう方々が不妊治療を受けてみようかと意識を変えるきっかけにはなったと思いますし、そういう方々を妊娠させるだけのテクニックと技量は十分に積んできています。高額療養費制度も使えるので、50万円ほどかかっていた体外受精を数万円程度に抑えることも可能です」
なるほど、まさに私たち夫婦のような比較的年齢が若いものの、自然妊娠は難しいというカップルにとっては効果が大きいようだ。
【『子どもを持ちたいすべての人に』】
一方、課題もある。クリニックに通っている方にお話をきかせてもらった。

こちらは新潟市内に住む40代後半の女性。
7年前から不妊治療に取り組んでいるが、今回の制度では年齢制限のため、体外受精などは保険で受けることができない。
40代後半の女性
「世代的にも、20代は仕事を一番にしてきました。30代になってやっと自分のことを振り返って考えられる時期になったときに、子どもを持つのはタイムリミットがあるかなと思い、そこからのスタートになってしまいました。今回、年齢制限が設けられたことは残念です。一番子どもが欲しいのは私たちのような世代だと思うので。子どもを持ちたいすべての人に、チャンスがある限り対応してもらいたいです」
【保険適用での治療断念した夫婦も】
また、保険適用での治療を断念した人もいる。
こちらは県内の37歳の夫婦。

4年以上、不妊治療に取り組んでいて、今回の保険適用拡大にも期待していた。
これまでに何度も、体外受精を続けてきて、状態のよい受精卵を子宮に戻してもうまく着床しなかったため、「二段階胚移植」という特殊な治療を検討している。
保険適用拡大にあたり、国は一部の先進治療と保険が適用される診療との組み合わせを認めているが、この「二段階胚移植」については国の審議が続いていて、組み合わせることができない。
100%自費で治療を受けるか、保険適用の範囲内で治療を行うか-。
迷った末、自費での治療を決断したという。
夫婦の妻
「このまま同じ治療をしても妊娠しないんじゃないかって不安なんです。自費か保険適用か、どっちかしか選べないとなったときに、すっごく悩んだ。でも、少しでも可能性があるなら有効な治療をしたいと判断しました。もう少し柔軟な形で『混合診療』(保険適用と自費での治療を併用すること)を認めて欲しい」
【オーダーメードの治療が大事】
晩婚化や女性の社会進出が進む中、このクリニックでも受け入れている患者のうち50%超は40代以上で、難しい相談も多いという。
それでも希望に応えるには、より柔軟な診療が認められるべきだと荒川医師は訴えている。
荒川修 医師
「この人を妊娠させるにはどうしたらいいのか、その人にあったオーダーメードの治療を行うことが不妊治療には不可欠だと思っています。年齢が若かったとして、難治性の人に保険適用の範囲内で治療を続けても妊娠しないかもしれない。難しい患者さん、高齢の患者さんを切り捨てるような制度であってはいけないと思います」
【自治体の支援にも温度差】
今回、取材にあたり、行政による支援の状況も調べてみた。(4月中旬現在)
これまでは体外受精や顕微授精といった治療に対して国が費用を補助する制度があったが、それが今回、保険適用となった。
自治体で独自に行ってきた助成制度は新年度どうなっているのか、県内20の市を取材した。
これがその一覧。

13の市は、保険適用後の自己負担分に対して費用を補助する制度を設けていた。
1年に1回だけ申請できるという自治体もあれば、阿賀野市のように1回につき上限15万円、最大6回申請できる自治体もある。
佐渡市の場合は島内に不妊治療を行っている医療機関がないため、交通費や宿泊費も補助している。
一方、こちらは、制度がない自治体。

南魚沼市などは現状、制度がないものの、導入を検討しているという。
一方、新潟市の担当者は「基本的な治療はすべて保険が適用される上、政令指定都市のほとんどが独自の制度を設けていない」と話していた。
「高額療養費制度」で、ひと月の自己負担額を抑えることもできるので、厳しい財政状況の中、独自の助成がないからと言って必ずしも批判されるものではないと思う。
とはいえ、支援にはかなり差が出ていて、自治体の「思い」の濃淡が伺えた。
【『卵子は若返らない』教育など幅広い対策を】
インタビューで荒川医師は力を込めて、こうも訴えた。

「保険適用の制度を改善していくだけではなく、もっと広い視点をもたなければいけない。例えば教育。卵子は若返られない、年齢とともにどんどん減ってくるし、さらに質が落ちてくる。そうしたことを小学校や中学校の教育の中で伝えていかないといけない。また、不妊治療を卒業した人に、里親や特別養子縁組について伝えていく支援の枠組みは不十分だ。今回の制度変更をきっかけとして、社会全体のボトムアップをしていかないと、日本の少子化は止まりません」
最後に、今回の取材で出会ったご夫婦の妻の言葉をお伝えしたいと思う。
「不妊治療は大変だし、夫婦の間で意見がぶつかりあうこともあるけど、夫婦として向き合えたことについては良かったと思う。男性にできることは限られているかもしれないけど、クリニックの雰囲気や待ち時間の状況を知ってもらうだけでも違うし、一緒に協力していきたい」
保険適用の制度をよりよいものにしていくことももちろん大事だが、パートナーどうし相手を思いやり、一緒に向き合っていくことが何より大事だと感じた。