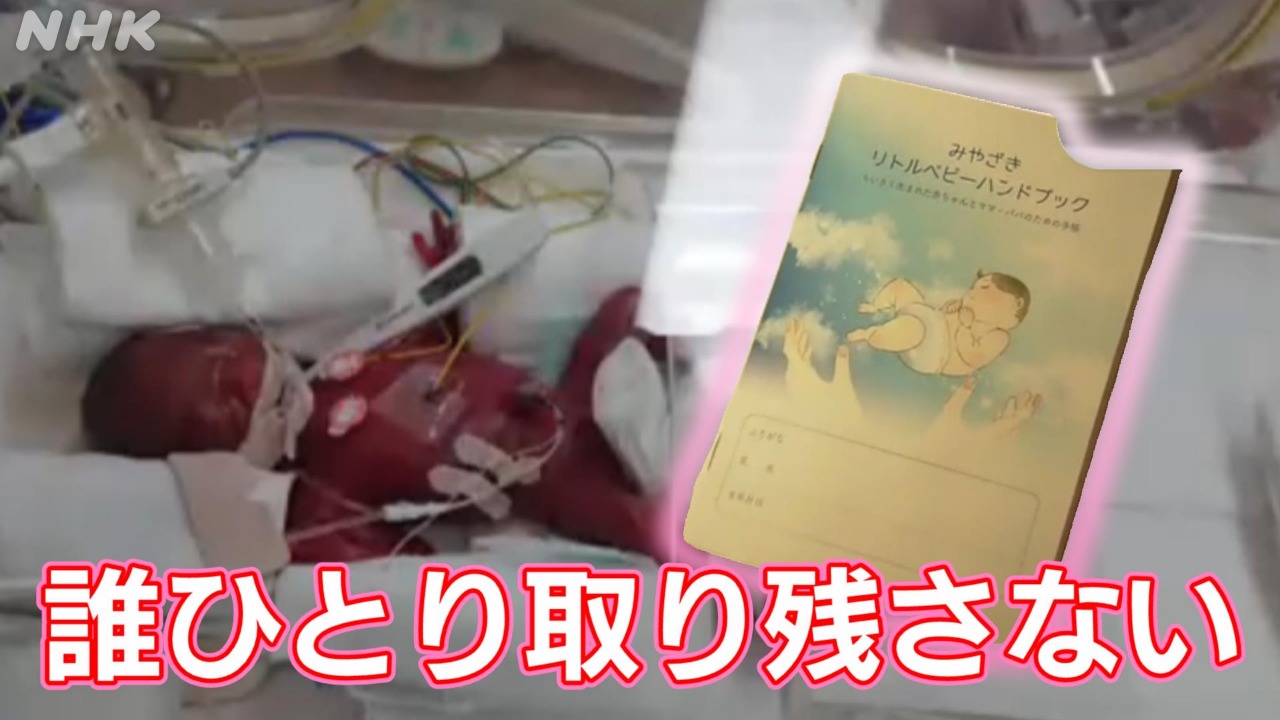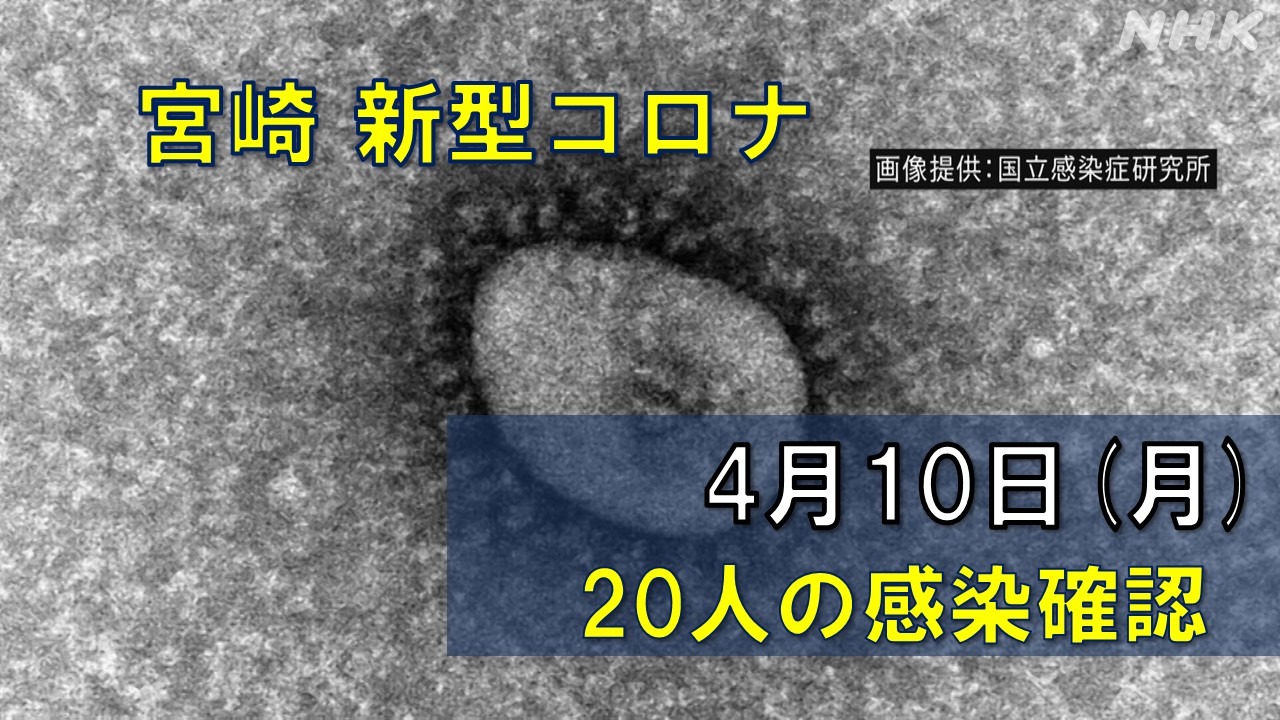乳児うつ伏せ寝は大丈夫?宮崎で死亡事故 リスクを詳しく解説
- 2023年04月11日

宮崎市の保育施設で、3月、うつぶせで寝ていた1歳未満の乳児が死亡しました。
保育園の対応や事故発表までの経緯、うつ伏せ寝のリスクを詳しく解説します。
宮崎市で死亡事故
3月19日、宮崎市の保育施設で1歳未満の乳児がうつ伏せの状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。宮崎市によりますと、この施設では以前からうつぶせの状態で寝た子どもをそのままにしていたほか、国の基準よりも配置する職員の数が少ない時間帯があったということです。警察は乳児の死因について調べています。
保育施設は現在、休園となっていて、市は改善勧告を行ったうえで、4月24日までに報告書を提出させるということです。
なぜ発表するまで時間が?
事件が起こったのは、3月19日ですが、宮崎市がこれを発表したのは、4月6日でした。
期間にして2週間以上の時間がありますが、宮崎市は「乳児の詳しい死因が分かっていないので、発表を控えていた」としています。仮に病気などで亡くなっていた場合は、公表の基準にあたらないためです。
死因はいまも分かっていませんが、6日に消費者庁が「重大事故」として発表したため、急きょ宮崎市も公表することにしたということです。
うつ伏せ寝のリスクは?
うつ伏せで寝ている赤ちゃんが死亡する主な原因として、「窒息死」「乳幼児突然死症候群」(元気な赤ちゃんが寝ている間に突然亡くなる原因不明の病気)「病死」などがあります。

厚生労働省は、うつ伏せをすることで「窒息死」だけではなく「乳幼児突然死症候群」も発生のリスクが高まるとしています。
国の事故防止ガイドラインで乳児をうつぶせで寝させることは原則、禁止されていますが、宮崎市によりますと、この施設では以前からうつぶせの状態で寝た子どもをそのままにしていたということです。
仮に死因が「窒息死」や「乳幼児突然死症候群」だった場合は、施設側の対応が問題となる可能性があります。
対応の現場は?
0歳児から預かっている宮崎市の認定こども園「光が丘幼稚園」では、昼寝の時間は保育士たちがつきっきりで対応にあたっています。

ブレスチェックといって寝たときの体制や呼吸を見て、どういう状況で寝ているのかを確認しています。
市が推奨する基準にもとづいて、0歳は5分に1回、1歳~2歳は10分に1回、チェックシートを使って呼吸の状況や体勢を確認し、子どもがうつぶせになれば、あおむけにさせています。子どもによっては、うつぶせの方が寝やすく泣いて起きてしまうこともありますが、事故のリスクを減らすためにあおむけを徹底しているということです。


保育現場で死亡事故につながることは絶対にあってはならないという気持ちです。
子どもがうつ伏せで寝ると、気持ちよく寝られるという話もお母さんたちから聞きますが、命がなくなることを防ぐため、必ずあおむけにして昼寝をしてもらっています。
事故防止の徹底を周知
宮崎市は、市内にあるすべての保育園や幼稚園など241か所に対して対策を徹底するよう文書で指導しました。文書では、睡眠中の乳幼児について、医師がうつぶせ寝を勧める場合以外は、仰向けに寝かせることや口や鼻を覆ったり、首に巻き付くものを置かないこと、顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察することなどを求めています。
また、宮崎県も宮崎市以外の県内すべての保育園や幼稚園など409か所に対して、対策の徹底を求める通知を送りました。
限られた人員で対応する保育施設はとても大変ですが、痛ましい事故が二度と起きないよう、すべての施設で対策の徹底が求められています。