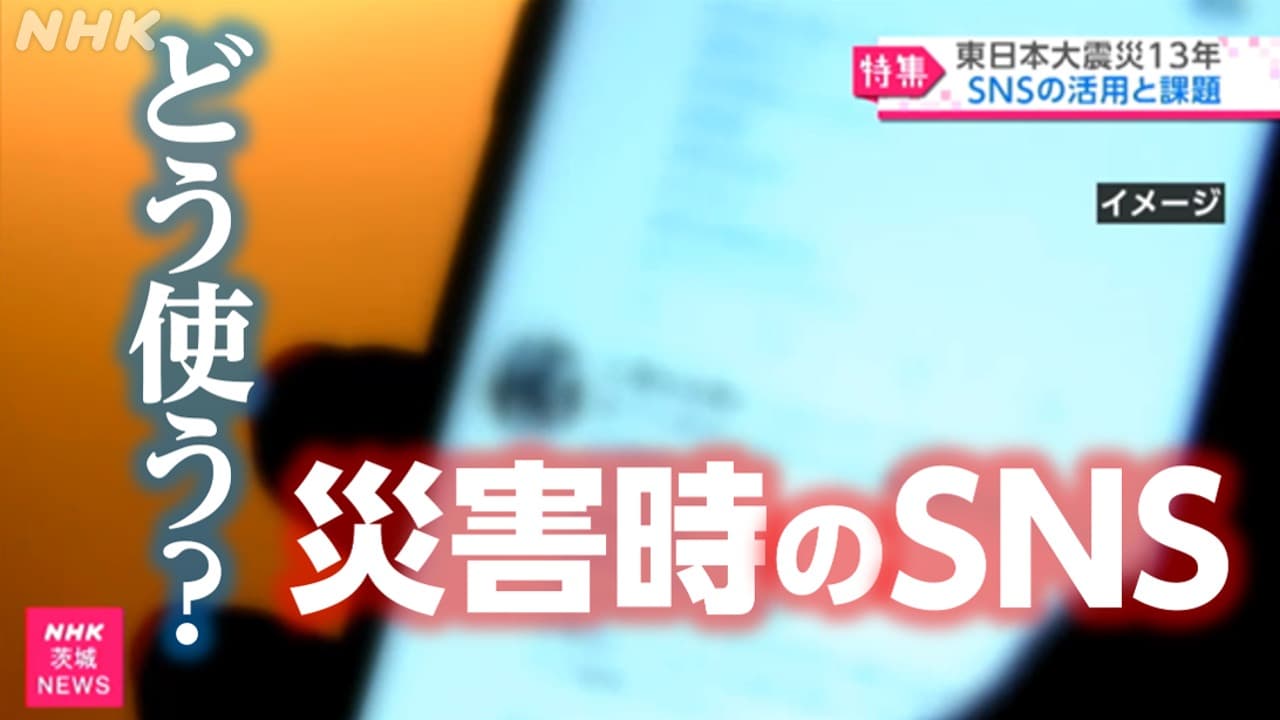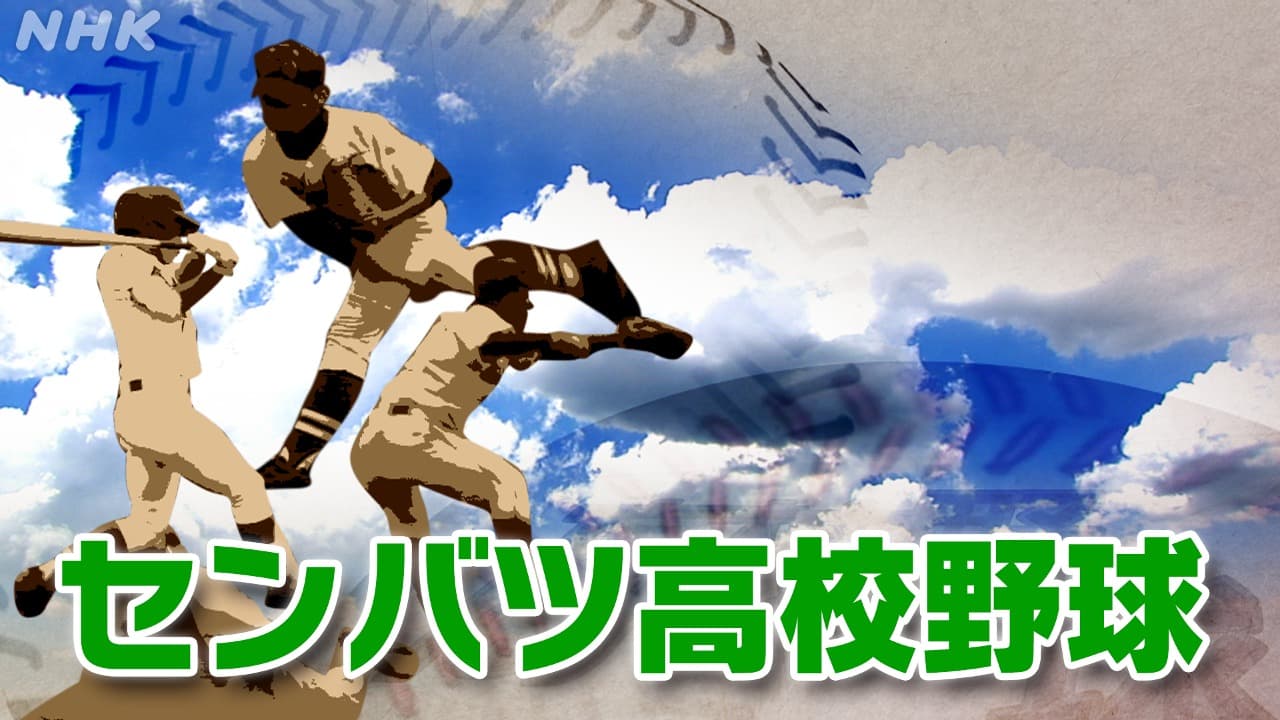茨城 東日本大震災13年 被害・復旧復興の状況 各地の表情は
- 2024年03月11日

茨城県内で24人が亡くなった東日本大震災から3月11日で13年です。大切な家族を亡くした人、そして、震災を知らない子どもたち。多くの人たちが犠牲者を悼み、復興への祈りをささげた1日を取材しました。
NHKプラスで見逃し配信 3/18(月) 午後7:00 まで

県内の被害は 原発事故に伴う福島からの避難者は
2011年の東日本大震災で、茨城県内では震度6強の揺れを観測し、最大で約7メートルの津波が観測されました。



県内で亡くなった人は24人で、1人が行方不明となり、避難生活で体調が悪化するなどして亡くなったいわゆる「震災関連死」に認定された人は42人にのぼりました。

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、福島県から県内に避難している人は2月1日時点で2322人と全国の都道府県で最も多くなっています。

防潮堤工事 6月末に完了へ
震災の被害を受けて茨城県は北茨城市から神栖市にかけての約39キロにわたり、津波や高潮対策として堤防をかさ上げしたり、新たに設置したりする工事を令和2年度の完成を目指して進めてきました。

このうち、大洗町の大洗港周辺では地元の意見を踏まえ漁港の利便性や景観との両立を図った結果、計画が見直され、当初の予定より大規模になったこともあり、完成が遅れていました。

県港湾課によりますと大洗港周辺での工事がことし(R6年)6月末ごろに完成する見通しになり、
これで復興事業として計画された防潮堤はすべて整備されることになるということです。

一方で、茨城沿岸には極めて頻度が低いとしながらも最大で14.8メートルの津波が想定されていて、県は完成する防潮堤もこうした津波には対応できず住民避難を柱とする総合的な対策が必要としています。

人口減少や高齢化に伴う地域の変化や防災意識の低下も懸念されていて地震や津波の防災対策は引き続き課題となっています。
北茨城の漁協幹部「忘れない」

北茨城市では東日本大震災で最大で高さ約7メートルの津波が押し寄せ、5人が死亡、1人が行方不明になったほか、5人が「震災関連死」で亡くなっています。

北茨城市の大津漁港では、東日本大震災で、大津漁業協同組合所属の村山正一さん(当時62)が漁船を沖に出そうとしたあと、行方が分からなくなっています。

大津漁業協同組合の坂本 善則 専務理事は「組合員が行方不明になって13年がたつが、忘れずにいる。震災後も原発事故の影響で漁場の制限が続いていて、今も不安が残ったままだ」と振り返りました。

また、東日本大震災の後も全国で大規模な地震が相次いだことから、「ことし1月の能登半島地震の映像を見ると13年前を思い出す。漁師にとって船は自分の財産だが、組合員には『津波が来る前にとにかく逃げろ』と伝えている」と話していました。
北茨城 高齢のきょうだいが墓参り

北茨城市の磯原町で1人暮らしをしていた平塚幸男さん(当時80)は自宅が津波に流され死亡しました。

11日午前、弟の信次さん(85)は96歳の姉などあわせて4人で市内にある墓地を訪れ、花と線香を供えて静かに手を合わせました。


姉で3女の久江さん(96)は「海を見るたび悔しい気持ちになる。今も夢で『あんねーっ』と私を呼んでいる。みんなに来てもらって幸男も喜んでいると思う」と話していました。

信次さんは「震災の日は寒かったけど、きょうは穏やかな陽気でみんなで来ることができてよかった。
能登半島地震もそうだが津波が来たら高台に逃げることが大切だと感じます」と話していました。

信次さんたちきょうだいは高齢になり、体調を崩すこともあるため、東日本大震災以降、毎年、欠かさず行ってきた命日の墓参りをことしで最後にすることも考えているということです。

福島から避難してきた人たちの展示会

水戸市では、11日までの2日間、記憶の風化を食い止めていこうと福島県から県内に避難している人たちが作った作品の展示会が開かれました。

会場には絵画や織物、竹細工など25人が作った約60点の作品が展示されました。

このうち、布を縫い合わせたキルトの作品には「忘れてはダメ、3.11」とか、「ふつうの生活に戻りたい」などというメッセージが刺しゅうされていました。
また、それぞれの作品のわきには「あの時の止まった時計がゆっくりですが動き出した」などと避難生活の中で感じた作者の思いが添えられています。

会場では、避難した人たちと来場者との交流会も行われ、福島県浪江町から北茨城市に避難している
吉田充雄さん(83)は「北茨城市はふだん2時間ほどで来られるところでしたが当時は道路の状態が悪く8時間かかりました。北茨城市の方はいい人でそれが一番うれしかった」と震災当時や避難生活について話していました。

そして、地震が発生した午後2時46分になると、会場の全員が黙とうをささげていました。
吉田さんは「いつまでも浪江町のことを思っています。帰還は諦めるしかないと思っていますが、早く復興してほしいと思います」と話していました。
北茨城市 慰霊塔や小学校で

太平洋に面した高台にある北茨城市の五浦岬公園には、東日本大震災の慰霊塔や石碑が建てられています。

遺族と住民たちが公園を訪れ、地震が発生した午後2時46分になると、海に向かって手を合わせ、黙とうをささげていました。
市内に住む遺族の1人、吉田 安守さん(83)は母親の一子さん(当時94)が、津波でけがをし体調を悪化させて4か月後に亡くなり、その後、「震災関連死」に認定されました。
追悼式には唯一、遺族として出席した吉田さんは、慰霊塔に設置された鐘を鳴らして追悼していました。

式のあと吉田さんは「13年が経過して当時のことを忘れてしまいそうになるが、こうして振り返るたびにしっかり思い出したい。時間が経つことで悲しさや寂しさがやわらいでいるので、母には『安心して見守っていて』と伝えたい」と話していました。
一方、震災で2人が死亡、1人が行方不明となっている大津地区の大津小学校では集団下校を前に児童110人余りがグラウンドに集まりました。

児童たちは、市の防災行政無線の放送が流れると黙とうを行い犠牲者に祈りをささげました。
6年生の女子児童は「東日本大震災のときは生まれていなかったのですが、家族から家で飼っていた犬が津波で死んでしまったことを聞きました。災害が起こったら家族で決めた避難方法を思い出して自分の命を守りたいです」と話していました。


龍ケ崎市 父親を亡くした男性

龍ケ崎市でかばんや節句人形などを扱う店を経営していた成嶋洋三さん(当時69)は、13年前の東日本大震災の地震で激しい揺れの中、崩れてきた店の外壁の下敷きになって死亡しました。

父親から店を受け継いだ長男の成嶋英貴さん(51)は、午後2時46分になると店内で黙とうをささげました。

英貴さんは、店を継いだ直後は突然、父がいなくなり店の経営などに思い悩む時期もありましたが、その後、乗り越えて仕事も順調にできるようになりました。
今では、父親と同じく町内会の役員を務めるようになり地元の人たちとのつながりや支え合いを大切にしながら前を向いて生きていきたいと考えています。

英貴さんは「元日の能登半島地震で真っ暗なトンネルの中に入ったような状況につい自分を重ね合わせてしまったような気がします。2歩進んで1歩下がる苦しい状況ではありますが、父が大切にしてきた地域の人たちに恩返ししながら頑張って店を続けていくことが使命だと思います」と話していました。
高萩市 震災直後にも出産対応した医師

13年前の東日本大震災の直後に被災しながらも30件以上の出産を担当した高萩市の産科の医師がいます。
茨城県高萩市の「県北医療センター高萩協同病院」で2008年から産科を担当している渡邊 之夫 副院長です。

13年前、東日本大震災発生からの1ヶ月間で30件以上の赤ちゃんの出産を担当しました。

高萩市は巨大地震で震度6強の揺れに襲われ当時の状況について渡邊医師は「帝王切開で患者に麻酔をかけたときに大きな揺れに見舞われ、その後も余震が続いていたからその日の出産を中止しました。エレベーターも使えず職員や看護師とともに担架で運んでいました」と話していました。
この時の妊婦は翌日に帝王切開の手術を行い出産したということです。
その後、市内は停電や断水が続き、病院では自家発電設備や貯水設備で対応しましたが近隣の病院から
入院患者を受け入れたこともあり徐々に水が足りなくなったといいます。

渡邊医師は「どうしても水が足りず市や自衛隊の協力を得て給水車で水を供給してもらった。産婦人科医会などからもミルクなどを運んでもらいなんとか対応することができた」と話していました。

震災のあと、病院では飲み水や食料の備蓄品を新たに準備したほか、赤ちゃんのミルクに使用できるようにウォーターサーバーの設置も行ったということです。

渡邊医師は東日本大震災から13年となることを受けて、「震災の時はこの病院が新築だったことが幸いだったと思います。発電設備や水などを常に備えて患者さんたちを安心して受け入れられる体制を作っていくことが大切だと考えます」と話していました。
液状化被害の潮来市

震度6弱の揺れを観測し、潮来市の日の出地区では、約2500棟が液状化の被害を受けました。
この地区にある「潮音寺」では、本堂など16棟が傾くなどの被害を受けました。
11日は、地区の住民など約20人が集まり境内にある地蔵ぼさつの前で震災の犠牲者を悼む法要を行いました。

このあと、地元の認定こども園の園児も参加して、地震の発生時刻にあわせて住職と園児らが一緒に鐘楼の鐘をつき、被災地の復興を祈りました。


参加した70代の女性は「液状化でひどい被害をうけたのですが、いまは元に戻ったような状況になりました。いまの子どもたちは、当時のことは分からないと思うので、頑張って伝えていきます」と話していました。

NHKプラスの配信終了後はこちらから