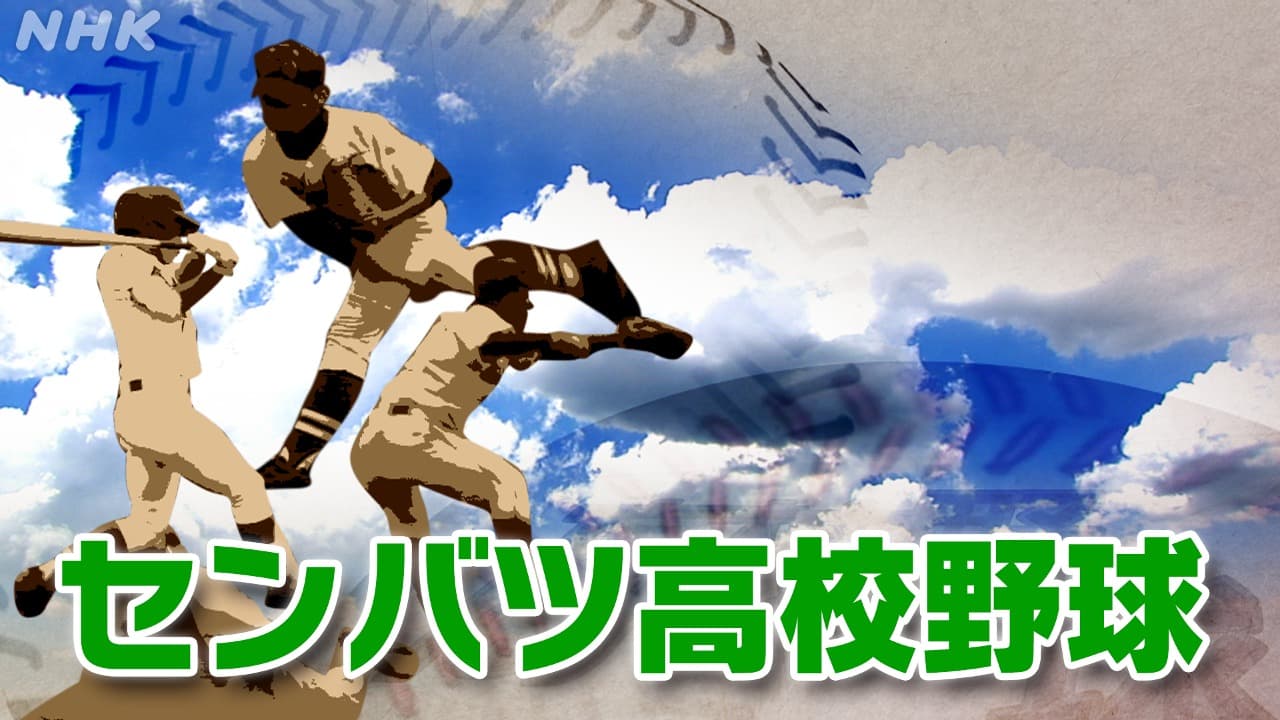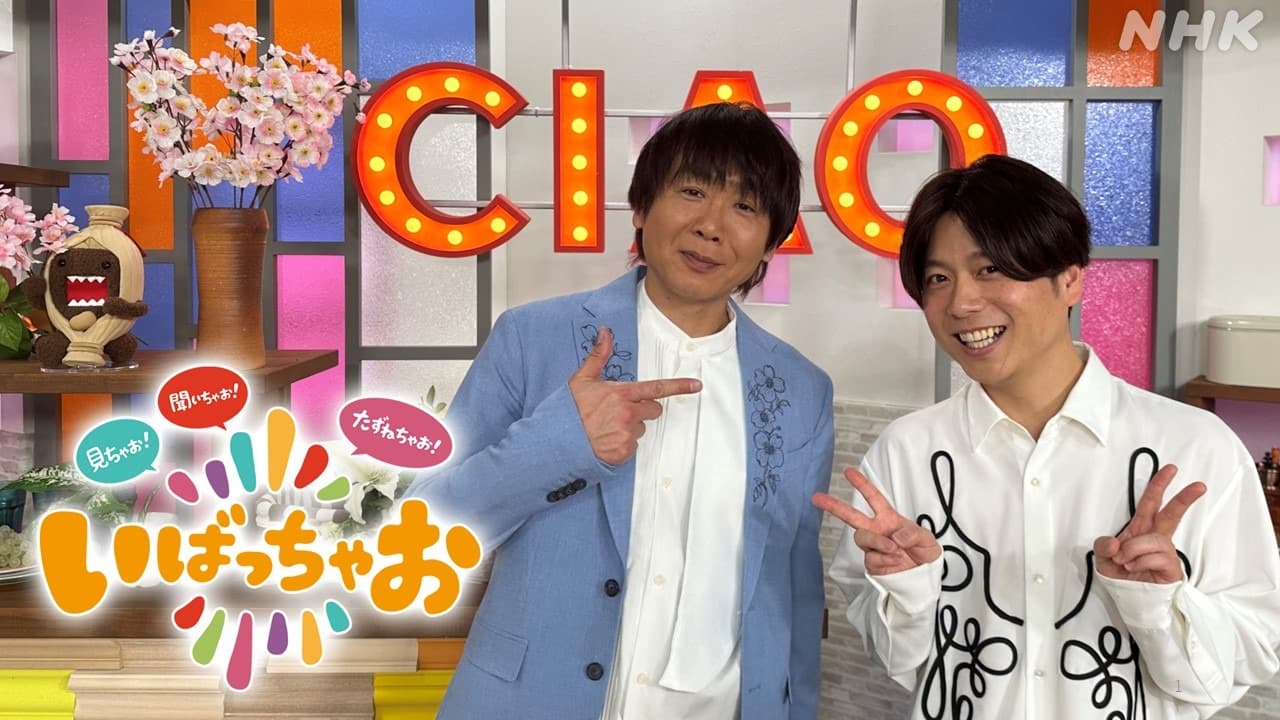X(旧ツイッター)LINEなどSNSを災害時どう活用?
- 2024年03月09日

東日本大震災で注目されたSNSの力。一方で、デマなどによる課題も見えてきていて、茨城県の研究所や福島県の被災地では、SNSの特徴を生かした活用の動きが進んでいます。私たちが災害時にSNSを活用する時に大切なキーワード「だいふくあまい」とは。
(NHK水戸放送局 記者 小野田明)
NHKプラスで配信 3/14(木) 午後7:00 まで

震災の教訓を踏まえて

ことし2月に水戸市で行われた防災訓練。身の守り方や災害時の対応を確認してもらおうと、東日本大震災をきっかけに11年前から続けています。

この訓練の中で、水戸市が市民に呼びかけて行おうとしているのは、旧ツイッターの「X」を使った被害情報の収集です。被害にあったり、見たりした場合は「#水戸一丸」をつけて、情報を投稿してほしいと呼びかけています。

(水戸市防災・危機管理課 鬼澤英一課長)
SNSは東日本大震災以降だいぶ普及していて、被害情報を集めるツールとしても活用しています。救助要請が(旧)ツイッターにあがり、それに基いて救助できたということがありました。

水戸市内を流れる那珂川が氾濫した、2019年の台風19号。当時のツイッターの投稿をきっかけに、取り残されていた住民が救助されたケースもありました。一方で、この災害では、課題も明らかになったといいます。

(水戸市防災・危機管理課 鬼澤英一課長インタ)
救助が終わったあとでもツイートが残っているので、それを見た市民の方が多数電話をかけてきて、その電話応対に追われたというような課題がありました。
SNSへの注目と課題

SNSの活用が大きく注目されたのが東日本大震災でした。それから13年。飛躍的に普及したSNSをめぐっては、救助などに役立つだけでなく、その課題も見えてきています。

つくば市にある防災科学技術研究所の臼田裕一郎さんです。能登半島地震では、石川県の災害対策本部で情報集約の支援にあたりました。
(防災科学技術研究所 総合防災情報センター
臼田裕一郎センター長)
公式な報告情報があがってくるにはどうしても時間がかかるので、SNS等で現地の写真があがってきたり被害情報がみえてくると、本当に推定のとおりにひどい状況だとか確認できるとういうことで、そういう使い方はしています。

能登半島地震では、真偽不明や誤りの情報が拡散され、偽の投稿をみた人の通報で、消防が出動したケースもありました。臼田さんによりますと、発災直後、石川県の災害対策本部では、SNSはあくまで参考情報にとどめていたといいます。そのうえで。

発信された情報が本当にそのとおりなんだとうのみにせず、本当にそうなんだろうかと落ち着いてみる姿勢と、特に公式情報をしっかりみて、比べながら見ていくことがいちばん重要なんじゃないかと思います。
災害時の活用にむけて
どうすればSNSを災害時に活用できるのか。臼田さんたちが、LINEを使って研究開発してきたシステムがあります。


Xのような一方向的な発信を集約するというやり方だけではなく、SNSの良さである双方向のやりとりを生かした情報集約です。

XのようなSNSは、世界中から不特定多数の人が一方的に投稿していて、匿名性もあることから、嘘やデマが混じることがあります。これに対し、臼田さんたちのシステムは、自治体単位などで、あらかじめ利用者を登録して運用します。さらに、一方的な投稿ではなく、双方のやりとりを行って、より正確な情報を得ようという仕組みです。
システム導入 福島県南相馬市

福島県南相馬市では、東日本大震災を教訓にSNSの情報収集を強化しようと、4年前からこのシステムを活用しています。
システムでは住民から情報が寄せられるとAIが自動で返信。やりとりを行い、対話によってより具体的な情報を引き出していきます。

2023年9月 記録的大雨でも活用
2023年9月の記録的な大雨では、市民から120件の被害情報などが寄せられ、避難指示などに活用しました。偽の情報はなく、被害状況の迅速な把握や、職員の負担軽減にもつながっているといいます。


(南相馬市危機管理課 山本陽副主査)
エリアごとに、どういった事象なのかということが事細かにわかるので、有益かなと思います。友達登録してもらった人だけが利用できるといったところで、デマを投稿する人があまりいないところの特徴なのかなと思います。

システムの登録者は、現在約6000人。南相馬市ではさらに増やしていきたいとしています。
(南相馬市危機管理課 山本陽副主査)
市の総合防災訓練でも、みなさんに「こういったものがある」「こういったことを投稿してほしい」と周知しています。市民の方にご協力いただいて情報提供いただくのは、重要な情報源だと考えています。
専門家「時代に合わせた対応を」
東日本大震災から13年。大きく変わったSNSをめぐる環境。防災科学技術研究所の臼田さんは「時代時代に合わせた対応」が重要だと指摘しています。

(防災科学技術研究所 総合防災情報センター
臼田裕一郎センター長)
SNS自体も時代によってどんどん変わっていきますし、情報の使い方とか向き合い方、あるいはスマホだって10年前は全然つかわれなかったような仕組みでした。それがいまでは誰もが使うような仕組みになっていますので、どんどん状況は変わっていく。その変化に合わせて研究開発も、情報を使う側も変わっていかなければいけないと思っています。
SNS活用のキーワード「だいふくあまい」

臼田さんによりますと、SNSで悪意を持って発信された偽の情報を見た人が、善意で拡散してしまうケースが多くあるということです。そのため、情報を見たり発信したりする時は「だいふくあまい」のキーワードが大切だとしています。
情報収集のときは「だいふく」

SNSを見るとき、情報収集するときのキーワードが「だいふく」です。
「だ」は誰が発信したのか。「い」はいつ発信された情報なのか。過去の情報ではないか注意が必要です。「ふく」は複数の情報を確認するということです。1つの情報では真偽が分からないこともあるためほかに似たような情報がないか確認が大切です。
情報発信のときは「あまい」

自分が情報を発信する場合のキーワードは「あまい」です。
「あ」は、まずは自分の「安全を確認」することが必要です。「ま」は、発信する際に「間違った情報にならないか」と考えること。「い」は、それがどこで起きているのか「位置情報」を伝えることです。救助などにつなげる場合にも必要になってきます。
みじかなSNSだからこそ、その活用方法が重要になっています。