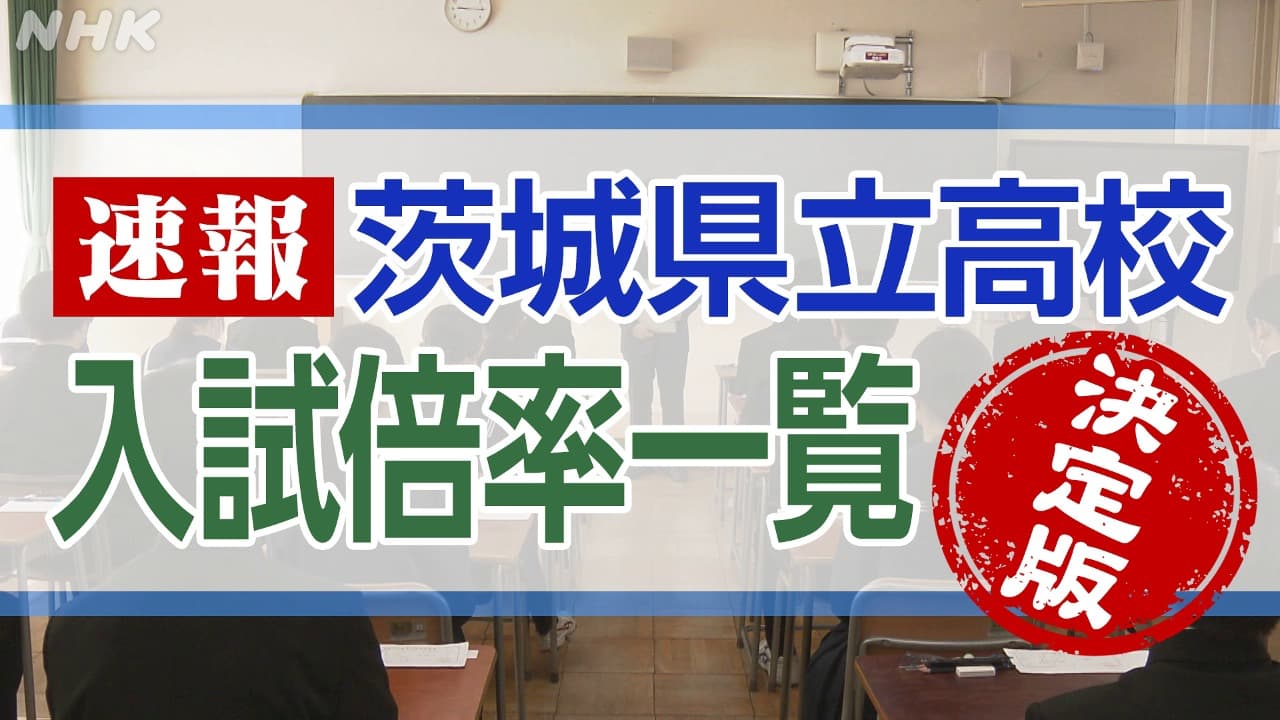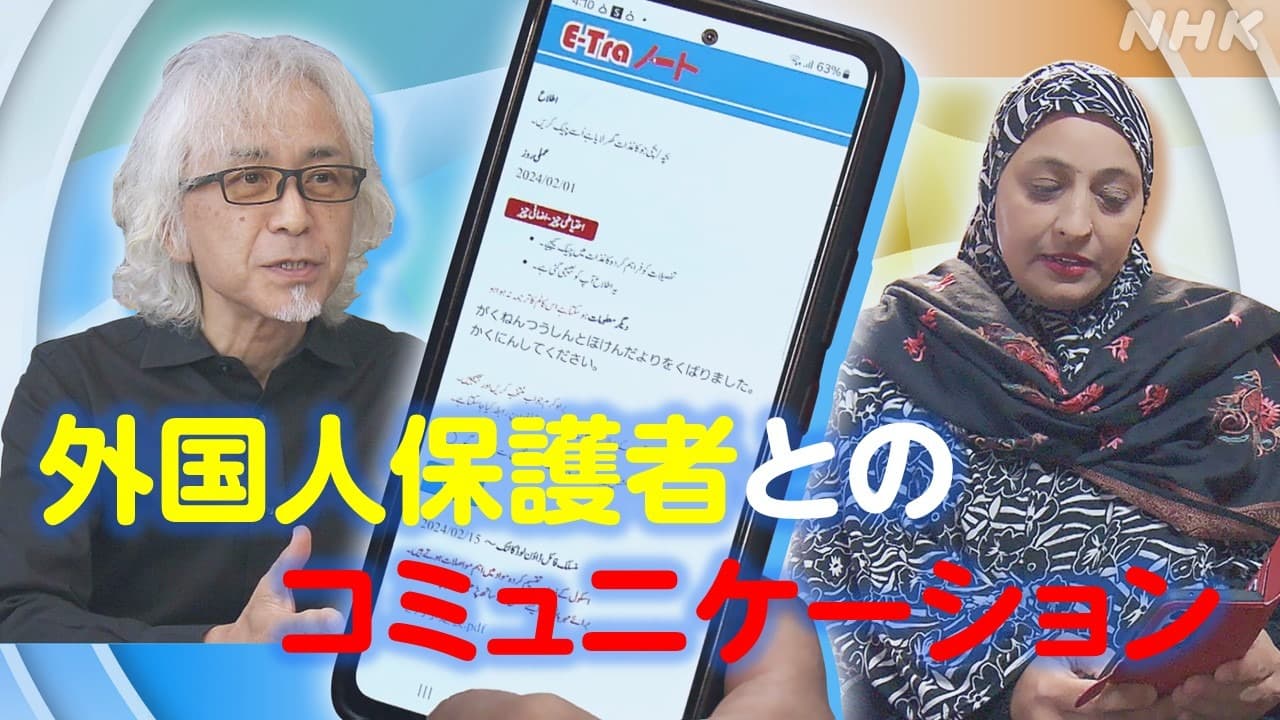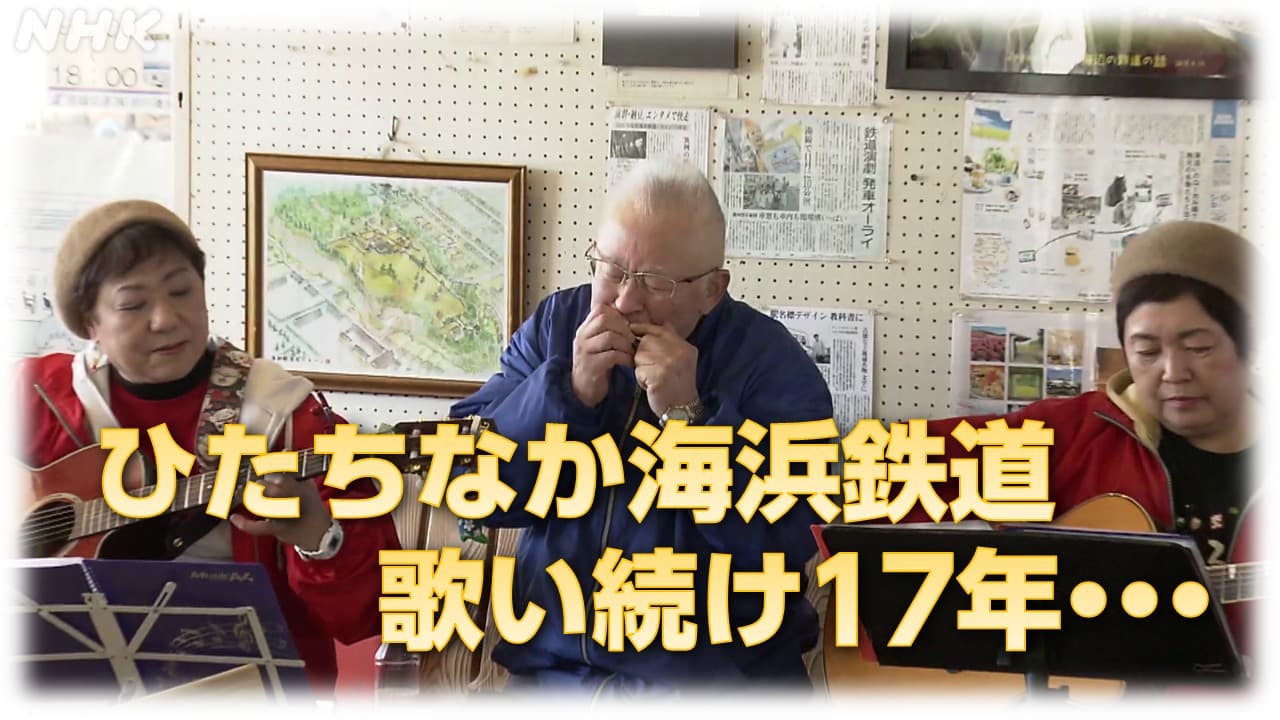水戸の室内管弦楽団などで親交 ホルン奏者が語る小澤征爾さん
- 2024年02月11日

小澤征爾さんが総監督を務めていた水戸室内管弦楽団の楽団員代表で、ホルン奏者の猶井正幸さん(73)。NHKのインタビューに応じ、40年来の親交を通じて知る小澤征爾さんの指揮者としてのすごさ、そして人柄について語りました。
(NHK水戸放送局 記者 清水嘉寛)
小澤征爾さんは2月6日に都内の自宅で亡くなり、9日夜に広く伝えられました。インタビューは10日に行いました。
猶井正幸さんは小澤さんと40年来の親交があり、小澤さんの死去の知らせを受け、9日午前に、小澤さんの自宅で対面したということです。

(猶井正幸さん ホルン奏者・水戸室内管弦楽団 楽団員代表)
やっぱりぽっかり穴があいたというか。そういう覚悟と言うのは変ですが、小澤さんが指揮をなさる回数がだんだん減ってきて、これからどうなっていくんだろうなっていう不安が僕たちにはありまして。きのう小澤さんの亡くなられたお顔を見て、なんていうのかな、こういうときが来たんだっていう、本当にぽっかり穴が空いた感じで。
すごく安らかにいかれたようで、お顔を見ていてもすごく穏やかな顔で、すごくきれいなお顔でした。
本当に涙が止まらなくて、最後のお別れですから小澤さんに誓うような感じで、「あとは任せてください」と心の中で言いました。
すごくショックだったんですけれども、小澤さんが一番望んでいるのは、「これから君たちに託したぞ」っていう、そういうメッセージがすごくたくさん感じられました。それは僕たちメンバーが、みんなそれを共有していることだと思うので、そこは小澤さんの一番の願いだった大きなことを僕たちがつないでいくという、そういう決心をきのう本当にしたところです。
忘れられない「初めての音合わせ」
小澤さんとの出会いは1984年に、小澤さんが師事した音楽家の故・齋藤秀雄さんをしのんだメモリアルコンサートを開いたことがきっかけでした。
特別に編成されたオーケストラには、小澤さんらの呼びかけに応えた世界中で活躍する齋藤さんの門下生が集まり、今の「サイトウ・キネン・オーケストラ」の母体となりました。
猶井さんはメンバーで初めての音合わせをした時のことを「あの日は忘れられない」といいます。
当時、僕はドイツのボンのオーケストラでやっていて。電話をもらったか何かで、すごく驚いて「そうか、そういうことができるんだ」と、わくわくして日本に帰ったのを覚えています。それが1984年のメモリアルコンサート。それが一番最初です、小澤さんとは。
初めての音合わせは、本当に忘れないです。小澤さんもすごく高揚されていて、もうすごくエネルギッシュだったのを覚えているんですよね。それまで小澤さんと一緒にやったことがないからわからなかったんですけど、すごい迫力に圧倒されたのを覚えています。
そうしたらみんな負けじと音を出すんで。当時、桐朋学園の教室がありまして、そこで初めてリハーサルをしたんですれど、その教室もそんなに大きいものじゃなかったんで、フルオーケストラが入ってみんながガンガンひくんで、もう壊れそうなくらい。
その後で、堀さん(堀伝さん バイオリニスト・水戸室内管弦楽団楽団長)から聞いたんですけど、小澤さんが「これ、もしかしてやっていけるな」「ちょっとやっていこうよ」って言っていたという話があったらしいんです。
その後、猶井さんも参加した「サイトウ・キネン・オーケストラ」はヨーロッパのツアーも行って絶賛されました。
小澤さんが「これは実験の場だ」と最初におっしゃって。「斎藤先生から習ったことが本場でどれだけ通用するのか、それを見てみたい」って言って。それが最初のツアーで証明された。いろんな新聞の記事ですごい批評をもらって、それでみんな自信をつけた。
あれだけの演奏をすれば高い評価を受けるだろうと思っていたけれども、やっぱりアジアからきた人間ばかりで、ブラームスとかそんな音楽がどんな音をするんだろうと、たぶんみんな興味本位で来たと思うんですけれども。だけどやっぱりそこで、小澤さんと僕たちが音を出して、ヨーロッパの人たちにも音楽を共感することができたという。そういうことがすごい自信につながったんだと思う。
小澤さん自身は当然すでに世界に認められていたんですが、小澤さんも「かつてヨーロッパなど海外でやるとき、最初は認められなかった」っておっしゃっていましたね。だけどそれから実績を積んで、評価を得た。その小澤さんに僕たちは乗っけてもらったっていう意識がすごくあります。小澤さんがいなかったらそういうことは絶対経験できなかったし、だからそういう意味ではすごく感謝しています。

指揮者としての「すごさ」とは
小澤さんの指揮者としてのすごさはどこにあるのか。猶井さんは、「普通の指揮者や指導者とはまったく違う」と話しました。

小澤さんの音楽の姿勢としては、全然変わらない、大人であろうが子どもであろうが接し方はみんな同じ。少し言葉づかいはかわるかもしれませんが。小澤さんは、「みんなと音楽をつくろう」というところですから。
普通の指揮者というのは、自分の音楽をみんなに伝えて「こうしてくれ」「ああしたいんだ」、それで一つの音楽をつくる指揮者が多い。小澤さんの音楽の作り方は、音符があったら「音符の裏には何かメッセージがある」と。そのメッセージっていうのは、人それぞれ受け入れ方が違う。それを小澤さんはすごく思っていらっしゃる。例えばフレーズの意味というのを表現したいとき、小澤さんは、全てにキャラクターがある。キャラクターというのはすごく大事で、「キャラクターをみんなで意識しよう」と、そういうリハーサルの仕方ですよね。
だからそこには小澤さんの腕の持っていきかた、間のタイミング。それは演奏家でないと、音を出していなきゃ感じないであろうというような時間が流れていく。
(猶井さんが、指揮の振りをしながら)小澤さんはこうやっても、なんかここに抵抗があるんですよ、摩擦っていうのが。だから音にもそういうキャラクターが生まれてくるんですよ。それがみんなすごく心地よくて。小澤さんの指揮でやりたいっていう演奏家は世界中にごまんといるというのは、そこですよ。空気に抵抗を感じるような。点がはっきりするけど、点だけの指揮ではない。そんなことは、誰もできない。まねする人はいるけどそれは無理。小澤さんだけですね。
“目を見なかったら当てられるわよ”
小澤さんと演奏家が「目を合わせる」ことをめぐるエピソードも話してくれました。
僕は実は臆病者で、小澤さんの目を見るのが怖くて。小澤さんは必ずアイコンタクトをするんです。そのために全部楽譜を覚えて、暗譜で振っていらっしゃる。「そうでないと音楽できないだろう?」という小澤さんの持論なんです。
僕は普通の指揮者とやっていましたから、「えっ」て思いました。小澤さんと目が合わなかったらよく捕まるんですよ。そこで、小澤さんに「きみ、こうしたらいいんじゃないかな」と言われる。「こうしなさい」とは言わないんです、いつも提案みたいな形で。
よく当たるから、「俺やばいな、来年からないな」と思っていたら、新日(新日本フィルハーモニー交響楽団)のビオラ奏者から「小澤さんは、目を見ていなかったら当てられるわよ」と言われて。それで僕はそこから小澤さんの目を見るようになって。その目を見ることでメンバーも小澤さんもどれだけ近づいていくのかっていうことを実感した。「これがオーケストラか」っていう。

小澤さんはそれを絶対に説明なさらない。だから目を見るまで見ます、小澤さんは。そういう流れもあって、小澤さんに「こういうものだよ」と教わるのは、口では理論立てて言わないんですけど、肌で僕たちに感じさせてくれる。これが本当の教える、影響を与えてくれるというもの。
影響を与えるというのは、共感をつくろうとする空間のなかで、共有しようという姿勢。高圧的じゃなくて、いつも「だよね?」と。表情とか、小澤さんの人となりが全部混ざりあって、音楽の音符の裏側のことまで、僕たちに見てもらおうとするんです。僕たちもおのずと小澤さんの世界に入っていくというか、「こんな世界があるんだ」っていうのを何回も経験しましたね。
僕はいま(桐朋学園大学の特任教授として学生に)教えていますけど、教えるってそういうことなんだと小澤さんから教わって、普通の先生の教え方は、僕はあまりしていないつもりで、「こういうことがあるよ」「オケのなかではこういうことがあるよ」と。そういう、教えてもらったことがエネルギーになっています。
水戸でともに
1990年には水戸芸術館の開館とともに専属楽団である「水戸室内管弦楽団」が創設され小澤さんが音楽顧問に就任します。
その後、小澤さんは水戸室内管弦楽団の総監督になり、猶井さんは楽団員代表という立場で交流は続きました。

吉田秀和先生(音楽評論家・水戸芸術館初代館長)がいらっしゃって、「水戸にこういうものを作りたい」と。当時の水戸室内管弦楽団は「サイトウ・キネン・オーケストラ」のコアなメンバーです。小澤さんと一緒に音楽を学んできた人とか、同年代の方たちが多くて、小澤さんとやりたいという人たちが集まって、今のスタイルがあるんです。
小澤さんにとって、チェンバーオーケストラ(水戸室内管弦楽団のような小編成の室内オーケストラ)というのは、ビッグオーケストラの基本というか、縮図というか。小澤さんがいつもおっしゃっていたのは「カルテットが基本だ」と。弦楽四重奏が一つの基本で、そこでみんなが音楽のやりとりをやるうちに、ひとつの音楽にまとめていく。だからビッグオーケストラでも、カルテットでも同じなんだと。そういう気持ちを共感しながらやっている。
カルテットからチェンバーオーケストラにいく、すごく濃縮された音楽をつくる現場を小澤さんは望んでいらして、小澤さんもそういうオーケストラがあって、すごく幸せだったと思います。
普通の人以上に普通の人
水戸でも、公演のあとに楽団のメンバーと居酒屋でリラックスした表情を見せるなど、親しみやすいエピソードの多い小澤さん。猶井さんも、その人柄についてこう話しました。
オンオフがあんなにすごい人はいないと、それは昔からみんなが言っていたんですけれども、本当にオフのときは、普通の人以上にですね、普通の人なんですよね。着るものも別に、まあ、小澤さんが着ればどんな格好したって格好良いなあと僕ら思っていたのだけども、着流しでですね、興味があるところだったら1人でどこにも行っちゃうし、そこで店の人と話したりとかね、マエストロがそんなこと、という。
電車なんかも普通に乗るから、「小澤さんですよね」と話しかけられて「はい」と気さくに話しちゃうんですよね。電車のなかで「小澤さん、小さいころに、(子どもたちのためのコンサートで)ベートーベンの運命を聞いたんですよ」と言われて、小澤さんもそのことを喜んで話していました。
だから、小澤さんに影響をすごく濃く受けた人もいるし、ほんの瞬間の人もいるかもしれないけど、そのすそ野を考えればとてつもない人たちに影響を与えていますよね。
病をおして
食道がんや持病の腰痛などで活動を休止することがあった小澤さん。晩年は水戸市で指揮台に立つ回数は減っていきましたが、楽団でのリハーサルで指揮を執った際にも、時間を忘れて没頭し、周囲を心配させたほどだったといいます。
最初は時計がなかったんですよ、水戸の(リハーサル室の)小澤さんから見えるところには。そこで、おそるおそるみんなで「そろそろ、小澤さん」と声をかけて。
スタンドが付いた大きな時計を置くようになって、あるとき、「20分でピリオド、区切りを付けましょう」と。20分リハーサルしたら20分休む、というのが続いたんですが、それでも小澤さんは時計が目に入らないですね。何回か振り切ってやったことはありました。そういうものなんですね。音楽って。そこに没頭しているときに時間だからとやめられない、ジレンマはぼくらが想像する以上に大きかったと思う。
本人にしかわからないので、(病の)きつさや苦しさは。体のコンディション以上に、自分のキャパシティーを超える音楽の精神、欲求があったわけですから。だからそこで小澤さんの苦しみは倍増していると思う、僕たちが思っている以上に。
何度も熱があっても振り切ったり。演奏会が終わったら入院されたり。本当に気持ちのほうが先にいく。それだけの情熱があるからこそ、小澤さんは病気の状態でもあれだけの演奏をされたと思うんですよね。だからすごく無理をされたんだろうなと。

小澤さんに伝えたいことばとは
猶井さんは、「小澤征爾さんの遺志を継いでいく」と話しました。
僕たちが小澤さんからもらったいろんなこと、メッセージを仲間同士がみんなが共有していますから。それを若い人たちにいかに伝えるかが課題だと思っています。いまの(水戸室内管弦楽団の)メンバーは、小澤さんはここ何年か、指揮する回数は減っていた。だけど、小澤さんがつくったオーケストラの音がしているわけです。どんな指揮者が来たって、小澤さんからしみこんだものはみんなが持っていますから、それは安心してやっていけるんですけれども。
だけど、未来永劫そういうものを続けていきたいという小澤さんの遺志を継いでいくつもりなので、いかに若い人たちに伝えていくか。僕らはそれを経験させてもらってすごく良い思いをさせてもらったので、若い人たちも経験してもらいたい。
ひたむきに音楽と向き合い続けた小澤さんにいま、伝えたいことばとは。
猶井さんは、インタビューをこう締めくくりました。
もう一言です。ありがとうございました。本当にそれだけです。僕は73歳ですけれども、人生の半ばごろに小澤さんと巡り会って、小澤さんと僕たちが一緒に音楽ができたことで、自分の人生が変わっていったと思いますし、みんなそうだと思います、メンバーも。
ありがとうございました、という気持ち一つです。