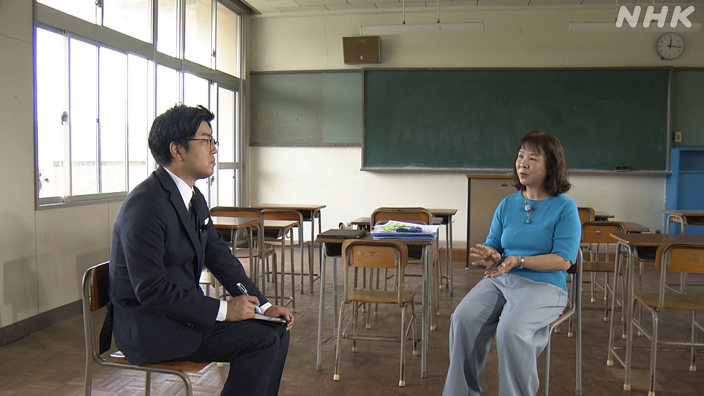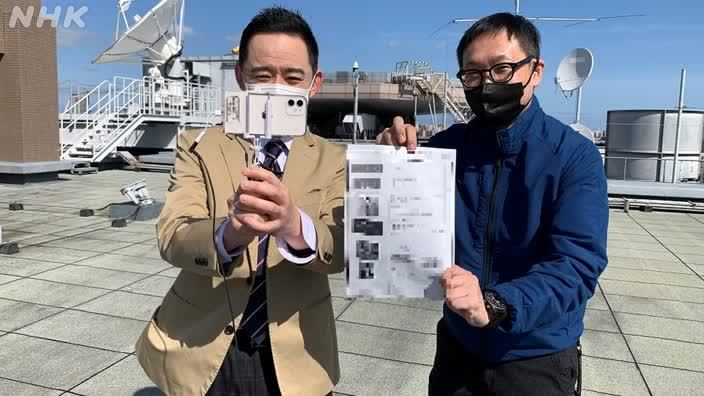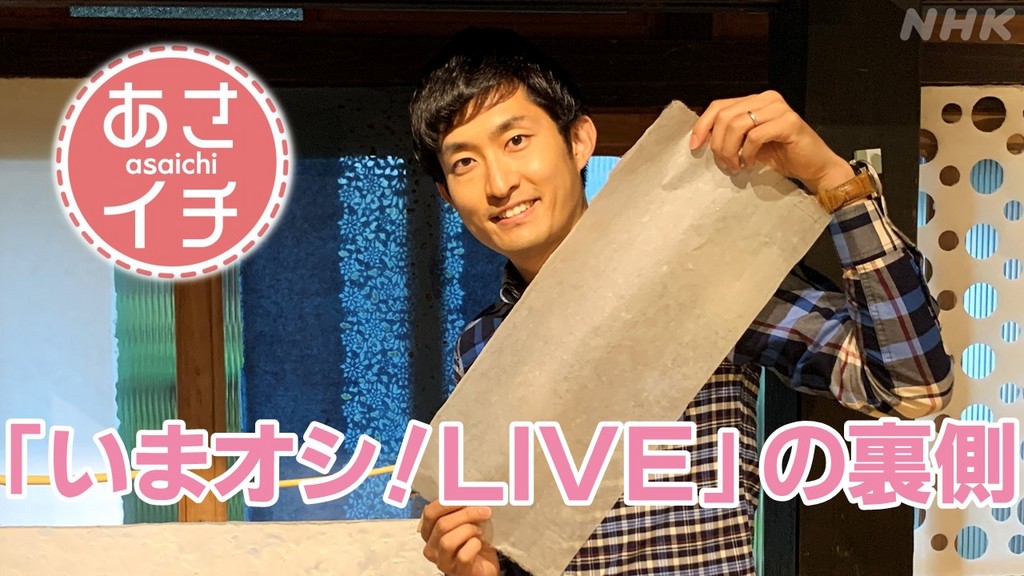問題のある一部の教員が引き起こすこと?
子どもが怒られ慣れていないから?
決して、そうではないといいます。
今回の「ザ・ライフ」で考えるのは、
大声で長時間叱責するといった
教員の行き過ぎた指導によって、
子どもが自ら命を絶つ“指導死”。
指導を受けた直後に、
命を絶ってしまうケースもあります。
私もひとりの保護者。
朝、ふだんと変わりなく送り出した子どもを
突然失う悲しみ、衝撃を考えると
言葉もありません。
そして、なぜこうしたことが起きるのか、
そして繰り返されるのか。
子どもを守るために、何が出来るのでしょうか。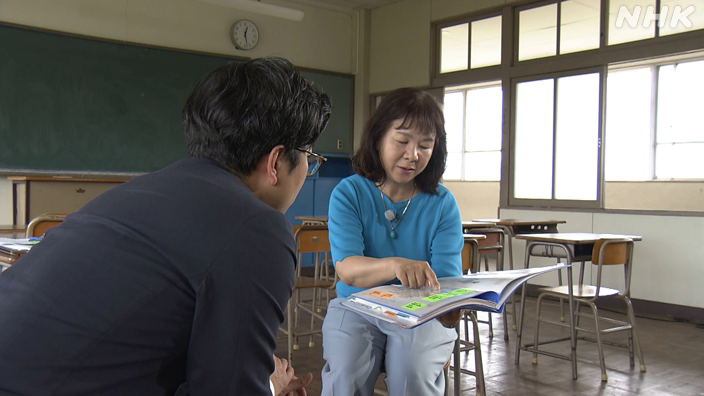
教育評論家の武田さち子さんに、話を聞きました。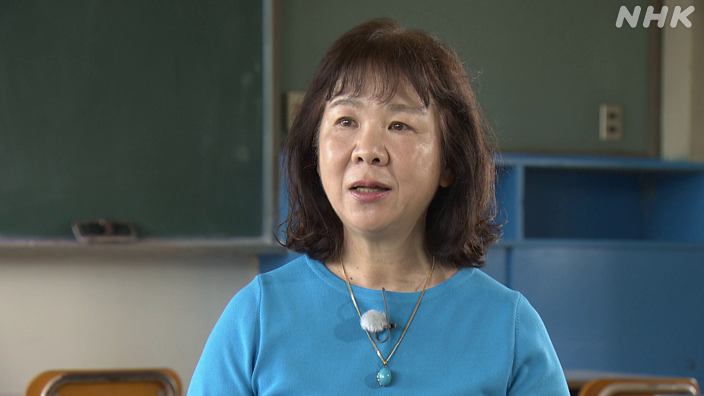
武田さち子さん
「指導死が起きたあと調べると、たくさんの子どもたちが(指導死を引き起こした)教員の言動で傷ついて、転校したり、不登校になっていたりする。その段階で周りが、指導の問題、言動のあり方の問題に気がついていたら、指導死にまで至らなかったのではないか」
子どもが宿題を忘れた場合など教育の現場として、
“指導”はもちろん必要だという武田さん。
しかし、それが“不適切な指導”になっていたときでも、
教員同士で指摘しあえるような風土や余裕が、
学校現場にないことが課題だといいます。
「先生たちの心にある程度、余裕がないと不適切な指導はなくならない。ほかの先生とも交流できる環境を整えるべき」
番組では、かつて不適切な指導で
追い込まれてしまった男性にも取材。
子どもたちの心理状態についても考えます。
多様な子ども、多様な教員がいることで、
多くを学び、成長できるはずの教育現場。
子どもが苦しむことはあってはなりません。
今何が求められるのか、ぜひ一緒に考えてください。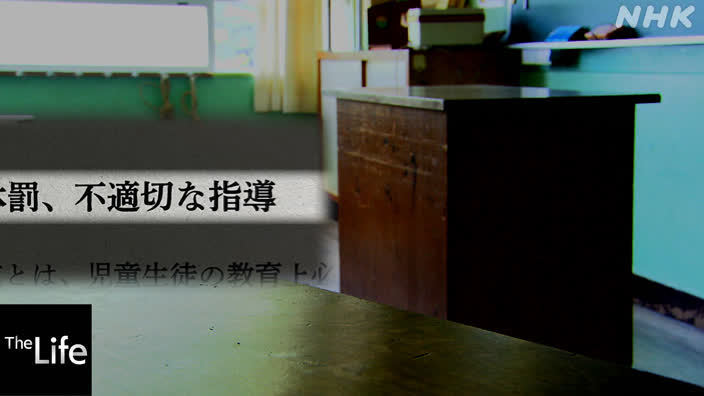
番組詳細はこちら⇒ https://www.nhk.jp/p/ts/9RZY9ZG1Q1/episode/te/DJ483Y7RGZ/
ザ・ライフ
「調査報告 指導死 子どもの命を守るために」
7/21(金) 午後7:30~
NHK+でも配信します。