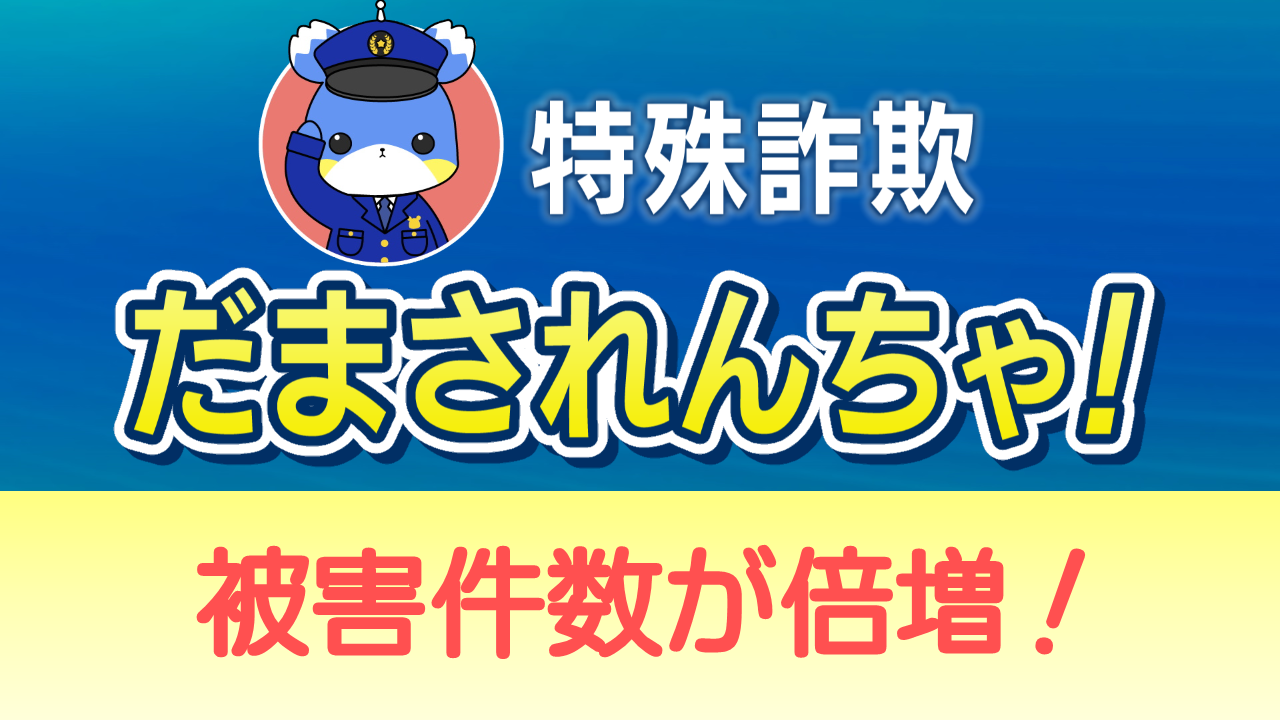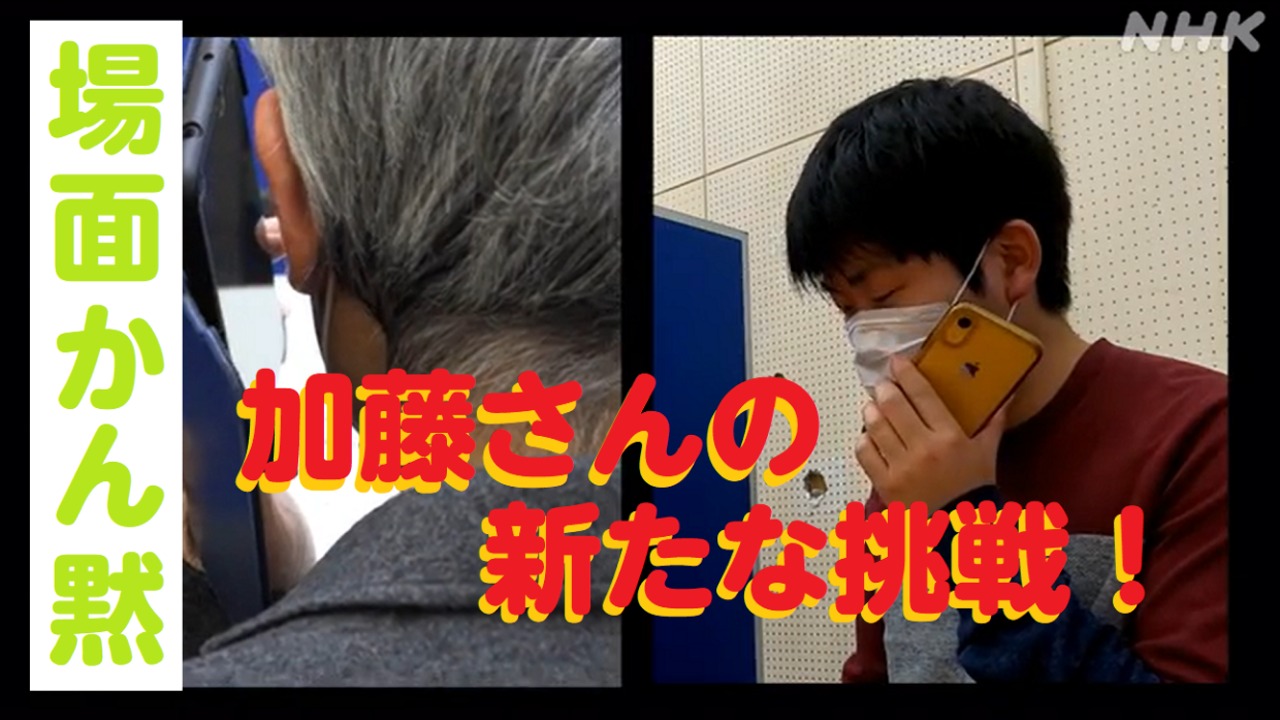鎮火に時間かかるのはなぜ?富山は火事が少ない?
- 2023年09月26日

「ニュース富山人」では、視聴者の皆さんの疑問に記者が答える「それ調べます」というコーナーを放送しています。今回は火事に関する疑問にお答えします。
(記者 吉田紘生)
鎮火に時間かかるのはなぜ?

ニュースでも「何時間後に消し止められた」などとお伝えすることの多い“鎮火”。
消火にあたる現場ではどのように使っているのか、取材に行きました。
本当にもう燃えない?“再燃”のリスク
お話を伺ったのは、富山市消防局の杉野伸次郎さん。消防では、火が完全に消えたのを確認できてから“鎮火”と発表していますが、その確認に時間がかかるといいます。

杉野さんが指摘したのは、“再燃”のリスク。
特に、布団や衣類などは、水をかけても内側までかかりづらいため、内側に熱がこもり再び燃えてしまうことがあります。
実際に、ことし5月8日の朝に火事があった山形県の住宅では、消火活動が終わったあと、翌日の明け方に再び燃え始めました。地元の消防が調査したところ、火元は布団の残り火で、火が消えているのを隊員が見ていたものの、結果的に確認が不十分だったといいます。この“再燃”を受け、チェックシートを導入するなど、さらにていねいに確認を行っているそうです。
こうした事態を防ぐため、消防では、布団やたんすなどの家財道具を外へ運び出し、必要なものは分解してから、改めて水をかけています。
しかし、分解といっても素手ではできません。
そこで、必要な道具が消防車に積んであります。取材にお邪魔した際に、いくつか見せていただきました。
例えば、鳶口(とびぐち)。先端にかぎ状の部分があります。

このかぎ状の部分で、燃えた布団をかきわけて薄くすることで、内側まで水で浸せるようにするそうです。

もっと力が必要なときは、バールやおのも使うんだそう。想像するだけでも大変そうです。
煙が出なくなれば、再び燃える可能性は限りなく低くなります。
これで基本的には“鎮火”になりますが、それでも万一の事態に備え、しばらくは消防車が待機や巡回を続けています。
ひと言“鎮火”というまでに、これだけの手順がありました。時間がかかるのも納得です。
取材の最後に、わたしたちができることについても聞きました。

もちろん、そもそも火事を起こさないよう注意するのが大前提ですが、杉野さんは、消火活動を早く終えるためには、押し入れなどに余裕を持ってモノを入れることが大事だといいます。
いっぱいにモノを詰め込み、スペースがなくなると、水が奥までかかりにくくなってしまうためです。
私も自分の部屋を確認してみようと思いました。
富山は火事が少ない?
今回いただいた疑問には、こんなことも書いてありました。

富山県に引っ越して1か月の私(記者)には、まだ実感はありませんでしたが、こちらも調べてみました。
なお、ことし(令和5年)火事が多いのかも確認してみましたが、県によると、ことし1~8月の出火件数は123件と平年並み。去年(令和4年)の同じ時期は99件と、なぜかきわめて火事の少ない年だったそうです。
一方、ことしは8月までに火事で16人が亡くなっていて、過去10年で最も多くなっています。
今回の取材では、その理由まではわかりませんでしたが、火事のニュースは多かったかもしれません。
人口あたりの火事は、30年以上全国最少
県が毎年まとめている火災統計によると、出火率(人口1万人あたりの出火件数)の値は、直近の令和3年、全国平均が2.8だったのに対し、富山県は1.6でした。
確かに、かなり少ないようです。
この出火率を都道府県別にみたとき、富山県はどれくらいの位置にあるのか。調べてみると…。

およそ30年にわたり、全国で最も小さい値を記録。
視聴者の方の疑問をきっかけに、富山県の“全国1位”を知ることができました。
なぜ富山は火事が少ない?
その理由についても、県や専門家に取材してみました。すると、
・北陸は雪国で乾燥しにくい
・富山県は持ち家や三世代同居の割合が高いため“自分の家を守る”意識が高い
といった可能性が聞かれました。
ただ、出火率の順位をさかのぼると、記録が残っている昭和26年には33位と、どちらかといえば火事の多い地域だったことがわかります。
およそ30年続く“全国1位”には、ほかの理由もありそうです。
県民が富山を“全国1位”に
この疑問に答えていただいたのは、防火・避難計画に詳しい、兵庫県立大学の室崎(※たつさき)益輝名誉教授。

北陸は雪国で乾燥しにくい一方、山を越えて乾燥した空気が流れ込む「フェーン現象」の影響で、ひとたび火が出ると大規模な火災につながりやすいといいます。そこで、民間の防火組織が増えるなどして、ほかの地域以上に火事が減ったのではないかと指摘していました。
いわば、県民の危機感が富山を“全国1位”に押し上げたというのです。
そんな意識の高さをうかがわせるデータもあります。

建築・都市防火に詳しい東京理科大学の関澤愛教授が、出火率を火事の原因ごとに分けて分析したところ、富山県は全国平均と比べてすべての原因について低いことがわかりました。
その中でも特に低かったのは「調理器具」と「たばこ」。いずれも全国平均の半分以下でした。
関澤教授は、台所の火をつけっぱなしにして目を離す、寝たばこをする、といった不注意によって起きる火事が少ないことから、県民の“火の用心”の意識が高いのではないかとみています。

そして、“全国1位”がおよそ30年続いたことについても、火事の少なさへの県民の誇りが“火の用心”の意識を根付かせているのかもしれない、と話していました。
私も県民の1人として、その意識を受け継いでいきたいと思いました。
疑問があれば「ニュース富山人」まで!
NHK富山放送局では、視聴者の皆さんの疑問や気になることを募集しています。
いただいた疑問は、記者が調べて「ニュース富山人」のコーナー「それ調べます」の中でお答えします。