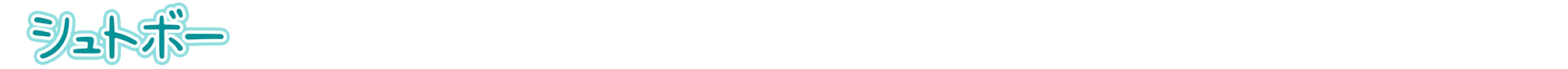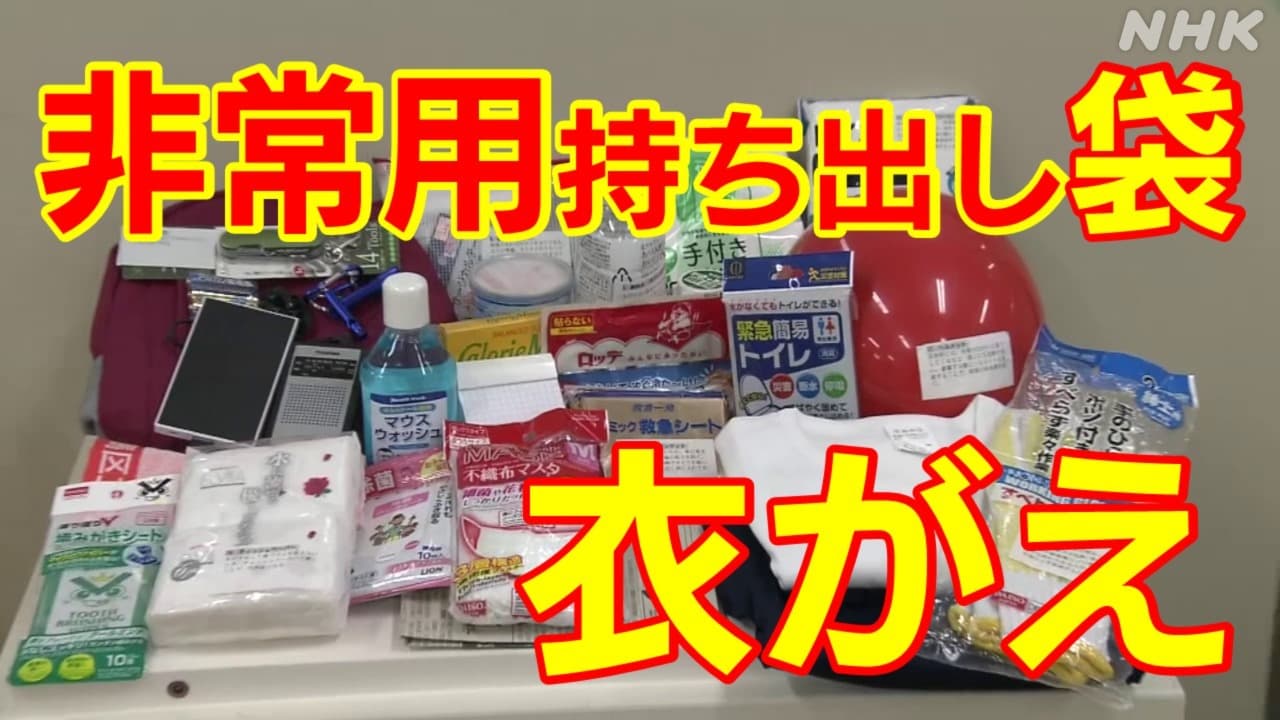命を守るマイ・タイムライン <取り組み編>
- 2020年9月9日

全国で台風や豪雨の被害が相次いでいます。激甚化する自然災害の中でひとりひとりの命を守るためには?
その備えとして、いま注目を集めているのが、「マイ・タイムライン」です。「マイ・タイムライン」とは、台風などが来る数日前から、「いつ」「誰が」「何を」するのか、あらかじめ考えておく、いわば「我が家の防災計画」です。
この取り組みで全国から注目を集める小さな地区があります。
もう逃げ遅れない 地区の決意が生んだマイ・タイムライン
1級河川の鬼怒川が流れる茨城県常総市。
5年前の関東・東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊。常総市では、およそ8000棟が浸水する被害が出ました。


およそ100世帯が暮らす常総市・根新田地区では、地区の9割が床上浸水。
ヘリコプターで救助される住民もいました。
地区の自主防災組織のリーダー・須賀英雄さんは、「避難の呼びかけが繰り返されていたのに、なぜ多くの人が逃げ遅れたのか」と考え続けました。
そこでたどりついたのが、「マイ・タイムライン」でした。「いつ」「誰が」「何を」するのか、あらかじめ決めておけば、より早く避難の行動をとることができます。

根新田地区では1メートル70センチの水位まで冠水した場所も

須賀英雄さん
「避難計画を決めていない中での避難指示が出ても、スムーズに避難できない。マイ・タイムラインは水害の避難行動に関して、貴重なツールだと思っています」
マイ・タイムラインとは
誰ひとり逃げ遅れを生まないために、「マイ・タイムライン」にとりくもう。
根新田地区では、講習会を開催。いまでは地区の7割近くが、「我が家のタイムライン」をつくっています。
川崎真吾さんも、地区の講習会で学び、家族でマイ・タイムラインをつくったひとりです。
川崎家のマイ・タイムラインです。


台風が来る3日前。まず、持ち物の準備を始めます。
2日前。足りないものを買い出し。
1日前。あらかじめ声をかけていた知人の家へ、避難の可能性を伝えます。
去年の台風19号では、これを元にスムーズに避難できました。
家族で取り組むマイ・タイムライン
いま、川崎さん一家は、タイムラインのさらなる改良を考えています。

この日は一家で議論。息子の流生くんからは持ち物についての提案が。
流生くん
「浮き輪も入れたい」
母・由佳さん
「なんで?」
流生くん
「水にぷかぷかって浮かべるように」
川崎家では、1階が浸水するおそれがあるため、2階に家電などを運ぶことにしています。
母・由佳さん
「杏凛の担当は家電だね、覚えておいて」
今回、小学4年生の杏凛さんと2年生の流生くんにも初めて役割を与えることに。実際に運べるか、試してみると・・・。
モニターや炊飯器などの家電を運びあげることができました。


マイ・タイムラインは、家族全員の防災意識を高めることにつながっています。
杏凛さん
「大きいものだったり、荷物をまとめたりするのは手伝えると思います」
川崎真吾さん
「子どもが大きくなると戦力になってくるので、役割も与えられますし、その分、もっとうまく非難できるようになってくるのでは」
マイ・タイムラインで”地域の防災”を考える
さらに今年、近所との助け合いも、マイ・タイムラインに加えることにしました。

2軒隣には、日系ブラジル人の家族が暮らしています。
去年10月の台風19号の際、避難の呼びかけが聞き取れず、困っていたのを知り、声かけをタイムラインに書き加えました。
隣人
「(川崎さんの声かけは)頼もしい」
川崎さん
「防災無線だとわからないんですよね」
隣人
「わかるのは、“防災” と “終わりにします” 。あとはウォーウォー言って全然わからない」

川崎真吾さん
「名前を覚えて、ちょっとでも会話ができるときはしていくと、災害が起こったとき、助け合える仲になっていると思う。そこができていないと、助かる人も助からないことがあると思う」
川崎さんは、マイ・タイムラインを作ることで、家族とともに、地域の防災についても考えるようになったと感じています。