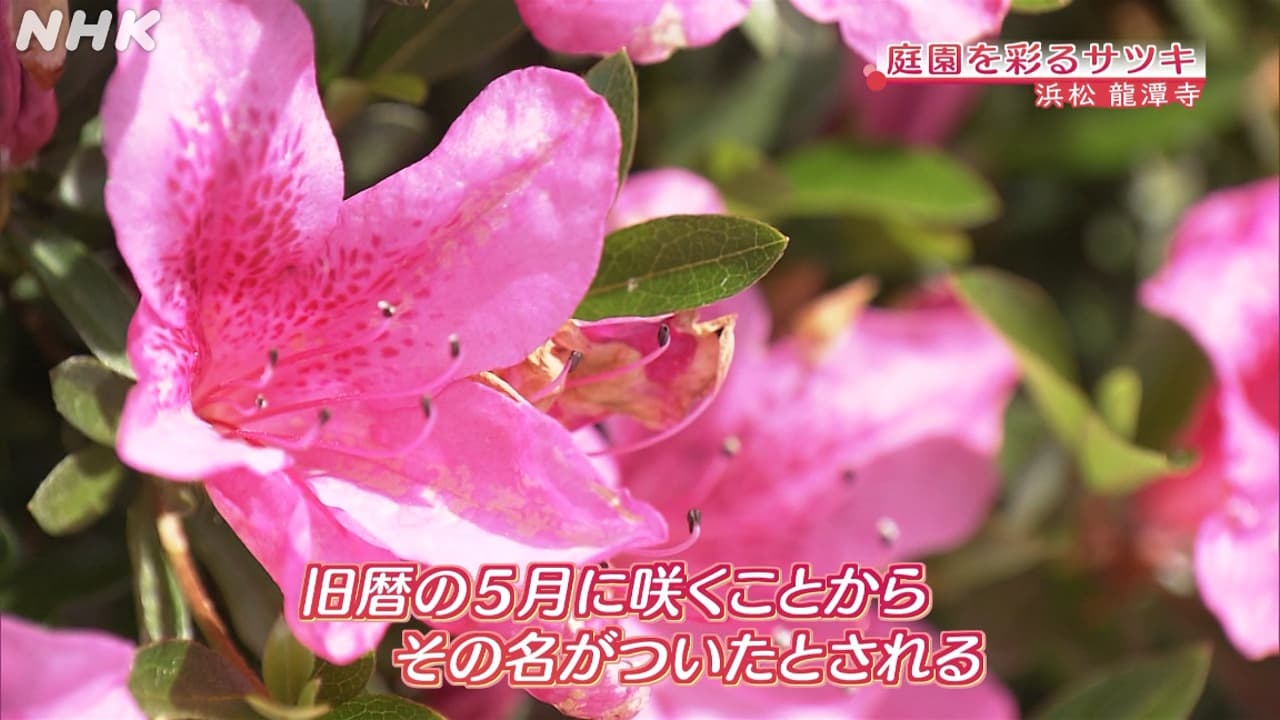多様化!障害がある人たちの就労支援
- 2024年05月17日

障害のある人たちが働く…といえば、どんな仕事を思い浮かべますか。パンやお菓子作りなどが身近なところでしょうか。
では、こんな仕事はイメージできますか?
▼ベトナムの料理に欠かせない香草の栽培
▼新しい食料として期待されるナマズの養殖
▼動画制作をしながらeスポーツの選手をめざす
これらが行われているのはどれも、障害のある人が働く静岡県内の事業所。いま、こうした福祉事業所の仕事の内容が、実に多様化しているんです。
障害の特性は人によってさまざま。数ある事業所の中から、より前向きに働ける仕事を選ぶことができれば、就労のチャンスが大きく広がります。
多様な仕事を取り入れたユニークな事業所で、障害者がいきいきと働く現場を取材しました。
「パクチーファラン」薫る畑で

静岡市駿河区の市街地にある農業用ハウスで、珍しい野菜が栽培されています。高さ15cmほどの
みずみずしい株がみっしり。収穫されるのは、その細長い葉です。

「パクチーファラン」。ベトナム料理に欠かせないという香草です。香りはその名の通り、見た目こそ違いますがまるでパクチーそのもの。麵料理フォーをはじめ、さまざまな料理の付け合わせにしたり、刻み入れたりします。

2022年から栽培が始まったパクチーファラン。冬場を除き週に1~2回、各10kgが浜松市内のベトナム人むけ食材店に出荷されています。品質の良さは県内在住のベトナム人のお墨付き。収穫すればした分だけ買ってもらえるほどの人気だといいます。

収穫作業にあたっているのは、発達障害や知的障害がある人たち。ハウスを運営する福祉事業所に通う利用者です。手作業で1枚1枚丁寧に摘み取っていきます。数人で2~4.5時間ほど作業すると、10㎏入るカゴが葉でいっぱいになります。

この事業所が利用者の仕事として元々手がけてきたのは、食品の容器詰めや縄跳びの組み立てといったいわゆる「内職」。これらに加え、より利用者の働く力を引き出し、給料にあたる工賃の改善にもつながるような新しい仕事を開発しようと考えました。
県内にベトナム人が増え現地の食材の需要が高まっていると聞き、他では作られていない「自社製品」としてパクチーファランの栽培を始めたんです。

「収穫の仕事は気持ち良く、楽しい」
「体を動かす分、内職よりもしっかり働いた感じがする」
利用者の皆さんも、屋内作業だけでなく外出して働く機会ができたことを喜んでいます。仕事の充実感は、自信をつかむきっかけにもつながっているそうです。
こうした、農業分野での活躍によって障害者の社会参画につなげていく取り組みを「農福連携」といいます。
今回訪ねた障害のある人たちが働く事業所は、いずれも「就労継続支援B型」という福祉サービスの形態です。これらの事業所では、一般企業に雇われること・雇用契約を結んで働くことが難しい人に、働いて工賃を稼ぐ機会を提供します。
「B型」は、最も多く利用されている就労支援サービス。利用者数は全国で約34万人(ことし1月)、静岡県では9100人あまりです(令和4年度)。
なぜナマズが福祉の現場に?
「農福」ならぬ水産業と福祉の組み合わせ、いわば「農水連携」の現場が湖西市にあります。

住宅街の古い倉庫を活用し、大きな水槽を設置して作られた養殖場。海や川とはつながっておらず、水をきれいにしながら循環させる陸上養殖です。飼育されているのは…

「ヒレナマズ」という魚。東南アジアなどでは一般的に食べられたり、養殖されたりしているそうです。丈夫で病気になりにくく、ぐんぐん成長します。去年12月から稚魚の飼育を始め、今では30cm以上に育っています。
ナマズの世話や清掃などの仕事にあたっているのは、精神や発達に障害がある人たち。なんとこの養殖場、障害がある人たちが働く福祉事業所として運営されているんです。

養殖場の運営元は、浜松市にある医療法人のグループ。病院経営をはじめ、障害者の就労訓練などを行う福祉事業所を運営しています。福祉事業所の利用者の就労訓練の一環として、このヒレナマズの養殖事業を始めたんです。
利用者の方に、この仕事のやりがいについて聞きました。

ヒレナマズが大きくなっているのを見ると、「自分たちで育てている」という実感がわいて、とてもうれしくなります。達成感があります!
生き物を相手にする仕事ならではのやりがいを口にしていました。利用者の方々は障害の特性上、積極的に働けるときとそうでないときがあるそうです。この養殖場では、ヒレナマズの世話を通じて責任感が芽生え、より安定して働くことができるといいます。

養殖したヒレナマズは泥臭さやクセがなく、特にフライなど油を使う料理と相性抜群。今後さらに大きく育て、運営元の医療法人グループが経営する「給食センター」に出荷する予定です。病院給食の食材として活用するのです。
医療法人の理事長、渡邊実輝宏さんは、この事業の意義についてこう話しています。

渡邊実輝宏さん
利用者の方々の就労訓練の一環として、ヒレナマズの養殖事業はとても魅力的な仕事だと考えています。
障害者を支援しながら、食料自給にもつながれば理想的だと思っています。
「就労継続支援B型」の課題の一つが、利用者の給料にあたる工賃の向上です。「B型」の平均工賃は全国で1万7031円、静岡県では1万6866円(令和4年度)。ともに記録がある中で過去最も高くなっています。ただ静岡県では平均工賃の現状について、経済的自立に向け改善の必要な水準だとして、2万円に引き上げることを当面の目標にしています。
パクチーファランの栽培やヒレナマズの養殖も、導入された大きな目的の1つは「工賃アップ」です。こうしたユニークな事業は、障害のある人が働く機会を広げるためだけでなく、収入を改善するために考えられた手立てでもあるのです。
ビデオゲームを通じて就労支援に!

大好きな趣味を障害者の就労支援につなげる。そんな「B型」の事業所が去年、浜松市にオープンしました。スタイリッシュな内装の居室には液晶モニターがずらり。それを真剣に見つめる利用者。取り組んでいるのは…

ビデオゲーム!なんと、ゲームを競技として行う「eスポーツ選手」として腕を磨いているんです。ここは、ゲームを通じて社会参画をめざす事業所。利用者は主に、自閉症や学習障害などの発達障害や、社交不安症(かつて「対人恐怖症」と呼ばれていました)などの精神障害がある人たちです。通い出すまでは家に引きこもっていた人も多いといいます。

利用者の仕事は、映像を編集して動画を作ること。ゲームと同じパソコンで、1日に50分間の作業を2回行います。
でもなぜ、ゲームが支援につながるのでしょうか?
通い始めて半年ほどの利用者の方に聞いてみました。

先日、所長に誘われて三島市で行われた格闘ゲームの大会に出場しました。緊張したけれど、わくわくの方が大きかった。相手と対戦したり、プロ選手の試合を観戦して盛り上がったり。初めての経験でした。
人が集まる場所にも出ていけるようになるかもしれない、と思いました。
もっと練習して強くなりたい。また出場したいです。
世界中で若者を中心に親しまれているeスポーツ。その人気は、国際オリンピック委員会が将来の大会競技として検討しているほどです。静岡県内でも毎年大会が開催され、プロ選手や愛好者がつどいます。
障害の特性上、意欲や目標を持つことの難しかった人たちが、そのeスポーツを通じて向上心をつかみ、他者と関わることが苦手でも社会に向けて一歩を踏み出そうとしています。ゲームがいわば「コミュニケーションツール」になって、障害者の社会経験につながっているんです。
この事業所は、福祉事業を営む群馬県の企業のフランチャイズ事業として運営されています。仕事の動画制作は、利用者が一から学ぶことができる仕組み。最初は基礎的なスキルを習得するため、簡単な編集作業から始めます。自身がプレーしたゲーム動画など自由な素材を使って編集し、作った動画を投稿サイトにアップすると、事業の「宣伝費」として工賃になります。

習熟してくると、取引先の企業から動画作りの仕事を請け負うことができるようになり、それが自信にも工賃アップにもつながります。映像編集の需要は高く、スキルがあれば自立へのチャンスも広がるといいます。
所長の高林章人さんは、去年8月に事業所が始まってから、ゲームを通じた利用者の変化について驚きを口にします。

不登校児や障害がある子どもたちにけん玉を教えた経験から、支援に関心を持ったそうです

高林章人さん
通い始めたころにはこちらの呼びかけに「はい」と返すくらいだったのに、見違えるように会話ができるようになった方もいます。
ここではeスポーツがいわば共通言語として存在していて、利用者にとっての「居場所」になっています。居場所があることで、時間を守る、仕事中はスマホを触らないなどの規律も芽生え、就労訓練も充実してきています。
「ゲームの力ってすごい」と驚いています。
この事業所ではeスポーツだけでなく、イベントの企画運営を行うコースも用意されています。利用者はビデオゲームの体験イベントを企画し、地域のイベント会場などで実施してきました。立ち寄った人たちに遊び方を教え、喜んでもらうことで手ごたえをつかんでいるといいます。
大好きなゲームを足掛かりにして、他者とふれあい、社会と関わる力につなげていく。ここはそのきっかけ作りをサポートする事業所なんです。
特性に応じて豊かに働くために
多様化する障害者が働く仕事。こうした就労支援の動向について、専門家に聞きました。

増田樹郎学長
入力障害者の就労支援は、従来は「どのように働いてもらうか」という視点から主に行われてきましたが、現在は当事者の「働きたい」という意欲を支援する方向へと見直されてきています。
こう話すのは、社会福祉学が専門の、静岡福祉大学・増田樹郎学長です。支援のあり方が、障害者自身の働く意欲に働きかけるようになる中、事業所で生産される製品(授産製品)にも変化が現れているといいます。

増田樹郎学長
授産製品については、利用者と事業所・企業との連携を通して、社会的な需要につながる商品の開発を検討する動きが続いています。
障害者が趣味の範囲で作れるようなものから品質などを見直し、適正価格の「製品」へ切り替えていくということです。
とはいえ「B型」の事業所にとって、このハードルを高く感じることも少なくありません。「B型」は就労だけに特化して支援しているのではなく、多様な障害特性に対応し、受け入れています。それゆえに市場原理に対して抵抗感もあるのは避けがたいともいえるでしょう。どのように取り組んでいくのか、今後、各事業所の力量が問われていくことになります。
障害がある人たちにとって、仕事の選択肢が増えることは、意欲や能力を発揮できるチャンスにつながります。今回取材した事業所では、新たなやりがいを得ていきいきと過ごす方々の様子が印象的でした。そこから生まれる製品やサービスも多様化し、私たちが消費することで、さらなる生きがいや工賃となって作り手の元にかえっていくようになってほしいと感じました。