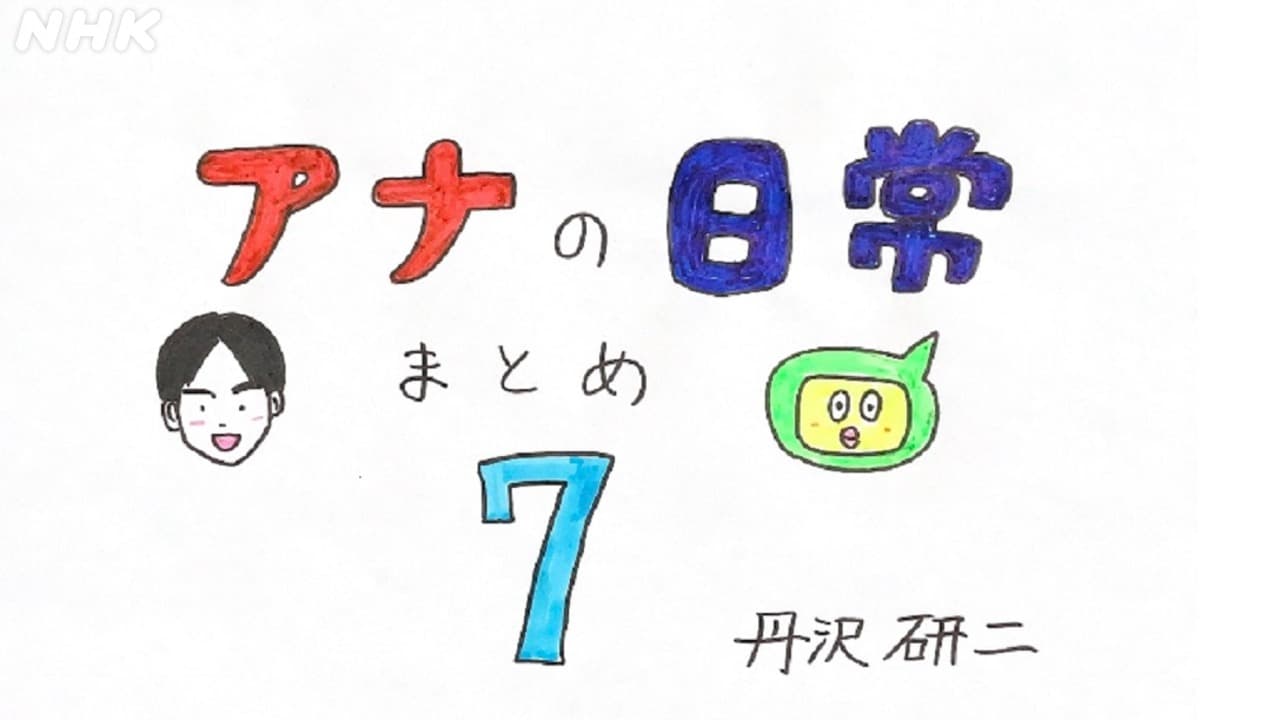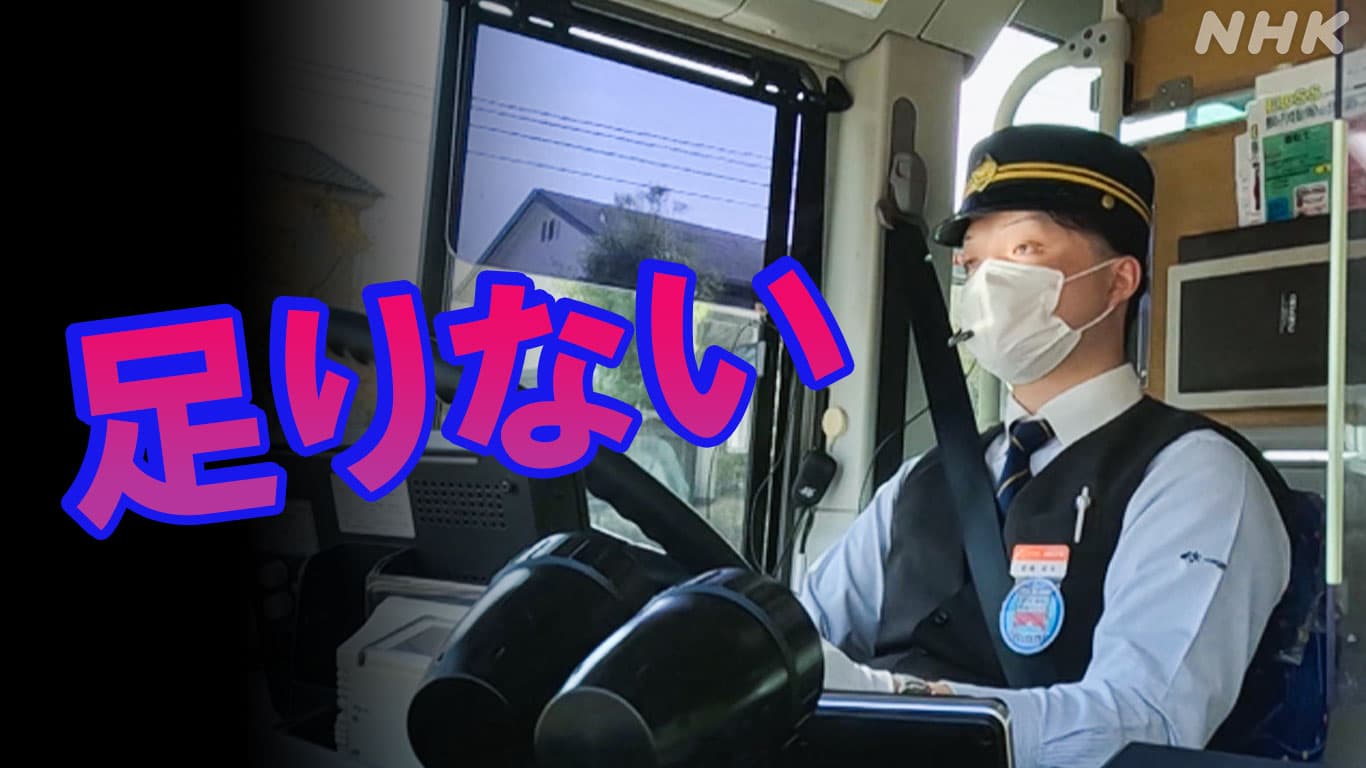被災地からの声 キャスター津田より「福島県 いわき・広野」
- 2024年05月08日

いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回はまず、福島県浜通り地方の南部にあるいわき市の声です。人口およそ32万の都市で、小名浜(おなはま)港など複数の大きな港があり、東北有数の漁業の町として知られています。震災の津波で460人あまりが犠牲になり、半壊以上の住宅やビルなどは5万棟を超えました。2016年に災害公営住宅(16団地・1513戸)の整備が完了し、2019年には被災した沿岸部の5つの地区で土地区画整理事業が完了しましたが、被災後に転居した人も多く、相当数の空き地が生じました。市は宅地利用を促進しようと『空き地バンク』を設立し、登録してある土地を買って家を新築すれば、30万円の補助金が出る制度を始めました。さらに子育て世代には10万円、市外からの移住世帯にも10万円を上乗せし、少しずつですが、被災した沿岸部でも新たな住民が生まれています。
はじめに、9年前に取材した若者を再び訪ねました。自動車工場で働く岡田健哉(おかだ・けんや)さん(28)は、高校生の時に風評被害を払拭するための団体を設立しました。いわきの野菜をPRするため、県外の人を農家に招く企画なども実現し、前回の取材時は働きながら熱心に活動していました。
「いわきの野菜を使って料理するシェフもいますし、たくさんの方にいわきの野菜を好きになっていただいて、実際にいわきに来て、人を知ってもらって、 野菜のおいしさを伝えられればと思います」
あれから9年…。時とともに農家の意欲も高まり、活動は発展的に解消したそうです。岡田さんは今、エンジンの生産に従事し、いわきのモノづくりを世界に発信したいと仕事に取り組んでいます。
「お客さんから喜びの声をいただいた瞬間が何よりも楽しい…当時はもう、ノリに乗っていましたね。生産者さんたちが熱く活動するようになったのが大きくて、もう自分たちがやらなくても…っていうところがありました。以前は僕が与えられる側で、周りの大人たちから本当にいい影響を受けて、いろんなことを学ばせてもらったので、今度は次世代の子どもたちに、いわきのいい大人たちの背中を見せていきたいですし、自分もその1人でありたいと思っています」

次に、『いわき震災伝承みらい館』に行きました。いわき市の津波被害と原発事故の被害に関する様々な物証や記録を展示しています。津波で薄磯(うすいそ)地区の自宅を流された大谷慶一(おおたに・けいいち)さん(75)は、この施設で語り部を務めていて、私たちは9年前にも取材しました。当時はまだ施設がなく、被災地見学ツアーのガイドをしていました。津波が来た際、高齢女性を背負って逃げましたが、自分が助かるのが精一杯で女性を救うことができず、激しく後悔していました。
「毎日、夢を見てうなされていたようで、朝起きると枕はいつもびっしょりでした。語り部をやって自分が背負った重い気持ちを話すことで、少しずつ軽くなるような気がしました。この経験なんか、すっかり忘れたいですよ。でも、忘れることはもう一生できない。繰り返し、繰り返し言うしかないです」
今回、改めて大谷さんに今のお気持ちをうかがうと、こう言いました。
「私は助けられなかったことを、ずっと負い目に感じていますから。これは今でもそうですよ。あのとき見た、あのおばあちゃんの目の色は忘れちゃいけないと思っています。小学生に“いざという時は、あなたのお父さんもお母さんも あなたを助けられないんだよ”と言うと、“自分の命は自分で守る”っていう答えが返ってきますよ。それを本当に理解してもらえるまで、話さなきゃいけない…」
大谷さんは6年前、薄磯地区に自宅を再建しました。現在、薄磯地区の世帯数は215で、震災前から約3割も減りました。しかも地区の半分ぐらいは震災後に新たに引っ越してきた世帯だそうで、大谷さんは磯遊びを企画するなどして新住民に海の魅力を伝え、コミュニティー再生にも取り組むつもりです。
その後、いわき市の山間部にある田人町(たびとまち)にも行きました。東日本大震災ではライフラインにも被害はありませんでしたが、1か月後の2011年4月11日午後5時16分、マグニチュード7の地震が発生し、大規模な土砂崩れで住宅3棟と車1台が土砂に巻き込まれ、10代の女性を含む4人が亡くなりました。この地震では、いわき市以外にも、古殿町(ふるどのまち)と中島村(なかじまむら)で震度6弱を観測しています。震源に近い田人町では、長さ14㎞にわたって最大2.1mの高さの“正断層”が地表に現れ、地表で目視できる“正断層”は国内唯一のため、日本だけでなく海外からも見学者が訪れます。田人町に住む斉藤富士代(さいとう・ふじよ)さん(79)は、4月11日の地震で家が半壊し、修繕して暮らしています。斉藤さんは断層の見学者のために自宅の一角を休憩スペースとして提供し、今年初めて、地元の小中学校でも4月11日の地震の体験談を話したそうです。
「1つの記録に残るような断層だったから、誰が来てもいい、見学や勉強する人とかに来てほしいと思います。断層だけではなくて、子どもにもきちんと地震のことを覚えてもらって、次の人、次の人って伝えていきたいです。離れて暮らす子どもが3人いるので、“山から降りて、こっちで暮らしたら”って言われるけど、“行かないよ”って。ここが一番、私に合っている所だから」

続いて、いわき市の北隣、広野町(ひろのまち)に行きました。町の人口は約4500で、震災では3人が犠牲になり(原発事故の関連死も含めると犠牲者は約50人)、およそ330棟の住宅が半壊以上の被害を受けました。原発事故では、国が立ち入りを規制する避難指示こそ出ませんでしたが、町独自の判断で全町避難し、1年後に解除しました。すでに多くの人が帰還し、人口の9割は実際に町内に住んでいます。避難指示が出た他市町の復興工事や廃炉作業の関係者が暮らす拠点にもなっていて、住民登録がないまま町に暮らす人は1000人を超え、実質的な町内居住者は震災前の人口(5490)とほぼ同じです。
2016年、大手資本のスーパーなど5店舗が入る商業施設『ひろのてらす』がオープンし、JR広野駅東側の再開発で、オフィスビルやホテル、集合住宅(114戸)が建ちました。さらに『広野駅東ニュータウン』の造成工事も完了し、1.8haの住宅用地(47区画)が整備されました。一昨年、文化交流施設『ひろの未来館』がオープンし、除染廃棄物の仮置き場だった場所には産業団地も整備されました。また震災後には、中高一貫教育の『ふたば未来学園』が開校し、新たな特産品として町の振興公社が高級バナナの栽培事業を始めました(2019年から出荷)。
広野町ではまず、10年前に出会った家族を訪ねました。お父さん、お母さん、息子2人に末娘の5人家族で、晴天の下、雪が積もった庭で子どもたちが無邪気に遊んでいました。お父さんは“戻っている人が少ないので寂しいんですけど、一生懸命、前に向かって頑張っていきたいと思います”と言っていました。当時、4歳だった末娘の猪狩茉洋(いがり・まひろ)さん(14)は、現在は町内の中学校に通っています。小学1年生からバレエを続けているそうで、元気に成長していました。
「親には本当に感謝しかないなって思います。町に戻るという判断をしてくれたおかげで、今の習い事もできているし、友達とも楽しく過ごせています。大変だった当時の思いとかを聞いて、いま元気に幸せに過ごしていることが当たり前じゃないんだなって…これは忘れずに大切にしていきたいです。日本で今、自然災害がすごく多いので、そういう仕事…復興とかの仕事にも携われたらいいなっていうのは考えていて、高校と大学、そこで 本当の夢を見つけていけたらなって考えています」

さらに、町在住の画家の男性も訪ねました。キャリアが半世紀を超える鶴田松盛(つるた・まつもり)さん(89)は、34歳の時に転勤で他県から広野に来ました。その頃に油絵を始め、40歳から様々な作品展に出品。これまで多数、入選しています。原発事故後、息子を頼って夫婦で埼玉県に避難し、1年あまり生活しました。その間、30点以上の絵を描いたそうで、空に浮かぶ家屋の絵には、地震や津波が絶対に来ない家が欲しいという思いを込めました。キツネの群れで、1頭だけ他のキツネからいじめられている様子を描いた絵は、埼玉県の駐車場で、福島ナンバーを見て両側の車がとっさに逃げていった思い出がモチーフです。2頭の馬の顔を並べて描いた絵には、妻と2人で避難生活を乗り切ろうという思いを込めました。町が全町避難を解除した後、すぐに自宅に戻りましたが、2年前に妻は他界しました。
「避難は2人きりで無人島に行ったような感覚ですよね。コミュニティーがないから。女房のつらさは見ていられなかったから、広野町に帰ってきたんです。愛さなければよかったと思うくらい、家内の死は本当に苦しかったですね。でも、少しずつ悲しみとか苦しみが薄らいでいくから、残された者は命をつないでいけるんです。3.11も忘れちゃいけないことはあるんだけれども、ずっと背負っていくのは かわいそう。だから、それがだんだん薄らいでいくようにしないといけないですよね」
89歳とは思えない力強い声とはっきりした言葉に、スタッフも思わず姿勢を正しました。
【見逃した方はこちらで】
NHKプラス 東北プレイリストで放送後2週間、配信します。
2024年3月以前の記事はこちらからお読みいただけます。