憲法改正発議は近い?遠い?「緊急事態条項」各党の思惑は

衆議院の憲法審査会で、憲法改正に向けて具体的な条文案の作成に入るかどうかが焦点となっている。対象は「『緊急事態』の際の議員任期の延長」。
憲法改正の発議は近いのか?遠いのか? 各党の思惑を探り、今後の見通しを考える。(政治部 与党・野党取材班)
「緊急事態条項」で集中的に議論
去年7月の参議院選挙の結果、憲法改正に前向きな自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党で、衆議院だけでなく参議院でも、改正の発議に必要な、全体の3分の2の議席を占めることになった国会。

衆議院の憲法審査会では、4党が主導する形で、去年の通常国会から議論が進み、去年1年間の開催回数は過去最多の24回となった。いまの通常国会でもこれまでに9回(5月1日時点)開かれている。
参院選後、4党が集中的に取り上げているのが、大規模な自然災害や戦争などの緊急事態が起きた際の対応を憲法に新たに規定する「緊急事態条項」の創設だ。
「緊急事態条項」の項目として具体的に議論になっているのは、大きく2つ。

1つは、政府による「緊急政令」だ。
国会が開けないような状況に陥った際などに、政府が法律と同じ効力を持つ政令を定めることができるようにするとしている。
もう1つが「議員任期の延長」だ。
国会は開けるものの、選挙の実施が難しい状況が長期化した場合などに、国会議員の任期が切れ、国会の機能が維持出来なくなる事態を避けることが目的とされている。
「議員任期延長」に対する各党のスタンスは
「緊急政令」については憲法改正に前向きな4党の間でも考え方に開きがある。一方で「議員任期の延長」は、衆議院の憲法審査会の議論で、4党が必要だと主張し、「4党の間で大きな意見の相違はない」との認識を示している。
これに対し、立憲民主党は、衆議院側の議論で「今後の議論次第では、憲法の今の規定に、選挙困難事態における議員任期の特例を設ける必要が出てくる可能性もありえる」と発言するなど、今後の対応に含みを持たせている。
一方、共産党は、改憲の議論自体を進めるべきではないという考えを強調している。
維新・国民が条文案を発表

こうしたなか、日本維新の会と国民民主党は、ことし3月、衆議院の無所属議員でつくる会派「有志の会」とともに、「議員任期の延長」について、憲法改正の条文案をまとめ、発表した。
条文案では、
▼広い地域で選挙の実施が70日を超えて困難なことが明らかな場合に、6か月を上限に任期を延長できる(再延長可)、
▼任期延長には、内閣の発議を受けて、衆参両院で出席議員の3分の2以上による議決が必要と定めた。
維新・国民両党は、憲法改正に向けて、衆議院の憲法審査会として具体的な条文案の作成に入るべきだと主張。
各党に、それぞれ条文案を示すよう求めている。
【課題①:小さくない相違】
ただ、このまま「議員任期の延長」で憲法改正の発議に向かっていくのかというと話はそれほど単純ではない。
そこには、大きく3つの課題が存在する。
1つは「議員任期の延長」の具体的な要件について、賛成する4党の間でも考え方に小さくない違いが存在していることだ。
その代表例が、任期延長を決めるにあたっての司法の関与の是非だ。
衆議院の憲法審査会の議論では、維新・国民両党が、政権与党による恣意的な任期延長を防ぐため、裁判所によるチェックが欠かせないと主張しているのに対し、自民・公明両党は、「裁判所が判断するのは難しい」としている。自民党は「任期延長が適切だったかどうかは、後に行われる選挙で国民が判断すべきだ」という立場だ。
また、維新・国民両党が条文案で「出席議員の3分の2以上」としている衆参両院での議決要件についても、自民党は審査会の場で「過半数」を主張している。
憲法改正の発議には、これらの相違点がクリアされなければならない。
【課題②:参議院側の議論】
もうひとつの課題は、衆議院に比べ、参議院側の議論が進んでいないことだ。

参議院議員は任期が6年で、3年ごとに半数が任期満了となるため、任期切れで議員が一斉にいなくなる事態は想定されていない。
このため、憲法では、衆議院が解散され、衆議院議員が1人もいない状態の際、内閣が必要と判断した場合は、参議院の「緊急集会」の開催を求めることができると定められている。「緊急集会」は、終戦のあと、1950年代に2度開かれたことがあり、暫定的な予算や法律が議決されている。
立憲民主党は、緊急事態で選挙の実施が困難となり、衆議院議員が不在になった場合も、この「緊急集会」で対応するのが基本だと主張し、任期延長の議論の前に、まずは「緊急集会」の権能について検討すべきだとしている。
これに対し、自民党などは、「緊急集会」では国会の機能の維持は難しく、緊急事態が長期化する場合も想定して、任期延長が必要だと主張している。
衆議院の憲法審査会は、参議院側でも「緊急集会」について議論を深めてもらう必要があるとしているが、参議院の憲法審査会では、まだ議論が始まったばかりだ。
こうした状況もあって、同じ党内でも衆参の間で「議員任期の延長」に対する考え方に温度差がある党もある。
例えば公明党。
衆議院側では、維新・国民両党のように条文案の作成にまで理解を示す意見がある。
一方で、参議院側は、憲法審査会で「衆議院の任期延長などのため憲法を改正すべきという意見があるが、緊急集会の意義や特徴を振り返ったうえで、丁寧な議論が必要だ」と慎重な立場を示し、他党を驚かせた。
このほか、立憲民主党も、「任期延長」への対応に含みを残している衆議院側に対し、参議院側は、憲法審査会で「議員任期延長のための憲法改正には反対する」と明言。衆議院側とのスタンスの違いが目立っている。
参議院側でも議論が進むとともに、各党内で衆参の間の認識のすり合わせが行われるのかも課題となっているのだ。
【課題③:発議までのプロセス】

最後の課題は、各党が想定している発議までのプロセスにも違いがあることだ。
今後、「議員任期の延長」で改正案をまとめることができたとしても、それだけで発議に踏み切ってもいいとの姿勢を明確にしているのは、国民民主党だけだ。
日本維新の会の幹部は「国会議員の身分に関わる話だけで発議することは避けるべきだ。ワンイシューで国民投票を行うのもコスパが悪く、複数の項目がまとまってから発議すべきだ」としている。
また、自民党も「議員任期の延長」だけでの発議は想定していない。
自民党は、「緊急事態条項」のもうひとつの柱である「緊急政令」とセットで実現することを目指している。
そして、引き続き憲法審査会を安定的に開催するためには、野党第一党の立憲民主党を議論に巻き込んでいきたいとの思惑もあり、現時点で「任期延長」の条文案の作成に入ることには慎重な姿勢を崩していない。
自民党の幹部の1人は「立民を置いていけば、一気呵成に進められるとは思うが、ゴタゴタした状態で国民投票をしても、いい結果は出ないし、国民の間に分断が生じる恐れもある」と指摘する。
このため、自民党は、9条への自衛隊の明記をはじめ、党が目指すその他の改憲項目についても論点の整理を進め、国民世論も含め、憲法改正に向けた機運を醸成していく戦略を描いている。
ただ、公明党は衆議院側でも、「緊急政令」や9条の改正には慎重な意見が強く、自民党としても手探りの状態が続いているのが現状だ。
憲法論議 いま何合目?
「憲法論議がこれまでになく活発になっている」と指摘されているが、各党は現状をどのように捉えているのか。
最後に、衆議院の憲法審査会で議論に加わる各党に聞いてみた。

▼自民党
「いま何合目などとは言いようがない。目安をひとつ作ってしまうと、各党に駆け引きの材料を与えてしまうことになる。いまは、静ひつな議論の場を安定的に作り続けていくことに尽きる」

▼立憲民主党
「『議員任期の延長』だけに論点が偏り、改憲にはほど遠く、山に登り始めてさえもない。条文案を出し合っても、合意形成にはつながらない。改憲の手続きを定めた国民投票法改正の議論が進んでいないのも問題だ」

▼日本維新の会
「いまは2合目ぐらいだ。丁寧に議論することは認めるが、『全会一致でないとダメ』というのはありえない。最後は、民主主義のルールである多数決で決めるべきだ。今後は自民党にもハッパをかけていきたい」

▼公明党
「全体で言えば、まだ2、3合目あたり。衆議院だけなら8合目くらいだが、参議院の議論が追いついていない。憲法改正を発議するには衆参両院で3分の2の賛成が必要なわけだから、まだまだ先の話だ」

▼共産党
「国民は、改憲を優先項目として望んでいない。いま必要なのは改憲のための議論でなく、憲法の原則に反する政治を正すことだ。改憲派は、みな好き勝手なことを言っているから、まとまらないまま、そのうち材料が尽きてくるのではないか」

▼国民民主党
「いまは4合目だ。ことし秋の臨時国会で立民も交えて条文案づくりに着手して、来年の通常国会の会期中に発議するイメージを持っている。『議員任期の延長』が不要だという主張の根拠を1つずつ潰していきたい」
駆け引きは続く
憲法改正に前向きな4党は、今後も、国会開会中、衆議院の憲法審査会を毎週木曜の定例日に確実に開催したいとしている。
「議員任期の延長」をはじめ、どのテーマをどのように議論していくのか。それぞれの思惑を胸に、各党の駆け引きが続くことになりそうだ。

- 政治部記者
- 花岡 伸行
- 2006年入局。憲法審取材キャップ。毎週水曜夜のお酒は「3合目」程度に控えている。
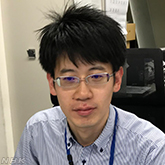
- 政治部記者
- 仲 秀和
- 2009年入局。維新担当。私の心の平和のための「9条」は、おいしいごはんを食べること。

- 政治部記者
- 矢島 有紗
- 2009年入局。現在は自民党担当。

- 政治部記者
- 桜田 拓弥
- 2012年入局。自民担当。大学入学直後に挫折した憲法を15年ぶりに猛勉強中。

- 政治部記者
- 鹿野 耕平
- 2014年入局。津局、名古屋局を経て政治部。去年から野党クラブ所属。趣味は山登り。

- 政治部記者
- 佐々木 森里
- 2015年入局。大分局を経て政治部。総理番、野党担当を経て現在は公明党の番記者。







