即位の儀式、どう見た?

10月22日に行われた「即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀」
国内外のおよそ2000人の参列者が儀式を見守りました。
今回は「令和の時代の到来を実感した」という声も出ましたが、前回の代替わりの際には、憲法との整合性をめぐって激しい論争が行われました。儀式が憲法に抵触するとの批判は、いまも根強くあります。
そこで日本在住の外国人はどう見て、何を感じたのか。そして儀式の何が問われているのか、改めて取材してみました。
(仲秀和・木下隆児)
皇帝を再興しない「ドイツ」
まずは、ドイツの方から。上智大学国際教養学部のサーラ・スヴェン教授は、ドイツ出身で日本とドイツの近現代史が専門です。

日本とドイツは、ともに第2次世界大戦の敗戦国です。スヴェンさんは、両国はともに多額の賠償金が課されなかったため、経済の立て直しに力を入れることができたという共通点があるとする一方、政治や平和へのアプローチに違いがあると指摘しました。

「戦前の日本は軍国主義であり、天皇は大元帥をつとめるなど、軍事的な役割の象徴でした。戦後、天皇制が存続されることになり、その役割を変化させる必要に迫られる中、平和の象徴として天皇制を進化させてきました」
一方のドイツ。第1次世界大戦の末期、1918年11月の革命で当時の皇帝・ウィルヘルム2世が退位するなどして、君主制が崩壊し、翌年、ワイマール共和国が誕生しました。しかし、少数政党が乱立して政治が不安定化し、結果的にナチスの台頭を招きました。

「ドイツは、ヒトラーの出現やナチスの台頭を許した反省から、戦後は徹底的にナチズムを排し、民主化を目指しました。皇帝を再興しようという動きは、まず考えられませんでした。天皇制と共生してきた日本と、過去から離れることを目指したドイツとは、この点で違います」
そして、スヴェンさんは、いまの天皇制の役割について、次のように分析しています。
「いまの上皇さまは、さまざまな国を訪問されている」

「また、戦争への反省のお言葉を述べられることで、日本のよいイメージを発信してきました。確かにドイツ人から見ると『この時代にまだエンペラーがいるのか』という印象があり、天皇は日本の特殊性の一つです。一方で、国民と膝を突き合わせて話すなど、距離感の近さや優しそうなお人柄は、一般的な日本人の姿を想起させ、身近な存在だと思わせてくれます」
スヴェンさんは、上皇さまの平和への思いを、即位された天皇陛下にも引き継いでいただきたいと話しました。

「天皇陛下は留学を経験されており、皇后さまも元外交官と、日本と世界とのつながり、国際親善の分野で、さらに活躍が期待されます。一方で、直接戦争を知らない世代となる天皇陛下には、今後は、慰霊や追悼の新しいかたちを模索されるなど、ご自身のお姿を通して、平和に対するメッセージを発信し続けていただきたいと思います」
長く王制が続く「タイ」
一方、長く王制を敷いている国がタイです。現在のチャクリー王朝は200年以上続いています。「不敬罪」があるこの国のジャーナリストからは、報道にあたって現地の難しい実情も聞こえてきます。
「日本は、お祝いムードがいっぱいでよいですね」
うらやましそうに話すのは、スパラット・プンバートさん。東京・新宿でタイを中心にアジアの食材を扱うスーパーマーケットの店主です。日本に住んで、もう20年になるといいます。

タイでは、3年前に前のプミポン国王が亡くなり、ワチラロンコン国王が即位しました。前回の代替わりの際の日本と同様、タイでも喪に服す期間が長く続いたそうです。

「タイの国旗は、上下が赤と白で、真ん中に青があり、この青色が国王を意味しています。わたしは本当に悲しくて悲しくて、新しい国王の即位を祝う気分には、なかなかなれませんでした」

「日本ではこれだけ多くの人がお祝いしているのですから、天皇陛下は、きっとみんなに愛される存在になっていくんでしょうね。私も楽しみにしています」
「着物文化」から見る皇室
天皇皇后両陛下が身につけられた装束に注目した人がいます。
十文字学園女子大学で教授を務めるシーラ・クリフさん。イギリスから来日して30年余りになるクリフさんは、日本の着物を専門に研究しています。

「着物には、昔から伝わる伝統的な染め方や柄などがあり、生地を見ればどこで作られたかわかります。その土地にしかない植物から生まれる独自の染料を材料とする着物は、世界中どこでも作れるファストファッションとは正反対のもので、日本の地域に根ざした素晴らしい文化です」
クリフさんは、皇后さまの「十二単(じゅうにひとえ)」に着目したといいます。

「平安時代に完成したとされる十二単は、大変美しく豪華ですが、重くて歩きにくく、実用的なものではありません。しかし、当時の女性は家を飾ることが重要な役割とされていて、十二単には、女性が『家の中の花』になるという意味が込められていたという説もあります。十二単を身につけた皇后さまの姿は花のように美しく、松の間の荘厳な雰囲気や、ほかの皇族方の服装もあいまって、まるで平安絵巻のようであり、日本の伝統や歴史の重みを感じました」
そしてクリフさんは、着物を身に付けることで、養蚕文化の担い手という役割も果たせるといいます。

「着物をひもとくと、もともとは糸であり、養蚕文化にたどりつきます。養蚕農家がどんどん減少している中、皇居では歴代の皇后さまが養蚕に取り組まれていて、最後の砦と話す研究者もいるほどです。新しい皇后さまにもぜひ、儀式や海外訪問の場で着物を身につける機会を増やしていただき、伝統文化の担い手としての役割も果たしていただけると嬉しいですね」
一連の儀式をめぐる議論
さて、冒頭のスヴェンさん、過去との決別を図ったドイツと違い、日本は戦後、軍国主義の象徴だった天皇を平和主義の象徴と位置づけ、天皇制と共生してきたと指摘しました。
しかしそれは、社会の中で必ずしもすんなりと受け入れられたわけではありません。
天皇を中心とする国家神道体制と軍国主義が結びつき、日本を戦争に導いたという反省のもと、天皇制と国民主権や政教分離の原則を定めた憲法との関係は、しばしば議論を呼んできました。
皇位継承に伴う一連の儀式もそうです。
前回の代替わりでは、国会での激論のほか、過激派によるゲリラ事件、右翼による銃撃事件なども全国で相次ぎました。

「即位礼正殿の儀」をめぐっては、前回、憲法違反だとして、裁判も提起されました。
最終的に国が勝訴したこともあり、政府は今回、儀式を行うにあたって、前例を踏襲することを早々に決定しました。
本当に論争は決着したのでしょうか?
2人の憲法学者に話を聞きました。
「儀式には憲法上の問題あり」横田耕一氏
九州大学の横田耕一名誉教授です。明治期同様、神道形式で行われた今回の儀式は、憲法との整合性をめぐり、大きな問題点があると指摘しました。

「即位礼正殿の儀をはじめとして、即位に関わる儀式は神話に基づく儀式です。これは、憲法20条で定める政教分離の原則に違反しています」
特に、天皇陛下がのぼられた「高御座」が問題だといいます。

「高御座は天照大神がおわすところという説や、天照大神が日本の国土を治めるために孫を高千穂峰に降ろしたという神話に基づき、高千穂峰を意味するという説などがあります。いずれにしても、高御座は神話に基づいて天皇の正統性を担保する場なんです。一方で憲法は、天皇の地位について、『主権の存する日本国民の総意に基づく』(第1条)と規定しています。つまり、神話に基づいて天皇の正統性を示す儀式は、明確に憲法1条に違反しています」
そして、横田さんは、儀式の内容にも、問題があるとします。
「国民の代表である安倍総理大臣は、高御座にのぼった天皇に対して、仰ぎ見る形で寿詞を述べ、万歳三唱をしました」

「これでは天皇が上、国民が下ということになります。つまりは国民主権の原則に反しています。また、寿詞の中でも、『天皇陛下を象徴と仰ぎ』と下からの目線になっていて、問題です」
その上で、横田さんは、戦前と戦後で、憲法で定める天皇の地位が変わったにも関わらず、即位に関わる儀式の内容が変わらなかったことが問題だと指摘します。

「政府は今回の儀式に関し、『憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統等を尊重したものとする』として、明治以降の即位の儀式を踏襲しました。でも、大勢の人が参加するような儀式になったのは、明治以降です。伝統とは何かを考え直さなければならないし、『伝統』ということばが前面に出て、憲法との関係に関する精査が十分になされませんでした。やはり伝統よりも憲法を優先しないといけないと思います」
「すでに多くの人が納得」八木秀次氏
これに対し、憲法との整合性はかなり整理され、問題ないとするのが、麗澤大学の八木秀次教授です。

政治と宗教的儀式の関わりは、社会常識の範囲内ならば許容されるとします。
「憲法は宗教性そのものを否定しているわけではなく、『儀式の目的と効果が世俗的なものであれば、宗教性が多少あっても、それは憲法の認めるところだ』というのがこの40年以上、日本の司法と行政がとってきた考え方です。伝統といまの憲法との整合性についてはかなり整理されていて、多くの人が納得できる結論に導いていると思います」
「高御座」も問題ないといいます。

「高御座で天皇が行うのは宗教的な行為ではありません。あくまでも天皇として即位したことを宣言するということです。その意味で高御座は、即位を宣言する舞台という性格なのではないでしょうか。また前回の代替わりの際の議論で、高御座を使わずに天皇と総理大臣をフラットな位置関係することもできたと思います。ただ、『昔ながらのやり方でやれ』という人たちと、憲法が規定している国民主権・政教分離の原則との整合性はどうなんだという両方の声があり、そこを政府が整理して『折り合わせた』ということです」
八木さんは、皇位継承の儀式のあり方は、すでに確立されていて、国民に理解されているという考え方を示しました。

「いまの憲法での皇位継承はこれで2回目で、儀式のあり方は確立したと考えていいと思います。天皇の伝統的な姿を即位礼正殿の儀などの儀式で示す。外国からの賓客は、古くから伝わる儀式に興味を持ったと思いますし、日本の国民も同じような感覚だと思います。また、前の天皇陛下、いまの上皇さまの存在によって、天皇という存在、天皇制自体が、国民の大多数によって極めて好意的に迎えられ、国民に一番寄り添ってくれている存在だという理解が広がっていると思います」
取材を終えて
好意的に受け止める人がいる一方、天皇制は戦前の歴史、憲法との整合性など、日本に住む私たちがこの先も考え続けなければならないテーマと密接に結びついていることも事実だと思います。即位に関連する儀式は、このあとも続きます。そうしたタイミングに合わせて、引き続き天皇制の意義、憲法との関係について考えていきたいと思います。
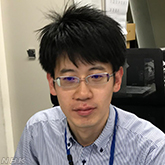
- 政治部記者
- 仲 秀和
- 2009年入局。前橋局、首都圏センター、選挙プロジェクトを経て18年から政治部で官邸クラブに所属。太平洋を見て育つ。

- 政治部記者
- 木下 隆児
- 2006年入局。金沢、鹿児島局、政治部、ネットワーク報道部。19年に政治部に戻り、ひげを剃った。





