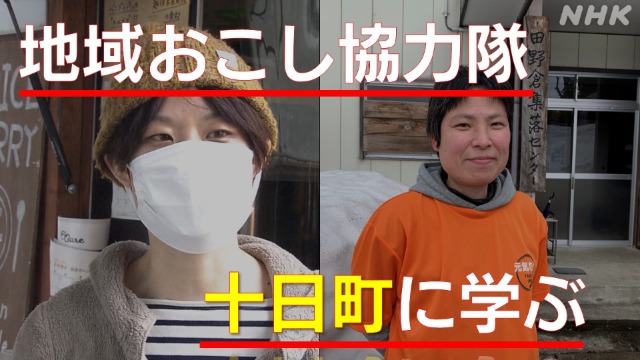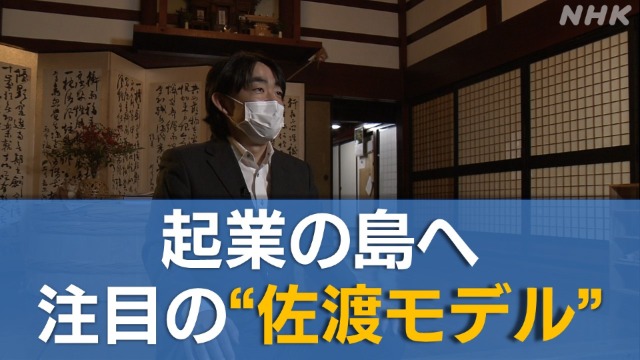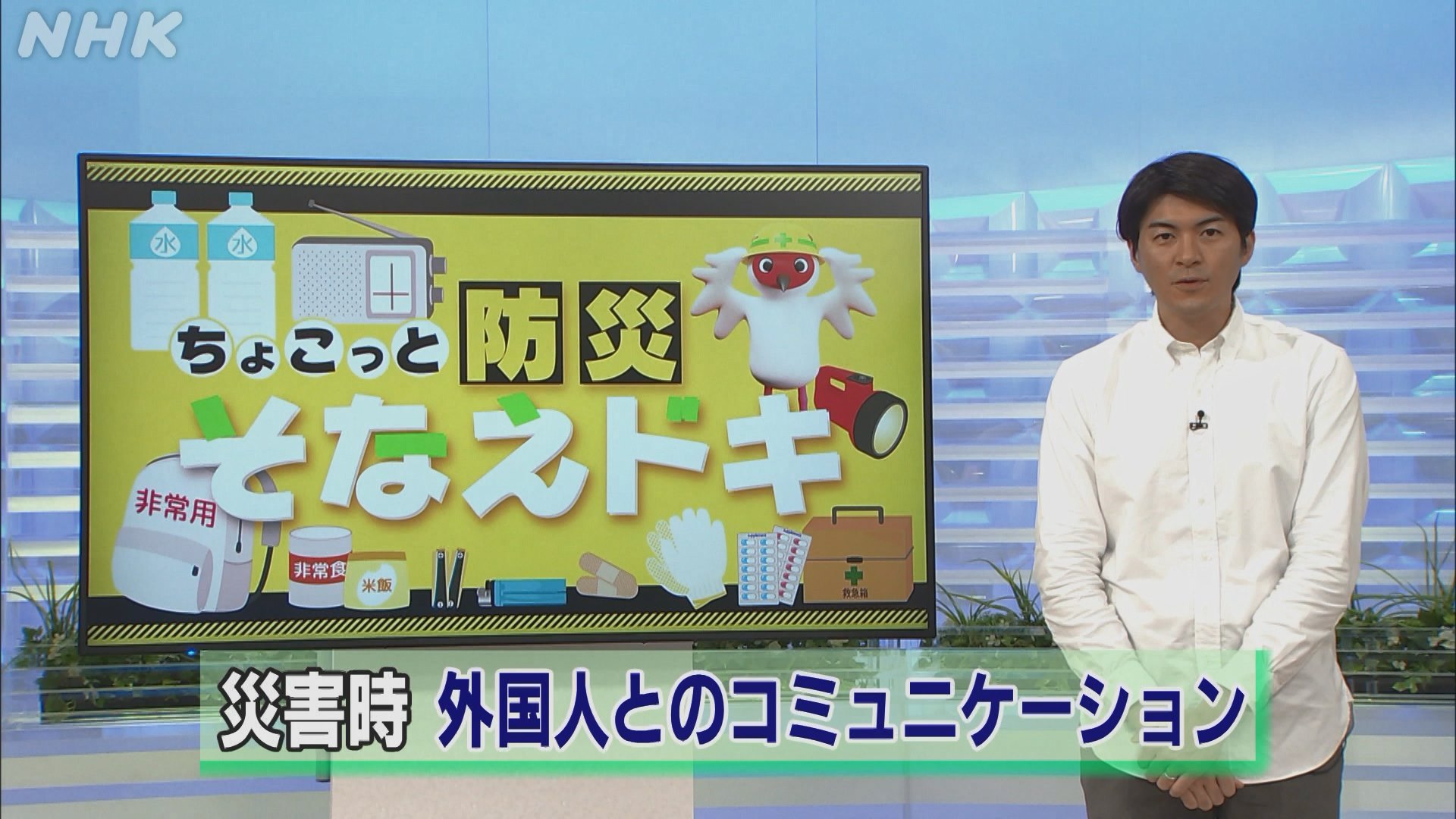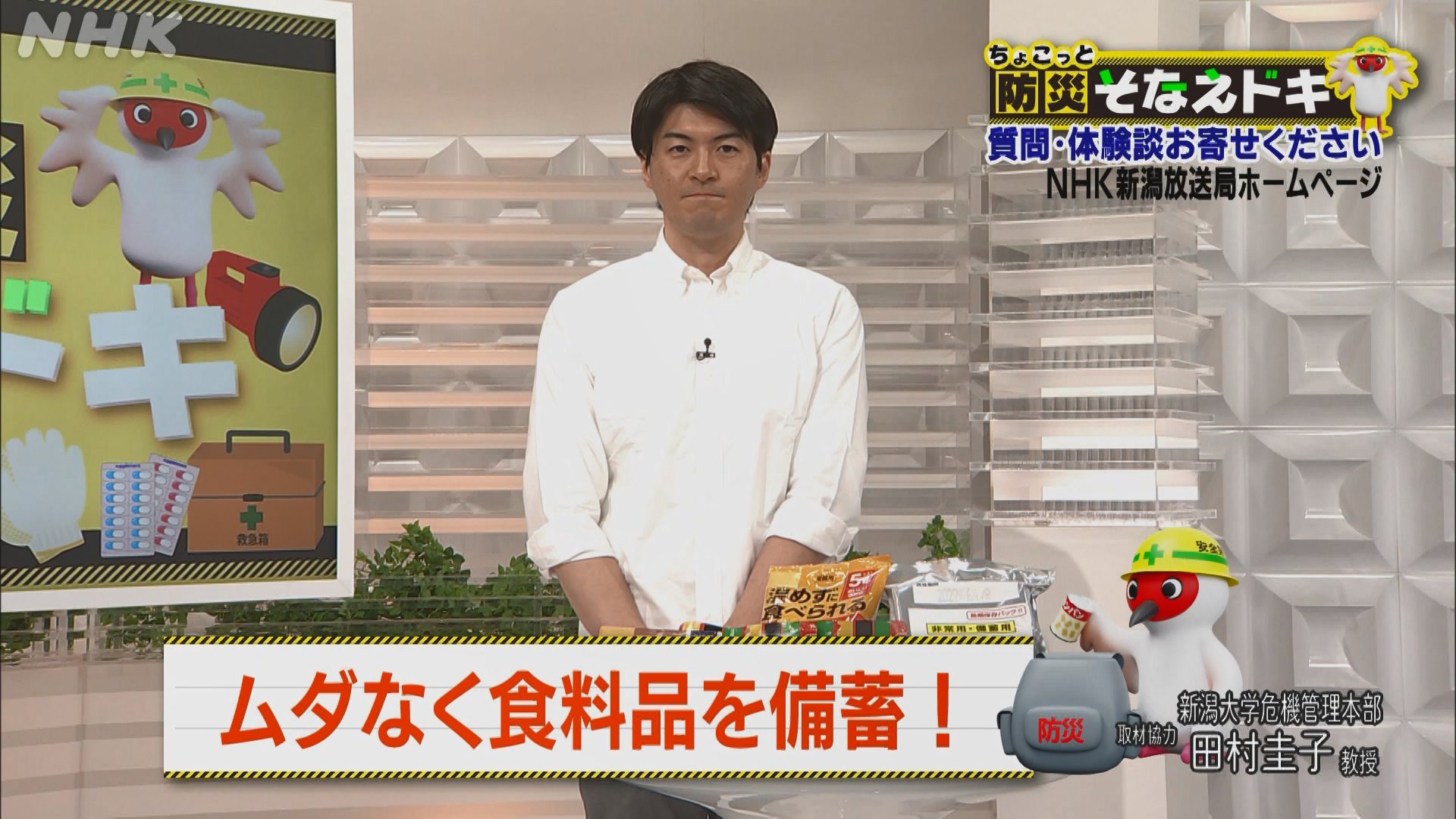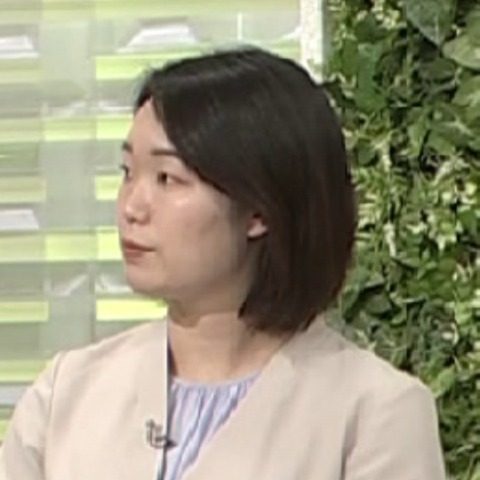糸魚川 どうなる大糸線?「持続可能な路線」方策検討へ
- 2022年05月27日

沿線の人口減少やマイカーによる移動が増え利用者が大幅に減ったことで全国的に危機的な状況となっている地方の鉄道。糸魚川市を走る大糸線も利用者の減少に歯止めがかからない中、どのようにして路線を守っていくのか課題になっています。糸魚川市を含む沿線自治体やJR西日本などが持続可能な路線をめざして議論をスタートさせました。
新潟放送局記者 油布彩那
山あいを走る1両の車両

日本海側の糸魚川市から長野県松本市をつなぐJR大糸線。
沿線にはスキーリゾートとして知られる白馬村もあり、新幹線を利用して訪れる北陸からの観光客などの輸送に大きな役割を担ってきました。
しかし、少子高齢化や人口減少、道路整備による自動車利用の増加などで糸魚川駅から長野県の南小谷駅を結ぶ約35キロの区間で利用者の減少が深刻な問題となっています。
1日の利用「1人」の駅も
JR西日本によりますと、1キロあたり1日に平均何人運んだかを示す輸送密度は令和2年度で50人。
ピーク時の30年前(1992年)と比べると20分の1以下になりました。
こちらは新型ウイルス感染拡大前の駅ごとの1日の平均乗車人数です。

北陸新幹線の乗車人数もカウントされている糸魚川駅や、松本方面への乗車人数もカウントされている南小谷駅を除けば大半の駅が一桁にとどまり、中には1人という駅もあります。
2022年4月、JR西日本はこの区間の2020年度までの3年間の平均収支が6億1000万円の赤字だったと発表しました。
「自社だけではこれまで通りの運行は難しい」

JR西日本は新型ウイルスの影響で厳しい経営状況が続いていて、大糸線以外にも特に利用者が減っている区間の収支を公表し、今後のあり方について沿線の地域と議論を加速させたい考えを示しています。
JR西日本・総合企画本部地域共生部 飯田稔督 次長
大量輸送という観点で鉄道の特性を発揮できていないと考えられる線区につきまして、当社がこのまま単独でやっていくのは非常に難しいと考えている。待ったなしの課題なので具体的な議論を始めさせていただきたい。
「なくなれば困る…」利用者の声

一方で、大糸線の利用者からは、生活や観光に鉄道が欠かせないといった声も。
県外からの観光客の男性
北陸から松本の方に出るのはこれしかないので、なくなったら不便になる。
沿線に住む女性
車の運転が出来る人は通うことができるかもしれないけど、みんな年をとって運転が出来なくなるし…。なくなれば困るので続けてもらいたい。
振興部会「持続可能な路線としての方策を検討したい」

こうした中、5月19日、糸魚川市や松本市など沿線の自治体や商工団体などからなる期成同盟会の中に新たに振興部会が設置されました。
JR西日本もオブザーバーとして参加し、地域の実情や住民のニーズなどを共有しながら、路線の存続を目指す自治体関係者らと沿線の活性化策など今後のあり方を幅広く議論することになりました。
JR西日本の担当者
今後も現状をしっかり共有させていただきながら沿線の活性化、それから持続可能な路線の方策について前提なく幅広く話をさせていただきたい。
今後の議論は...

Q:今後の議論はどのように進むのでしょうか?
油布記者
糸魚川市を含む沿線の自治体は観光や生活の足として欠かせないため大糸線の存続を目指しています。振興部会の中でも持続可能な路線となるよう関係者が知恵を出し合いながら沿線の活性化策なども話し合いたいとしていますが、具体的な議論はこれからです。
Q:議論にあたっては何が重要でしょうか?
油布記者
沿線の住民からは、
▼「鉄道がなくなると人が入ってこなくなり過疎化が進むのが心配」
▼「目的地の近くまで行くにはバスの方が便利だけど値段が高いから困る」と存続を求める声がある一方で、
▼「たとえ鉄道でなくても何らかの移動手段があればよい」といった声も聞かれました。
採算性が特に悪い路線の存続は難しいという見方もありますが、鉄道は地域のライフラインでもあり、鉄道をなくせば地域がますます衰退しかねないという懸念もあります。
「利用者や地域にとってはどうすることがよいのか」ということをにいちばん考え、議論していく必要があると思います。