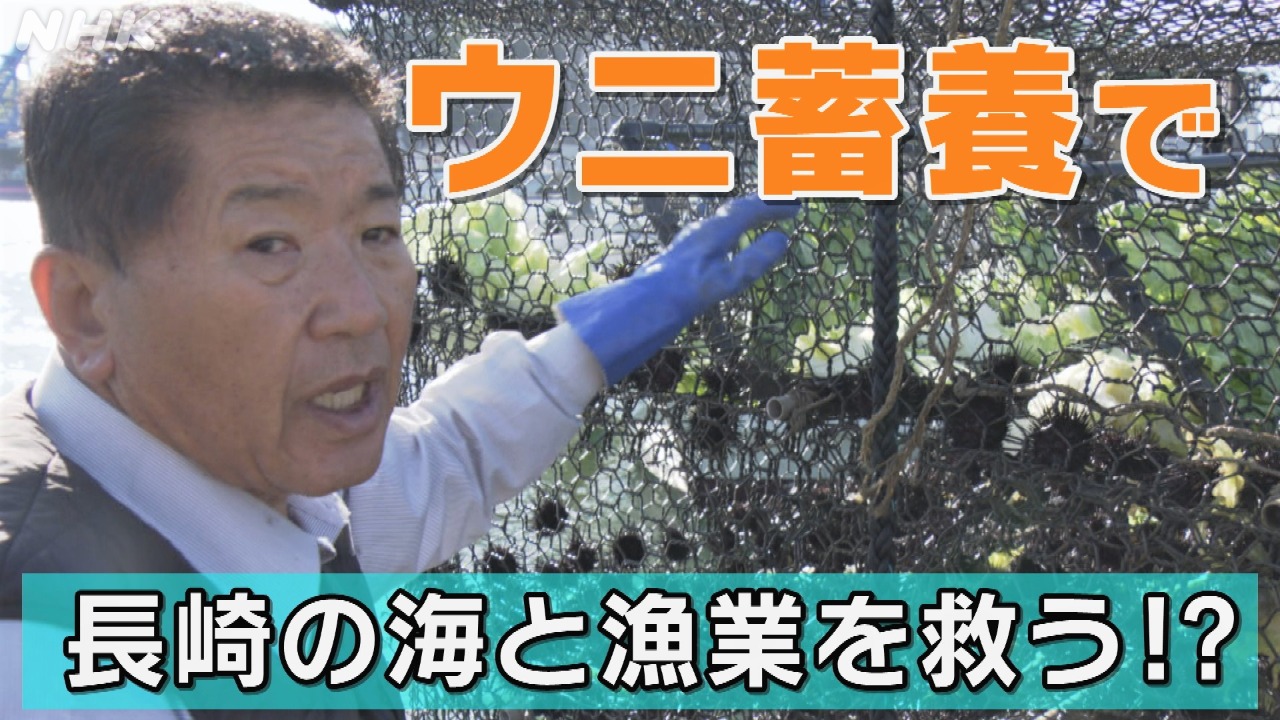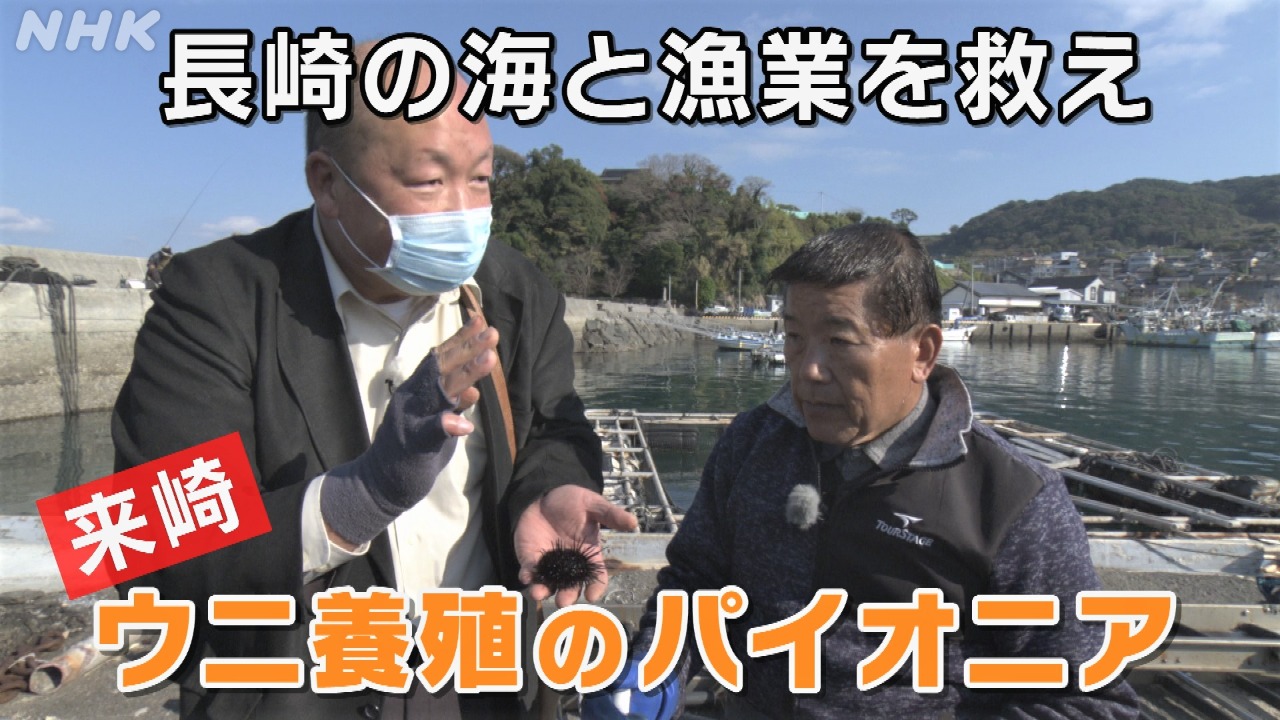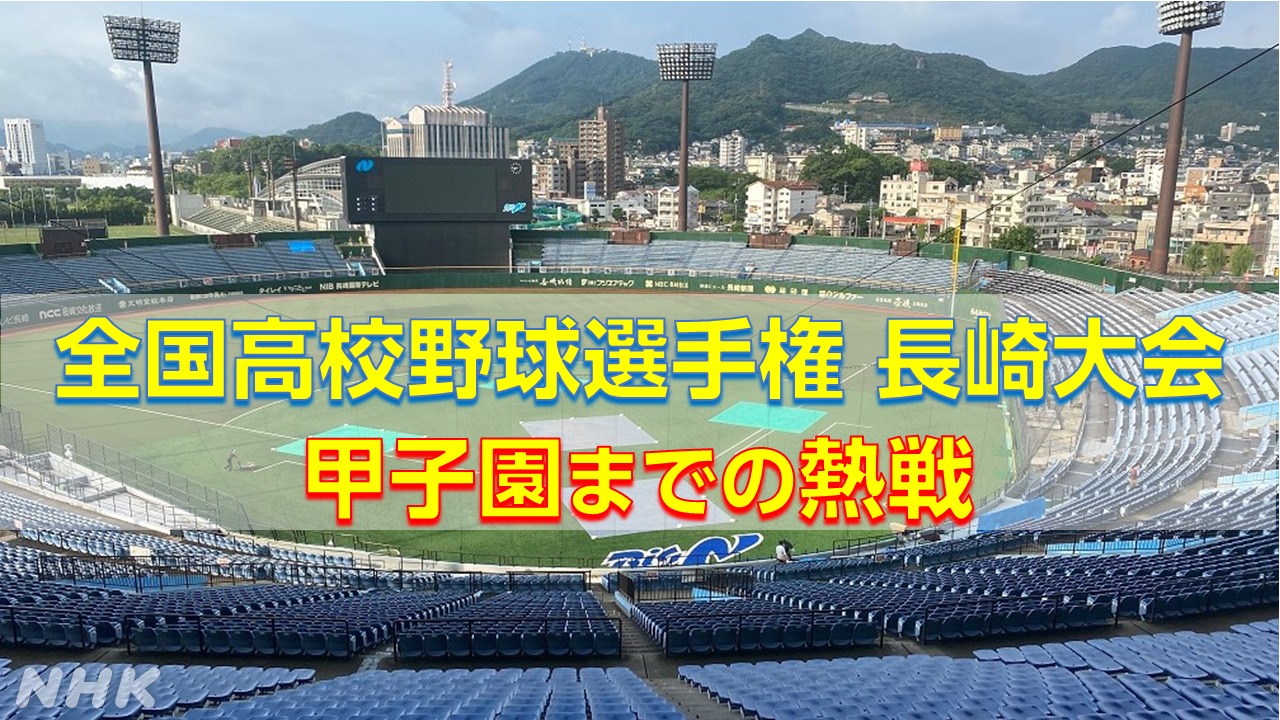いま注目!対馬で始まった「食べる」磯焼け対策
- 2023年07月20日
海藻が生える場所である「藻場」の減少、いわゆる海の「磯焼け」が止まらない…

魚の「産卵場所」や「住みか」といった機能を持つ海藻の消失は、漁業に大きな影響を与えています。
そんな中、対馬では海藻を食べ尽くす「食害魚」を『食べて』、磯焼け対策に一役買おうと全国でも珍しい取り組みが始まっています。その舞台裏を取材しました。
長崎放送局ディレクター 河野早杜
漁師たちが感じる海の“異変”

九州北部の玄界灘に浮かぶ国境の島・対馬。豊富な水産資源に恵まれ、漁業は主要産業を担っています。しかし、長年海を見てきた漁師からはある「異変」が聞こえてきました。

昔は周り一面、藻が生えていた。今は全然ない。

ずらーっと「磯焼け」してしまった。異常ですよ。
その「磯焼け」の現状とは。海の中を覗いてみると…
海藻が生えず、岩肌が剥き出しとなり、まるで砂漠のような光景が広がっていました。

長年、アワビやサザエなどの素潜り漁を続けてきた築城茂徳さんです。磯焼けの現状に強い危機感を抱いています。

築城茂徳さん
昔は1日で7キロほどアワビの水揚げがあったが、最近は1週間で7キロにも満たない。今は壊滅的な状態で、涙がでるくらい悲しい…。
なぜ、磯焼けは進むのか。県内で藻場の調査を行う、長崎大学の西原グレゴリー教授は「温暖化」による影響を指摘します。

温暖化により海水温の上昇が起きています。冷たい水を好む海藻の成長が阻害され、磯焼けがさらに進行しています。生態系のバランスが壊れつつあり、かなり深刻な状況です。
県の調査によると、県内の藻場の面積は8200ヘクタール。この25年間で約4割減少したことが分かりました。

藻場の急速な減少は水産資源の枯渇につながると県は危惧しています。さらに、近年、磯焼けに拍車をかけるある魚の存在が明らかになってきました。
温暖化で急増する“食害魚”

対馬・豆酘崎(つつざき)の定置網漁船に同行し、その「魚」を追いました。定置網の中に混じっていたのは…

体長40センチほどの「イスズミ」という魚です。温かい海を好む魚ですが、海水温の上昇と共に対馬でも多く見られるようになりました。

鋭い歯で海藻を根こそぎ食べるため、磯焼けを広げる食害魚だと考えられています。
一方で、イスズミなどの海藻を食べる「食害魚」は独特な磯臭さがあり、商品価値が低いため漁師からは敬遠されています。

対馬市では「磯焼け対策」として駆除を行っているものの、繁殖力が強く、あまり数は減っていませんでした。そこで、島では駆除に加えて新たな対策に乗り出しました。

食害魚を有効活用して「磯焼け対策」と「漁業活性化」を両立しようという取り組みです。その名も「食べる」磯焼け対策。地元の漁協や企業に呼びかけ、3年前から本格始動しました。


市では食害魚の水揚げや出荷費用などに約1200万円の補助金を出し、流通面をサポートしています。水揚げ量も増加し、手応えを感じています。

島内の流通ルートも整備され、水揚げされた食害魚は余すことなく地元の水産工場へと運ばれて行きます。
全国に広がりを見せる「食べる」磯焼け対策

漁師たちを悩ませていた「食害魚」。その加工・販売を手がけてきたのは、地元対馬で水産業を営む犬束ゆかりさんです。商品化で最も苦労したのは「臭い」でした。

しその葉やお酒と漬けたりして、いろんなものを作りました。失敗もたくさんしましたが、「対馬の海を守りたい」という強い思いがあり、諦めることはありませんでした。

試行錯誤を繰り返すこと3年。地域の協力もあり、独自の加工技術を開発しました。

まずは、臭みの原因となる「血合い」の部分を丁寧に取り除きます。そして、血合いを取った「切り身」は水で3時間洗い流します。さらにもう一つ一手間が・・・

水洗いした「切り身」を冷凍し、細かな血合いをピンセットなどで取り除くといいます。丸一日、地道な処理を経て白身魚に仕上げていきます。そして、生まれた商品がこちら…


淡白な白身フライとタルタルソースがよく合い、磯臭さは全くありません!
現在、対馬産の食害魚は特産品として、東京や大阪などのレストランでも採用され、販路を拡大しています。

また、小学校では「食育」の一環でイスズミを使った料理が提供されるなど、島内での活用も盛んに行われています。地元漁師も「磯焼け対策」と「漁業振興」につながると期待しています。

これまで商品価値が低く、取引先がなかった魚を買い取ってくるので助かる。これが全国に広がってくれたらいいですよね。

日本各地で深刻さを増す海の磯焼け。「食べる」磯焼け対策は、日本の漁業を救う新たな「糸口」となるのか。離島・対馬の挑戦に大きな関心が集まっています。