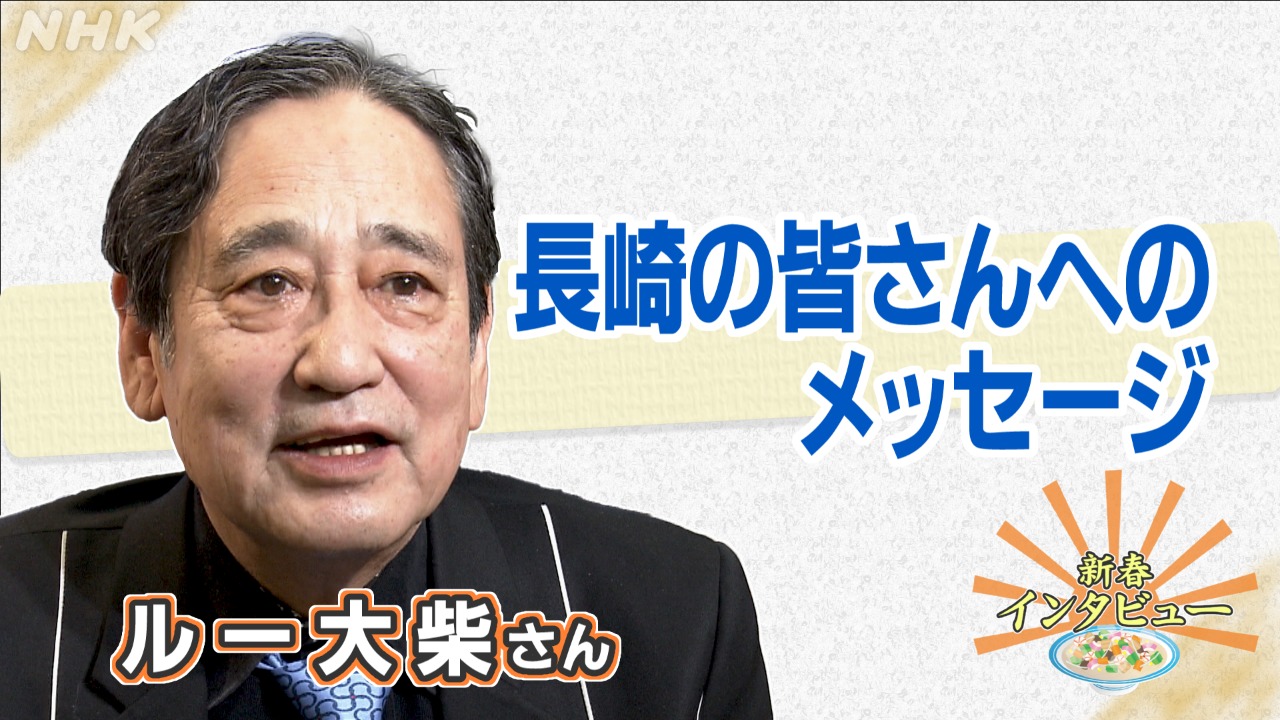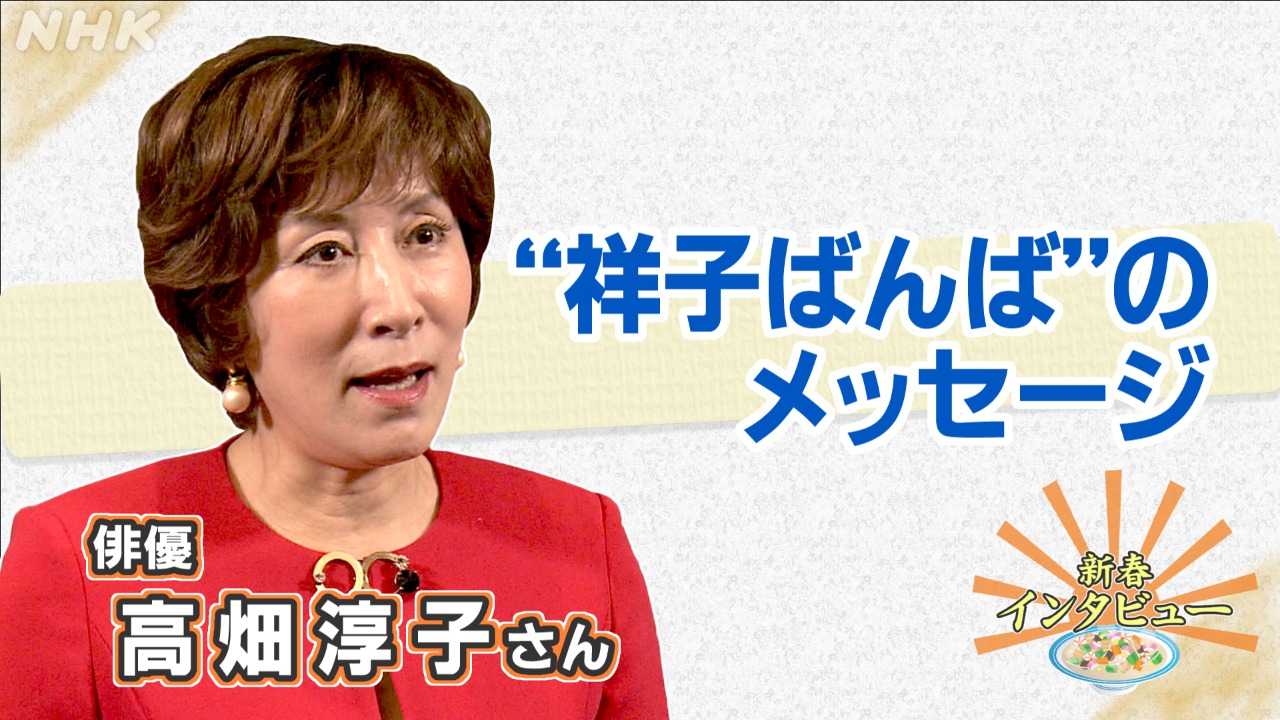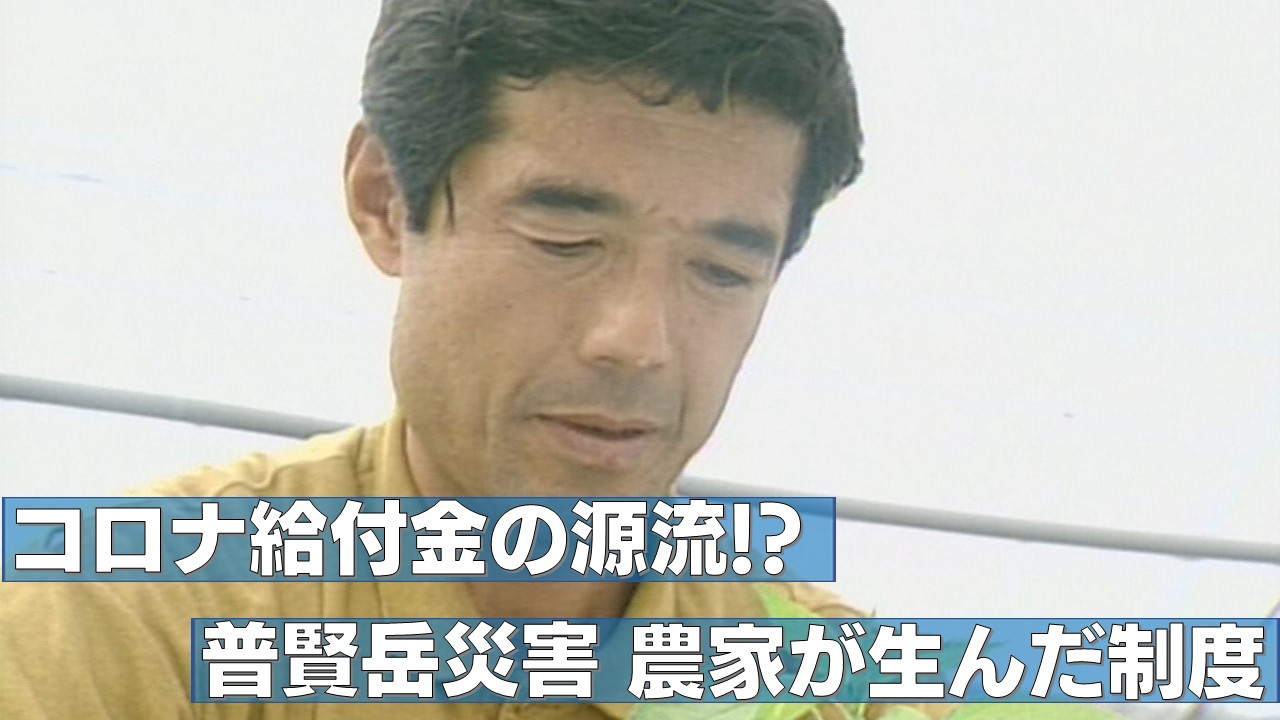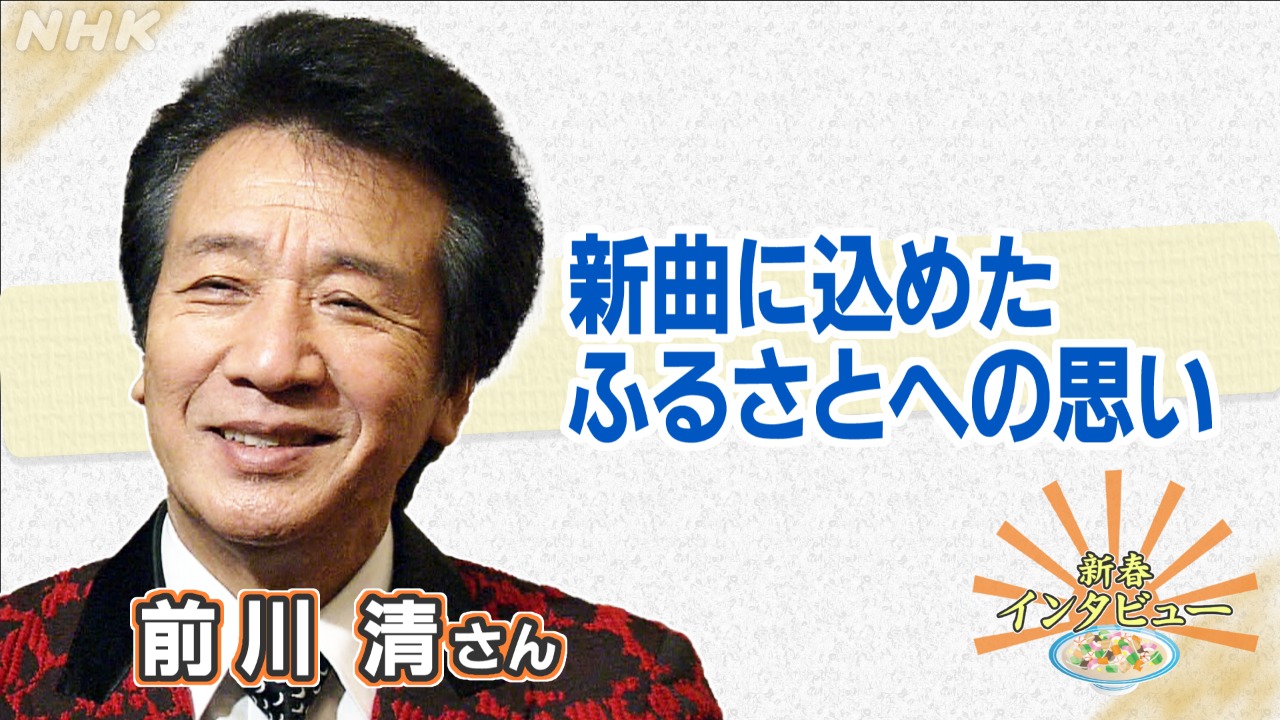グミで鬼退治!~変わる豆まき~
- 2023年02月08日

NHK長崎放送局 榊汐里 池田麻由美
節分といえば、豆まき。今年も、鬼に向かって豆をまく子どもたちの元気な姿をお伝えしようと、長崎県内のこども園や幼稚園を取材すると・・・ 「あれ?変だぞ。なんか豆じゃないものをまいている!」 背景には、消費者庁からの注意喚起がありました。
鬼をはらうのは個包装のグミ

節分の日、我々が取材に訪れたのは島原市の認定こども園「ひかわ第一幼稚園」。赤鬼が部屋に現れると、「鬼は外」のかけ声とともに園児たちが一斉に鬼はらい。でも、子どもたちが手にしていたのは豆ではなくお菓子のグミです。

こちらのこども園では、食物アレルギー対策のため、お菓子を豆の代用としてまいている、とのことです。この取り組み、もう10年間も続いてるそう。
副園長 佐藤智恵さん
食物アレルギーの園児に配慮して、豆をまくのはやめました。衛生面を考え、ひとつひとつ包装してある柔らかいグミにしています。安全に楽しく伝統行事を学んでもらえるよう試行錯誤しながら取り組んでいます。
子どもたちにも好評で、鬼はらいに成功すると、園児たちは投げたグミを拾い集めておいしそうに食べていました。
意外に多い “豆じゃない” 豆まき
調べてみると、節分の豆まきに豆を使わない施設がたくさんあることがわかりました。

長崎市上野町にある長崎信愛幼稚園では、2匹の鬼に向かって新聞紙をまるめたボールを投げつけていました。

豆まきのあと、園児は豆の代わりに配られた卵ボーロやおかきを食べました。やはり、食物アレルギーを配慮してのことでしょうか。
園の主幹教諭 大橋小夜さん
大豆やピーナッツでは誤って飲み込み喉に詰まったり、アレルギーが起きたりすることがあるので他のものを使っています。鬼退治は泣いてしまう子もいますが、最後は楽しんでほしいと思います。
節分の豆、5歳以下は危険!
じつは、子どもの豆まきに豆を使わなくなった理由として、ある危険性が指摘されています。消費者庁によると、5歳以下の子どもが食品をのどに詰まらせた事故は、2020年までの10年間で全国の医療機関から141件報告されています。このうち全体のおよそ2割を、大豆やピーナッツなどの「豆・ナッツ類」が占め、2020年2月には節分の豆をのどに詰まらせた4歳の子どもが窒息して亡くなる事故も起きています。

子どもがかんだり飲み込んだりをスムーズにできるようになるのは6歳ごろとされています。そうした力が未熟だと、豆などがのどに詰まりやすく、気管に入ってしまうと中で膨らんで窒息するおそれがあるのです。そのため消費者庁は、節分に合わせて、かたくてかみ砕く必要のある豆やナッツ類などについて「5歳以下には食べさせないで」と注意を呼びかけているのです。
乾燥した豆は要注意

「窒息は短い時間でも命に関わる」と話すのは、子どもの事故予防に詳しい、小児科医の出口貴美子さんです。「節分で使われる乾燥した豆は、崩れやすい性質があるため、気管の中に入ると周りの水分をすって膨らみ、気管をふさいでしまう。そこで肺炎になってしまうと大がかりな手術が必要になる」と指摘します。
出口貴美子さん
保育所などで対策が進められていても家庭でも事故は起きる。特に年上の兄や姉がいると、かわいそうだからと5歳以下の弟や妹にも食べさせてしまうおそれがある。
窒息のリスクを知って、5歳以下の子どもは豆以外のもので節分を楽しむなど時代にあわせながら伝統行事を楽しんでもらいたい。
もし窒息が疑われた場合にはどうしたらいいのでしょうか?出口さんは「子どもに近づいて状況を確認しつつ、周囲に人がいれば、すぐに助けを呼んでほしい」と話します。また、子どもの背中を叩いて異物を取り除く『背部叩打法』などを日頃から練習しておくことも大切だといいます。
まくものは変わっても

変わる節分の豆まき。伝統文化を継承するという観点からはどう考えればよいのでしょうか?日本文化を研究する国立歴史民俗博物館の新谷尚紀(しんたに たかのり)さんによると、そもそも節分は1年をリセットする行事で、前の年の罪や汚れ、災いや病気などあらゆるものをきれいにするねらいがあるといいます。
国立歴史民俗博物館 名誉教授 新谷尚紀さん
文化は常に変化するもので、幼稚園での新たな取り組みは新しく面白い変化だと思います。節分と言えば豆ですが、投げるものをお菓子にしてでも、小さな子どもたちが節分の行事を続けることが大事です。

まくものが変わっても、鬼はらいに興じる子どもたちのうれしそうな姿は、私たちの頃と変わりません。今回取材した幼稚園でも、鬼がやってくる前に節分の意味を園児たちにしっかりと伝えていました。誤飲などの危険を避けながら、節分の行事を続けていくことはできるのではないかと感じました。