
「幸運なひと」はこうして生まれた。20年考え続けたこととは?
2023年4月、2週にわたって放送したドラマ「幸運なひと」。
30代でステージ4の肺がんを患った夫(生田斗真さん)と、その妻(多部未華子さん)の日常を、闘病記としてではなく笑いやユーモアを大切にしながら、病ではなく幸せにフォーカスした人生を送ることができるのか、問いかける物語でした。
今回の特集ドラマの企画・演出を担当した一木です。
このドラマを実現するために、私は20年を越える時間を要してしまいました。そこには取材過程での挫折と、企画を通せない敗北感が累々と横たわっています。
しかしその「熟成」のお陰もあって、新しい出会いに恵まれ、これまで関わることがなかった報道番組、情報番組、福祉番組などの担当者と共に実現した、記念すべき作品となりました。

さて、私はなぜ、がんを患うひとのドラマを作らねばならなかったのか。
なぜ20年以上かかったのか、なぜ今実現することができたのか。
ここに至るまでの軌跡を通して、
・取材対象者との距離感に、悩んだこと考えたこと。
・当事者ではない自分が、どこまで他者の内面に踏み込むべきなのか。
など、あくまで私の視点ではありますが、挫折をお話しすることで、
取材をすることで人を傷つけてしまうのではないか?
無用な苦労を強いているのではないか?
結局、私達取材者がやっていることは何かの役に立つのか?
そんなことを悩んでいる人の背中を、少しでも押すことができたら、これ以上の喜びはありません。
がん医療取材で感じた決定的な敗北感、その道のり
私は1993年にNHKに入局し、すぐにドラマ部に配属されました。
ドラマに憧れがなかったと言えば嘘です。しかし当時名だたる映画研究会や、小劇場で腕を鳴らした人がごろごろしていたNHKドラマ部は、私には別世界でした。以降3年、記憶がないくらいに必死に働きましたが、何かをクリエイトしたとは言えない日々でした。
1996年にドラマを出て、BSハイビジョン局に所属。この間、インド、イエメン、パプアニューギニア、アメリカで番組を作りました。
1998年に起きたパプアニューギニアでの地震と津波の取材では、当時、東京大学地震研究所の都司嘉宣氏、京都大学防災研究所の河田恵昭氏、東北大学防災研究所の今村文彦氏他、後の東日本大震災でも最前線におられた研究者達と寝食を共にして被災地を歩きました。
「災害現場において、テレビ取材に一体何ができるのか?」という若者だからこそ許される問いに、彼らが教えてくれた言葉は、私のその後のディレクター人生を支えてくれました。
「死者が命を懸けて伝えてくれていることを、学びつくすのだ」と。
この取材でクローズアップ現代を制作する機会も得ました。
私はもしかして、ドラマ以外の世界でもやっていけるのではないか?
そう思い始めたころ、巡り合ったのが「がんと生きる」というテーマでした。
私は取材で、人々を傷つけていく
BSスペシャル「がんと生きる」制作のため、たくさんの医師や患者さんの話を聞くことから始めました。
Sさんと、出会ったのはこのころでした。
彼女は乳がんを患っていました。乳房温存を選択したものの1年待たずに再発。再手術で全摘。
再発までの時間の短さから、再発転移は近いと見られていましたが、以降10年にわたってがんを抑え、「奇跡の患者」と呼ばれていました。もともと教養が深く頭のいい人で、医師とも対等に意見交換していました。
そんな彼女を頼って治療方針や病院選びを相談する人は多く、彼女を通してたくさんの医師や患者さんを紹介してもらいました。
私は当初、Sさん自身のこともカメラで撮影させてほしいとお願いしていました。しかし、取材を進める中で、今は症状を抑え込めているSさんへの取材は、不要ではないかと考え始めていました。むしろ喜ばれると思っていました。
撮影なんていう面倒から解放されて良かったと思ってくれるのではないかと。
しかし実際は違いました。
「Sさんへの取材はしない」と伝えた翌日、私はSさんの夫に呼ばれ、「なぜ取材は必要ないと変わったのか理由を説明してほしい」と抗議を受けました。
妻は非常に傷ついている。あなたは軽い気持ちで頼んだのだろうが、承諾するにはどれだけの葛藤があったか分からないのか?
病という究極のプライバシーをさらしてでも、伝えたいことがある。
その覚悟をした人間を、あなたは踏みにじったんだと。
当然ながら、取材対象者は構成要素のコマじゃない。
ただ、私は経験も引き出しも、人間としての熟成も足りなかった。
取材対象者というのは、迷惑を承知でカメラを向ける人のことをいうのではなく、伝えたい言葉を共に問いかける共同制作者なのだと、今ならば言えます。
しかしこの時はただ、すみませんとひたすら頭を下げ、さらには「本当はドラマが専門で、ドキュメントの訓練を受けてないんです」と言い訳したことを記憶しています。
「へー、ドラマを作る人だったんだ」と認識したSさんに言われた言葉は、「あなたも表現者なら、ユーモアを描きなさいよ」というものでした。
お涙ちょうだいはまっぴらだ、そんなものは見ない。日常をどう生き抜くかを患者は考えているんだよ。
今のドラマはスーパードクターの活躍か、死のセンチメンタルを描くにとどまっている。それは、本当のがん患者を見ていない。
もっとレベルをあげてくれ、と言われたのです。
私はこの日から、一体ユーモアとは何か、本当の当事者の姿とは何かを、探し続けることになりました。
もう一人、この「がんと生きる」の番組に出演してくださったIさんのことが忘れられません。
40代の乳がんの患者さんで、茨城からわざわざ京都の著名な外科を選んで手術を受けていました。この外科は個人病院だったので、Iさんのために、病院は気を利かせて個室を用意しました。
しかしこれが他の入院患者さんの不満を生むことになり、Iさんは完全に孤立してしまいました。
誰もが彼女を避けていることが、私にも明白に分かりました。
Iさんの話し相手は、茨城からやってくる家族だけになってしまいました。
私はこの病院に密着することで、保険のこと、治療費のこと、配偶者との関係、ドクターとの関係、患者相互の関係など、様々なものを見せていただきました。
しかし私は、番組には前向きな尊いものしか映せませんでした。
自身の命のために、無防備な姿で、必死にそこにいる人に対して、自分の肚
が座らないせいで、彼らの内面に迫れない、映せない自分に絶望していました。
人を傷つけるだけで、人間らしい葛藤や迷いや弱さを映しこめないならば、フィクションだからこそ炙り出せる人間の内面を描くことに、この後のディレクター人生を賭けるしかない。
がんの方々との出会いが、私の道を決めてくれました。
しかし、企画は10年落ち続け…
壮大な決意をしてドラマの現場に戻ったかに見えますが、現実はしょぼいものです。
私は10年にわたって放射線科医を主役にしたドラマの提案を書き続けますが、全く通りませんでした。
ちょうど、「東大のがん治療医ががんになって」という書籍が発売されました。この著者である加藤大基先生は東京大学の放射線科の治療医にして30代で肺がんを経験された方。何度も会っていただきました。その指導医の中川恵一先生とも頻繁にあって打ち合わせを重ねました。
Sさんとも、何度打ち合わせを重ねたか分かりません。
でも、どんなに当事者の具体的な話を盛り込んでも、企画を通すことはできませんでした。
(このころ、後に「幸運なひと」の医療考証をしていただくことになる高野利実先生とも知己を得て、腫瘍内科医としての話を何度も伺いました)
「ユーモアを描く」という命題に、到達できていないことは分かっていました。だから企画を通せないのだ、ということも。
ドラマの登場人物として、モデルになってもいいと言ってくださっていた方もいました。
彼女は、乳がんを患い、肝臓、骨に転移。3人のお子さんのお母さんで40を越えたばかりでした。何とか彼女にドラマを見てもらいたいと思っていましたが、間に合いませんでした。
その後、がんを扱うドラマをいくつか制作したものの、それは私が志した、そして勝手に「託された」と考えていた「がんの描き方を大きく変えるドラマ」ではありませんでした。いつか必ず約束を果たしたいと思いながら日々が過ぎ、2021年を迎えていました。
私はチーフ演出として、「おかえりモネ」の制作に 邁進していました。
私の”人生をかけた一作”「おかえりモネ」を振り返ってみました ※NHKサイトを離れます
はじめまして。朝ドラ「おかえりモネ」チーフ演出の一木です。助監督時代を経て、ドラマ演出歴は17年ほど。この記事では、これまでのドラマ制作で思うことについて、プライベートも含めてつづってみたいと思います。
きっかけは、朝ドラ「おかえりモネ」に寄せられた手紙
朝なのに暗いのではないか?というネットの評価に、新しい風を吹き込んでくれた「#俺たちの菅波」こと菅波洸太郎医師は、末期がんで自暴自棄になる人物に、「時間稼ぎすることは、実はとても大事なことではないか」と伝えます。
このシーンの放送後、私はがん研究会有明病院の乳腺内科部長になっていた高野利実先生から、封書の手紙を頂きました。
菅波医師のスタンスは素晴らしいということ、医師の界隈においても、「おかえりモネ」の菅波の評価はとても高い、と言ったことを伝えて下さるものでした。私もうれしくなって、封書の手紙を送りました。
この手紙のやり取りがなかったら、「幸運なひと」はなかったかもしれません。
ある時私は仕事仲間から、「食道がんの母の治療方針を巡って主治医ともめている。主治医は選択肢を提示してくれない。どうしたらいいか」と相談を受けました。
聞けば、手術が怖いと訴える80歳近い方に、医師は手術しかないと言い続けるのだと言います。その医師の横暴ぶりに、がん医療はまだそんなところにいるのか?と怒りが湧きました。
たとえどんなに無茶な要望だったとしても、他でもない自身の命の問題が、自身の納得の行かないまま進むなどあり得ない。
がん治療は肉体の苦痛も精神の問題もかなり研究され、もはやドラマでやることはないのか…と思いかけていた私の心に、火がつきました。

ついにたどりついた「ユーモア」の仕掛け=夫婦というバディものを!
高野先生に「日本のがん医療はまだこんなところにいたのか。これじゃ20年前とそう変わらない。やっぱりドラマを作らなきゃいけない」と、矢継ぎ早にメールを打っていました。
メールを書きながら、私は自然と、当事者のみならず影響を受けてしまう家族、特に配偶者の人生も激変させることも注目すべきだ、とか、特に妻はパートナーが病気になったら、自分が仕事をセーブしてケアに専念すべきではないかという思い込みがあるなど、「幸運なひと」の骨子になる文言を打ち始めていました。
そして高野先生とのメールのやり取りの中で、不意に「夫婦だ」と天啓を得たのです。
夫婦というバディものなのだと。
闘病ものではなく、バディで課題をクリアしていく痛快物語にするのだと。日常を愉快に生きるノウハウを込めるのだ、と見えてきたのです。
ユーモアの具体的手法が分からず20年経ってしまいましたが、ようやく突破口を見つけた気がしました。
脚本家・吉澤智子さんと共同で企画書を書くも・・・
吉澤智子さんとの出会いも、「幸運なひと」を実現する重要なファクターでした。
吉澤さんは肺がんを患った夫を看取っています。病気が分かった後でお子様を授かられました。
今回の企画を書けるのは、この人しかいません。
吉澤さんに企画書を見せて、彼女から出てくるアイデアをどんどん取り入れました。
「つわりと抗がん剤の吐き気はどっちがつらいのか?」「にんじんジュースでがんは消えないけど、シミは消えた」など、「幸運なひと」でも印象的なシーンとなるアイデアを企画書に盛り込みました。
さらに吉澤さん自身の経験から、「夫の命が短いかもしれないのに、子どもを授かりたいと思う人間は尊いか、あるいはエゴイストなのか」という命題が、大きく浮かび上がってきました。
生と死の問題が、夫・妻・子というミニマムな家族の中に同時に存在するという、ドラマ空間が生まれました。
吉澤さんとのブレストを通して、私はこれまでの闘病ドラマが抱えていた「ちょっとした違和感」を明確に意識しました。
私たちが新しく生み出そうとしているドラマは、夫婦の極めて日常的な、ささやかな会話劇がメインになる。その会話の中に、恐らく演劇的な泣いたり叫んだりと言った場面は、一度あるかないかであろう。
なぜかと言えば、私たちはたとえ家族であっても相手を慮
って生きているから。なるべく家族を苦しませないように、ショックを与えないように、重大なことをライトに伝えようと苦心してしまうから。
必死に笑い冗談を言う姿こそが、つまりは究極的な愛情なのだ。
病を得た当事者たちが見て、物足りないと思っていた違和感は、ここにあったのだ。
つまりドラマ的に必要だと思われる「苦悩する姿」や「涙」は、本来心の最奥に秘められたものであり、その代わりに笑いやユーモアがあるのだ。
「あなたも表現者なら、笑いやユーモアで、人間の本当の苦しみや孤独を描いてみろ!」。
そうか、こういうことだったんだと、齢50を越えてようやく確信できるようになりました。
一方で、がんの患者さんを描くのに、笑いだユーモアだって、何を不謹慎なことを言っているのか?という考え方もあります。
しかしさて、当事者の方々は、そんな風に腫れ物に触るように扱われたいと思っているのでしょうか?
私の知る限りそれは真逆であると思うのです。もっと誰もがかかりうる身近な出来事として、フラットにニュートラルに話したい。
重く捉えないでほしい、孤立させないでほしい。そう思う方が多いように感じます。
そして、重い病であり、悲劇であり、苦悩する姿というイメージを押し付けているのは、他ならぬテレビであったりドラマであったりすることを、私たち制作者は自覚すべきでしょう。
さて、このように理論武装して挑んでも、企画を通すことはできませんでした。
確かに企画意図は分かるものの、完成のイメージが湧きづらく、そしてこれが多くの人の心に届くものになるのか、分かりづらいことは理解できます。ならばラジオドラマとして脚本開発し、そこから映像化への道を探ろうかと考えていた矢先、この企画は、意外なところから復活していきます。
妊よう性温存という情報的価値
がんは世界的には減少傾向にあります。
患者が増加しているのは、日本だけといわれています。
また3年にわたるコロナ禍で、がん医療は相対的に緊急度が下がり、特に肺がんのスペシャリストたる呼吸器外科・内科の人材が、コロナ対応に回りました。
アフターコロナとして、がん医療の3年の「停滞」は顕在化する可能性がありました。
また、このドラマで描こうとしていた「妊よう性温存」は、不妊治療の現場においてもホットな話題でした。
不妊治療ではようやく保険が適用されるようになりましたが、運用には諸問題が噴出していました。そしてがん患者さんの「妊よう性温存」については、保険適用ではないことも課題でした。
またひいては、がんを患うか否かに関わらず、子どもをもし授かるとするならばそのタイミングはいつかというのは、現代に静かに横たわる喫緊の課題でもあります。
「幸運なひと」は、こうした情報的価値を重視する局内のセクションの人々の目に留まり、復活します。
情報を出すだけでは伝わらない層に、いかにして訴えかけていけるのかを模索してきた番組スタッフ。彼らの協力や知見を得て、ドラマはさらにパワーアップして制作に漕ぎつけることになっていきます。
いつもは「あさイチ」「ハートネットTV」「ニュースウオッチ9」等で制作しているスタッフがコアメンバーに加わりました。
ボトムアップで連帯したメンバーによって、このドラマは制作されたのです。
他者にどこまで踏み込むか、非当事者がやらねばならないこととは?
20年解決できなかった課題が、一つ一つ解きほぐされていく中で、最後に問われてくるのは制作者としての肚の座り方、覚悟であったと思います。若いころからずっと悩み、問いかけてきたこと。
<がんを患い、様々な悩みや葛藤を抱える人々に、その内面をさらけ出して欲しいなんて、迷惑以外の何ものでもないのでは?私は私の仕事ノルマ?編集で恥をかかないために?人の迷惑に踏み込んでいるだけではないのか?>
この問いに一つの光をくれたのは、朝ドラ「おかえりモネ」での脚本制作を通して、作家の安達奈緒子さん、そして、プロデューサー・演出陣と交わした思考の数々を経て到達した、ある「考え」でした。
それは「非当事者だからこそ出来ることがある」というものです。もっと言うと、非当事者がやらねばならないことがある、ということです。
当事者だからこそ理解できること、見えるものがあります。
その風景を軽々しく「分かる」と言えるはずもありません。
しかし、彼らが抱える痛み、葛藤は、当事者だけで解決できるものではない。必ず、非当事者の客観性が必要なのではないでしょうか。
そして時には非当事者だからこその冷静な視点、判断、ドライな行動力も、何かを動かすためには不可欠なのだと思います。
「自分にその資格があるのか」を問い続けることを止めるべきではないと思います。しかし一方で、誰もが遠慮して近づかなかったら、当事者は孤立するばかりです。
「おかえりモネ」のセリフの中に、
「あなたの痛みは僕には分からない。でも、分かりたいと思っています」というものがあります。これはドラマの最重要テーマを語っています。「あなたのことが分かる」という一見優しいが、実は独りよがりな嘘は決して言わない。でも、理解するために傍にいる、学ぶ、寄り添うことを止めない、という約束です。
自分が本当にそうやれているのか、正直自信がありませんが、心からこうありたいと思えた言葉に、やっと出会えました。
そしてこのことへの気づきが、「幸運なひと」の中で最も挑戦的だった場面を生むことになります。
「幸運なひと」で最も印象的で繊細だった場面について
「幸運なひと」には、治療に前向きになれない主人公が、患者会に参加する場面が出てきます。この場面にいたのは、本当のがん当事者の方々でした。
この場面に台本はありません。皆さんの心からの思いを語っていただきました。
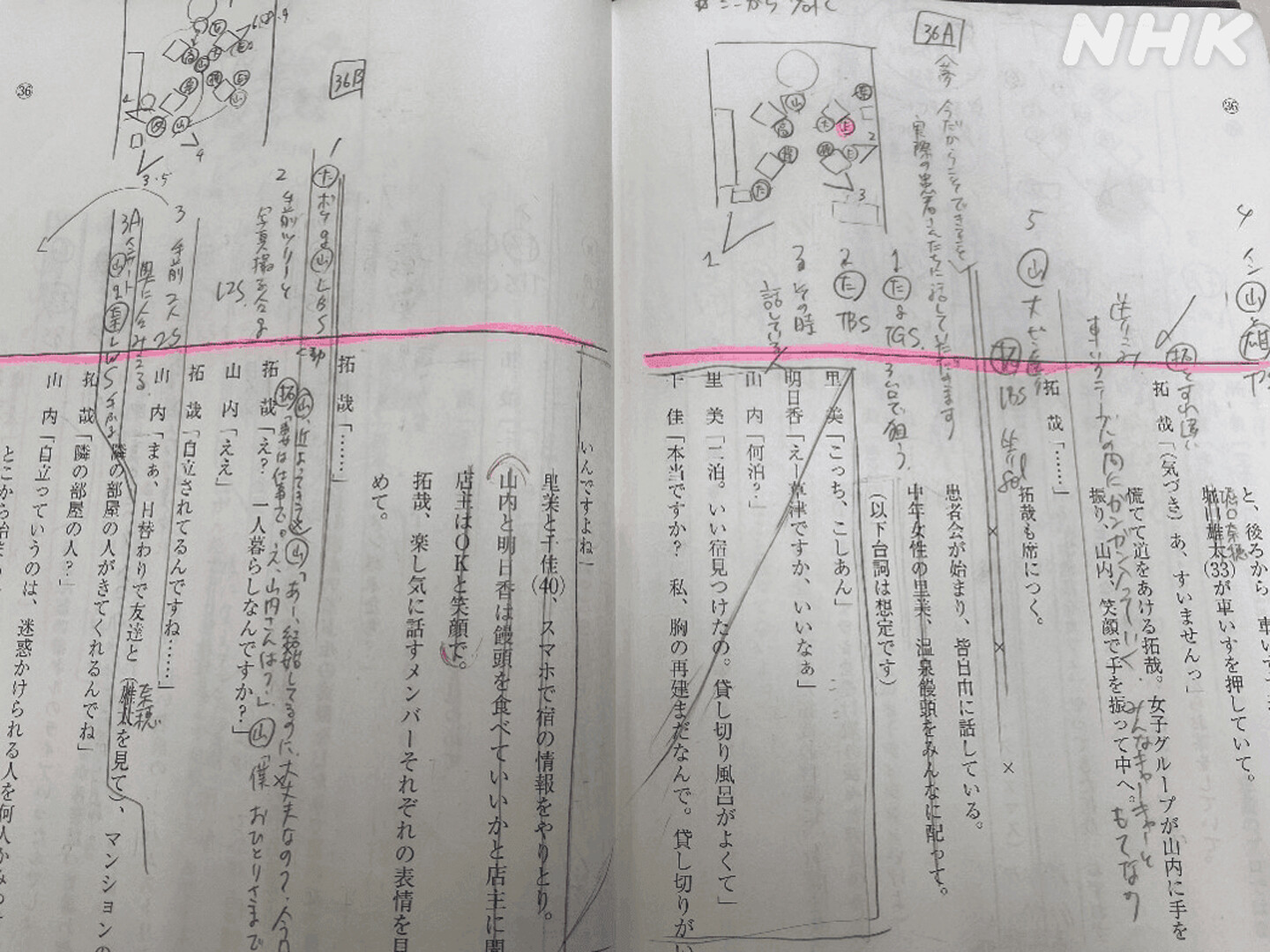
ここに役者さんではなく当事者の方々に来ていただいた最大の理由は、がんという病のイメージを作ってきたテレビ、ドラマの刷り込みを打破する。これに挑むためでした。
患者会に集う人々とは、どういう方々なのでしょうか。ウイッグや帽子をかぶっているでしょうか。車いすや杖を使っているでしょうか。顔色が悪く、疲れた様子なのでしょうか。
これら「イメージ」は大きな誤解を生みかねないものです。
がん医療はもっと進化しています。
がん研有明病院やがんセンターの待合室を見せていただいても、正直誰が患者さんなのか分かりません。治療による副作用のコントロール、アピアランスケアは確実に進化しています。鋳型にはめようとしているのはこちら側であることを改めて痛感させられました。
もう一つ重要なことは、「患者会に参加しよう」という人間が、闘病そのままの状態で来るのか?ということ、つまり誰だって出かけるならばそれなりの身支度を整える。おしゃれをする。
そうした、人としての自然な気持ちに、フィクションは残念ながら応えられていないと感じます。ドラマではどうしても、この病の典型的な特徴を表現しようとしてしまいます。「普通」と同じでは表現にならない怖さがあるからです。
こうした悩みを突破するために、当事者に参加してもらって、「共に創る」ことを決意しました。
フィクションだからこそできることがある、と決意してドラマに戻ったのに、矛盾しているのではないか?何度も何度も自問自答しました。
これを突破させてくれたのは、情報番組や報道番組の新しい仲間達の支援と、考え続けた20年の重みだったと思います。自分の究極のプライベートをさらしてでも伝えたいことがある、と決意した方々に出会えたならば、勇気をもって踏み込み、媒介者になる。
ようやく自分の肚が座ったからこそ、実現できた場面だったと思います。

さて、私は現在、間もなく放送されるNHKスペシャルのドラマ「アナウンサーたちの戦争」の総仕上げの最中です。
第2次世界大戦下の日本放送協会は、戦況を有利に進めるために、進んで戦意高揚やフェイクニュースに携わりました。その重い事実を、生々しい感情を持つ人間同士の葛藤を通して描いています。
戦後放送協会の先輩達は、その痛恨の思いを胸に、マイクを自分で握りしめるのではなく、人々の声を聞くために、外に出たそうです。そこからドキュメンタリー番組、インタビュー、そして昼どきの中継やのど自慢などが生まれました。
これを知り、やはり私たち制作者は、声を出せない人の声を聞く媒介者になるために存在するのだと、思いを新たにしました。
私は取材を通して出会った人々に、あまりに多くのことを教えて頂いたと思います。
注意深く、思慮深く、繊細に、人と関わるのだということ。これは同時に、社会人として生きていくためにも、最も基本的なことだと言えます。
そうしてつながった制作者と当事者の絆から放たれる情報や情感や思いが、一つ一つ社会を良くしていきます。
勤続30年、協会人生何周かした末に今、私はこのことを信じています。
-
一木 正恵
-
北海道出身、1993年NHK入局。主な演出作品に、朝ドラ「どんど晴れ」「ゲゲゲの女房」「おかえりモネ」、大河ドラマ「義経」「天地人」「八重の桜」「いだてん」など。









