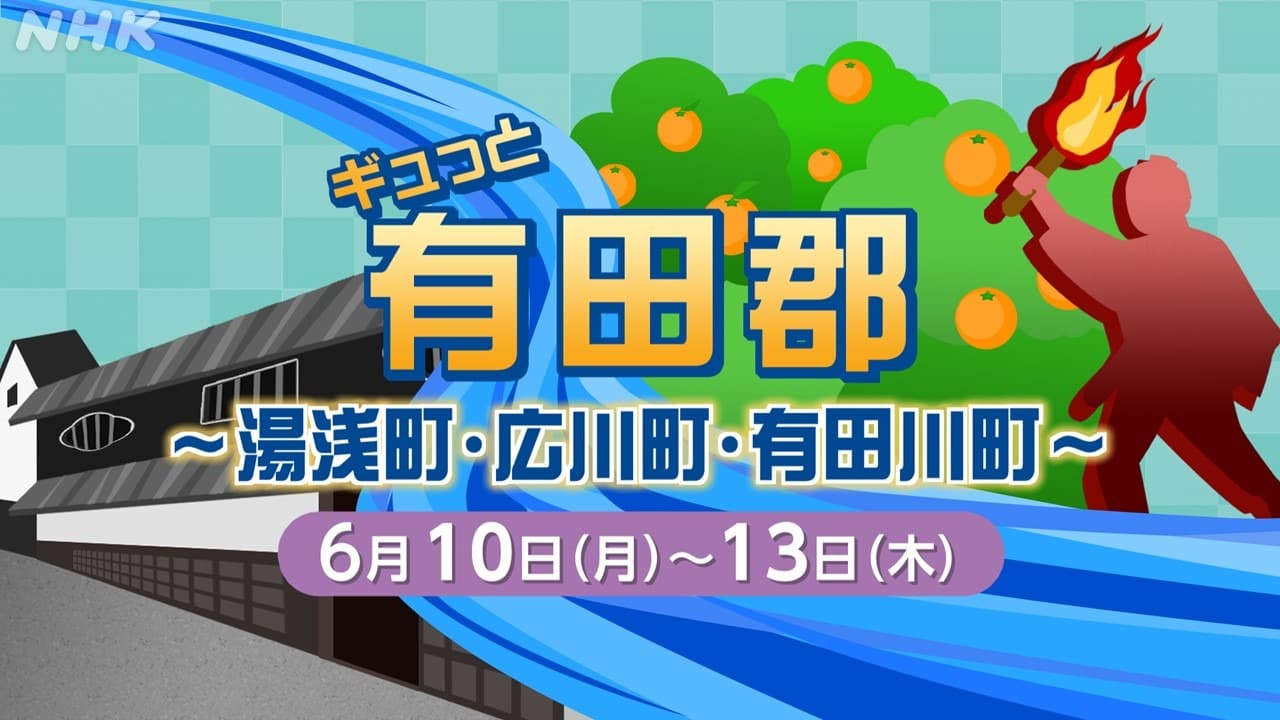ラジオ防災講座「災害看護と心のケア」
- 2024年05月23日

県内4つのコミュニティーFM(和歌山・橋本・白浜・田辺)とNHK和歌山放送局が共同制作する、シリーズ「ラジオ防災講座」。今年度第1回は「災害看護と心のケア」をテーマに、能登半島地震の被災地を始め全国の災害現場で被災者に寄り添い続けた看護師の皆さんの声を交え、被災後に求められる看護について考えました。スタジオゲストには、和歌山県立高等看護学院の中尾ひろみ学院長をお迎えしました。(和歌山放送局 アナウンサー 今城和久)
《被災地でも活躍できる人材を》

ことしも県立高等看護学院(紀の川市)には看護師を志す50人の新入生が加わりました。県内に2校ある看護学校の一つで、その歴史は74年。現在は5千人を超す卒業生たちが和歌山県を中心に各地の医療現場で活躍しています。
どうして看護師になりたいのか。新一年生の皆さんに聞きました。「母が看護師だったので小さい頃から患者さんに寄り添う姿に憧れてきました」「中学生の時に逆流性食道炎にかかって看護師と触れ合ったのを機にこの仕事を目指すようになりました。将来は心のケアにも取り組みたいです」「祖父の入院中、担当看護師は家族のことも考えてくれました。死との向き合い方まで教えてくれて、心の支えになりました」。

「将来、南海トラフ巨大地震が発生した時に、災害医療の現場でも力を発揮できるよう育てたいと思っています」
かつて日本赤十字社和歌山医療センターで千人の看護師を束ねる看護部長を務めた中尾さん。東日本大震災直後には岩手県山田町で避難所となった小学校に派遣され、負傷した人や病気になった人のサポートはもちろん、心のケアにも携わりました。

「図書室で遊ぶ子どもたちを見守りながら、心身の健康観察にも取り組みました」
《能登半島地震の被災地で心のケア》
ことし元日に起きた能登半島地震の被災地に、和歌山県から駆け付けた人がいます。日本赤十字社和歌山医療センターの臨床心理士、倉山正美さんです。倉山さんは同センターで20年近く心のケアに携わってきました。過去には、東日本大震災や熊本地震など、各地の被災地でも活動。日赤職員に対する指導役も担う、「心のケア」の第一人者でもあります。倉山さんたちの医療チームが向かったのは、石川県内の役場です。3月上旬に1週間に及ぶ活動を終えた倉山さんに話を聞きました。


「災害や事故で大きな衝撃を受けた時に起きる心や体の不調を、できるだけ最小限に抑えて回復させるケアを『心のケア』ととらえています。今回は、被災者支援と支援者支援を行いました。支援者支援とは医療機関や役所で働き、被災者を支援する人たちへの支援です。リフレッシュルームを開設し、手にクリームを塗る『ハンドケア』やリラクゼーションを実施。体が緩むと気持ちも緩む。話しやすい環境になりますよね。リラックスしてもらい、お話を伺いました。来た時は疲労で目もどんよりしていたのが、ケア後は目に力が宿り『もうひと踏ん張りする!』と言う姿が印象的でした」

春に起きた熊本地震のケースと違って、今回はまだ肌寒いうえに断水が長引いていたため、温かな足湯が喜ばれたそうです。心の傷は目に見えない分、ケアは容易でないと倉山さんは話します。

「一人で抱えると孤独になり悪化します。県外から助けの手を差し伸べるのも大事。被災者でないから話せたと言われたことがあります。同じ被災者同士だと被害の違いで本音を言い辛い、というケースも。外から来た人なら遠慮なく、本当に辛い思いを話せる事もあります。外の支援は大切。初めて会う人だから話しやすい事もありますよね」

「大好きな人がしんどかったら背中をさすったり手を握ったりすると思います。私も看護師時代に何も言わず患者さんの手を握り続けた事がありました。暖房ではなく人のぬくもりで心がほぐれることもありますよ」
《「レジリエンス」を大切に》
臨床心理士の倉山さんがもう一つ、平時から準備してほしい「心のケア」として挙げたのは「レジリエンス」です。「精神的な回復力」や「逆境からの復元力」という意味が込められた「レジリエンス」。重視する理由とは。

「ストレスやダメージを受けた時、人は跳ね返す力、乗り越える力を持っています。力がある事を分かっていれば、混乱せず乗り越えられます。レジリエンスを高めるために自分の事をよく知っておきましょう。人間関係、新しい環境…自分がどんな事で不調になりやすいのか。不調時にどんなサインが出るのか。イライラする、落ち込む、頭痛が出るとか。そしてサインが出たらどう乗り越えたらいいか。方法が分かっていると対処能力がつきます。災害時は何も持たずに逃げるので、身一つで出来る方法を知っておくといいと思います。深呼吸やヨガ、ストレッチ、瞑想など。リラックスできて心も癒される方法を、被災する前の平常時から見つけておきましょう」

「災害だけでなく感染症など予期せぬ出来事が起きる不確かな時代、未来の看護を担う学生たちにも、しなやかに生きる力を持ってほしいと思っています。自分の強みを知るレジリエンスは大事だと教えています」
《変わる「災害支援ナース」》
阪神・淡路大震災を教訓に誕生した「災害支援ナース」をご存知でしょうか。専門の研修を受け、被災者の健康管理や心のケアを行う看護師の皆さんです。

「登録制のナースです。災害が起きたら要請を受けて支援をしに行きます。感染症発生時にも活動するので、新型コロナウィルスの対応にもあたりました。これまで全国の看護協会が主導してきた研修や派遣は、ことしの4月から法律が変わって国が担う事になりました。活動費用が公的負担となるので、より安定的な活動ができるようになると思います」
今回、能登半島地震の被災地へ、和歌山県看護協会からは初めて災害支援ナースの派遣が行われました。石川県輪島市や金沢市へ、1月下旬から2月上旬にかけて駆け付けたのは県内14人の看護師の皆さん。避難所で被災者支援などに携わりました。派遣内容の報告に加え、今後の南海トラフ巨大地震に備えるために必要ことは何なのか考えるため、報告会と意見交換会が4月に海南市の和歌山県看護協会大ホールで開かれました。

この日は県内各地の病院に勤める看護師およそ50人が参加。和歌山市や串本町から被災地へ向かった6人が活動報告に臨みました。紀美野町の病院に勤める男性は、高齢の女性が土砂災害で亡くした家族について話してくれた時の思いを伝えました。「初めて会う私にここまで話してくれました。被災して1か月近くたってやっと言葉に出来たのかもしれません。聞く事に徹しました」。続いて開かれた意見交換会では少人数のグループに分かれて、災害支援ナース経験者に質問したり、課題について話し合ったりしました。テーマは「外国人被災者への対応」や「避難所と普段の病院との活動の違い」など、多岐に渡っていました。この日、最前列で熱心にメモを取りながら参加していた中尾さんは…。

「地域の病院に勤める人たちが被災地で活動したことに大きな意味があると思います。グループワークでは、当初災害看護に興味がなかった人が実際に被災地を訪ねて『分からない事がたくさんあった』と話していました。このままでは自分の病院を守れないという気付きや危機感を覚えること、体験者が発信し共有することが大切ですよね」
参加者の一人で、和歌山県看護協会の災害対策委員の二河絵美さんは、現在御坊市の病院などで勤務しています。「災害支援ナース」としても1月下旬に金沢市で活動しました。二河さんは那智勝浦町出身。南海トラフ巨大地震の被災地となり得る地域で、以前から看護師として災害時に何ができるか考えてきました。今回は、若手看護師たちに「支援ナースとして活動できる機会があれば、看護の価値観も変わります。災害に関する知識や技術を身に着けた看護師が少しでも多い方が減災につながるので、連携や協力を得るためにも支援ナース登録を呼びかけました」と話していました。

「どんなに訓練したとしても、災害現場に赴くのは初めての人がいます。情報が限られる中、必要とされることを見つけて取り掛かるのは大変です。経験者の発信を若手がしっかり受け止めて備えてほしいと思います。看護師として活躍してくれる仲間が増えればうれしいです」。
今回の「災害支援ナース」の報告会の模様は、和歌山県看護協会のホームページ上でも紹介されるということです。
【制作後記】
中尾さんと初めてご一緒したのは8年前、当時の和歌山放送局のニュース番組「あすのWA!」でのインタビューコーナーでした。日赤和歌山医療センターの看護部長だった中尾さん、いま未来の和歌山の看護を担う十代の皆さんを育てるお立場です。当時と変わりなく、思わず何でも打ち明けたくなる優しい笑顔と包容力にほっとしました。看護師への道を歩み始めたばかりの十代の皆さんから、今回の能登半島地震被災地での経験を若手に繋ごうと取り組むベテランナースの皆さんまで、それぞれの覚悟が胸に響きました。