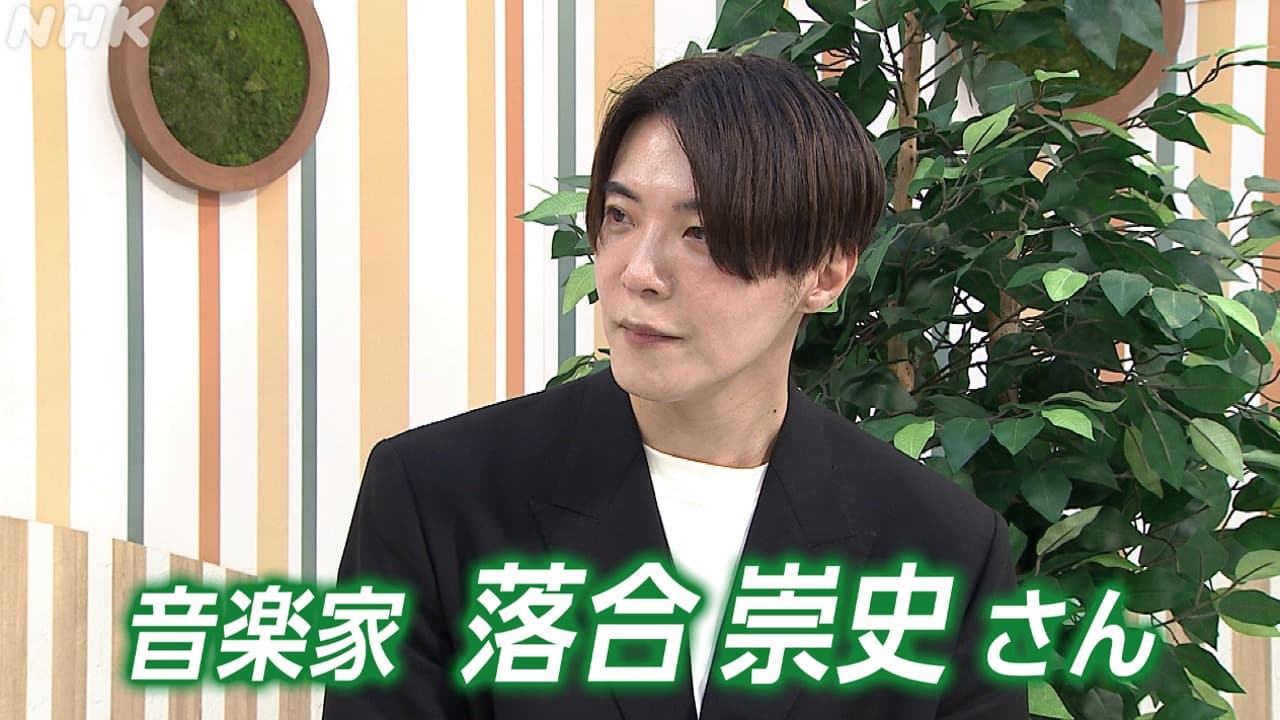言葉の壁はITで打ち破る!〜外国にルーツのある子どもへの支援〜 宇都宮大学客員准教授・若林秀樹さん
- 2024年05月24日
毎月最終金曜日にNHK-FMで放送してる「金曜カフェとちのき堂」。
栃木への愛、とちぎ愛あふれる方をゲストにお招きしています。
2024年4月26日放送のゲストは
外国人の児童生徒教育、日本語教育が専門の宇都宮大学客員准教授・若林秀樹さん。
外国にルーツがある子どもたちをサポートするべく活動を続ける姿をご紹介しました。
(宇都宮放送局 アナウンサー 橋本奈穂子)

(橋本)
金曜カフェとちのき堂、今日のゲストは宇都宮大学客員准教授の若林秀樹さんです。
若林さんは栃木県下野市のご出身。公立中学校の英語教諭として、また外国にルーツがある子どもなど日本語の指導が必要な子どもに日本語を教える「日本語教室」の専任教諭として14年前まで県内の中学校で働いていらっしゃいました。その時の経験をもとに、日本語がわからない保護者との連絡を確実に取るためのシステムを発案。2年前に実用化され今さまざまな学校現場で導入されています。

(橋本)
まず日本語の教育が必要な子どもたち、特に外国籍の子どもたちの日本語教育の現状から伺っていきます。文部科学省の調査によりますと、日本語の指導が必要な外国籍のお子さんは全国的に増えていて、令和3年の調査では全国の公立の小中学校で4万7000人以上、およそ10年間で1.8倍ほどに増えている。ふだん暮らしていて外国の方増えたなっていう印象がありますけれども、若林さんは専門家としてこの状況どうご覧になってますか?
(若林さん)
増えること自体は世界的に人流が変化してるので当然だと思っていますね。
外国にルーツがある子どもの課題については数が増えたと考えるよりも、日本語指導を必要とする子どもが在籍する学校数が増えたというとらえ方をする必要があるんですね。4万7000人で1.8倍になったって言いますけど、実は学校数はこの10年間で数千校増えてるんですね。学校の数が増えたことで、これまで日本語指導に縁がなかった学校の多くで対応が必要になってきた。その学校で何ができるんだろうということが課題になっています。
栃木県に関して言えば今約40校ぐらいの小中学校に日本語教室っていうのがあって、そこに教員がきちんと割り当てられています。僕が指導していたころは、多くて30数人ぐらい1つの学校に日本語指導が必要な子どもたちがいました。
(橋本)
日本語教室での指導は、ふだん在籍しているクラスとは別の場所で行われます。日本語の基礎だけではなく、学校生活で必要な日本語だったり生活習慣だったりを一人一人に合わせて指導しています。また日本語教室がなくても、通訳や支援員を配置するなどして子どもたちをサポートしている学校もありますが、すべての学校でサポートや指導が行われているわけではないんですよね。

(若林さん)
子どもたちの使用言語が多岐にわたるため通訳が見つからないというケースはとても増えてますね。僕は学校現場の課題解決を考えているのですが、多言語だから何も伝えられないんだと先生たちが思い込んでいて情報が家庭に伝わらないという課題が一番大きいと思います。
お子さんの教育にとって学校と家庭の連携というのは欠かせないものですけれども、現状日本の学校は日本人に伝えると同じ情報を多言語の家庭には伝えられていない。伝えられていないことによってさまざまな弊害が起きている。もちろんこれは学習だけではなくて学校と家庭の信頼関係にしてもそうです。
先生たちって何とか伝わってるって思っちゃう事が多いんですね。具体的に言うとプリントを配って読めないかもしれないと思っても、外国人のお子さんとか保護者が何も言ってこないからわかってるのかなと思ったり。先生たちは、子どもたちは普通に生活してるから大丈夫だって言うんですけれども、それは子どもが普通に生活するすべを身につけているだけだったりするんです。やっぱり誰でもそうじゃないですか。わからないふりをするのはつらいから、わかったふりをする。情報が伝わらないといろんなことに支障が出ますから、そこが僕はなんとかしたいなと思っています。
(橋本)
そこで若林さんが発案したのが「多言語連絡帳」というシステム。
保護者との学校との連絡がある程度やり取りのパターンが決まっていることに着目して開発されたウェブのシステムです。
例えば「授業参観にお越し下さい」とか「何時にお迎えにきてください」など500種類以上の定型文が登録されていて、11の言語に対応しています。必要な定型文を学校側は日本語で送信。保護者は自分の使用言語でその連絡を確実に受け取ることができます。
(若林さん)
学校から家庭に伝えることを想定している内容のほとんどを網羅して定型の文章にして入れ込んでありますので、それをどう組み合わせようと誤訳は起きないという独特の仕組みです。これまでは外国語っていうと翻訳しなきゃとか通訳を探さなきゃって思うてたと思うんですけど僕はもうそういう時代は終わったと思っています。
(橋本)
このシステムを発案するにあたっては、若林さんご自身の日本語教室での経験がもとになっているそうですね。
(若林さん)
インターネットが普及していなかった頃は辞書を持って家庭訪問していました。外国人の子で学校に来てもけんかしたり全然勉強しなかったりという子がいたんです。最初僕は言葉が通じないからだなって思ったんですけれども、それではちょっと諦めきれなくて、そこで保護者に協力を訴えるようにしたんですね。僕もポルトガル語が話せないから、その保護者に言いたいこと、文書を自分で作って定型文化してリストを作って、それをバーッと言えるようにして家庭に乗り込んで親御さんにバーッと様子を伝えて。恐らく通じてないんですね、発音がめちゃめちゃだったと思うし。通じてないんだけど、でもそれで変わってくんですよね、家庭の様子とかお子さんの様子が。
伝えようと思っている人のことはなんとか聞こうと相手は感じてくれている。これがコミュニケーションっていうものだと思ったんですね。僕は言葉のせいだと思っていたけども、言葉が完全じゃなくても変わるんだなということを覚えたのがその時です。同時にこれを言いたいっていう言葉文章作り込んで行ったっていうのもそのころだったので、それは現在の技術でやれば結構簡単なことかなという発想からこのツールを開発しました。
コミュニケーションって会うことが一番基本だと思うんですよね。でも言葉が通じないって思い込んじゃうと会えないって思い込むしかなくて、じゃあ伝わらないってなって全く進まないんですよね。
このツールを使ってふだんから簡単なやり取りをしていると、いつの間にか相手と通じ合ってるようになっちゃうんですね。だから必要があれば会うのも怖くないしもし、コミュニケーションの土台がこのツールで作ればいいなという気持ちです。とにかく言葉が通じないから何もできないんだと思っている人たちの壁を、言語の壁というよりは心の壁のようなものをなくしたいという願いがあります。