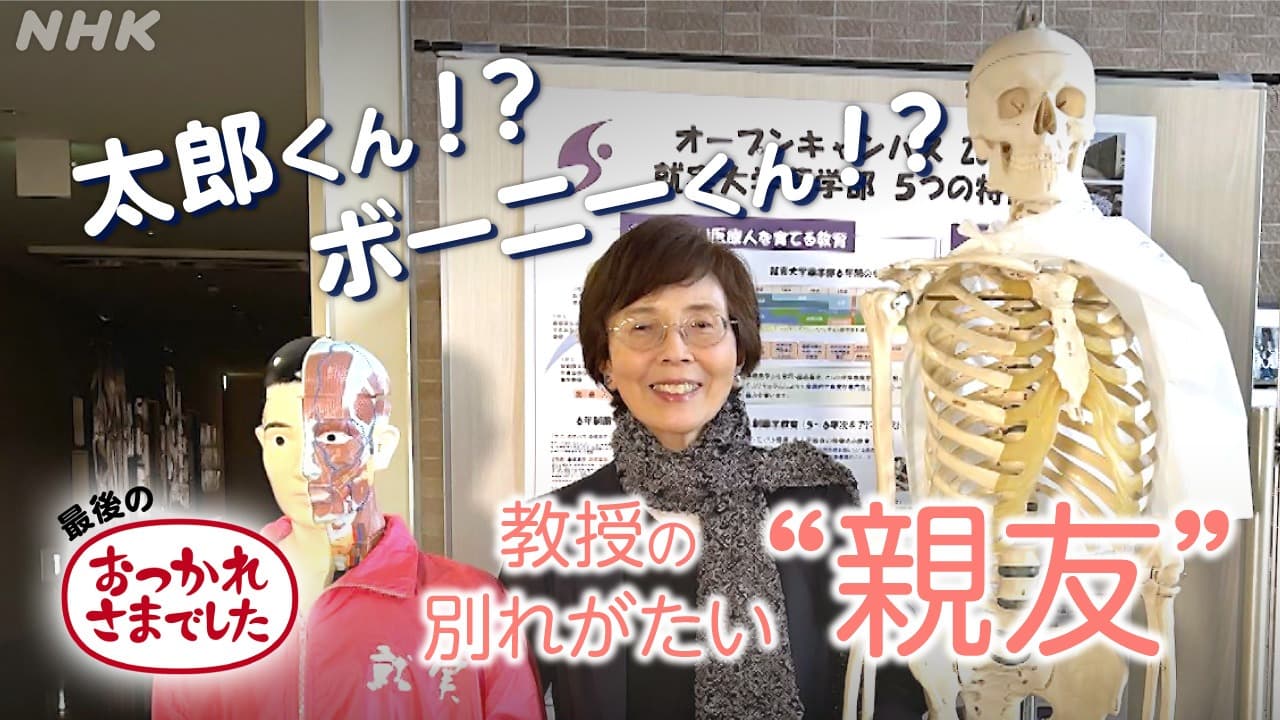捨てられる布をなくしたい!アトツギ甲子園に挑む岡山の生徒!
- 2024年04月26日

後継者たちがビジネスプランを競う中小企業庁が開く全国大会「アトツギ甲子園」。
史上最年少で出場した当時・中学3年生の生徒が将来について考える姿を取材しました。
(松本真季アナウンサー)
アトツギ甲子園に史上最年少で出場

後継者たちがビジネスプランを競う中小企業庁が開く全国大会『アトツギ甲子園』
地方大会を勝ち抜いたアトツギたちが、家業の新しいビジネスプランを発表します。
参加資格は、39歳以下の後継者です。

そこに史上最年少で出場したのは、3月まで中学3年生だった姫井美桜さんです。

活動のきっかけは…
「廃棄される布をなくしたい」と考えたのは、中学校で行われている課題研究がきっかけでした。

美桜さんは、そこで父の経営する会社について調べました。



廃棄される布が倉庫に並んでいて、すごくショックでした。
こんなにも多くの布が廃棄されてしまうんだっていうことを本当に肌で感じました。
美桜さんの父は、140年以上続く染色加工会社を経営しています。


年間およそ1千万㎡、東京ドームおよそ210個分の面積にもなる生地を染めて国内外へ出荷しています。

しかし、染めむらや傷があるものは出荷できず廃棄せざるを得ません。


そこで、捨てられる布をなくすために会社で開発したのが新素材「NUNOUS」です。

この新素材がどのように作られるかというと…



廃棄布が、ひとつとして同じ模様がない新素材として生き返りました。
現在、環境に優しい素材としてインテリアや、ファッション、商業施設の飾りなどに採用されています。



しかし企業間での取引が多く、広く知られていないのが現状です。
新素材を知ってほしい!
廃棄される布を減らすため、美桜さんは新素材を使った製品を返礼品としてクラウドファンディングを行いました。

いまの時代にも合っていて、素晴らしい素材だと思っているので、知ってもらっていないのはもったいないと思い、認知度を広めるという活動をしました。
製作したのは3種類。

デザインは美桜さんが考え、カバン工房に持ち込みました。

同年代にも使ってほしいと、何度も改良。

開閉のしやすさや、文房具が十分収まる大きさなど機能性を重視しました。


こうした取り組みの中で「将来的に、家業を継ぐ」という意識が高まってきたといいます。

最初は跡を継ぐとか、そんなことは一切考えてなかったのですが
研究を進めていくうちに、愛情が芽生えてきました。
この素晴らしい素材や技術をもっとつないでいきたいです。
いよいよアトツギ甲子園の決勝大会
3月上旬。 東京で行われた「アトツギ甲子園」



発表後、審査員から質問が…。


廃材を使った商品作りは進んできている。
NUNOUSのブランド自体の特徴は?

厚さを調整することができて、ブロックのように固いものを作ったり、薄いものを作ったりと幅があるのが特徴です。
粉砕をしないので布本来の柄を生かしながら活用できます。
質問にも的確に答え、発表は無事終了。いよいよ結果発表です。


入賞はなりませんでしたが美桜さんはこの大会に出場したことで将来の目標が見えてきたといいます。


この大会に出て、アトツギとしての立場を実感しました。もっともっと事業をブラッシュアップして何か役に立てたらなと思っています。
同世代の人と協力して、何か新しいことをつくりあげて、もっといいものにしていきたいです。
4月から高校生になった美桜さん。
新素材を使った製品の開発が事業として成り立つように取り組んでいきたいということです。