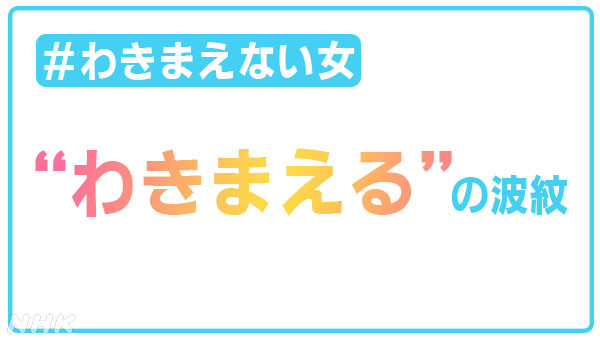
Vol.9 “わきまえる”の波紋
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長が、みずからの女性蔑視と取れる発言の責任を取って辞任する考えを明らかにしました。
「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」という発言に加え、「組織委員会にも女性がいるが、みんなわきまえている」という発言に対しても、SNSを中心に大きな議論が起きました。広がる波紋を取材すると、スポーツ界だけでなく、私たちの社会、組織のありように対する疑問の声が聞こえてきました。
(「おはよう日本」取材班)
#わきまえない女 声を上げる人たち
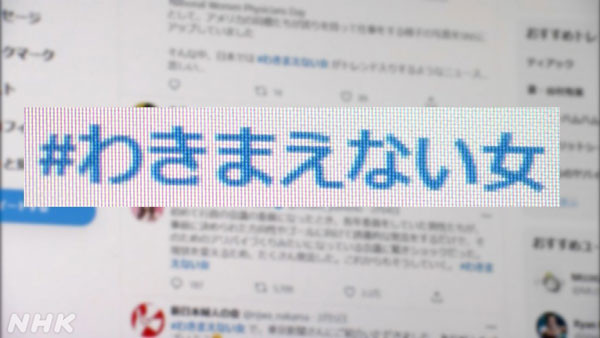
「わきまえない女、ここにいます」
「わきまえろと言われても声を上げ続けるのが私たちのやり方です」
森会長の発言以降、「わきまえない女」というキーワードをつけた投稿が、SNSで相次いでいます。
特に多くの賛同を集めているのが、家庭に居場所がなかったり、性搾取を受けたりしている10代の女性に衣食住を提供する活動をしている仁藤夢乃(にとうゆめの)さんの投稿です。青少年の支援について話し合う行政の会議に参加した際、出席者のほとんどが男性で、議論が既定路線で進む様子にショックを受けたとつづっていました。
『初めて行政の会議の委員になったとき、長年委員をしていた男性たちが、事前に決められた方向性やゴールに向けて誘導的な発言をするだけで、そのためのアリバイづくりみたいになっている会議に驚きショックだった。現状を変えるため、たくさん発言した。これからもそうしていく』

-
仁藤夢乃さん
-
「“もとから考えられている路線と違うことを言うなよ”という空気を感じながら、言うことは言うようにしています。女性差別とか、性搾取とか、多くの女性が困っている問題が放置されてきたのも、男社会で男性たちが権力を握って決めてきたから。現状を変えるためにも、多くの女性がはっきりと発言をして議論の場、決定の場に入っていくことが重要だと思っています。おとなしくしていることが『わきまえる』ことになってしまうという日本社会の現状が、女性差別の深刻な状況をあらわしていると思います。」
わきまえたこと、ある?
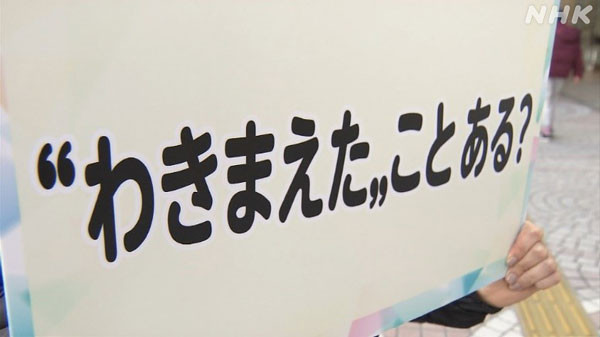
街の人に聞くと、男女を問わず、“わきまえた” 経験があるといいます。
-
20代 女性
-
「前の会社だと男社会という感じだったので、強気な『こうした方がいいのではないですか』という発言はしづらかった。」
-
18歳 男性
-
「部活とかだったら、年代が3世代で後輩先輩の差があるので、先輩に意見するときは自分の感情をちょっと抑えてというのが “わきまえた”経験かな。」
-
70代 男性
-
「男の人は出世しなきゃいけないところがあるじゃない。男の人だけでないかもしれないけど。みんな中央に向いている。」
“わきまえる”リスク 企業トップも・・・
こうした中、“わきまえる”ことについて危機感をにじませる意見を投稿した人がいます。
「これは私たち日本が育んできた文化・社会でもあります。私としては猛省する」
投稿したのは、国内最大級のフリマアプリ、メルカリの代表取締役・CEOの山田進太郎さん。“わきまえる”ことで多様な意見が出づらくなったら、企業は生き残れないといいます。

-
山田進太郎さん
-
「サービスが広がるほど、年齢、性別、外国人など、さまざまな方々の多様なニーズに対応するためには、社内で多様な声があるということがすごく重要。“わきまえる”というのは明確なマイナスがあると思う。」
山田さんはいま、社内で萎縮せずに意見を言える環境作りを模索しています。
-
山田進太郎さん
-
「誰も意見を言ってくれなっちゃったら、(自分が)どんどん“裸の王様”になってしまって、いくら気をつけていても(周りが自分に意見を)言いにくいことなどあると思います。だから、まずは みずから自覚することが大切。言い方もそうですし、“言える文化”というか、言い続けることで“言える文化”にしていくしかない。
私には子どもがいますが、今のこの社会、世界のまま、子どもたちに残せないと感じています。今回の件をきっかけにして、いろいろな人がダイバーシティを考えることが重要だと思います。 」
取材して感じたこと
そもそも「わきまえる」とは、「ものの道理を十分に知る」という意味で、必ずしも「黙ったほうがいい」というわけではないはず。しかし、改めて自分の経験を振り返ると、「リーダーは男性の方がいいだろう」など性別を理由に、プロジェクトの代表を決める場で、やってみたい意志があったものの立候補しなかったことがあったのを思い出し、反省しました。
今回の発言をきっかけにして、知らず知らずのうちに「言っても仕方がない」と思っていた問題に対して、きちんと声を発していく社会にどうすれば変えていけるのか、考え続けていきたいと思います。
みなさんから寄せられる声をもとに取材を続けます。ご意見をお待ちしています。